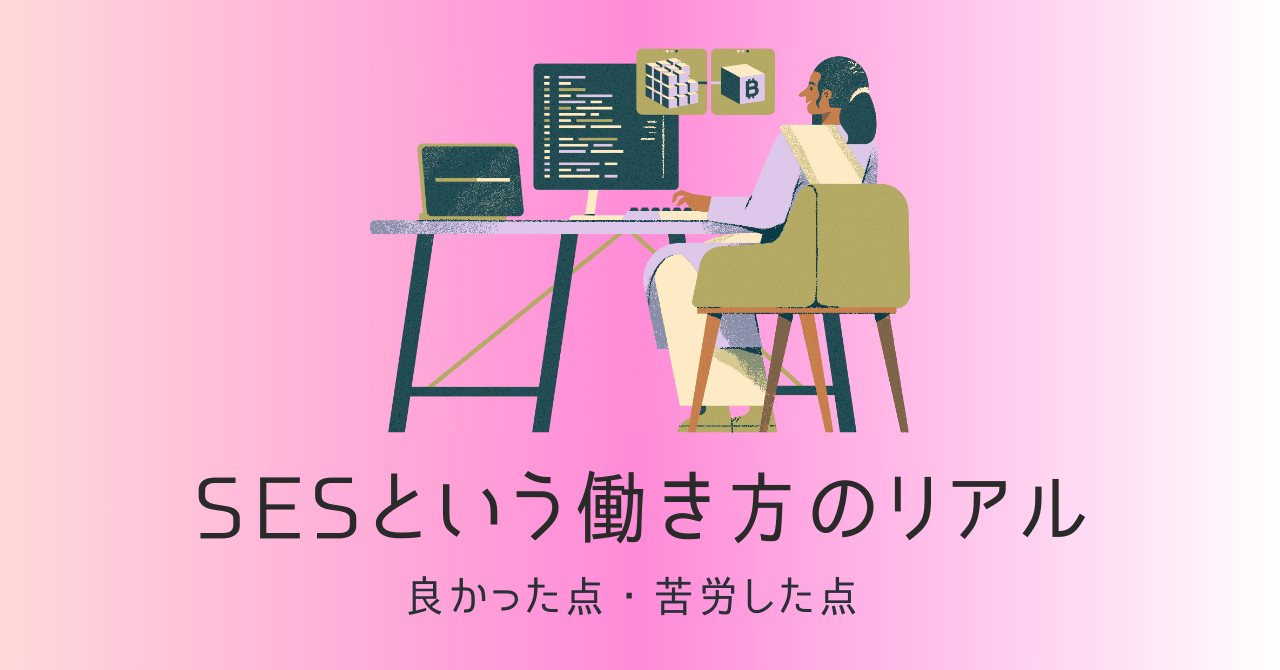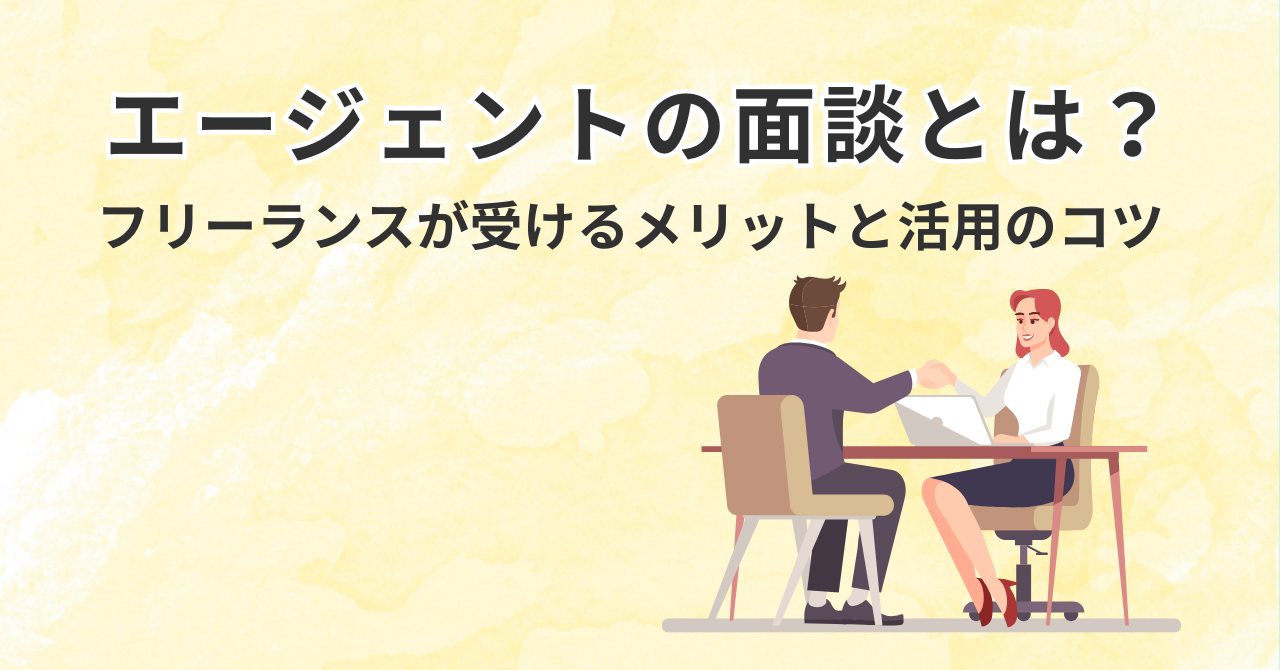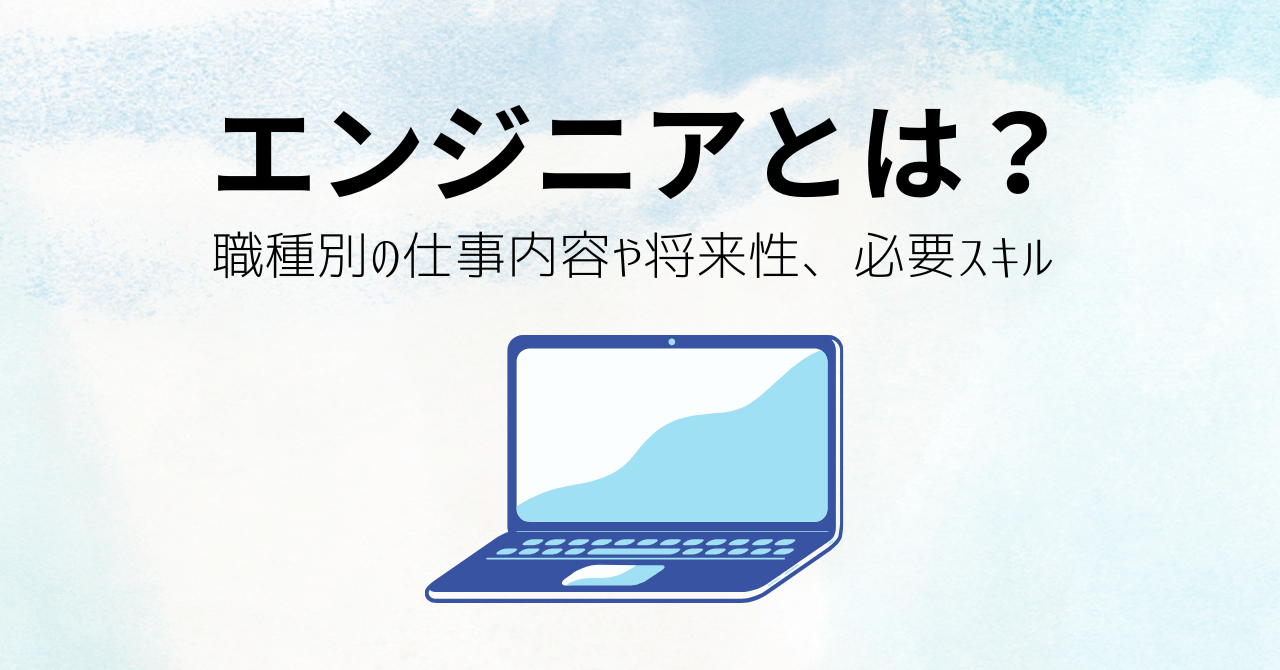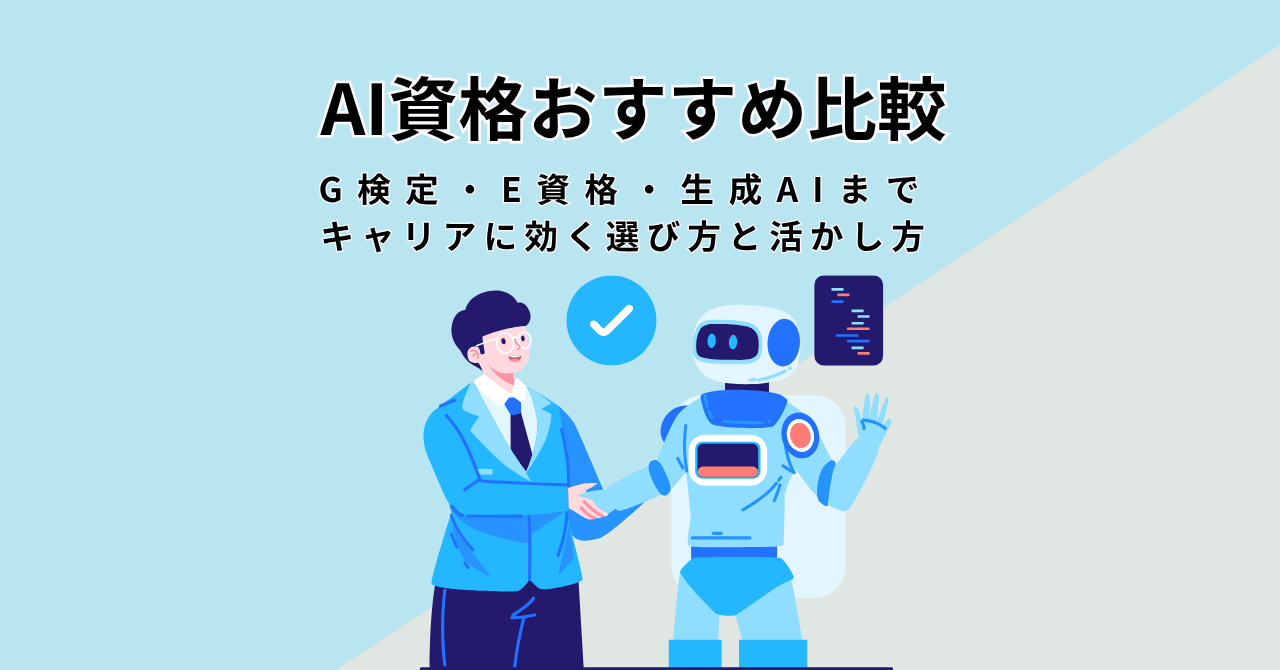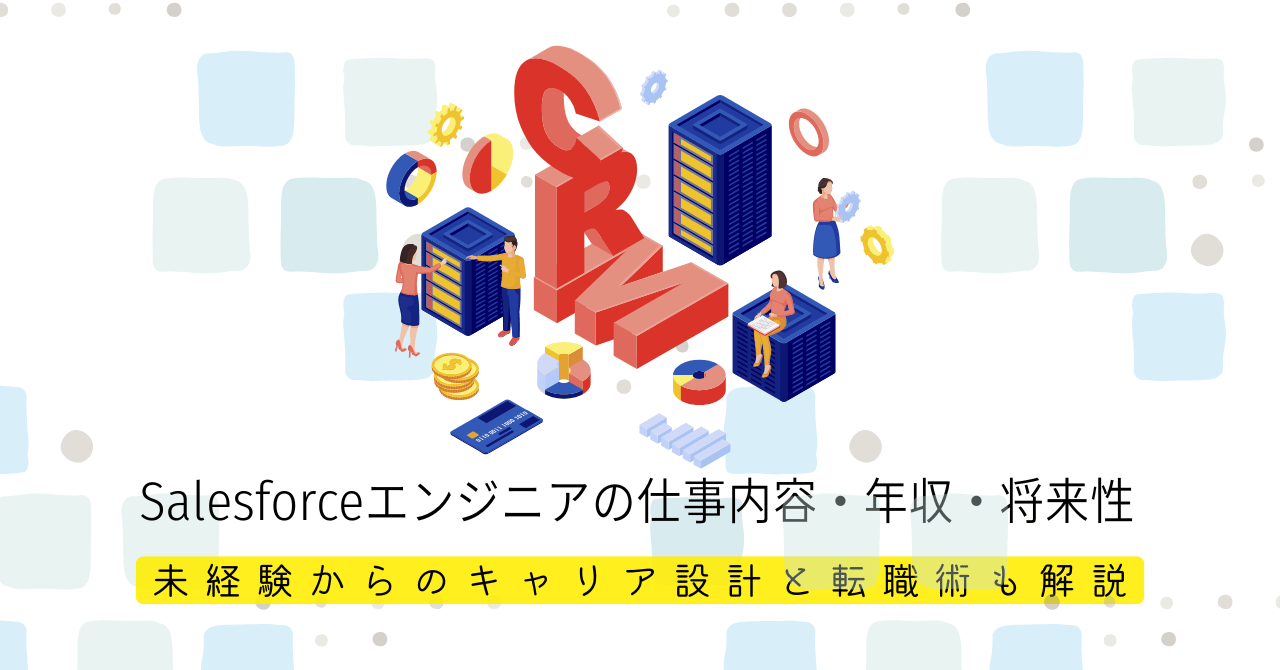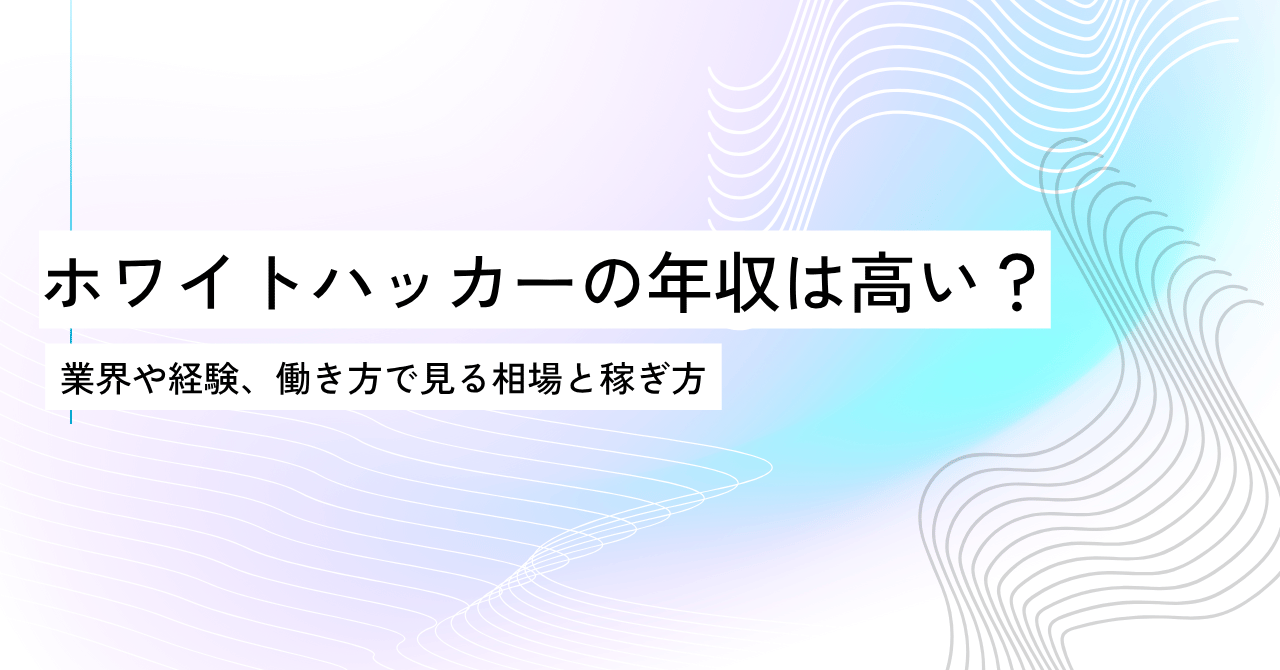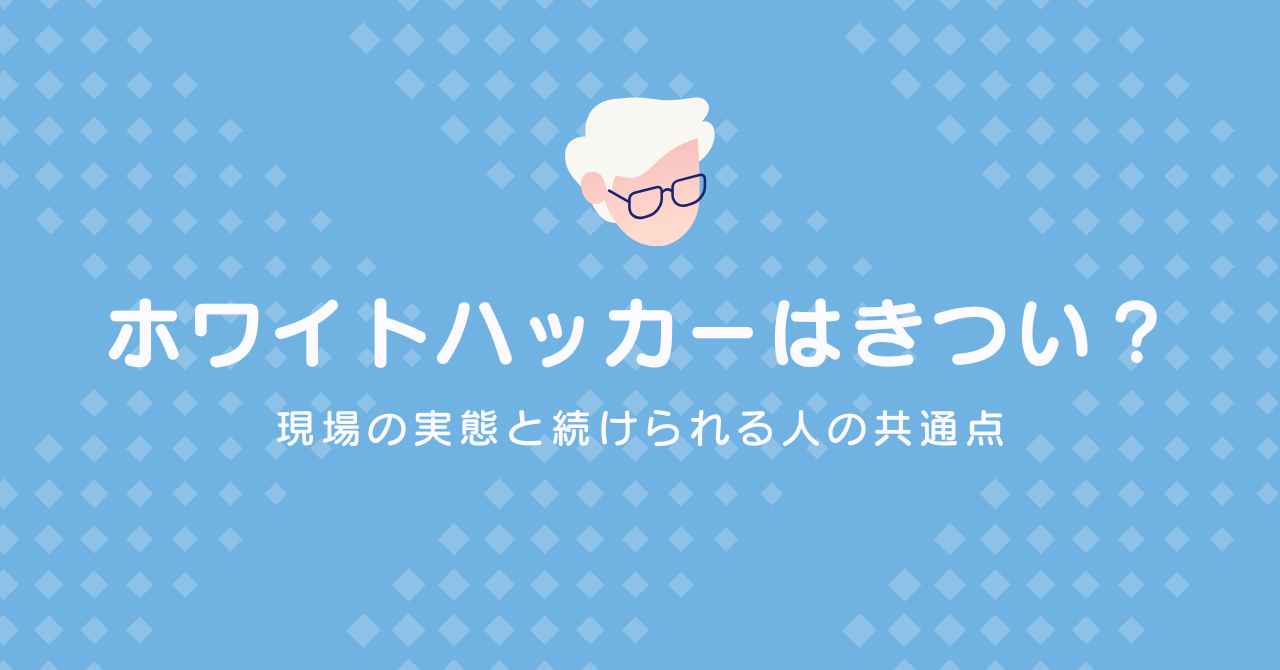SESとして働いているエンジニアは実際に現場での経験をどのように捉えているのでしょうか。SESとしての実体験や生の声を知りたいと思ったことはないでしょうか。
本記事ではSESエンジニアとして3年間業務をしてきたR.KotomoがSESとして働いて良かった点や苦労した点について実体験をベースに紹介し、最後にSESエンジニアとしてのキャリア形成の考え方についてお伝えします。
SESに興味を持っている方や現在SESとして働いている方の参考になれば幸いです。
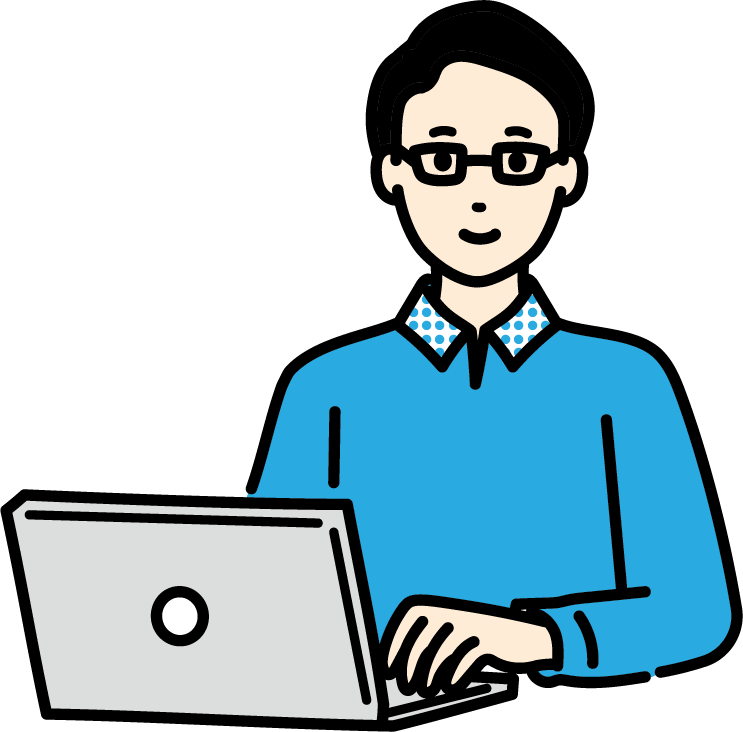
ライター:R.Kotomo
プロフィール:見習い中のデータエンジニアとして、PythonやSQL、クラウドを日々の業務で扱っています。ITエンジニアが執筆した技術記事から多くを学び、自身の経験も誰かの役に立てたいと考えライターを始めました。データ人材やデータ業界に関する情報を、初心者にもわかりやすくお伝えすることを目指しています。実務に基づいた具体的な内容や、現場で役立つノウハウを共有することで、読者のみなさまに気づきを与えられたらと思います。
SESとは?
SES(システムエンジニアリングサービス) とは、エンジニアが企業に常駐して技術支援を行う契約形態のことです。
企業はシステム開発や運用のために必要なエンジニアを、時間単位で契約して派遣のように受け入れます。
契約形態:準委任契約(成果ではなく「作業時間」に対して報酬が発生)
働き方:クライアント先に常駐し、チームの一員として業務に参加する
メリット:エンジニアは安定して案件に参画できる、企業は必要な期間だけ人材を確保できる
デメリット:成果物ではなく「工数」での契約なので、スキルアップやキャリア形成の観点では課題もある
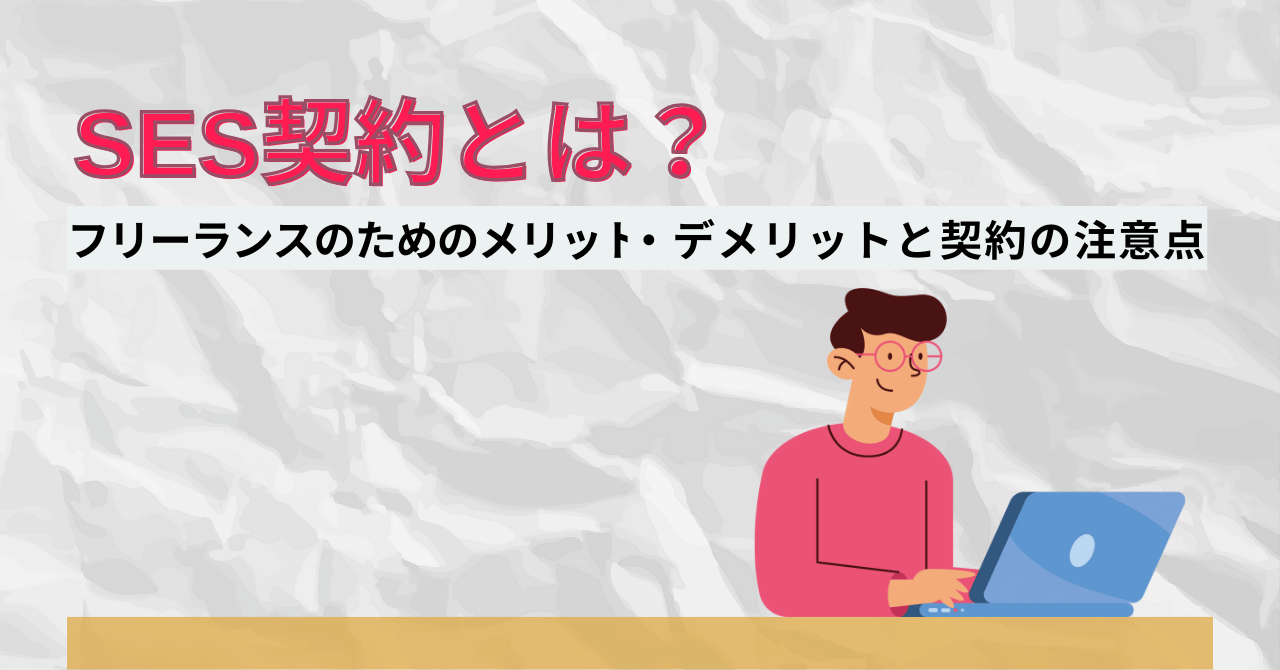
SESとして働いてよかった点5つ
SESエンジニアとして働くことで得られるメリットは少なくありません。ここでは、私が実際に感じた「良かった点」を5つご紹介します。
幅広い技術を学べる
SESエンジニアとして働くメリットの一つは、短期間で多様な技術スタックに触れられることです。参画する各現場で採用している技術スタックが異なるため、技術的な広がりを獲得できると私は考えています。
私の実際の経験では、AWSでのラムダアーキテクチャを採用したETL開発、Google CloudでのELT開発、機械学習システムの運用保守など各現場で異なる技術スタックに触れることができました。現在はGoogle Cloudをメインにデータ基盤の開発やCI/CDの開発などに取り組んでいます。
このように3年間で異なる技術スタックを実務で経験することでジュニアデータエンジニアとして、業務を遂行できるスキルを身につけられたと私は感じています。
幅広い人的ネットワークを構築できる
SESエンジニアの業務を通じて、様々な現場を経験することで幅広い人的ネットワークを構築できます。各現場で関わった方たちと良好な関係を築くと、参画終了後も定期的に情報共有や交流が可能です。お互いのキャリアに対する考え方や現状の共有など何気ない会話から転職やスキル向上のヒントが得られると私は考えています。
具体的な例として、現場で知り合ったエンジニアとは現在も技術的な相談を行う関係が続いており、「生成AIの導入や検証って進んでる?」「転職エージェントと最近どんなやり取りした?」「最も使用頻度の高い生成AIはどれ?」など技術トレンドや転職に関する情報交換を定期的に行っています。
特に最近では生成AIをどのように業務に取り入れるか、といった話題が中心になっています。
様々な業界での実務経験を積むことができる
SESエンジニアは決まった業界の企業で働くことが少なく、様々な業界を経験できるため、業界特有のビジネスモデルやシステム要件などを知ることができるのが強みになると私は考えています。
私の場合、エンタメ業界、美容業界、通信業界、小売業界など多くの業界のシステム開発や運用に携わってきました。下記にそれぞれの案件で得た気付きや学びを整理しました。
| 業界 | 担当 | 気付きや学び |
|---|---|---|
| エンタメ業界 | ELT開発 | ・大規模なデータ量を扱い、トレンド技術を活用した実装を経験 ・エンジニアのレベルが高く、GDPRなど国際的な法規制への対応を学習 |
| 通信業界 | ETL開発 | ・社会インフラを支えるサービスに携わり、リアルタイム性を重視した設計を体験 ・高い可用性と安定稼働を求められる現場での実践知を獲得 |
| 小売業界 | 分析案件 | ・実店舗での顧客行動や棚割りを分析し、利益拡大につながる施策を支援 ・店舗運営側の視点から「売上を伸ばす仕組み」を理解 |
このように、異なる業界での実務経験があることで、単なる技術的解決にとどまらず「業界特性を踏まえた提案」ができるようになるのがSESエンジニアの大きな強みだと感じています。
自身の市場価値を客観視できる
SESエンジニアとして多様な現場を経験することで、エンジニアとしての市場価値を客観的に把握しやすくなります。さまざまな企業・業界でのスキル需要と報酬水準を直接体験できるため、自分自身の技術レベルを市場相場と照らし合わせて評価できるようになるからです。
実際に現場Aでのリーダークラスの単価は〇〇円、ジュニアエンジニアの単価は〇〇円とおおよその単価を把握することで、より単価を上げるために自分に不足しているスキルセットが明確になります。
また現場Bでは同じスキルセットでも現場Aより単価が高い場合があるので、エンジニアに予算を割り当てる額が大きい企業・業界などを知ることができます。
繰り返しになりますが、SESエンジニアとして多様な現場を経験することは、単にスキルを磨くだけでなく、自身の市場価値を冷静に見極める目を養えると私は考えています。
個人事業主に近い働き方を経験できる
SESエンジニアとして働いている方の中には、フリーランスエンジニアという選択肢を考えている方もいるかと思います。私自身、SESエンジニアとしてプロジェクトに参画する中で、フリーランスエンジニアに近い勤務形態やタスク内容を実感しました。
理由としては、プロパーが行うような資料作成や社内業務はほとんど任されず、自分に与えられたロールに応じた業務に専念できるからです。実際にフリーランスエンジニアと同じプロジェクトに参画した際も、契約形態が違うだけで「外部からアサインされ、決められた単価・工数で参加する」という点はほぼ同じでした。
SESエンジニアとしての経験は、フリーランスに近い働き方を肌で感じる貴重な機会となり、将来的に独立を考える際の具体的なイメージづくりにもつながると私は考えています。
SESとして働いて苦労した点3つ
もちろん、SESには課題や大変な面もあります。ここからは、私がこれまでに直面した「苦労した点」を3つ挙げてみます。
待機期間の収入減少リスク
SESエンジニアのリスクの一つは、プロジェクト間の待機期間中に収入が減少する場合があることです。会社の制度によって収入への影響度合いは異なりますが、経済的な不安定さを生む要因となります。
実際に私も現場が合わずに抜けてしまったあとの2、3ヶ月の待機期間中に収入が3分の1以下になることで、収入より支出が多い期間が続き、精神的にも苦しい時期がありました。
待機期間の収入減少リスクは、家族の生活費など固定的な支出があるエンジニアにとっては生活に支障をきたす可能性があります。
そのためSESエンジニアは収入が減少するリスクがあることを念頭に置いて、参画するプロジェクトを選択する必要があるでしょう。
運用がうまくいっていないシステムの運用保守
私が経験したシステムの運用保守業務の中に、ドキュメントが整理されず属人化していて、十分に運用が回っていない案件がありました。そのような現場では、まず現状把握やドキュメントの整理から始めることとなり、技術的な成長よりも「業務を安定させること」が優先されるのだと学んだ貴重な経験でした。
具体的には、エンジニアの入れ替わりが多いベンチャー企業に参画した際、当初から運用を任されましたが、エンジニア向けの資料はなく、情報源はソースコードと過去のSlack履歴しかありませんでした。そのためキャッチアップに苦労し、運用初月の異常対応やバグ修正には必要以上の工数を割いてしまったと感じています。
それでも課題整理やドキュメント作成を進めることで運用を軌道に乗せ、最終的には引き継ぎが可能な状態にできたのは良い成果でした。SESエンジニアは整備の追いついていない現場に入ることもありますが、その分、環境を改善する力や柔軟に対応する姿勢が自然と鍛えられるのだと考えています。
企業文化の違いによる適応コストと負担
SESエンジニアは案件参画後、即戦力として働くために短期間で異なる企業文化に適応する必要があり、この適応プロセスが精神的な負担となることが少なくありません。
各企業には独自の業務フロー、コミュニケーションスタイル、企業文化があり、これらに素早く順応することがSESエンジニアには求められます。
具体的な経験として、厳格な階層構造を持つ現場では、実装前の調査についてパワーポイントの資料にまとめたり、オフラインでのコミュニケーションが多かったりと慣れるまでの2ヶ月間は常に緊張状態が続きました。
一方で、ベンチャー企業では、意思決定の速さと業務フローの曖昧さに戸惑い、適応するのに苦労しました。このような企業文化への適応の繰り返しは、エンジニアとしてのコア業務以外にもエネルギーを要し、長期的には精神的な疲労蓄積の原因となる場合があります。
SESは自分自身でキャリア形成できる
SESの働き方は「案件にアサインされるだけ」という受け身のイメージを持たれがちですが、実際には自分の意思でキャリアを形づくることができます。ここでは、その具体的な考え方を紹介します。
軸となるスキルや業界を選択する
SESエンジニアは所属している企業によっては、参画先が使用している技術スタックや参画先の業界を選択できる場合があります。その利点を活かし、自分の軸となるスキルセットやドメイン知識を戦略的に選択することで、自身のキャリア形成が可能であると私は考えています。
実際に私はテスター、データ基盤構築、機械学習システムの運用保守など複数社で幅広く経験した中で自分の軸となるスキルを醸成し、自分に合った業界を知ることができました。
伸ばしたいスキルや働きたい業界が明確になってからは、営業に意向を伝え、軸に沿った現場の提案をしていただき、現在はインフラやデータ基盤構築のスキルを伸ばすことに重きを置いた現場で業務を行っています。
軸を明確にする過程で、仕事に対するモチベーションの低下やキャリアに迷うことも。しかしさまざまな経験の中から、自分に合ったスキルと業界を見つけられたことは、SESエンジニアとして働くメリットであり、今後のキャリア形成における指針となっています。
さまざまな役割を経験する
SESエンジニアは参画先企業によって1つの役割だけでなく、設計などの上流工程、テスト、プロジェクトマネジメント、運用保守といった様々な役割を経験する機会があり、エンジニアとしての総合力を高められると私は考えています。
実際に私の場合は最初の現場でテスターを経験することから始まり、データ基盤構築、ETLの設計/開発/テスト、機械学習システムの運用保守、データ分析案件などデータエンジニアとして必要な技術スタックや役割を経験できました。
様々な役割を通じて得た経験は、多角的な視点でシステムを捉えるきっかけとなり、先日CI/CDの実装を行った際に、システムの運用保守の経験を活かすことができました。
多岐にわたる役割を担えるのは、SESならではの働き方の利点であり、将来的にどの分野に軸を置くかを判断するための貴重な経験になったと考えています。
フリーランスの案件探しはエンジニアファクトリー

SESとして多様な現場を経験することは、技術力や市場価値を磨き、自分の軸を見つける大きな糧になります。その先のキャリアとして「フリーランスエンジニア」という選択肢を考える方も多いのではないでしょうか。フリーランスとして働くには、案件の探し方や参画条件の見極めが重要ですが、個人での情報収集には限界があります。そこで役立つのがエンジニアファクトリーです。
私たちは10,000件以上の豊富な案件を取り扱い、継続率95.6%と安心して働ける環境を提供しています。さらに年商が最大300万円アップした実績もあり、技術力と働き方の両面でステップアップが可能です。SESで培った経験を活かし、次の挑戦をフリーランスとして考える方にとって、エンジニアファクトリーは最適なパートナーになるはずです。まずは気軽にご相談ください。
まとめ
SESエンジニアは、多様な技術や業界に触れられる点で自社開発や社内SEとは異なる魅力があります。また幅広い経験を通じて市場価値を客観視し、自分の軸となるスキルや業界を見極められるのはSESならではの強みだと私は考えています。一方で待機期間のリスクや企業文化への適応負担など、苦労する場面も少なくありません。
SESエンジニアとして重要なのは、これらの特性を理解した上で、軸となるスキルや業界を戦略的に選択し、様々なロールを経験することで自分自身のキャリアを主体的に形成することです。SESは受動的に案件をこなすだけでなく、能動的にキャリア戦略を立てることで、エンジニアとしての総合力と市場価値を高められる働き方といえるでしょう。