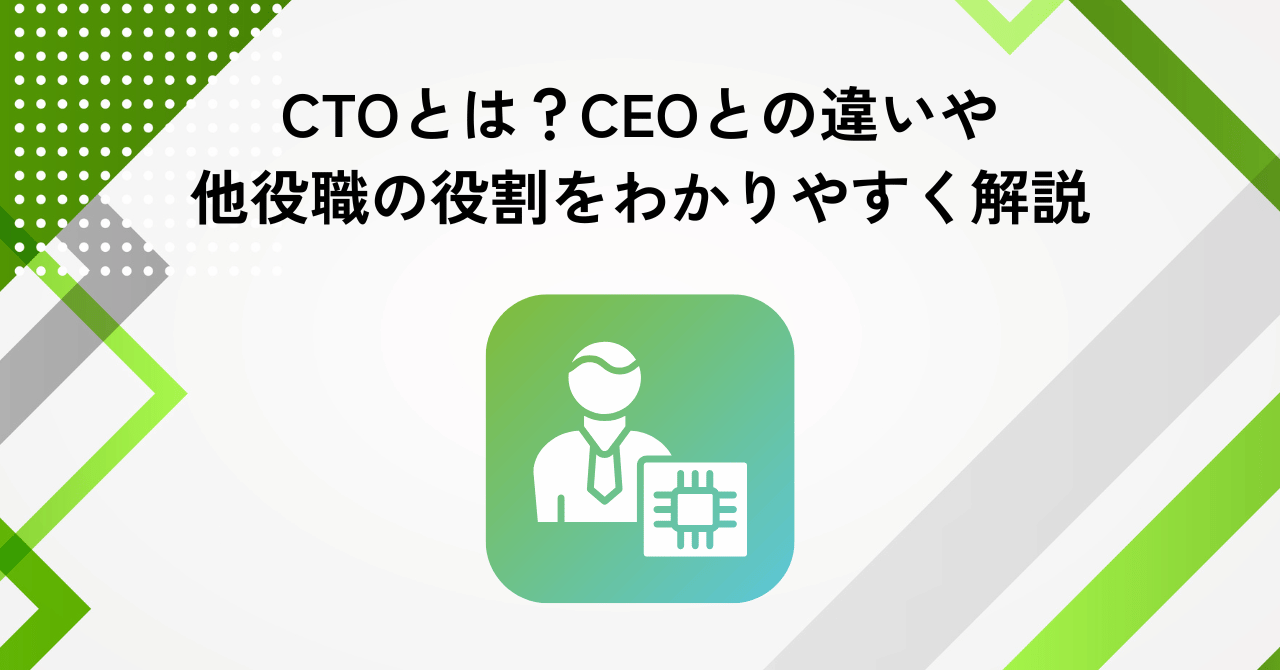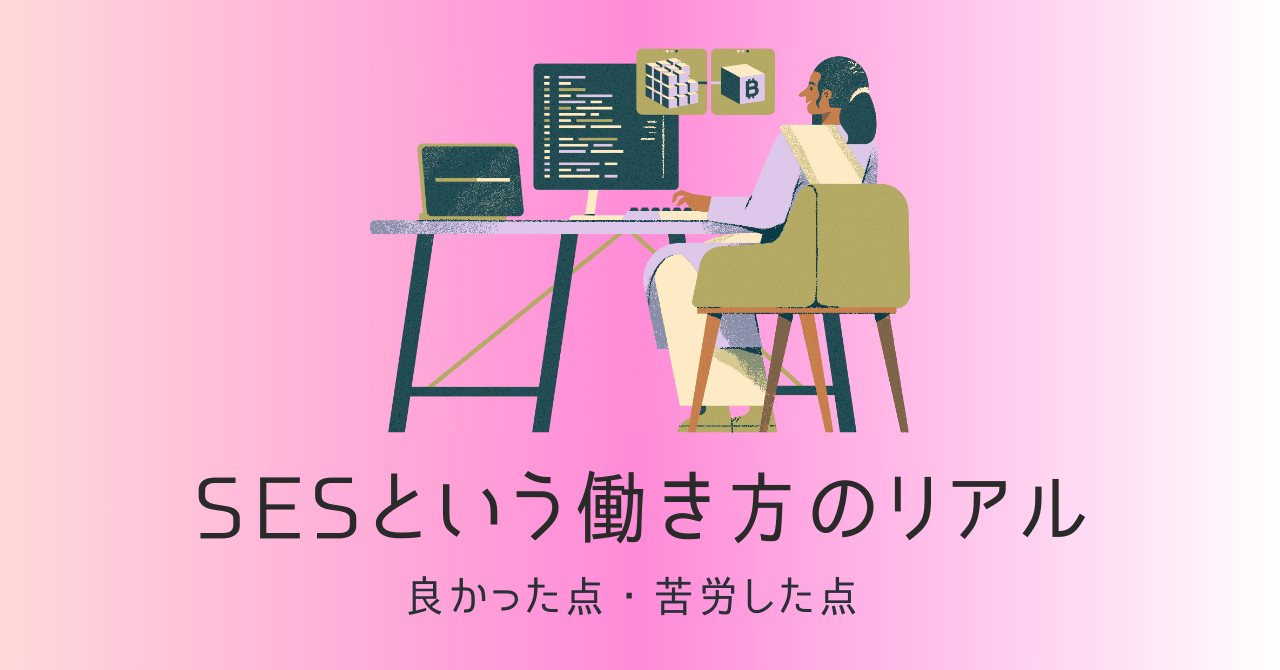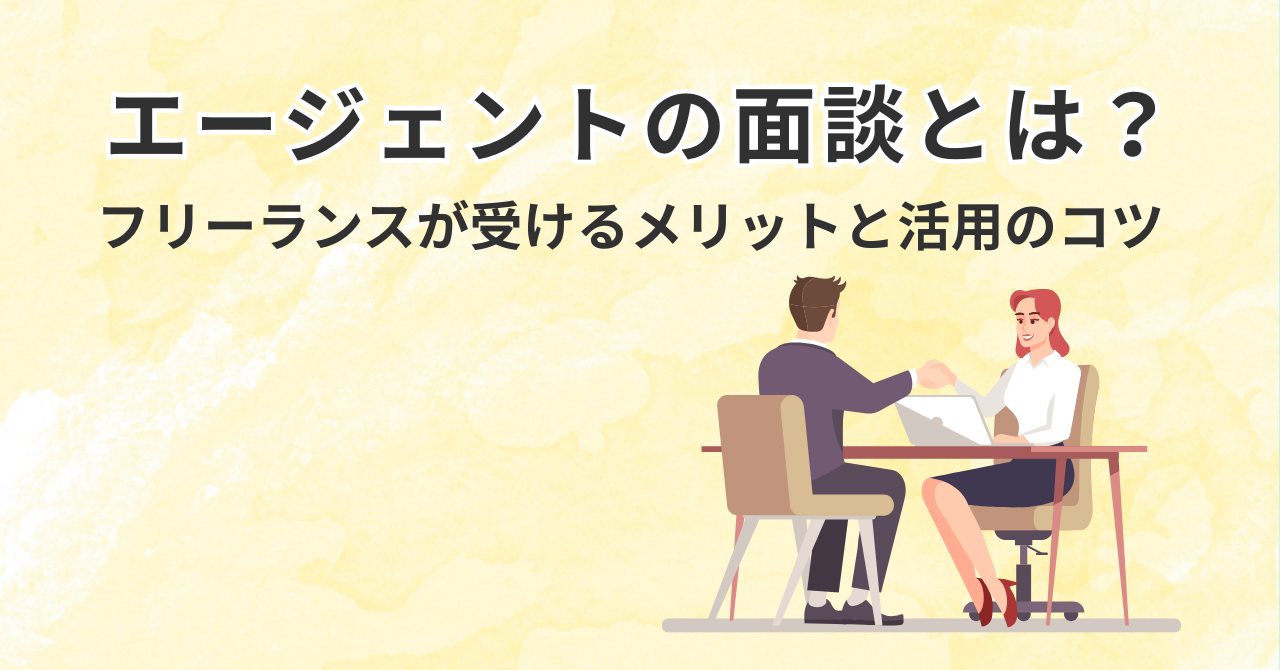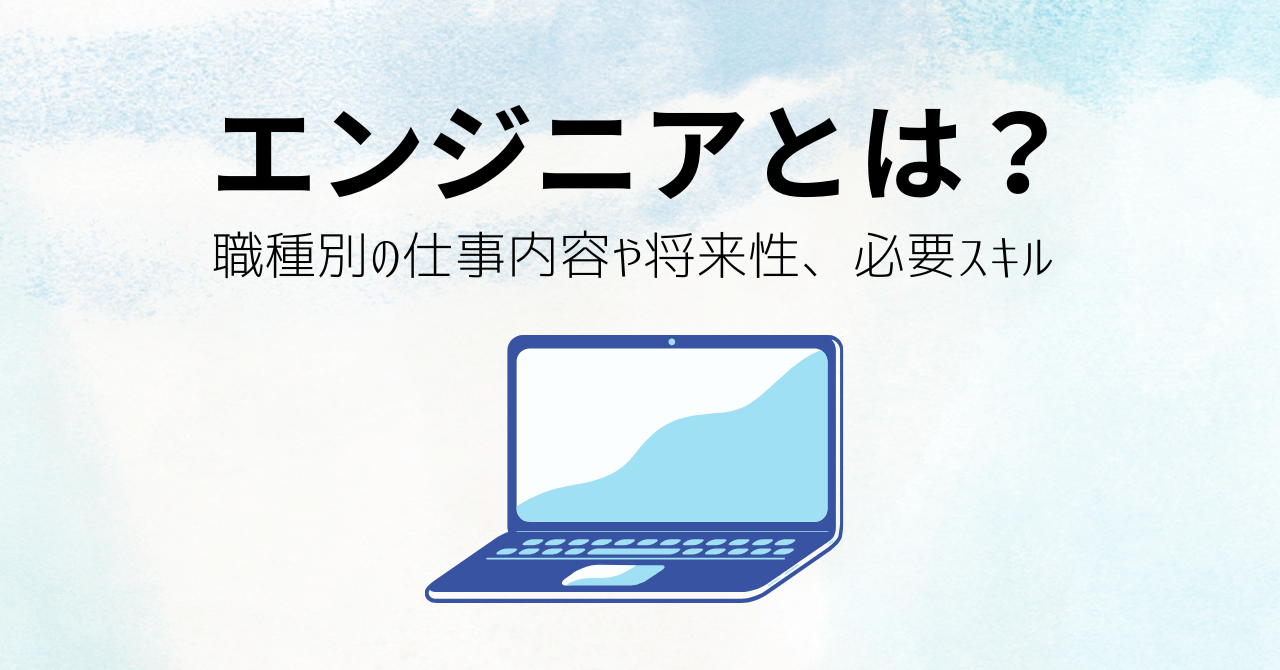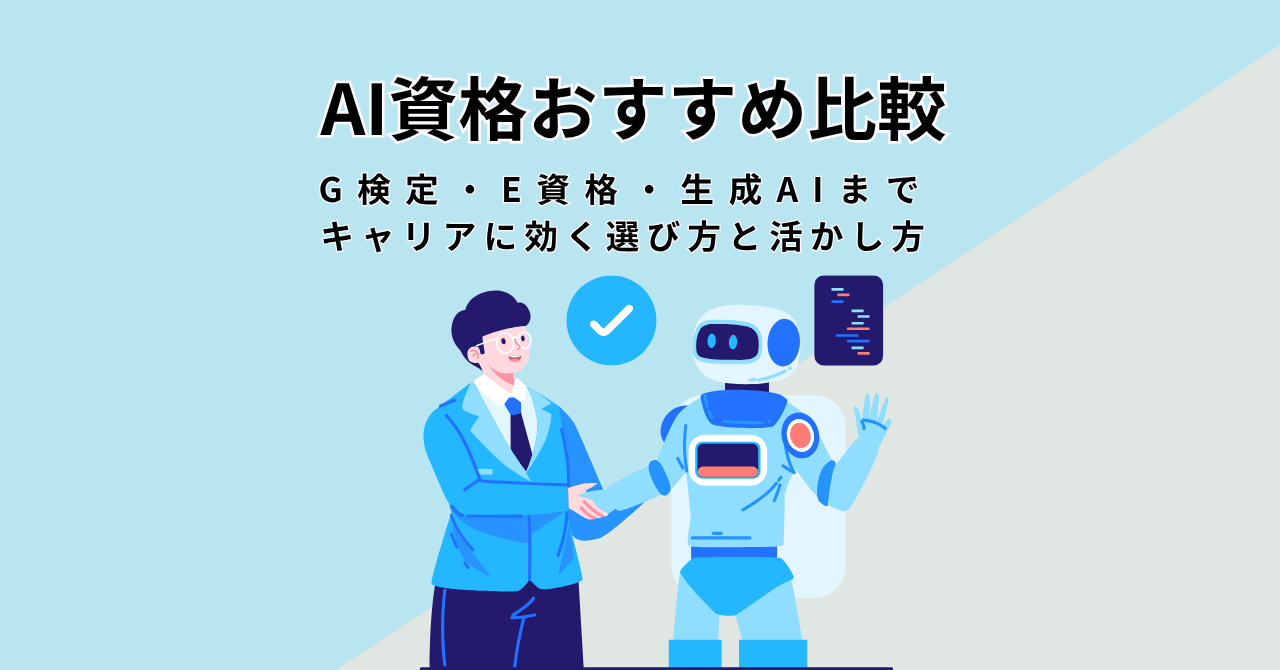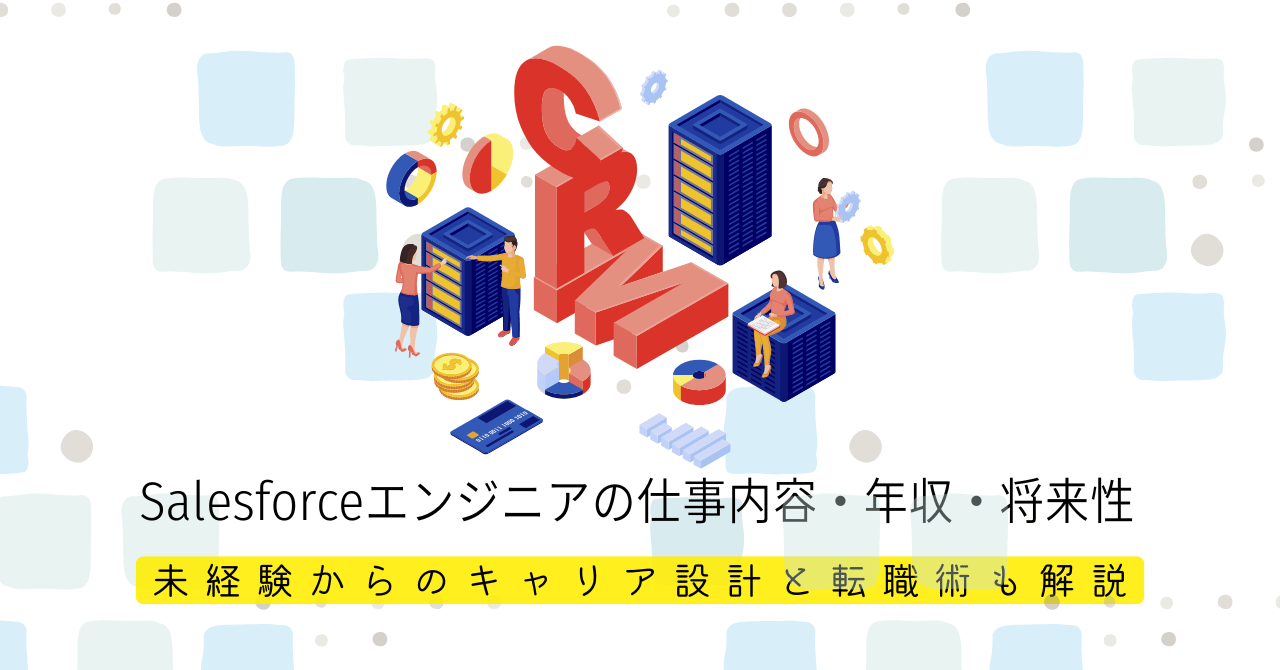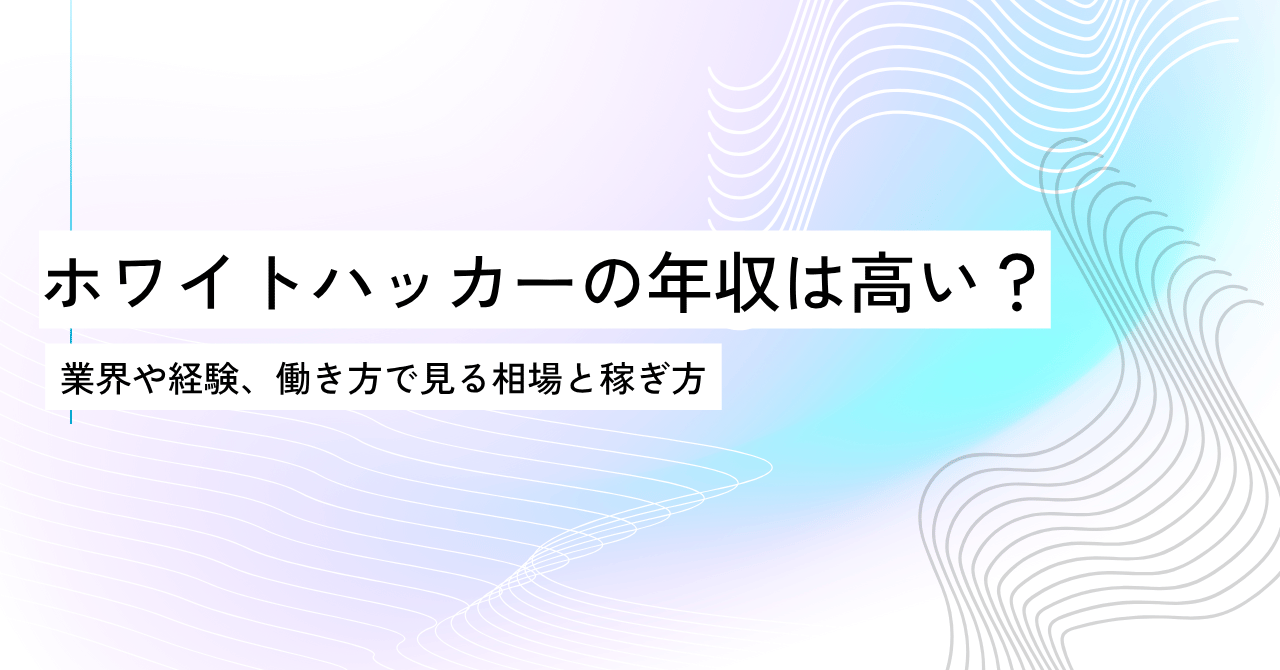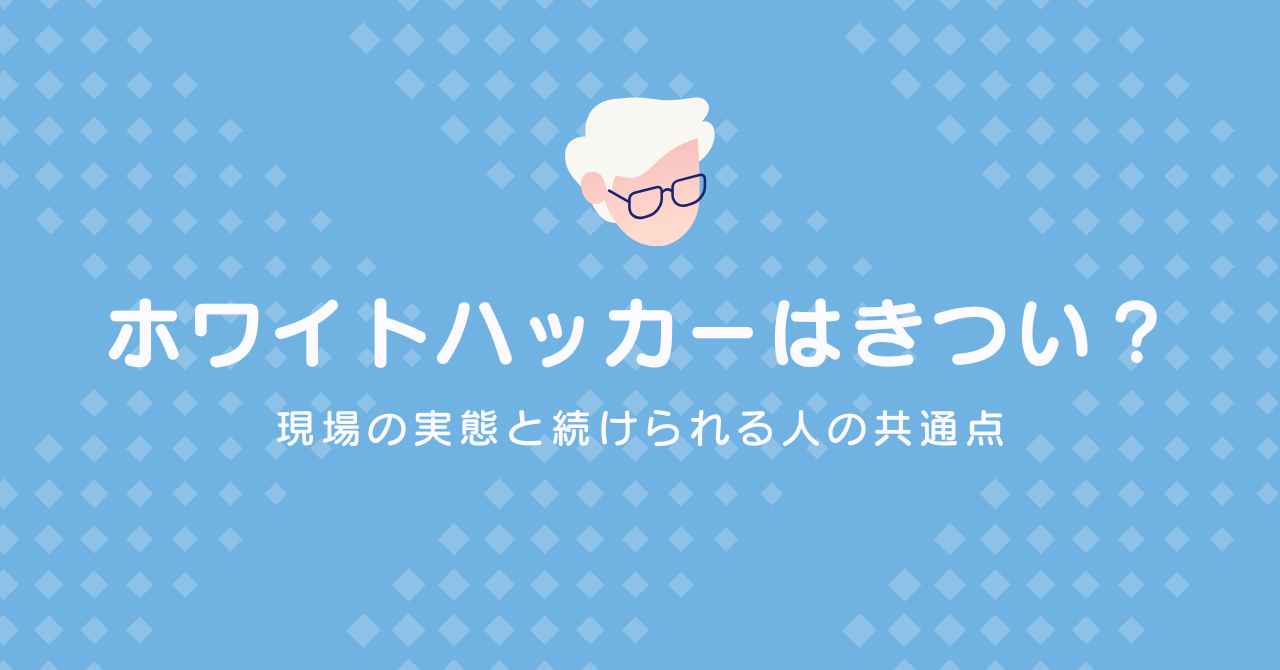CTO(Chief Technology Officer)は、技術戦略の中核を担うポジションであり、エンジニア出身の経営層として注目されています。本記事では、CTOの役割や年収、キャリアパス、向いている人物像までを体系的に解説します。
特に、
- 将来CTOを目指したいエンジニア
- CTO候補を探している採用担当者・経営層
- フリーランスから経営ポジションを目指したい方
に向けて、CTOの実像や求められるスキルセットを、実務視点でわかりやすくまとめています。
最後には、CTO候補求人の動向や、よくある質問への回答も紹介しますので、「自分がCTOに向いているか知りたい」「キャリアの次の一歩を考えたい」という方も、ぜひ参考にしてください。

エンジニアファクトリーでは、フリーランスエンジニアの案件・求人をご紹介。掲載中の案件は10,000件以上。紹介する案件の平均年商は810万円(※2023年4月 首都圏近郊のITエンジニア対象)で、ご経験・志向に合った案件と出会えます。
簡単なプロフィール入力ですぐにサポートを開始。案件にお困りのITフリーランスの方やより高条件の案件と巡り合いたいと考えている方は、ぜひご登録ください。
CTOとは?
CTO(Chief Technology Officer)は、日本語で「最高技術責任者」と訳され、企業における技術戦略を統括する役職です。
プロダクトやサービスにどんな技術を採用するか、開発方針をどう定めるか、どの技術に投資すべきかなど、経営レベルで技術に関する意思決定を行う存在です。クラウド移行やアーキテクチャの刷新、新技術の導入判断など、会社の成長に直結する判断を任されるケースも少なくありません。
日本においては比較的新しい役職ですが、スタートアップやテック系企業を中心に、CTOの導入は広がりを見せています。エンジニア出身者が就くことが多く、技術力と経営視点の両方が求められるポジションといえます。
なお、CTOやCEOなどの肩書き(いわゆる「CxO」)は、日本の法律で定義された役職ではなく、企業ごとにその役割や裁量は大きく異なるのが実情です。名称だけで判断せず、実際の業務内容や責任範囲を理解することが大切です。
また、CTOに代表される「CxO」という経営スタイルはアメリカ発祥で、1990年代以降、日本でも急速に普及。経営と実務を分離し、それぞれの役割を明確にすることで、企業の意思決定スピードを高める狙いがあります。
CTOの役割とは?
CTOの役割は、企業規模やフェーズによって幅広くなりますが、主に以下の3つに集約されます。
技術戦略の意思決定
CTOは、プロダクトやサービスの方向性を左右する技術的な意思決定を担います。どの技術スタックを採用するか、アーキテクチャはどう設計するか、内製か外注か――といった選択が、開発効率や保守性、将来の事業成長に直結します。
たとえば、モノリス構成をマイクロサービス化する判断や、オンプレ環境からクラウドへの移行方針など、中長期的な視点での技術判断が求められます。
技術組織のマネジメント
開発チームの採用・育成、評価制度の整備、文化づくりもCTOの重要な仕事です。特に成長フェーズの企業では、「誰を採るか」「どう育てるか」といった組織戦略が事業成長に直結するため、技術力と同じくらいマネジメント力が問われます。
現場との1on1や技術方針の共有、制度設計など、プレイヤー時代とは異なる視座でチームを支える必要があります。
経営陣との連携
CTOは経営チームの一員として、CEOやCOO、CFOと並び、事業全体に技術視点を取り入れる役割を担います。セキュリティ、スケーラビリティ、開発コストなどを踏まえた判断や提言を行い、経営の意思決定を技術面から支えます。
特に技術の専門性が高いプロダクトを扱う企業では、CTOがどれだけ経営視点を持てるかが、事業の成否に直結することもあります。
CTOの社内での立ち位置:ベンチャーと大手の違い
CTOという肩書きは同じでも、企業の規模やフェーズによって求められる役割やスタンスは大きく異なります。
ここではスタートアップ/ベンチャー企業と、大手・上場企業での違いを整理します。
スタートアップ・ベンチャー企業の場合
小規模な組織では、CTOがプロダクトの立ち上げから深く関わり、自ら手を動かす「ハンズオン型CTO」であることが一般的です。技術選定、設計、コーディング、チーム立ち上げまで幅広く担いながら、事業の成長と一体になって動きます。
少人数ゆえに意思決定スピードが早く「技術と経営の垣根なく動ける人材」が求められます。創業メンバーの一角として、事業に対する熱量と覚悟も重視されやすいです。
大手企業・上場企業の場合
ある程度組織が整っている企業では、CTOはより「経営と技術の橋渡し役」としての役割が強まります。日々の開発はチームや部門に任せ、中長期の技術戦略や部門横断の意思決定に関与するポジションとなります。
このフェーズでは、組織に任せる力・調整力・外部との折衝力が問われ、プレイヤーではなくリーダー/経営者としての視座が重要になります。子会社や外部ベンダーとの協業が発生することも多く、技術よりも人や体制を扱う側面が強くなります。
このように、CTOの役割は企業規模によって大きく変わるため、「自分がどのステージの組織にフィットするか」を理解しておくことが、キャリア選択のうえでも重要です。
企業がCTO候補に求めるスキルと経験とは?
エンジニアファクトリーが保有するCTO候補求人では、以下のような経験・スキルが重視される傾向にあります。
まず重視されるのは、Webサービスや自社プロダクトにおける技術選定やアーキテクチャ設計の実務経験です。特に新規サービスの立ち上げや、大規模なリプレイスプロジェクトをリードした実績があると評価されやすくなります。
次に、チームマネジメントや評価制度設計、採用活動など、技術組織づくりに関する経験も重要です。単に「開発ができる」だけではなく、「どうチームを育てるか」「どう組織を拡張するか」といった視点が求められます。
さらに、事業KPIに基づいた意思決定の経験も強みになります。経営層と連携しながら、技術面だけでなく事業視点での提案や改善を推進してきた経験は、CTO候補としての信頼性につながります。
スタートアップでは「開発現場との距離が近く、プレイヤーとしても動ける人材」、一方でメガベンチャーや中堅企業では「スケールに耐える組織設計と戦略立案ができる人材」が求められるなど、企業のフェーズによって求められる役割や強みは変わってきます。
自分の経験を棚卸ししながら、どのフェーズの企業にフィットするかを見極めることが、CTOを目指すうえでの第一歩です。ーラビリティを実現した経験や、経営層との合意形成を進めた経験が評価される傾向にあります。
CTOの課題と資質
CTOは、企業の中でも非常に大きな責任を担うポジションです。そのぶん、乗り越えるべき壁も多く、求められる素養は多岐にわたります。ここでは、CTOが直面しやすい課題と、それに対応するために必要な資質について解説します。
技術とビジネスのバランス感覚
新しい技術を導入することが常に正解とは限りません。たとえ魅力的な技術であっても、コストや収益性、チームの運用力を考慮しなければ、プロダクトの成功にはつながりません。「ビジネスを前に進めるための技術選定」ができる視点が必要です。
現場と経営、両方の視座を持つ
CTOはエンジニアチームと経営陣の両方と関わる立場にあるため、「技術的に正しいこと」と「事業にとって最善なこと」を常にすり合わせる必要があります。状況に応じて、スピードを優先すべきか、品質を担保すべきか、判断に迷う場面も多く、柔軟な意思決定力が求められます。
エンジニアの採用・定着
開発体制を整えるうえで、優秀なエンジニアの採用・育成・定着はCTOの重要なミッションの一つです。評価制度、働き方、開発環境など、チームがモチベーション高く働ける環境を整える力も問われます。
技術負債への対応
開発が進むにつれ、過去の技術選定が足かせになる場面も出てきます。リファクタリングや再設計を行うべきか、事業全体を見据えて判断しなければなりません。
これらの課題に向き合うためには、技術力だけでなく、経営感覚や対話力、そして俯瞰する視野が必要です。CTOとは「技術のプロ」であると同時に、「事業を動かす意思決定者」でもあります。
他のCxOとの違い
CTOの役割をより明確に理解するためには、他のCxO(経営幹部)との違いを押さえておくことが重要です。特に混同されやすいCOOやCIOとの違いについて見ていきましょう。
COO(Chief Operating Officer)との違い
COOは「最高執行責任者」として、営業、事業運営、カスタマーサポート、バックオフィスなど、会社の日々の業務を安定的に動かす責任者です。
一方CTOは、事業の将来を見据え、どんな技術を使い、どうプロダクトを進化させていくかを判断するポジションです。CTOの決定は、今というより「未来の競争力」に直結します。
COOが事業を“回す人”だとすれば、CTOは事業を“伸ばす技術の舵取り役”と言えるでしょう。
CIO(Chief Information Officer)との違い
CIOは、社内システムやITインフラ、セキュリティ、業務効率化などを担う「社内ITの責任者」です。目的はあくまで業務効率と安全性の向上であり、ユーザー向けプロダクトやサービス開発には関与しないこともあります。
一方でCTOは、プロダクト開発や技術戦略そのものをリードする役割です。事業の成長に直接かかわるポジションであり、守備範囲とミッションが大きく異なります。
CTOのキャリアパス
CTOは、エンジニアとしての経験を積み重ねたその先にあるポジションです。ただし、高い技術力だけでは不十分で、マネジメント力や経営視点、対話力といった複合的な力が求められます。ここでは、CTOに至るまでの一般的なステップを段階ごとに紹介します。
まずは、フロントエンド・バックエンド・インフラなど、いずれかの領域での開発スキルを磨きます。コードを書くだけでなく、パフォーマンス改善や仕様の最適化に積極的に関与することで、技術的視野を広げていきます。
次のステップは、チーム内での技術的なリーダーシップを担う立場です。設計方針の決定やコードレビュー、技術選定に関わるだけでなく、なぜその選択をするのかという「意図の言語化」が重要になります。
マネジメントのステージに進むと、メンバーの評価・育成、採用活動、進捗管理といった人と組織を動かす役割が加わります。プレイヤーでありながら、チーム全体の成果を最適化する「プレイングマネージャー」が求められます。
このフェーズでは、複数の開発チームを束ね、組織設計や戦略立案に深く関わる役割となります。技術と経営の“通訳”のような立場として、経営陣と対話しながら方針を定めていくことになります。
最終的にCTOに就任すると、企業の成長戦略やプロダクト戦略において、技術的な意思決定の最終責任者となります。組織内のエンジニアリング文化を育てるだけでなく、社外発信・採用ブランディング・IR(投資家向け情報)対応など、多面的な役割も求められます。
キャリアの各段階で求められる視座は変わっていきます。CTOを目指すには「今の自分がどのフェーズにいて、次に何を学ぶべきか」を意識することが大切です。
CTOの年収と他職種との比較
CTOの年収は、企業規模や事業フェーズ、技術領域、そしてその企業における役割によって大きく変わります。
ここでは、年収レンジの傾向と、他の技術系ポジションとの比較を解説します。
一般的なCTOの年収レンジ
エンジニアファクトリーが取り扱うCTO候補求人では、年収800万〜1,500万円程度がボリュームゾーンです。
具体的には以下のような傾向があります。
スタートアップ・中小企業:800万〜1,000万円前後
資金調達前や直後のフェーズでは、報酬よりもストックオプションや将来性を提示するケースも多くあります。
メガベンチャー・上場企業:1,200万〜1,500万円以上
技術組織が大きく、経営層としての役割が明確な場合には、年収水準も高く設定される傾向があります。
また、CTOクラスになると、年収の中には役員報酬・ボーナス・ストックオプションなどの変動報酬が含まれることが一般的です。そのため、表面的な数字以上に、中長期的な報酬設計を見ることが重要です。
他職種との年収比較
CTOは、他の技術系ポジションと比べても、責任範囲の広さに応じて報酬水準が高く設定されています。
- プロジェクトマネージャー(PM):平均600万円〜800万円
- VPoE(エンジニアリング責任者):800万円〜1,200万円
- CTO候補:900万円〜1,500万円以上
CTOには、技術的な専門性に加え、経営視点・意思決定力・対外的な信頼性といった要素も求められるため、報酬面にもその期待が反映されるかたちとなっています。
CTOに向いている人の特徴
CTOは「技術に強い人」がなるポジションと思われがちですが、それだけでは務まりません。求められるのは、技術・組織・経営の3つをつなぎ、事業全体に影響を与えるリーダーシップです。ここでは、CTOに向いている人に共通する特徴を紹介します。
技術を“手段”として捉えられる
技術そのものが目的にならず、「それを使って何を解決するか」「どんな価値を生むか」を考えられる人は、CTOに向いています。新しい技術に飛びつくよりも、「事業にとって意味のある技術」を見極める冷静さが求められます。
組織と人に関心がある
CTOはエンジニアチームを率いる立場である以上、「どう働くか」だけでなく「誰と働くか」「どう育てるか」にも目を向ける必要があります。
メンバーとの信頼関係、チーム文化の醸成、評価制度の設計といったテーマに取り組める人は、信頼されるCTOになりやすい傾向にあります。
俯瞰して意思決定できる
スピードと品質、投資とリターン、今と将来――常に相反する選択肢の中で最適な判断を下す必要があります。
その場の感覚ではなく、数値やリスク、経営判断を根拠に意思決定できる力が求められます。
経営との対話を恐れない
CTOは経営層との橋渡し役でもあります。ビジネス側の言葉を理解し、技術的観点に翻訳して伝える“通訳”のような役割を担うことも多いため、コミュニケーション力・共通言語化の力も重要です。
フリーランスエンジニアからCTOを目指すには
フリーランスとして技術力を磨いてきた方の中には、「より広い責任の中で力を試したい」「経営に関わってみたい」と考える方も少なくありません。実際、エンジニアファクトリーでもCTO候補の募集案件は多く扱われており、フリーランスの経験を活かして企業に参画するチャンスは十分にあります。
個人の技術力だけでは足りない
フリーランスとして優れた実績があっても、CTOになるためには「チームをどう動かすか」「技術でどう事業に貢献するか」といった視点が欠かせません。プレイヤーとしての力に加えて、組織と事業への関心が持てるかどうかが大きなポイントです。
小規模プロジェクトでマネジメント経験を積む
いきなりCTOを目指すのではなく、まずは小規模な開発チームで技術責任者やリードエンジニアを経験するのがおすすめです。スタートアップやベンチャー企業の技術顧問、業務委託でのPM兼エンジニアなども良い入り口になります。
0→1フェーズに関わる
プロダクトの立ち上げフェーズに関わる経験は、CTOへのステップとして非常に有効です。技術選定・初期設計・体制構築・ロードマップ策定といった要素は、のちの経営判断にも直結します。
経営陣との関係構築も視野に
経営会議に出る、事業計画に基づいて開発の優先順位をつけるなど、ビジネス側と対話する経験があると、CTO候補としての信頼が高まりやすくなります。エンジニア組織の言語だけでなく、「経営の言葉を理解できるかどうか」が、ひとつの分かれ目になります。
CTOに関するよくある質問(FAQ)
- CTOとVPoEの違いは?
-
CTO(Chief Technology Officer)は技術戦略やプロダクト全体の技術的意思決定を担う経営ポジションです。
一方、VPoE(Vice President of Engineering)は開発チームの組織運営に特化し、「どうチームを機能させるか」に責任を持つ立場です。CTOが「何をつくるか・どう技術で事業を支えるか」を考えるのに対し、VPoEは「その体制をどう作るか・どう回すか」に注力します。両者は補完関係にあります。
- CTOになるのにMBAや経営の知識は必要?
-
必須ではありませんが、あると役立ちます。CTOは経営会議に参加し、事業計画や予算、リスク判断などにも関わることがあるため、経営的な考え方や数字への理解が求められる場面が多くなります。現時点で知識がなくても、経営書を読んだり、他のCxOと定期的に対話したりするなど、日々の業務の中で少しずつ補っていくことは可能です。
- CTOが開発に手を動かす必要はありますか?
-
企業のフェーズによります。スタートアップや初期フェーズの企業では、CTOが自ら開発を行う「ハンズオン型」が一般的です。一方で、組織が成熟すると、技術戦略や経営調整に時間を割く「非ハンズオン型CTO」が求められる傾向にあります。
つまり、「手を動かすかどうか」よりも、「その企業で何を求められているか」を見極めることが重要です。
- CTO候補に求められるマインドセットは?
-
最も大切なのは、「技術で事業を前に進める」という視点です。「正しさ」より「実用性」や「運用可能性」を優先し、チームや経営と合意形成を重ねながら、最善の道を選べる人が評価されます。
また、最新技術を追うだけでなく、「なぜその技術を選ぶのか」「それを使うことで何が良くなるのか」を説明できる視座も必要です。 - CTOを目指すなら何から始めるべき?
-
最初のステップとしては、小さな開発チームでテックリードやEM(エンジニアリングマネージャー)としての経験を積むことが重要です。その中で、採用や評価制度、プロダクトロードマップの作成にも関わり、少しずつ組織や経営の視点を育てていきましょう。
まずは「開発以外のことにも関心を持つ」こと。それがCTOへの第一歩です。
開発以外の仕事に「関心を持てるか」「巻き込まれていけるか」が、CTOへの資質を判断するポイントになるでしょう。
フリーランス×CTOを目指すならエンジニアファクトリー

技術と経営の間に立ち、事業を前進させる存在。それがCTOというポジションの本質です。エンジニアファクトリーでは、CTO候補向けの非公開求人や、経営直下の技術責任者ポジションを多数取り扱っています。個人のスキルや価値観に合ったステージをご提案しますので、「いつかはCTOを目指したい」「まずは話を聞いてみたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
CTO(最高技術責任者)は、技術戦略の立案と実行、開発組織のマネジメント、経営陣との連携まで担う、極めて重要なポジションです。
単に技術力に優れているだけでなく、事業理解・対話力・組織運営力をバランスよく備えていることが求められます。
企業の規模やフェーズによって役割は変わるものの、「技術で事業を前進させる」ことがCTOに共通する使命です。
フリーランスとして経験を積んできた方にとっても、マネジメントや戦略に関わる機会を意識的に取り入れていくことで、CTOというキャリアは現実的な選択肢になります。