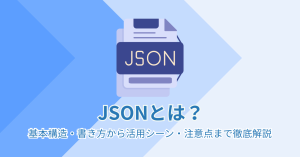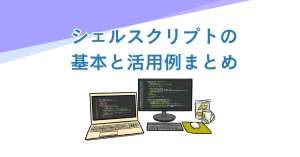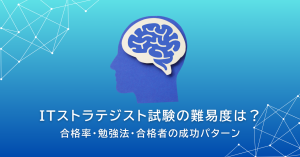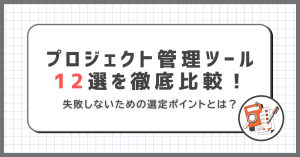多くのJavaエンジニア、特に学習を始めたばかりの方にとって、「Spring」と「Spring Boot」というフレームワークの違いはわかりにくいかもしれません。しかし、SpringとSpring Bootは世界中の多くのWebアプリケーションやシステムで採用されているため、双方の技術への理解が求められます。
この記事では、各フレームワークが誕生した背景から、具体的な機能、メリット・デメリット、そして実務での使い分けまでを比較・解説します。各フレームワークへの理解を深めて業務に活用したい方は最後までご覧ください。
Spring Frameworkとは?

Spring Frameworkは、Javaでエンタープライズ向けアプリケーションを開発するためのオープンソースフレームワークです。依存性注入(DI)やアスペクト指向プログラミング(AOP)などの仕組みにより、開発者は複雑な環境設定に煩わされず、ビジネスロジックの実装に集中できます。
Spring Frameworkの登場により、開発者はビジネスロジック、つまり「本当に作りたいものの実装」に集中できるようになりました。ここでは、Spring Frameworkについて、初心者にもわかりやすく解説します。
Spring Frameworkが誕生した背景
Spring Frameworkは、2000年代初頭、当時主流だったJava EE開発の複雑さを解消するために誕生しました。当時のJava EEは、一つの機能を作るために膨大なXML設定ファイルが必要で学習コストも高く、「EJBの冬の時代」と揶揄されるほど開発者の負担が大きかったのです。
この状況を打破するため、Rod Johnson氏はもっとシンプルで柔軟な開発を目指しました。特定の技術やサーバーに縛られない「POJO(Plain Old Java Object)」という普通のJavaオブジェクトをベースとしたプログラミングを推進し、開発者が煩雑な設定作業から解放される環境を整えました。これにより、
開発者は本来の目的であるビジネスロジックの実装に集中できるようになったのです。
Spring Frameworkの代表的な機能
Spring Frameworkは、Javaアプリケーション開発を包括的にサポートするための機能を提供しています。各機能はモジュール化されており、必要なものだけを選択して利用できるのが大きな特徴です。主要な機能は以下の通りです。
DI (Dependency Injection)
Springの中心にあるのがDI(Dependency Injection:依存性の注入)です。これは、クラス間の依存関係をコードに直接書き込むのではなく、外部の設定やコンテナに任せる仕組みで、部品同士の結合度を下げ、テストのしやすさや保守性を高めます。
AOP (Aspect-Oriented Programming)
次に、AOP(Aspect-Oriented Programming:アスペクト指向プログラミング)があります。ログ出力やトランザクション管理といった、アプリケーション全体で共通して必要となる処理を「横断的関心事」として切り出し、ビジネスロジックから分離して記述できるため、コードがシンプルに保たれます。
トランザクション管理
また、トランザクション管理もSpringの重要な機能の一つです。データベース操作において「すべて成功」か「すべて失敗」かを保証する原子性を担保し、整合性を維持します。
Springではアノテーションを付けるだけで高度なトランザクション制御を簡潔に導入できるため、エンタープライズ開発に欠かせない仕組みとなっています。
Spring MVC (Model-View-Controller)
さらに、Spring MVCはWebアプリケーション開発を支える代表的なモジュールです。処理(Model)、画面(View)、制御(Controller)を分離することで役割が明確になり、分業しやすく、変更や拡張にも強いアーキテクチャを実現します。
その他の機能
加えて、Springはデータアクセスを容易にする仕組みも提供しており、JDBCの複雑な記述を簡略化したり、HibernateやJPAといったORMとの統合をスムーズに行えます。
また、Spring Securityによる強力な認証・認可機能は、企業向けシステムで広く利用されています。さらに、メッセージングやWebサービス、バッチ処理などの統合機能も備えており、幅広い開発ニーズに対応可能です。
このようにSpring Frameworkは、依存性管理から横断的関心事の処理、データベースやセキュリティの統合までを一貫してサポートすることで、開発者がビジネスロジックに集中できる環境を整えています。
Spring Frameworkのメリット
Spring Framework最大のメリットは、高い「柔軟性」と「拡張性」です。必要な機能を組み合わせられるモジュール構造のため、プロジェクト要件に合わせた最適なカスタマイズが可能です。
DI(依存性の注入)により各部品の独立性が高まり、機能の追加や変更が容易になるため、長期的な保守・運用が前提の大規模システムに向いています。また、データベースアクセスやセキュリティなど、企業向けシステム開発に必要な機能が網羅されています。
Spring Frameworkのデメリット
Spring Frameworkのデメリットは、柔軟性の裏返しである「設定の複雑さ」です。開発を始めるまでの初期設定が煩雑で、データベース接続等をXMLやJavaConfigで手動で詳細に記述する必要があります。
このためフレームワークの深い知識が求められ、学習コストが高くなる傾向があります。多機能であるがゆえに、迅速さが求められる小規模な開発では、その設定の多さが逆に開発の足かせとなる可能性があります。
Spring Bootとは?
Spring Bootは、JavaのSpringアプリケーションを設定最小で迅速に開発・実行できるように設計されたオープンソースフレームワークです。
Spring Frameworkを基盤に、規約ベースの自動設定とスターター依存関係、組み込みサーバーなどで「Just Run」を実現します。
Spring Bootが登場した背景
Spring Bootは、Spring Frameworkが持つ「設定の複雑さ」や「高い学習コスト」といった課題を解決するために登場しました。
Spring Frameworkには多くのメリットがあるものの、Webアプリケーションを一つ作るだけでも、DispatcherServletの設定、XMLによるBean定義、TomcatなどのWebサーバーの準備といった、多くの「お決まりの設定」が必要でした。毎回手作業で設定する必要があり、開発者の負担となっていたのです。
そこで、「CoC(Convention over Configuration:設定より規約)」という思想を取り入れ、よく使われるであろう設定をあらかじめSpring Boot側で自動的に行ってくれる仕組みが考案されました。外部化設定(application.properties / application.yml)により環境差分も吸収できます。
# application.properties(例)
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost/test
spring.datasource.username=dbuser
spring.datasource.password=dbpass
# 多くの場合、ドライバのクラス名はクラスパス検出で自動設定されます
# spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.DriverSpring Bootの特徴
Spring Bootは、Spring Frameworkを基盤としながら、開発者の生産性を向上させるための特徴を持っています。これらの特徴を理解すれば、現代のJavaアプリケーション開発でSpring Bootが第一候補となる理由がわかるでしょう。各特徴について詳しく解説します。
自動コンフィギュレーション(Auto-configuration)
自動コンフィギュレーションは、クラスパス上のライブラリを検知し、必要となるであろう設定を自動で行う仕組みです。 例えばspring-boot-starter-webがあれば、Webアプリケーション用の設定が自動で有効になります。
スターターパッケージ(Starter Packages)
特定の機能開発に必要となるライブラリ群を一つにまとめた仕組みです。例えばWebアプリ開発ならspring-boot-starter-webを追加するだけで、関連ライブラリが一括で導入されます。
組み込みサーバー(Tomcatなど)
アプリケーション内にWebサーバー(Tomcat等)を内蔵する機能です。別途サーバーを用意せずとも、java -jarコマンド一つでアプリケーションを単独で起動できます。
Actuatorによる運用監視
実行中のアプリケーションの状態を監視・管理するための本番向け機能です。特別なコードなしに、ヘルスチェックやCPU・メモリ使用状況などの情報をHTTP経由で取得できます。
Spring Bootのメリット
Spring Boot最大のメリットは「開発スピードの速さ」です。自動コンフィギュレーションやスターターパッケージが面倒な初期設定や依存関係管理を不要にし、開発者はビジネスロジックに集中できます。
また、組み込みサーバーによりjava -jarコマンド一つでアプリを起動できるため、開発サイクルが高速化します。この迅速さはマイクロサービスやPoC(概念実証)、アジャイル開発といったモダンな開発スタイルに最適です。
Spring Bootのデメリット
Spring Bootのデメリットは「ブラックボックス感」です。多くの設定が自動化されるため、裏側で何が起きているかを把握しにくく、予期せぬ挙動の原因特定が困難な場合があります。
また、特殊で複雑なカスタマイズを行おうとすると、自動設定の仕組みが逆に障害となり、無効化するため余計な手間がかかることもあります。便利な自動化の裏返しとして、内部構造の深い理解が求められる場面がある点は注意が必要です。
Spring と Spring Boot の違い【比較表】
Spring FrameworkとSpring Bootの違いについて、以下の表にまとめました。
| 項目 | Spring Framework | Spring Boot |
|---|---|---|
| 設定方法 | XMLやJavaConfigによる手動設定が基本 | 自動コンフィギュレーションが中心、規約に基づき自動設定 |
| アプリ起動方法 | WARファイルをWebサーバーにデプロイする必要あり | 組み込みサーバーにより単独のJARファイルで実行可能 |
| 依存関係管理 | 必要なライブラリとバージョンを手動で管理 | スターターパッケージにより関連ライブラリを一括管理 |
| 運用・監視 | 自前で実装するか、外部ツールとの連携が必要 | Actuatorにより標準で豊富な監視機能を提供 |
| 開発スピード | 初期設定に時間がかかり、比較的遅い | 迅速な立ち上げが可能で、非常に速い |
| 学習コスト | 機能が多く設定も複雑なため、比較的高い | 基本的な使い方なら学習コストは低い |
Spring FrameworkとSpring Bootの単純な違いは、開発における「思想」です。
Spring Frameworkは開発者に最大限の柔軟性とコントロールを提供し、設定は基本的に手動で行います。システムの細部まで制御できますが、手間がかかります。
一方、Spring Bootは「設定より規約」を重視し、よく使われる設定を自動化して生産性を向上させています。依存関係管理がスターターで簡潔になったり、サーバー内蔵で起動が容易になったりと、開発者を定型作業から解放し、開発スピードを劇的に向上させる点に大きな違いがあります。
また、フレームワークの選定は開発規模に左右されます。
Spring Frameworkは大規模、Spring Bootは小~中規模向き
Spring Frameworkは、金融機関の基幹システムのような、要件が複雑で長期的な運用が前提の大規模システムに適しています。 きめ細やかな設定で独自の要件に対応できる柔軟性が強みです。
一方、Spring Bootは、新規Webサービスやマイクロサービスなど、迅速な市場投入が求められる小〜中規模開発に最適です。 立ち上がりの速さは、多数の独立したサービスを効率的に開発・管理するスタイルと相性が良いと言えます。
チーム体制・スキルセットの違い
さらに、チームのスキルセットや開発スタイルも重要な選定基準です。Spring Frameworkを使いこなすには、フレームワークへの深い理解を持つ経験豊富なエンジニアが揃っているチームが理想です。 全員が設定の意図を理解し、アーキテクチャを維持する必要があります。
一方、Spring Bootは規約に従い開発の進め方が標準化されるため、スキルレベルに差があるチームでも品質を保ちやすいです。 学習コストが低く、アジャイル開発のようにスピード感を持って進めたいチーム体制に適しています。
実務での使い分け
Spring FrameworkとSpring Bootには、実務において明確な使い分けが存在します。プロジェクトの要件や規模、将来的な拡張性などを考慮し、適切な方を選択しましょう。ここからは、Spring FrameworkとSpring Bootの使い分けを判断するための情報をお伝えします。
Springを使うべきケース
Spring Frameworkが真価を発揮するのは、大規模で、複雑な要件を持つエンタープライズシステムの開発です。長期間にわたる運用や保守が前提で、きめ細やかな設定や独自のカスタマイズが求められる場合に適しています。具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
Spring Framework を使うべきケース例
| ケース | 説明 | Spring Frameworkが向いている理由 |
|---|---|---|
| 大規模なモノリシックシステム | 金融機関の勘定系や大企業の基幹システムなど長期運用を前提とした大規模システム | 機能ごとに細かい設定やチューニングが可能で、独自のセキュリティ要件にも柔軟に対応できる |
| 複雑なレガシーシステムとの連携 | 古いシステムや特殊なプロトコルを持つ外部サービスと連携が必要な場合 | Bootの自動設定では難しいケースでも、低レベルから詳細に設定し柔軟に統合できる |
| 独自性の高いアーキテクチャ | プロジェクト独自の規約や特殊なライブラリ構成を採用する場合 | フレームワークをプロジェクトのルールに合わせて最適化できる柔軟性がある |
Spring Bootを使うべきケース
Spring Bootは、迅速な開発とデプロイが求められる、比較的小規模から中規模のアプリケーションに最適です。具体的なケースは以下の通りです。
Spring Boot を使うべきケース例
| ケース | 説明 | Spring Bootが向いている理由 |
|---|---|---|
| マイクロサービスアーキテクチャ | 小さなサービスを独立して構築・連携させる開発スタイル | サービスごとに迅速に開発・デプロイ可能、軽量で管理しやすい |
| 新規WebアプリケーションやAPI開発 | 新しいWebサービスやバックエンドAPIをゼロから開発する場合 | 初期設定なしですぐに開発開始でき、短期間で形にできる |
| PoC(概念実証) | 新しい技術やアイデアのプロトタイプ開発 | 「Just Run」で開発スピードを最優先できる |
| クラウドネイティブな開発 | クラウド環境やコンテナを前提にしたアプリケーション開発 | Docker等との親和性が高く、Actuatorで監視や運用をサポート |
実際の企業利用例
SpringとSpring Bootは、世界中の名だたる企業で採用されています。一般的に、比較的新しいWebサービス企業ではSpring Bootが、伝統的な大企業や金融機関ではSpring Frameworkが使われている、あるいは併用されている傾向が見られます。
例えば、動画ストリーミングサービスで有名なNetflixは、システムが多数のマイクロサービスで構成されているため、Spring Bootを採用していることで知られています。各サービスを迅速に開発・デプロイするという要求に、Spring Bootが完全に応えた形です。
一方で、日本の大手金融機関や通信キャリアなどの基幹システムでは、長年の運用実績と高いカスタマイズ性を理由に、Spring Frameworkをベースとしたシステムが稼働しています。
最新トレンドと選び方の指針
JavaとSpringを用いたエコシステムは、現在も進化を続けています。将来を見据えた技術を選定するには、技術のトレンドを把握し、最新バージョンの情報を把握しておかなければなりません。ここでは、最新トレンドと選び方の指針について詳しく説明します。
マイクロサービスやクラウド環境
マイクロサービスやクラウド環境において、Spring Bootは事実上の標準技術(デファクトスタンダード)となっています。 その理由は、独立したサービスを迅速に開発し、サーバー内蔵の実行可能ファイルとして単独でデプロイできる手軽さにあります。この特徴は、小さなサービスを多数連携させるマイクロサービスアーキテクチャの思想と完全に一致します。
また、Dockerによるコンテナ化やKubernetesでの管理が容易な点も強みです。さらにSpring Cloudと連携すれば、分散システム特有の複雑な設定管理やサービス間の連携もシンプルに実装でき、クラウドネイティブな開発を強力に後押しします。
大規模システム
金融機関の勘定系システムなど、厳密なデータ整合性が求められる大規模システムでは、Spring Frameworkの強みが活かされます。システムの隅々まで手動で制御できる高い柔軟性と、信頼性を担保できるからです。複雑な業務ロジックが絡み合う機能間の連携や、厳格なトランザクション管理は、全体を一つとして構築する方が実装しやすいのです。
自動化が進むSpring Bootのブラックボックス性は、障害発生時の原因究明が困難になるリスクも伴うため、システムの停止が許されないミッションクリティカルな現場では敬遠される場合もあります。
ハイブリッド利用
両者の長所を組み合わせる「ハイブリッド利用」も有効な選択肢です。
実務で最も多いのは、Spring Frameworkで構築された大規模な既存システムを維持しつつ、新機能だけをSpring Bootのマイクロサービスとして開発・追加するパターンです。 安定稼働する本体に影響を与えることなく、モダンな技術で迅速に価値を提供できます。
また、Spring Frameworkのプロジェクトにおいて、Spring Bootが持つ優れた依存関係管理の仕組みだけを取り入れ、ライブラリ管理を簡素化する活用法もあります。このように、プロジェクトの特性に応じた柔軟な組み合わせが、双方のメリットを最大化する鍵です。
最新バージョン
2025年現在、最新版はSpring Framework 6.xとSpring Boot 3.xで、いくつかの大きな変更点があります。
まず、Java EEからJakarta EEへ仕様が移行したことに伴い、パッケージ名が「javax.*」から「jakarta.*」に変わりました。次に、動作環境としてJava 17以降が必須となり、最新のJava言語機能やパフォーマンス改善の恩恵を受けられます。
さらに、GraalVMを利用したネイティブイメージへの対応が強化され、起動が高速でメモリ効率の良い実行ファイルの生成が可能になりました。
よくある質問(FAQ)
ここからは、Spring FrameworkとSpring Bootに関して、よくある質問について見ていきます。
- Spring BootでSpringの全機能は使える?
-
使用可能です。Spring BootはSpring Frameworkを内包しており、その設定を自動化・簡素化するためのラッパーと考えられるからです。Spring Bootを使っていても、必要であれば従来のXML設定やJavaConfigによる手動での詳細なカスタマイズも行えます。
- Springを学んでからSpring Bootを学ぶべき?
-
必須ではありませんが、Spring Frameworkを理解しておくと、Spring Bootの学習がスムーズになります。Spring Bootの自動設定が裏側で何をしているのかを理解できるため、問題が発生した際のトラブルシューティング能力が向上します。Spring Bootから始めて、必要に応じてSpring Frameworkを深掘りする学習方法も効果的です。
- Spring Bootだけ習得して実務で通用する?
-
はい、多くのWebアプリケーション開発の現場では、Spring Bootの知識だけで十分に通用します。 特に新規開発やマイクロサービス開発の求人では、Spring Bootが必須スキルとなっていることが多いです。ただし、長期的なキャリアを考えると、Spring Bootを入り口としつつ、その基盤であるSpring Frameworkの理解も深めていくことが理想的です。
- 企業での利用率はどちらが高い?
-
新規プロジェクトにおいては、Spring Bootの採用率が高い傾向にあります。開発スピードと生産性の高さから、ほとんどの新しいJavaプロジェクトで第一候補となります。一方で、既存システムの保守・運用という観点ではSpring Frameworkの需要も依然として高いです。全体としては、Spring Bootへの移行が進んでいる状況と言えます。

まとめ
本記事では、Spring FrameworkとSpring Bootについて、その背景から機能、実務での使い分けまでを解説しました。
結論として、「Spring Frameworkは柔軟で多機能な土台」であり、「Spring Bootはその土台を迅速かつ効率的に利用するための仕組み」と考えられます。Spring Frameworkは、きめ細やかな設定が可能で、大規模で複雑なシステムの構築に強みを持ちます。一方で、その自由度の高さから設定は煩雑になりがちです。
対するSpring Bootは、自動設定やスターターパッケージといった仕組みによって、煩雑さを解消し、容易にアプリケーションを構築できるように設計されています。どちらが優れているという単純な話ではないので、両者の得意分野を理解しておきましょう。
最終的にどちらの技術を選択するかは、システムの規模や複雑さ、開発チームが何を重視するか(柔軟性か、スピードか)によって決まります。プロジェクトの目的や開発スタイルに応じた最適なフレームワークの選択が、開発を成功に導くための重要な鍵となるのです。
ライター:にのまえ はじめ
・プロフィール
大手精密部品メーカーで社内SE・PGを経験。その後、国内のSIerに転職し生産管理システムの開発・導入・保守・運用を担当。現在は自らIT企業を立ち上げ、顧客企業のDX化やIT化による業務改善の支援を行っている。並行して企業サイトやWebメディアでライターとしても活動中。趣味は筋トレ・プロレス観戦。
Website:https://writer.yui-road.com/