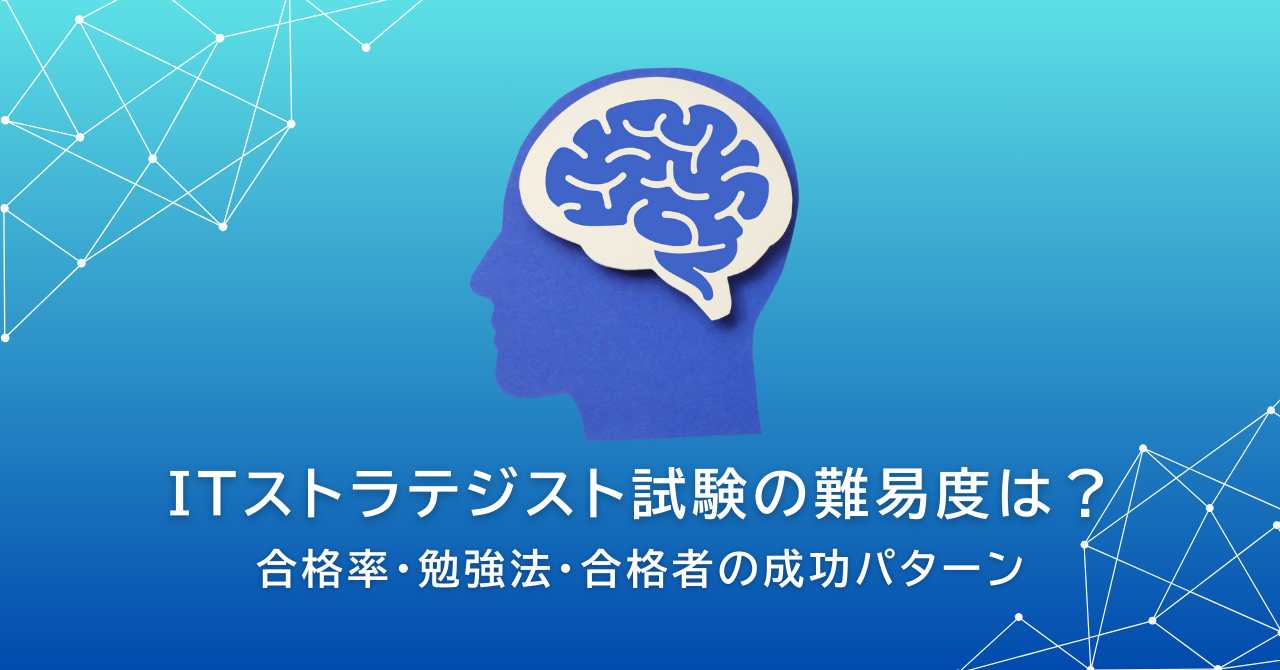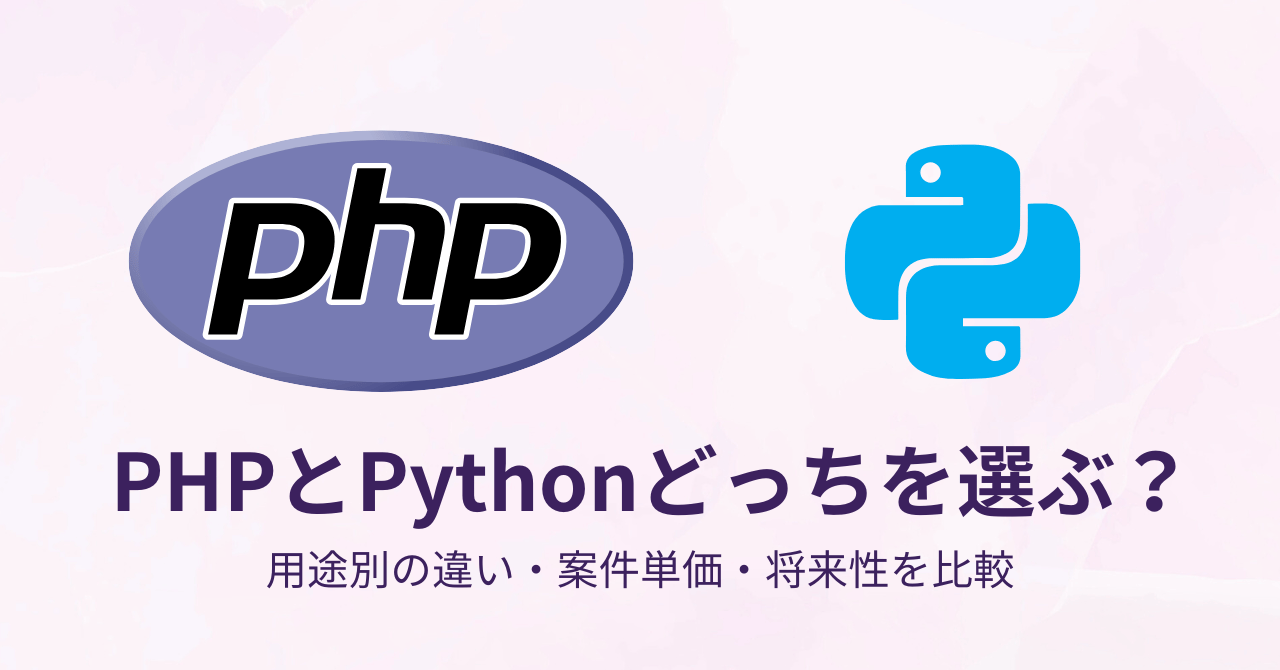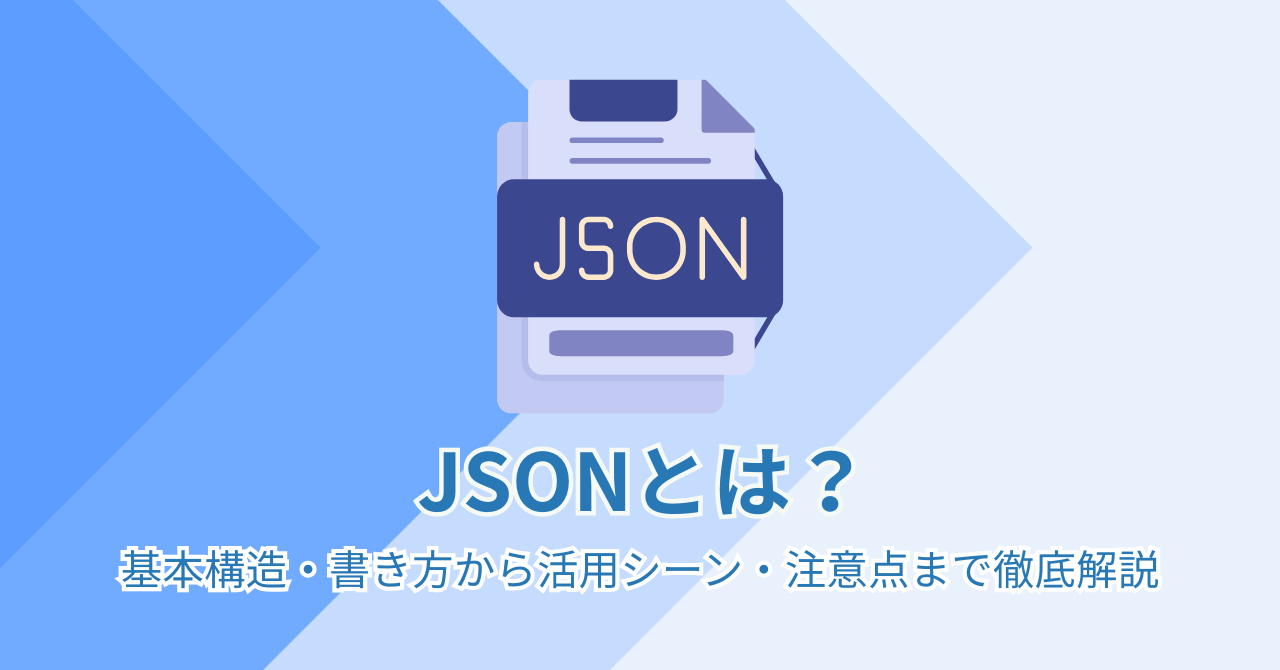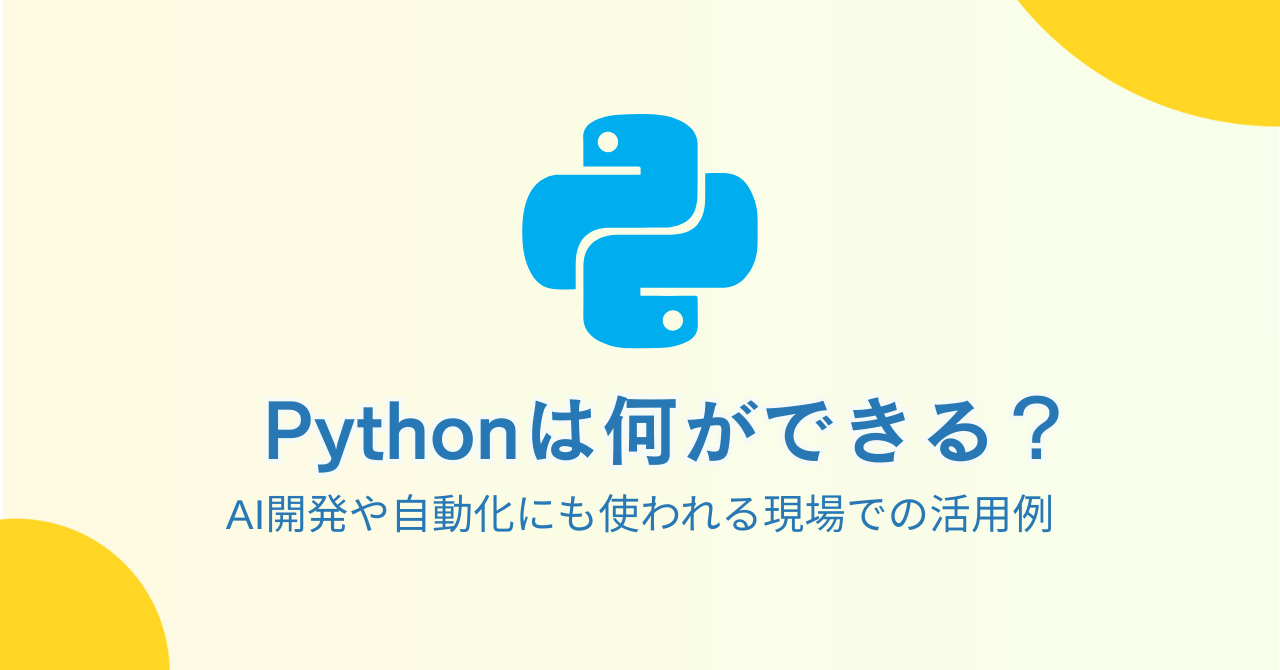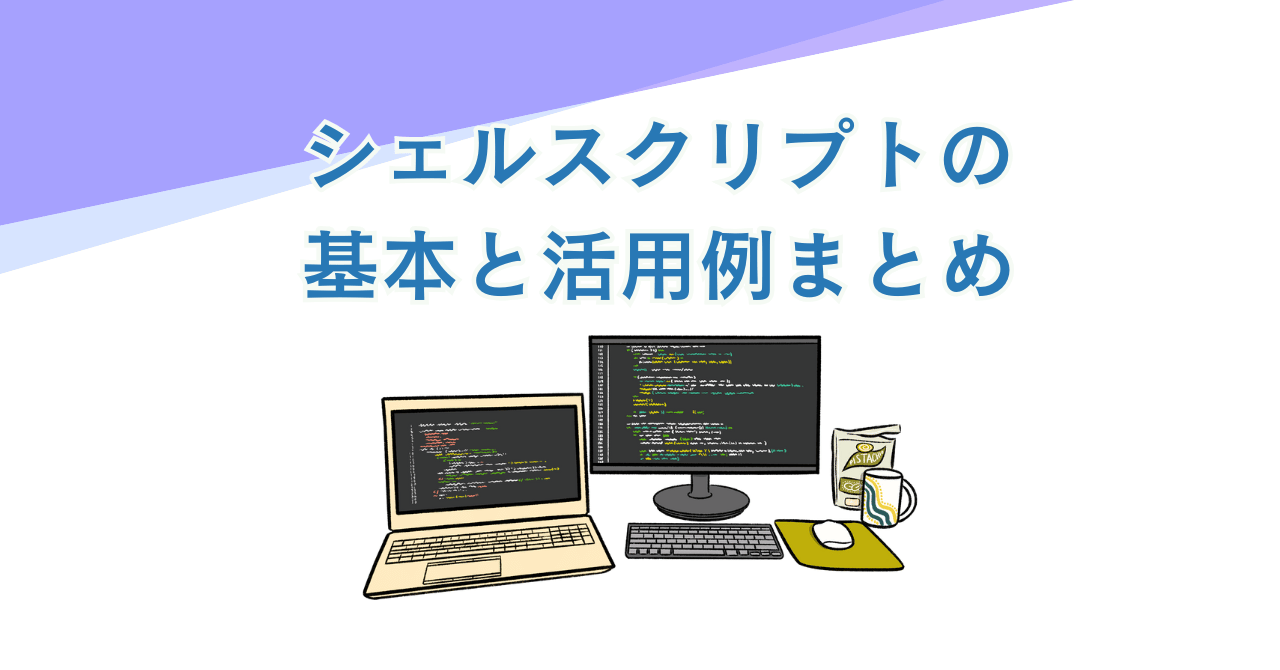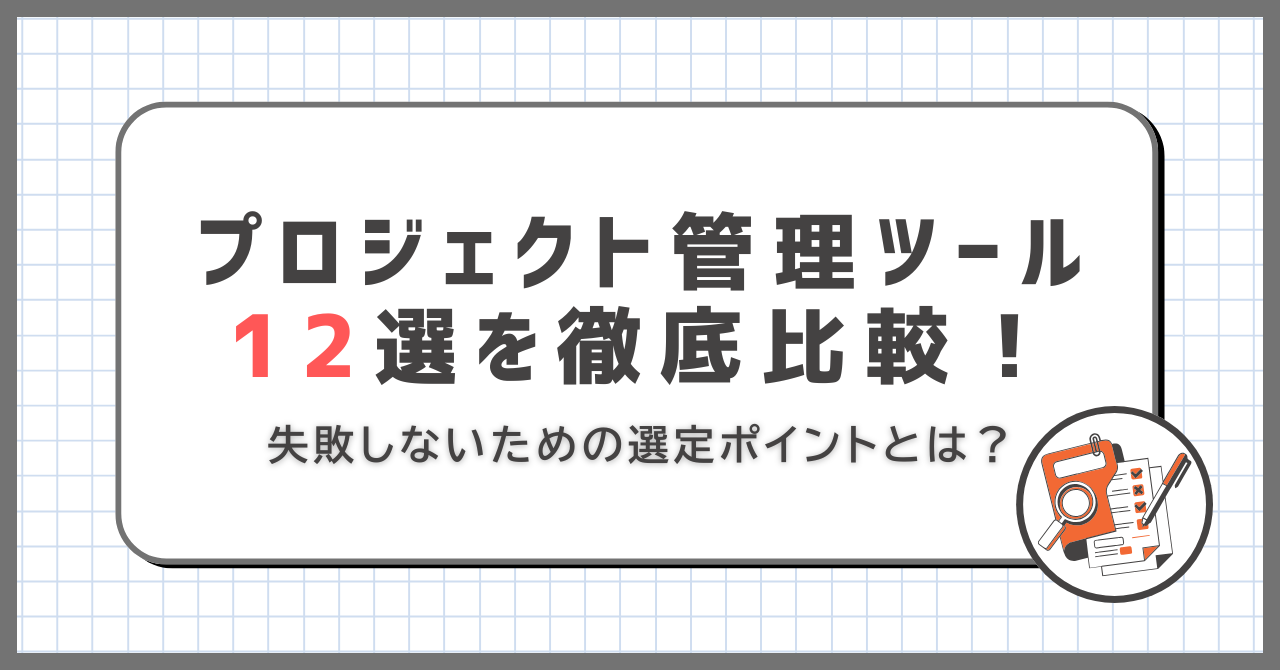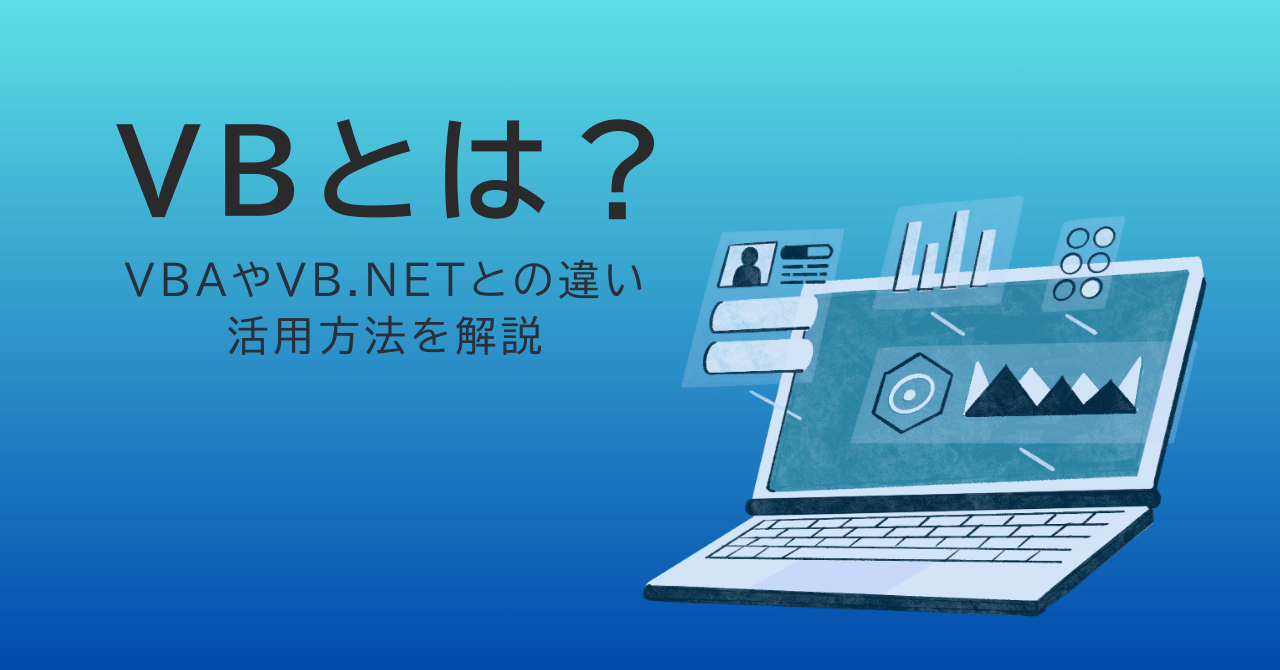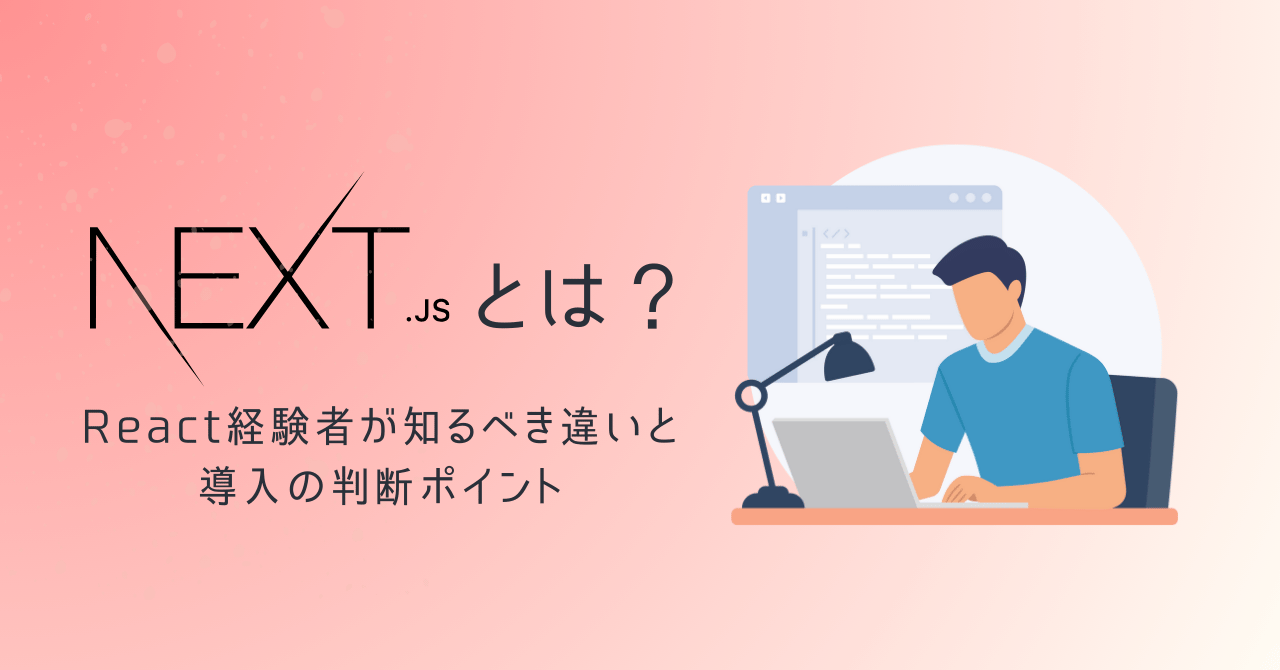ITストラテジスト試験の合格を目指しているものの、難易度や勉強方法がわからないと悩んでいる方もいるでしょう。ITストラテジストは、経営層や現場部門と連携し、ITを活用して企業の成長を支援する役割を担うため、難易度は高く試験内容も高度です。
この記事を読めば、ITストラテジスト試験の全体像から合格率、具体的な学習方法、そして資格取得後のキャリアまで理解できるでしょう。ITストラテジストは難関ですが、正しいアプローチで学習すれば必ず道は開けます。受験を検討されている方は、最後までご覧ください。

エンジニアファクトリーでは、フリーランスエンジニアの案件・求人をご紹介。掲載中の案件は10,000件以上。紹介する案件の平均年商は810万円(※2023年4月 首都圏近郊のITエンジニア対象)で、ご経験・志向に合った案件と出会えます。
簡単なプロフィール入力ですぐにサポートを開始。案件にお困りのITフリーランスの方やより高条件の案件と巡り合いたいと考えている方は、ぜひご登録ください。
ITストラテジスト試験の基本情報
ITストラテジスト試験とは、企業の経営戦略に基づいてIT戦略を策定し、ビジネスを成功に導く能力を証明する国家資格です。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する情報処理技術者試験の中でも、高度な知識とスキルが求められる「高度情報処理技術者試験」に位置づけられています。
ITストラテジストの受験資格に制限はなく誰でも受験可能です。受験料は7,500円(税込)で、2026年度からはCBT方式で試験が行われます。試験日程等の最新情報は、公式サイトにてご確認ください。
ほかの高度情報処理技術者試験、例えばプロジェクトマネージャ試験がプロジェクト管理の専門能力を問うのに対し、ITストラテジスト試験は事業企画や経営戦略といった、より上流の工程に焦点を当てている点が大きな違いです。
ITストラテジスト試験の難易度と合格率
ITストラテジスト試験は、高度情報処理技術者試験の中でも最難関の一つとして知られています。直近3年間の合格率は以下のとおりです。
- 2025年度:15.0%
- 2024年度:15.8%
- 2023年度:15.5%
合格率は例年14〜16%前後で推移しており、受験者の多くが不合格となる厳しい試験であるとわかります。また、プロジェクトマネージャ試験(例年14%前後)やシステムアーキテクト試験(例年15%前後)といった他の人気高度試験と同水準です。
ITストラテジスト試験が難しいとされる理由は、午後Ⅱで課される論文試験にあります。この論文試験では、単に知識を問われるだけでなく、自身の経験に基づいた具体的な事例を挙げ、論理的かつ説得力のある文章を2時間で3000字程度記述しなければなりません。深い洞察力と実践的な経験、高度な文章構成力が必要とされるため、多くの受験者にとって最大の壁となっています。
試験の出題範囲と形式
ITストラテジスト試験は、1日で4つの試験区分があり、問われる能力や対策方法が異なります。午前中は基本的なIT知識を問う選択式の問題、午後はより実践的な思考力や記述力が求められる問題が出題され、長丁場の試験を乗り切るための集中力と体力も必要です。各試験区分の特性を正しく理解し、それぞれに合った学習計画を立てましょう。
ここでは、午前Ⅰ、午前Ⅱ、午後Ⅰ、午後Ⅱの各試験の出題内容と形式を、詳しく解説します。
午前Ⅰ試験
午前Ⅰ試験は、ITに関する基礎知識を幅広く確認するための試験で、応用情報技術者試験の午前試験と同レベルの知識が問われます。出題形式は四肢択一の選択問題で、テクノロジ系、マネジメント系、ストラテジ系と、ITに関する全ての分野から出題されるのが特徴です。
出題される問題の多くが、過去に出題された問題の再利用または類似問題であるため、過去問題の演習で対策するのがおすすめです。市販の過去問題集やオンラインの学習サイトを利用して、少なくとも過去5〜10年分の問題を繰り返し解き、安定して高得点を取れるようにしておきましょう。
また、応用情報技術者試験に合格している場合や、ほかの高度情報処理技術者試験に合格または午前Ⅰ試験で基準点を獲得した場合、その後2年間は午前Ⅰ試験が免除される制度もあります。
午前Ⅱ試験
午前Ⅱ試験は、ITストラテジストとしての専門性を問う試験であり、経営戦略やIT戦略に関する深い知識が求められます。具体的には、企業の経営層が関わる以下のようなテーマが中心となります。
- 事業戦略の策定
- ビジネスモデルの分析
- ITガバナンス
- システム企画
- 法務・コンプライアンス
午前Ⅱ試験を突破するためには、用語の暗記だけでは不十分です。「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉一つをとっても、定義だけでなく、なぜ企業にとって必要なのか、どのような手法で推進するのかといった背景まで理解しておく必要があります。
学習方法としては、まずは、参考書を精読して各用語の概念を深く理解しましょう。さらに、各知識が実際のビジネスシーンでどのように活用されているのかを、企業の事例などを通じて学習することが求められます。
午後Ⅰ試験
午後Ⅰ試験は、長文の事例問題を読み解き、設問に対して的確な記述で解答する能力が問われる試験です。出題形式は記述式で、複数の大問の中から規定の問題数を選択して解答します。文章量が多く、制限時間もタイトであるため、高度な読解力と情報処理能力が不可欠です。
試験対策として重要なのは、問題文を要約する練習の繰り返しです。たとえば、ある企業のITシステムに関する課題が書かれた文章を読み、「誰が」「何に」「なぜ」困っているのかを短い文章でまとめる訓練を行います。
さらに、IPAが公開している過去問題の解答例を参考にし、どのような視点で、どの程度の具体性で解答すれば評価されるのかという「解答の型」を掴むことが合格への鍵となります。
午後Ⅱ試験
午後Ⅱ試験は、経営戦略やIT戦略をテーマとした論文試験です。提示された3つのテーマから1つを選択し、自身の業務経験や知見に基づいて、2時間で3000字程度の論文を作成します。午後Ⅱ試験で問われるのは、主に以下の能力です。
- 課題に対する深い洞察力
- 論理的な思考力
- 説得力のある文章構成力
効果的な対策としては、自分の経験をベースに書けるテーマを見極めましょう。たとえば、過去に携わったプロジェクトの中から、テーマに結びつけられる経験を洗い出し、論文の「ネタ」として整理しておきます。
その上で、序論・本論・結論といった論理展開の「型」を事前に決め、それに沿って論文を書き上げる練習を繰り返します。合格レベルの論文に仕上げるために、第三者に添削を依頼し、客観的なフィードバックを得るのもおすすめです。
ITストラテジストを取得するメリット
ITストラテジストを取得すると、エンジニアとしてのキャリアに計り知れない価値をもたらします。単に専門知識を証明するだけでなく、キャリアアップや年収向上、さらにはより上流のポジションへの道を開き、IT戦略の専門家としての市場価値を向上させる武器となるでしょう。
ここでは、資格取得がもたらすメリットを「キャリアへの影響」「スキルの証明」「キャリアチェンジ」という3つの視点で詳しく解説します。
キャリアへの影響(昇進・昇格・年収アップ)
ITストラテジスト資格は、キャリア形成を有利にします。多くの企業では、この資格を高度な専門性を持つ人材の証として高く評価し、昇進や昇格の重要な判断材料としています。管理職への昇格条件として高度情報処理技術者資格の保有を掲げている企業や、資格手当や報奨金制度を設けている企業も少なくありません。
たとえば、システム開発の現場でリーダーを務めるエンジニアが資格を取得すれば、技術力に加えて経営視点も持ち合わせていると評価され、プロジェクトマネージャーやITアーキテクトといった上位職への道が拓けます。
さらに、転職市場においても高く評価されており、履歴書に「ITストラテジスト」と記載すれば、IT企画部門や経営企画室といった、事業の中核に近いポジションへの転職が有利に進むでしょう。結果として、大幅な年収アップを実現するケースも珍しくありません。
IT戦略策定スキルの証明
ITストラテジスト資格の取得は、企業の経営課題を深く理解し、IT戦略を策定・提案できる能力を客観的に証明するのに有効です。エンジニアが経営層や経営企画部門と対等に渡り合うための「共通言語」を習得している証明にもなります。ITストラテジストは、IT投資が事業にどのように利益をもたらすかという問いに対して、論理的かつ具体的に回答できるスキルを持つ人材です。
たとえば、新しいシステムの導入を提案する際に、単に「最新の技術を使っているから」という説明では経営層は納得しません。ITストラテジストは、「システム導入により、3年後には売上が10%向上し、コストを5%削減できる見込みです」など、経営的な視点から説明できるため重宝されます。
このような提案力は、社内での信頼を高め、大規模で重要なプロジェクトを任されるきっかけとなるでしょう。
コンサル・マネジメント職への展望
ITストラテジスト資格は、ITコンサルタントやCIO(最高情報責任者)、CTO(最高技術責任者)といった、専門性の高いコンサルティング職やマネジメント職へのキャリアチェンジを目指すうえで重要です。技術的なバックグラウンドを持ちながら、経営戦略でも企業を支援できる人材であると証明するからです。
事業会社で経験を積んだエンジニアがITストラテジストを取得し、ITコンサルティングファームへ転職するケースは多く見られます。コンサルタントとして、クライアント企業の経営課題を分析し、ITを活用した解決策を提案する業務は、まさにITストラテジストに求められる能力です。
また、企業の情報システム部門でも、資格保有者は部門責任者やCIO候補として高く評価されます。ITを駆使して企業全体の競争力を高めるという重要なミッションを担う、やりがいのあるキャリアパスが開けるでしょう。
合格に必要な勉強時間と学習計画
ITストラテジスト試験の合格に必要な勉強時間は、とくに応用情報技術者試験などの関連資格の保有状況によって大きく異なります。一般的に、応用情報技術者資格の保有者など、ITの基礎知識が身についている方で200〜300時間程度、IT分野の学習が初めての初学者であれば500〜600時間以上の学習が必要とされています。
いずれの場合も、長期的な視点で学習計画を立て、継続的な取り組みが合格の絶対条件です。以下に、試験日から逆算した半年間(6ヶ月)の学習スケジュール例を紹介します。
6ヶ月前〜4ヶ月前(基礎固め・インプット期)
この時期は午前試験対策に集中し、初学者は応用情報技術者試験レベルの参考書でIT基礎知識を習得し、資格保有者は午前Ⅱの経営・システム戦略関連用語の理解を深めましょう。週末に参考書を読み、平日の隙間時間に過去問題を解くのが効果的です。
3ヶ月前〜2ヶ月前(応用力養成・アウトプット期)
インプットした知識を実践的なスキルに変換する期間です。午後I試験対策として過去問を解き、要点をまとめる練習を始めます。午後IIの論文対策として、業務経験の棚卸しを行い、論文に使える「ネタ」を複数準備します。
1ヶ月前〜試験直前(総合演習・直前期)
本番を想定して過去問を全区分(午前Ⅰ〜午後Ⅱ)通しで解く練習を繰り返します。とくに午後Ⅱの論文は時間を意識して書き上げる訓練が不可欠です。既に使用した教材の復習と間違えた問題の原因分析に集中し、体調管理も万全に行い本番に備えましょう。
上記の計画を参考にして、ご自身の得意・不得意分野やライフスタイルに合わせて、柔軟に調整してください。
ITストラテジスト試験の効率的な勉強方法
ITストラテジスト試験は出題範囲が広く、各試験区分で求められるスキルも異なるため、やみくもに学習しても合格は困難です。合格を勝ち取るには、各試験の特性を理解し、最適で効率的な勉強方法を実践する必要があります。
ここでは、午前Ⅰ、午前Ⅱ、午後Ⅰ、午後Ⅱの各試験区分に分け、合格につながる効果的な学習方法を具体的に解説します。限られた時間で最大の学習効果を得るための参考にしてください。
午前Ⅰ試験の勉強方法
午前Ⅰ試験の対策で効果的なのは、過去問題の演習です。ITストラテジストの試験は出題範囲が広い一方で、過去に出題された問題がそのまま、あるいは少し形を変えて再出題されるケースが多いからです。
多くの合格者は、オンラインで利用できる過去問学習サイトやスマートフォンのアプリを活用し、通勤時間などの隙間時間を使って学習を進めています。
まずは、直近5年分の過去問題を一通り解いてみましょう。間違えた問題や理解が曖昧な分野を特定し、参考書で重点的に復習します。そして、再び過去問を解くというサイクルを繰り返します。
目標は、常に9割以上の正答率を安定して出せる状態です。知識をインプットするだけでなく、問題を解くというアウトプットを繰り返して解答スピードと正確性を向上させましょう。
午前Ⅱ試験の勉強方法
午前Ⅱ試験は、ITストラテジストとしての専門知識、とくに経営戦略やシステム戦略の分野が問われます。専門用語の表面的な暗記にとどまらず、背景や意味を自分の言葉で説明できるレベルまで深く理解しなければなりません。出題の多くがストラテジ系に集中しているため、この分野を重点的に学習しましょう。
効果的な学習方法は、体系的にまとめられた参考書を熟読し、全体像を掴むことです。次に、各章の重要用語について、どのような経営課題を解決するために使われるのかを意識しながら学習を進めます。
さらに、学習した用語を使って、最近のIT関連ニュースや企業のDX事例を分析してみるのも良い訓練になります。実践的な学習を通じて、単なる知識を「使える知恵」に昇華できれば、応用力が問われる問題にも対応できるでしょう。
午後Ⅰ試験の勉強方法
午後Ⅰ試験は、長文の事例問題から要点を的確に抽出し、簡潔な文章で解答する記述力が求められます。試験対策で効果的なのは、問題文を数十文字程度で要約する練習です。複雑な文章の中から核心部分を見つけ出す読解力と、簡潔に表現する力が養われます。時間を計りながら行えば、本番の厳しい時間制約に対応する力も身につきます。
さらに、IPAが公開している解答例や採点講評の分析も不可欠です。どのようなキーワードが含まれている場合に評価されるのか、どのような論理構成が求められているのかといった「解答の型」を学びましょう。
最初は解答例の書き写しから始め、徐々に自分自身の言葉で再現できるように練習を重ねます。出題者が何を求めているのかを正確に把握し、得点に直結する解答を作成するスキルを習得できます。
午後Ⅱ試験の勉強方法
午後Ⅱの論文試験は、多くの受験者が苦労する区分であり、事前の準備が合否を左右します。最も重要な対策は、自身の業務経験をベースに、事前に論文の「骨子」を複数パターン用意しておくことです。
論文のテーマを選ぶ際は、必ず自分の言葉で具体的に語れる経験と結びつけられるものを選びましょう。その上で、「背景・課題」「解決策の策定」「実行と評価」「今後の展望」といった、論理展開の「型」を決めて書く練習を繰り返します。
書き上げた論文は、可能であれば予備校の添削サービスを利用したり、経験豊富な上司や同僚に読んでもらったりして、客観的なフィードバックを受けましょう。品質向上につながります。地道な準備が、本番での自信と合格へと結びつくのです。
合格者が実践している勉強法と工夫
ITストラテジスト試験のような難関資格では、合格者の成功体験や失敗談から学ぶことが有益です。とくに、最大の壁である午後Ⅱの論文試験をどう乗り越えたのか、また多忙な業務の中でどのように勉強時間を確保したのかといった具体的な工夫は、大きなヒントとなるでしょう。
ここでは、合格者の体験談を基にした「成功パターン」と、避けるべき「失敗例」を紹介します。
成功パターン① 論文対策は「自分だけのネタ帳」を作る
午後Ⅱの論文試験では、与えられたテーマに沿って 自分の業務経験を論理的なストーリーにまとめる力 が問われます。合格者の多くが取り入れているのが「ネタ帳」の作成です。
過去の経験からテーマになりそうな事例を洗い出し、「課題」「解決策」「成果」の3点で整理しておきます。例えば、在庫管理システム導入といったシチュエーションでは、以下
課題
旧システムでは販売実績データしか扱えず、需要予測が不正確で過剰在庫や欠品が頻発していた。その結果、在庫コストが高騰し、販売機会損失も発生していた。
解決策
POSデータと気象情報を組み合わせた需要予測アルゴリズムを設計し、新しい在庫管理システムを導入。さらに運用フローを改善し、営業部門とも連携できる体制を整備した。
成果
POSデータと気象情報を組み合わせた需要予測アルゴリズムを設計し、新しい在庫管理システムを導入。さらに運用フローを改善し、営業部門とも連携できる体制を整備した。在庫コストを20%削減できた
ここまで掘り下げて書いておけば、本番で出題される「業務改善」「新技術の活用」「システム導入時の課題対応」といったテーマにも、自分の経験を当てはめて論理的に展開できるようになります。
成功パターン② 勉強時間は「スキマ学習」を習慣化する
忙しい社会人にとって、まとまった勉強時間を確保するのは難題です。合格者がよく挙げる工夫は、日常生活に学習を組み込む「スキマ学習」です。出社前の1時間や通勤電車内の30分など、小さな時間を積み重ねて学習することで、継続的にインプットと演習を進められます。
避けたい失敗例
よくある失敗は「文字数稼ぎに気を取られて設問の趣旨から外れる」ことや、「時間配分を誤って論文を書き切れない」ことです。これを防ぐには、事前に制限時間内で論文を書き上げる練習を繰り返すことが欠かせません。
| 失敗パターン | 内容・具体例 |
|---|---|
| 文字数稼ぎで趣旨から外れる | 背景説明や一般論ばかりで、設問が求める「課題解決のプロセス」に触れられていない |
| 時間配分を誤る | 結論まで書けず「課題提示」で終わり、大幅減点につながる |
| 具体例が抽象的すぎる | 「効率化した」「調整した」など曖昧で、成果が伝わらない |
| 経験を盛り込みすぎる | 複数のプロジェクトを詰め込み、一貫性がなくなる |
| 文体が統一されていない | 口語表現や箇条書きを乱用し、論文らしさが損なわれる |
これらは事前に頭に入れておき、演習後の振り返りで確認する習慣をつけると効果的です。特に「趣旨逸脱」と「時間配分」は致命的になりやすいため、練習段階から意識して修正しておきましょう。
どんな人におすすめ?ITストラテジスト試験の適性
ITストラテジスト試験は、IT技術者として経営的な視点も持ちたいと考える人にとって価値のある資格です。とくに、企業のIT戦略をリードする立場や、ITで顧客の経営課題を解決したい人におすすめします。
ITストラテジスト試験は、経営層やCIOを目指すエンジニアにとって必須の資格です。現場での技術経験に加え、試験で得られる経営戦略や財務の知識は、技術と経営を結びつけるうえで不可欠です。資格の取得により、経営会議での影響力が増し昇進につながるでしょう。
次に、ITコンサルタントを志望する人にとっても適しています。ITを活用してクライアントの経営課題を解決する能力を客観的に証明するからです。クライアントからの信頼を得やすくし、大規模なプロジェクトへの参加機会を広げます。
さらに、事業会社の情報システム部門の責任者や候補者には、ITガバナンス強化や攻めのIT投資戦略立案につながるこの資格が強く推奨されます。企業全体の競争力向上に貢献できるでしょう。
フリーランスの案件探しはエンジニアファクトリー

ITストラテジストの学習は「戦略思考の言語化」と「経験の棚卸し」が要。これはそのままキャリア設計にも直結します。もし「どの業界・役割で強みを活かすか」「学習と実務をどう結びつけるか」で迷いがあれば、エンジニアファクトリー(EF)の無料キャリア面談で一度整理しませんか。
面談では、
- 経験の棚卸し:午後Ⅱの“ネタ帳”発想で職務経歴を構造化
- 市場観点の助言:いま狙える職種・単価帯・必要スキルの可視化
- 案件提案:上流(企画・PM/PMO)~技術特化まで、学習テーマと噛み合う参画先を提案
- 学習ロードマップ:試験合格と実務スキルを両立する計画を共同作成
「今の延長で良いのか」「上流へ踏み出すべきか」を、第三者と対話すると輪郭がはっきりします。情報収集だけでもOK。まずは気軽にご相談ください。あなたの“戦略”が、キャリアというプロジェクトを加速させます。
まとめ
この記事では、ITストラテジスト試験の基本情報から難易度、具体的な勉強方法、資格取得のメリットに至るまで解説しました。ITストラテジスト試験は、合格率が15%前後と非常に高い難易度であるものの、取得すれば得られる価値は非常に大きい資格です。
試験の最大の鍵は、経営とITを結びつけて考える戦略的思考力と、論文で表現する論理的記述力です。一朝一夕の対策では歯が立ちませんが、自身の経験を棚卸しし、論理の型に沿って書く練習を計画的に積み重ねれば、必ず合格レベルに到達できます。また、午前試験は過去問演習、午後Ⅰ試験は要約練習と、各試験区分の特性に合わせた効率的な学習の継続も大切です。
資格を取得すれば、昇進や年収アップだけでなく、ITコンサルタントやCIOといったキャリアパスも視野に入ります。本記事で紹介した勉強法を参考に、ぜひ挑戦してみてください。あなたのキャリアを、新たなステージへと引き上げる絶好の機会となるはずです。