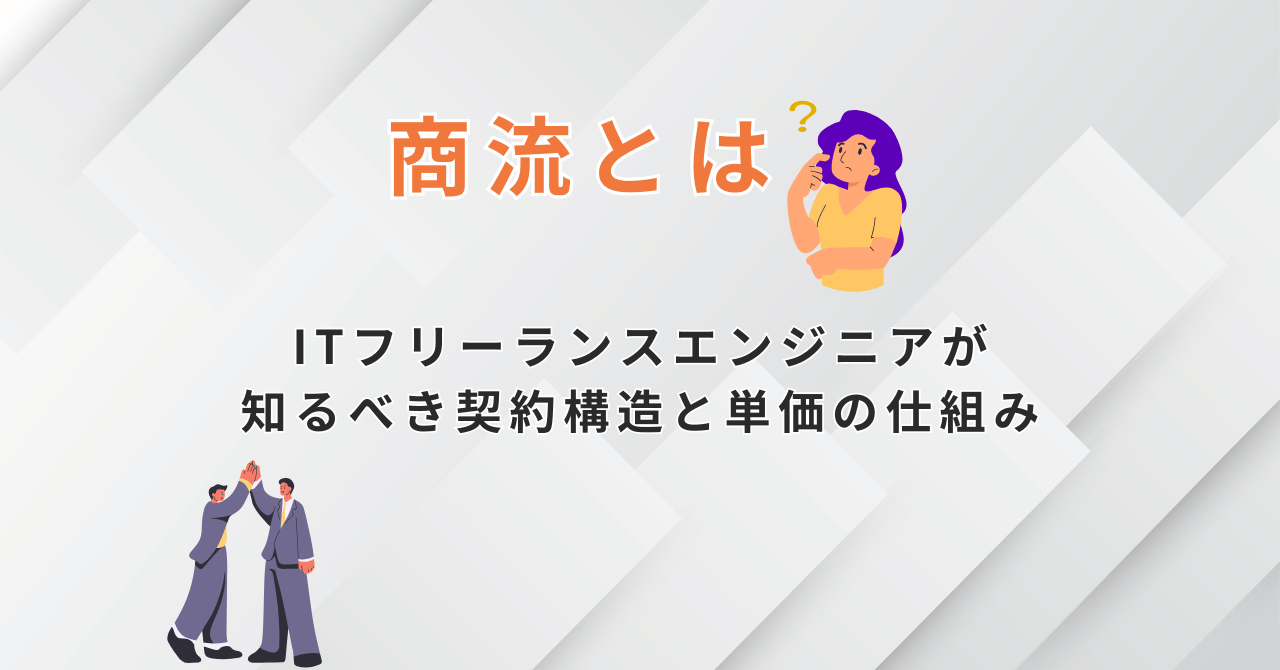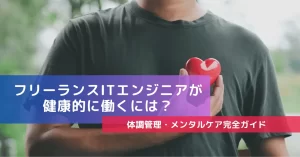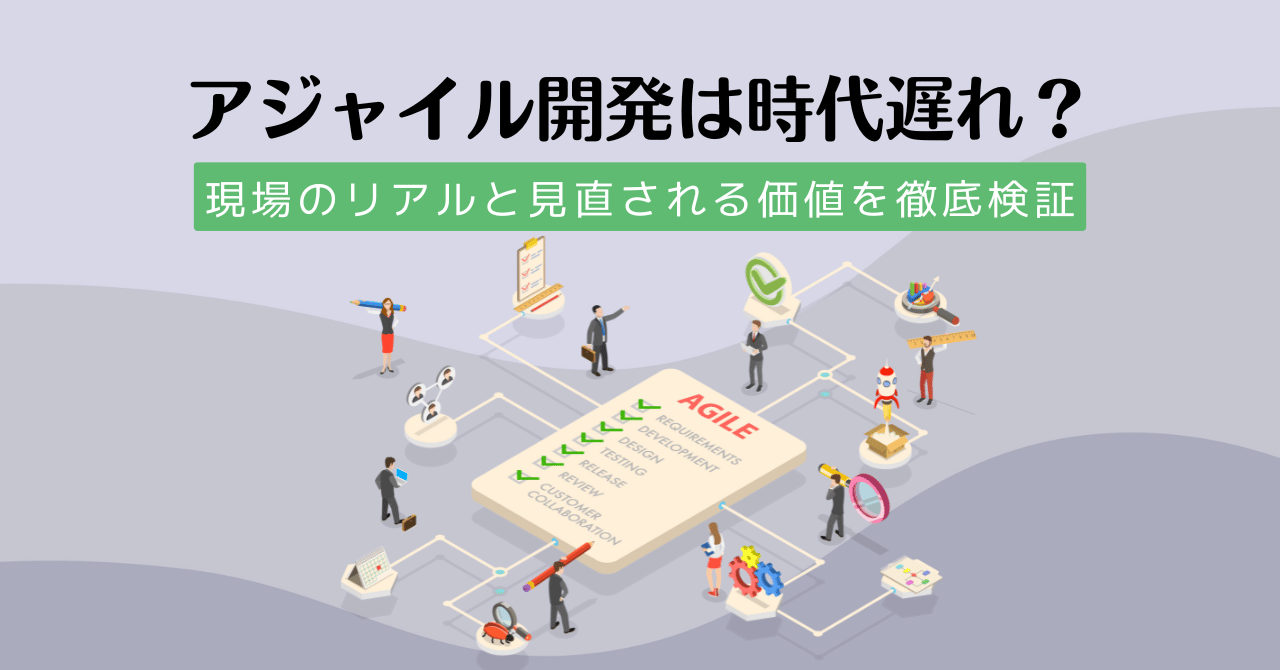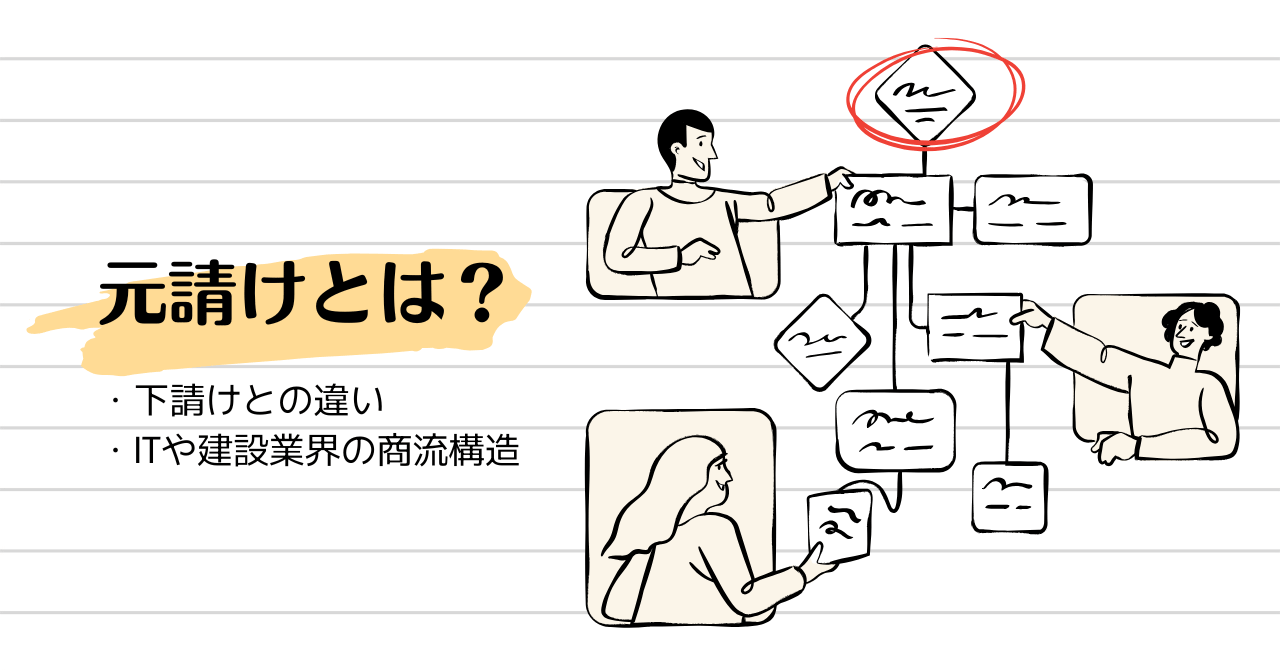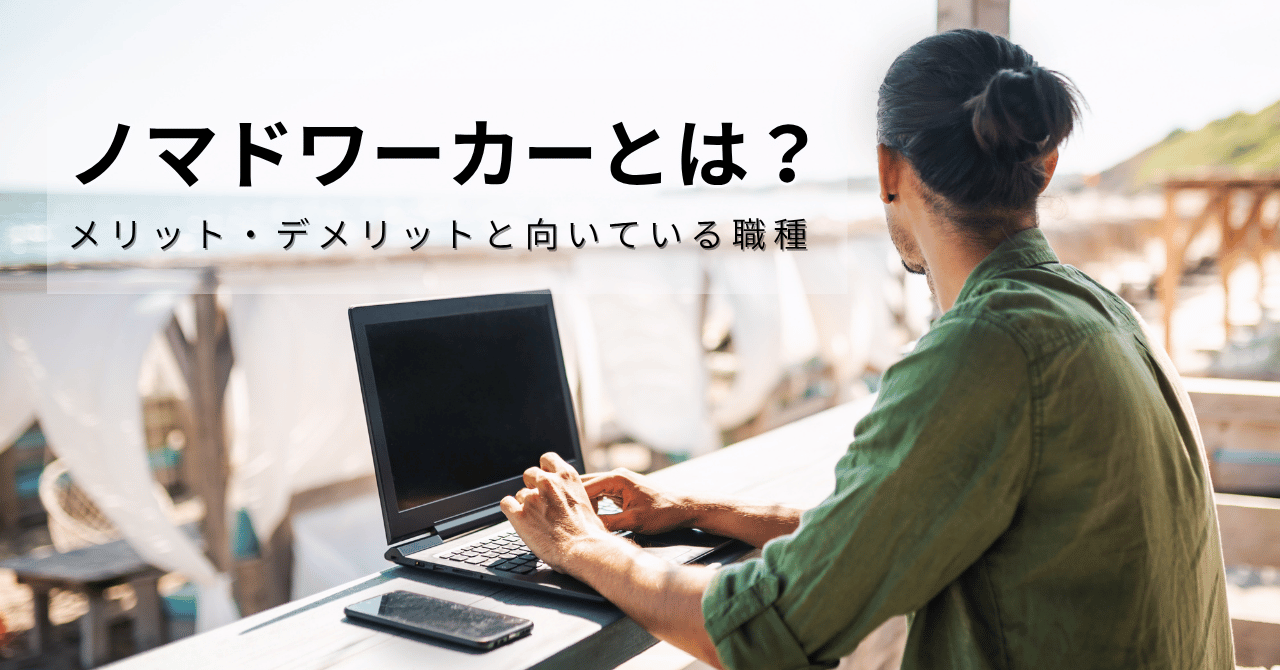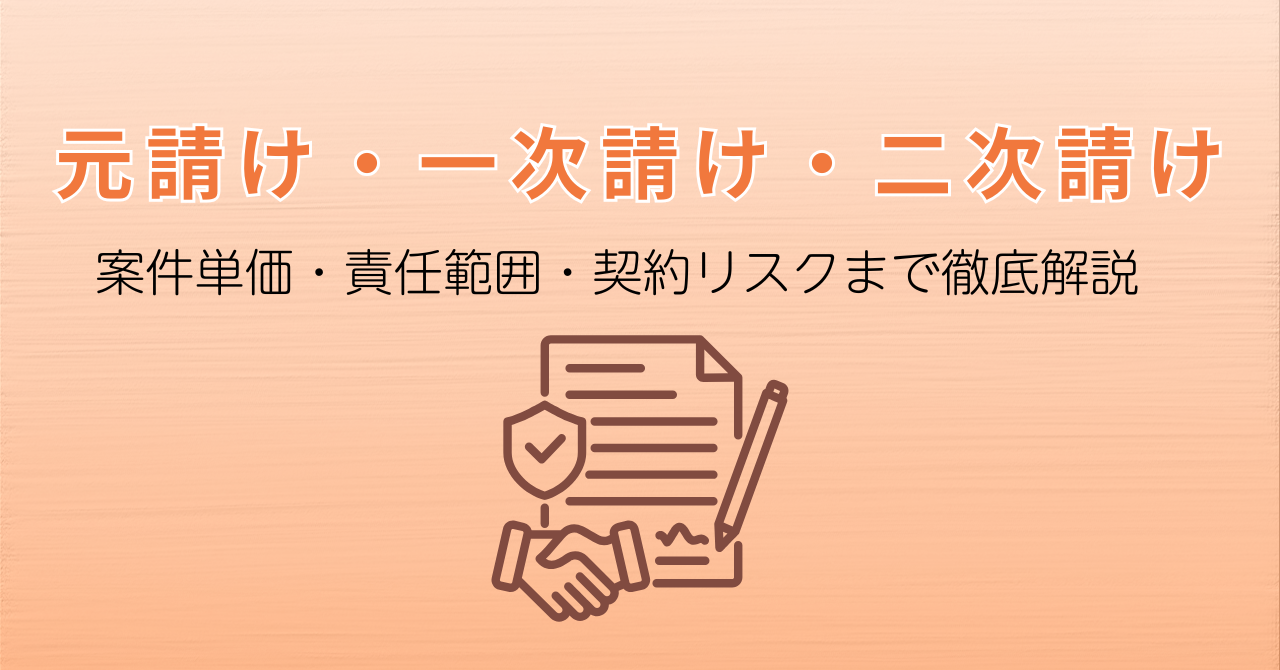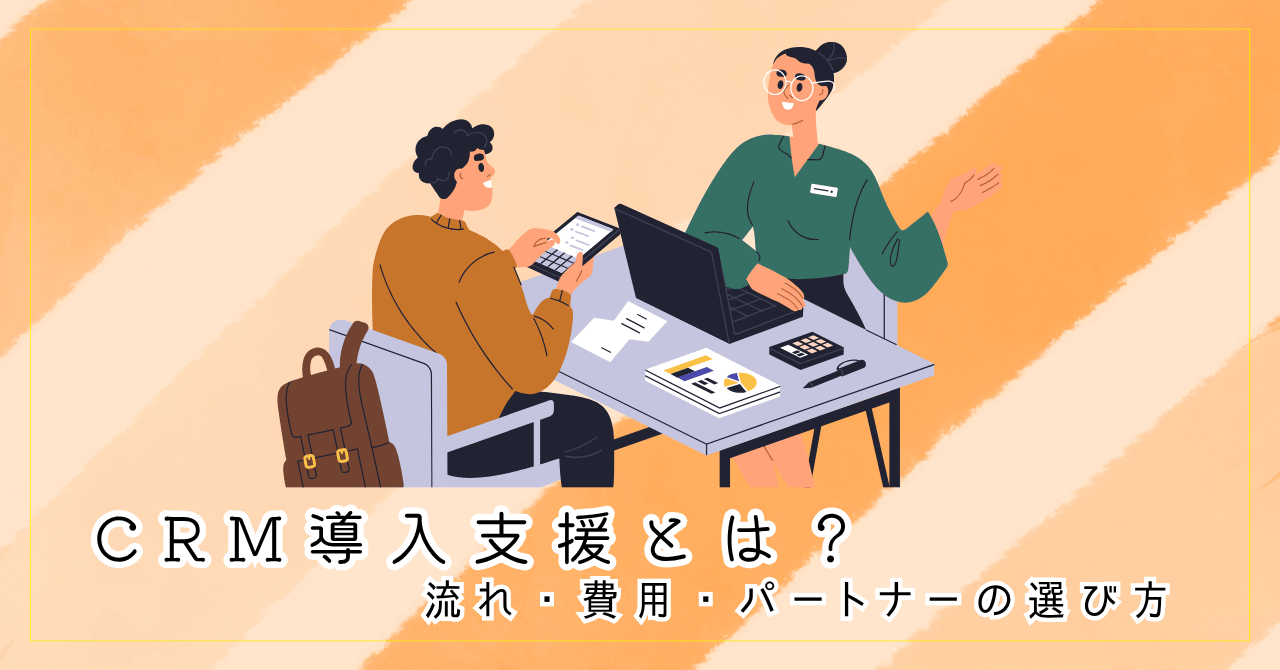IT業界に関わるフリーランスエンジニアのなかには「商流とは何か」「単価や契約条件とどう関係しているのか」といった疑問を抱えている方もいるでしょう。
この記事では、商流の基本的な意味から、IT業界特有の多重下請け構造における商流の実態について解説します。フリーランスエンジニアが自身の商流上の立ち位置を理解し、交渉力を高めるための具体的なアクションにも触れます。この記事を参考にして、有利な条件で仕事を進めるための知識を身につけてください。

エンジニアファクトリーでは、フリーランスエンジニアの案件・求人をご紹介。掲載中の案件は10,000件以上。紹介する案件の平均年商は810万円(※2023年4月 首都圏近郊のITエンジニア対象)で、ご経験・志向に合った案件と出会えます。
簡単なプロフィール入力ですぐにサポートを開始。案件にお困りのITフリーランスの方やより高条件の案件と巡り合いたいと考えている方は、ぜひご登録ください。
商流とは何か
IT業界で働くうえで「商流」の理解は、立ち位置や収益性を把握するために不可欠です。しかし、意味を正確に説明できる方は意外と少ないかもしれません。商流の理解はプロジェクト全体の構造の理解につながり、自身の価値を正しく評価するための第一歩となります。
商流の基本的な意味と読み方
商流(しょうりゅう)とは、「取引の流れ」、つまり商品の所有権が移転していく連鎖を意味します。「商的流通」という言葉の略称であり、生産者から最終的な消費者まで、商品が誰から誰へと売買されたかを示す権利の動きを指します。
たとえば、お菓子が工場で作られ、私たちの手元に届くまでの流れは以下のとおりです。
- 製菓メーカーが卸売業者にお菓子を販売する
- 卸売業者はスーパーマーケットにそのお菓子を販売する
- 私たちがスーパーでお菓子を購入する
上記の流れに伴い、お菓子の所有権は「メーカー→卸売業者→スーパー→消費者」の順で移転します。この取引の連鎖全体が商流です。
IT業界でいえば、「サービスの提供」や「システムの開発」といった役務が対象となります。契約を通して権利や責任が移転していく流れは全く同じです。商流の理解は、ビジネスの全体像をつかむうえで極めて重要となります。
物流との違い
商流(しょうりゅう)が「所有権の流れ」であるのに対し、物流(ぶつりゅう)は「モノの物理的な流れ」を指します。両者は密接に関係していますが、意味する対象は異なります。
商流は契約や取引に注目した概念で、目に見えない権利の移動を示します。一方、物流は商品を実際に運び、保管し、物理的に移動させる一連のプロセスを表します。
【商流と物流の違い】
| 項目 | 商流 | 物流 |
|---|---|---|
| 意味 | 売買・契約による「所有権」の移動 | 商品の「物理的」な移動 |
| 主な関係 | メーカー、卸、販売店、顧客などの取引関係 | 倉庫、配送業者、トラックなどの運送関係 |
| 起点と終点 | 売り手から買い手へ | 保管場所から届け先へ |
| 見える/見えない | 書類や契約書で管理(見えにくい) | 商品が目に見えて動く(見える) |
| 例 | 注文・請求・代金支払い | 梱包・輸送・配達 |
たとえば、ネット通販で本を購入した場合を考えてみましょう。
商流では、注文が確定した時点で「その本の所有権」が書店から購入者に移ります。つまり、ウェブサイトで「注文完了」と表示された瞬間に、契約上はその本が自分のものになります。
一方で、物流はその後に始まります。倉庫から本が出荷され、配送業者によってトラックで運ばれ、最終的に自宅へ届けられるという「実物の移動」が、物流にあたります。
IT業界での商流|SES・SIerにおける「多段商流」とは
IT業界、特にSIerやSESの分野では、「多段商流」と呼ばれる下請け構造が一般的です。
これは、1つのプロジェクトに対して「発注者→元請け→二次請け→三次請け…」といった形で複数の企業が連なって契約関係を結ぶ商流のことを指します。
たとえば、以下のような流れが「多段商流」にあたります:
- ある企業(=発注者)が、大手SIer(=元請け)にシステム開発を依頼する
- 元請けは上流工程(要件定義・基本設計など)を担当し、開発業務を中堅IT企業(二次請け)に再委託する
- 二次請けは、特定のモジュールや機能開発を小規模なIT企業(三次請け)に発注する
- 三次請けは、さらに外部のフリーランスエンジニアと契約し、実作業を現場で進めてもらう
このようにして「発注者 → 元請け → 二次請け → 三次請け → フリーランス」という契約の連鎖が構築され、これが多段商流です。
この構造では、エンジニアが実際に働く現場と、契約上の所属先が一致しないことも珍しくありません。たとえば、現場ではエンドユーザー企業の担当者と直接やりとりするものの、契約相手は三次請け企業であるというケースです。
自分が関与する商流フローを理解する意義
フリーランスエンジニアとして活動するなら、プロジェクトにおける「商流フロー(契約構造)」を理解することが非常に重要です。なぜなら、それが報酬の金額や業務内容の裁量、さらには今後のキャリアパスにまで影響を及ぼすからです。
商流を意識すれば、自分がどの立場にいて、どんな制約やチャンスがあるのかを客観的に把握でき、より戦略的にキャリアを設計できるようになります。
「商流が浅い・深い」とは?|エンジニア目線でのメリット・デメリット
「商流が浅い」とは、契約階層が少なく、発注者に近い位置で業務を行うことを指します。一方で、「商流が深い」とは、多くの仲介企業を挟んで契約階層が下層になっている状態です。それぞれのメリット・デメリットは以下のとおりです。
| 商流 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 商流が浅い | ・中間マージンが少なく、高単価になりやすい ・発注者と近いため、コミュニケーションがスムーズ ・裁量や発言権が大きい | ・高い交渉力やコミュニケーション能力が求められる ・案件獲得に相応の実績や人脈が求められる |
| 商流が深い | ・求められるスキルが限定的なので、経験が浅くても比較的参画しやすい ・担当業務と責任の範囲が明確に決まっている点も特徴 | ・中間マージンが多く、単価が低くなりやすい ・間に企業が多くなると情報伝達に遅延や齟齬が生じやすい |
自分の契約条件と商流の関係
自身の契約条件、とくに単価は、商流上の立ち位置と密接に連動しています。フリーランスエンジニアが業務委託契約を結ぶSES企業が、クライアントからどの階層で案件を受注しているかにより、提示される単価の元となる予算が変動します。
エンドクライアントから一次請けに月額150万円の予算が支払われている場合、三次請け経由で参画した場合のエンジニアの単価はどうなるのか、シミュレーションしてみましょう。
【シミュレーション:月額150万円の予算があった場合】
| 商流階層 | 請負金額 | マージン率 | 残額 |
|---|---|---|---|
| エンドクライアント → 一次請け | 150万円 | 20% | 120万円 |
| 一次請け → 二次請け | 120万円 | 20% | 96万円 |
| 二次請け → 三次請け | 96万円 | 25% | 72万円 |
| 三次請け → フリーランス | 72万円 | – | – |
このように、エンドクライアントからの予算に対して、実際にエンジニアが受け取る金額には、関係各社による調整が入ります。つまり、自分の契約先だけでなく、その企業が商流のどの位置にいるのかを知ることが、単価の背景を理解する手がかりとなるのです。
なお、マージンには単なる中抜きではなく、営業活動や契約交渉、トラブル対応、スケジュール管理など、各社が担う役割に対する対価という側面もあります。そうした役割分担も含めて、自分が参画する案件の商流構造を理解することで、納得感のある契約や、今後のキャリア選択に活かす視点が得られるでしょう。
商流を知るためには、面談時のやり取りや契約書に記載される発注元の情報、あるいは担当者への質問などから、ある程度推測することができます。
商流を意識することで得られる交渉メリット
商流の正確な把握は、良い条件を引き出すための強力な交渉材料となります。立ち位置を客観的に理解して現在の単価が適正かどうかを判断し、具体的な根拠をもって単価交渉に臨みましょう。
自分が三次請けの立場で、二次請けの企業の担当者とやり取りをしており、企業の信頼を得ているとします。現在の契約が満了するタイミングで、「二次請けの企業と直接契約を結べないか」と交渉する道筋が見えてきます。実現すれば、三次請けの企業に支払われていた中間マージンがなくなり、自身の単価に上乗せできるでしょう。いわゆる「商流アップ」です。
商流を理解していなければ、「単価を上げてください」という根拠の薄いお願いしかできません。構造を理解していれば、「同業他社や市場の相場と比較して、この金額が妥当だと考えます」といった、説得力のある交渉が可能となるのです。
ITプロジェクトにおける商流の具体例
商流の構造は、プロジェクトの契約形態によって大きく異なります。IT業界で代表的なSESやSIerでは、流れや特徴に違いが見られます。どのような契約のもとでプロジェクトに参画しているのかを理解することは、役割や立ち位置を把握するうえで不可欠です。
SES案件における商流の流れ
SES(システムエンジニアリングサービス)案件における商流は、典型的な多段構造になりやすい傾向にあります。発注者から始まり、複数の仲介企業を経てエンジニアに至るというフローです。具体的には以下のようになります。
| 商流の段階 | 主な立場 | 役割・特徴 |
|---|---|---|
| 発注者(エンドクライアント) | 事業会社・官公庁など | システムの開発・運用を外部に委託する立場 |
| 元請け(一次請け) | 大手SIerなど | 発注者から直接プロジェクトを受託し、全体管理や上流工程を担当 |
| 二次請け | 中堅IT企業など | 元請けから一部業務を請け負い、設計・開発・テストなどを担当 |
| 三次請け以降 | 小規模IT企業、SES専門企業など | 二次請け企業からさらに細分化された作業を受託 |
| エンジニア(個人事業主・フリーランス) | SES企業と業務委託契約を結ぶ | 実際に現場で作業を担当。所属企業と客先が異なることも多い |
フリーランスエンジニアの立ち位置
フリーランスエンジニアは、SES企業や小規模なIT企業と業務委託契約を結び、案件に参画するケースが一般的です。多くの場合、三次請けや四次請けといった商流の下層に位置し、実際に作業する現場の企業とは契約上の所属が異なります。
このように、商流のどの階層にいるかによって、受け取れる単価や仕事の裁量には大きな差が生じます。また、商流が深くなるほど中間企業が増え、マージンが発生するため、報酬面だけでなく、情報伝達や現場との認識ズレにも注意が必要です。
SIerプロジェクトでの商流パターン
SIerが手がける大規模な受託開発プロジェクトでは、元請けSIerが全体統括し、複数の協力会社を巻き込む多段階の商流構造が形成されます。こうしたプロジェクトにおける商流の特徴は、以下の通りです。
【商流の構造と主な役割】
| 立場 | 主な企業 | 担当工程 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 発注者(エンドクライアント) | 事業会社、官公庁など | 要件提示、予算確保 | システム開発を外部に委託する発注元 |
| 元請けSIer(一次請け) | 大手SIerなど | 要件定義、基本設計、PMO、顧客折衝 | プロジェクト全体を統括し、利益率が最も高い |
| 協力会社(パートナー/二次請け) | 中堅・準大手IT企業など | 詳細設計、開発、テスト | 元請けの指示で実装工程を担う。技術領域ごとに分担されることも多い |
| 三次請け~四次請け | SES企業、小規模開発会社 | プログラミング、単体テスト、ドキュメント整備など | 再委託された実作業を担い、契約単価は低くなりがち |
| エンジニア(個人事業主・フリーランス) | 三次請けやSES企業と契約 | 現場での開発・保守運用作業 | 現場と契約元が異なることも多く、商流の末端に位置する傾向 |
プロジェクトの規模が大きくなるほど、関わる人数や技術領域が多岐にわたり、工程ごとの役割分担が複雑化します。そのため、すべての業務を1社で対応するのは現実的ではなく、各工程に特化した企業に再委託する形が一般的になります。
また、開発、テスト、運用などそれぞれの工程で求められる専門スキルや業務知識が異なるため、得意分野をもつ企業がそれぞれの役割を担う構造になりやすいのです。
さらに、元請けや上位のSIerは、これまでの信頼関係や取引実績のある協力会社を優先して起用する傾向があります。こうした背景から、同じような商流構造が継続的に形成され、結果として多段階の商流が常態化しやすくなるのです。
フリーランスエンジニアの立ち位置
フリーランスエンジニアがSIerプロジェクトに参画する場合も、基本的にはSES案件と同様に三次請けや四次請けの企業と契約する形になるケースが多く見られます。そのため、直接元請けSIerや発注者とやり取りする機会は少なく、情報の伝達や裁量面では一定の制約がある点には注意が必要です。
受託開発の場合の商流
受託開発における商流は、完成すべき成果物(システムやソフトウェア)を中心とした構造になっており、契約形態は「請負契約」です。SESと異なり、「成果物の納品」や「所有権の移転」が商流の鍵となります。
【商流の特徴と契約形態】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 成果物の所有権 | 検収完了後にクライアントへ移転 |
| 契約形態 | 請負契約(成果物に対する報酬) ※SESは準委任契約 |
| 商流の構造 | 小規模:直接契約が多い 大規模:再委託により多段化 |
フリーランスエンジニアの立ち位置
フリーランスエンジニアが請負開発に直接関与するケースは多くありません。請負契約では「完成責任」が発生するため、法人やチームで体制を組んで受託する形が一般的です。
個人が関わる場合は、下請け企業に所属するか、開発パートの一部を担当するという形が多くなります。
商流と業務フローの関係
商流の構造、とくに階層の深さは、フリーランスエンジニアの日々の業務フローにとって重要です。商流が深くなるほど、業務の非効率性が増大する傾向にあるからです。ここでは商流と業務フローの関係について「業務負荷」「情報伝達スピード」「トラブル事例とリスク管理策」の観点で見ていきましょう。
商流の深さによる業務負荷の違い
商流が深いプロジェクトほど、エンジニアが現場で感じる業務負荷は増大する傾向にあります。コミュニケーションの非効率性と意思決定の遅延によって引き起こされます。
商流が浅い案件では、要件の確認や仕様変更の相談は直接可能です。疑問点があれば即座にキーパーソンに確認できるため、手戻りが少なく、スムーズに開発を進められます。
一方、商流が深い案件では、現場で発生した疑問点をまず所属会社の営業担当に報告しなければなりません。担当者がさらに上位の会社の担当者へ確認する伝言ゲームのようなプロセスをたどる必要があります。時間がかかるだけでなく、情報が不正確に伝わるリスクも高まります。
結果として、簡単な確認に数日を要したり、間違った情報に基づいて作業を進めてしまい、後で手戻りが発生したりするなど、不要な業務負荷が増えてしまうのです。
商流と情報伝達スピード
商流の階層の数は、情報伝達のスピードに反比例し、商流が深ければ深いほど、情報の伝達は遅くなります。クライアントからの重要な指示や仕様変更が、エンジニアの手元に届くまでに多くの段階を経由する必要があるためです。
たとえば、クライアントが緊急の仕様変更を決定したとします。
商流の深さと情報伝達スピードの違い
| 商流の深さ | 伝達ルート | 情報伝達の特徴 |
|---|---|---|
| 浅い | クライアント → エンジニア | 直接やり取りできるため、即時対応が可能。認識のズレも起きにくい。 |
| 深い | クライアント → 元請け → 二次請け → 三次請け → エンジニア | 各社を経由するため、伝達に時間がかかり、遅延や情報のズレが発生しやすい。 |
仕様変更の連絡が遅れたために、丸一日かけて実装した機能が全くの無駄になってしまった、という経験を持つエンジニアも少なくないでしょう。情報伝達の遅さは、プロジェクト全体の品質を低下させる大きな要因となるのです。
商物分離という考え方
SESや受託開発に関わる中で、商流と実際の業務フローが必ずしも一致しないという実情が見えてきます。このようなズレを整理して捉えるうえで、「商物分離」という考え方は非常に有効です。もともとは物流の概念ですが、IT業界でも応用できる視点として注目されています。
商物分離とは何か
商物分離とは、「商流」、すなわち所有権や契約の流れと、「物流」、すなわち物理的なモノやサービスの提供の流れを、意図的に切り離して管理・最適化する考え方です。多くの業界では商品を販売する企業が自社で配送まで行うなど、商流と物流が一体化していましたが、近ごろでは、これらを分離して専門性を高め、効率化を図っています。
たとえば、あるメーカーが商品を販売する場合を考えます。
- 商流:メーカー→卸売業者→小売店→消費者(所有権の移転)
- 物流:メーカーの工場→物流センター→各小売店の店舗(モノの移動)
上記のように二つの流れは、必ずしも一致しません。商流(販売活動)は自社で行い、物流(配送活動)は専門家に任せます。結果的に、メーカーは本業である商品開発やマーケティングに集中でき、物流会社は効率的な配送ネットワークを活かしてコストを削減できるのです。
商物分離のメリット
商物分離を推進するメリットは主に以下の3点です。
コストの明確化と最適化
商流と物流を一緒に管理していると、配送料が販売活動の経費に埋もれるなどしてしまい、どこにどれだけのコストがかかっているのかが不透明になります。商物分離により、物流コストと販売コストが可視化され、無駄の削減や価格設定の適正化につながります。
専門性の向上と品質向上
物流を専門業者に委託すれば、高品質な配送サービスが実現可能です。自社は販売や開発といったコア業務にリソースを集中できるため、全体のサービス品質が向上します。
柔軟な戦略立案
物流をアウトソーシングすれば、倉庫やトラックといった物理的な資産を持つ必要がなくなります。事業の拡大や縮小、新たな地域への進出などが、迅速かつ柔軟に行えるようになるのです。
IT業界への応用例
IT業界、とくにSESや受託開発において商物分離の考え方を応用すると、契約の流れと作業(価値提供)の流れを分離して捉えられます。プロジェクト管理の高度化やリスク管理の強化につながるでしょう。
SES案件での応用
SES契約では、契約(商流)は「発注者→元請け→…→所属会社→自分」と流れます。一方で、「作業の指示(物流ならぬ「務流」)」は「常駐先の担当者→自分」という流れになり、商流と実務の流れが一致しません。商物分離の観点から理解すれば、単価が低い理由(商流の問題)と指示が混乱する原因(実務フローの問題)」を切り分けて分析できます。
受託開発案件での応用
受託開発では、開発業務(モノづくり=物流)と、プロジェクト管理や顧客折衝(契約管理=商流)を各担当者が担うことで、専門性の向上を実現しています。このような役割分担は、まさに商物分離の考え方を応用した例といえるでしょう。
ITエンジニアが気になる商流の疑問を解決(FAQ)
商流の基本からIT業界特有の構造まで解説してきました。ここからは、とくにフリーランスエンジニアの方々からよく寄せられる、実践的な疑問についてQ&A形式で回答します。
- 「直請け案件」や「商流が浅い案件」はどうやって見分ければいいですか?
-
商流が浅い案件は、仲介企業の数が少なく、エンジニアがクライアントに近い位置で働く案件のことです。
見分け方としては、以下のような視点が有効です。
- エージェントに「エンド直案件か?」と確認する
- 現場の担当者と直接コミュニケーションが取れるかどうか
- 契約相手と実作業の現場が一致しているか
「クライアントとの距離感」と「契約経路の長さ」の両面から判断しましょう。
- 自分の「商流」を知るにはどうすればいいですか?
-
自分がどのような商流にいるかは、契約関係を確認することで把握できます。
まずは自分の契約相手が誰かを明確にし、エージェントや元請け企業に「この案件の商流はどこまでですか?」とストレートに確認してみましょう。「エンドから何社挟まっているか」「自社がどの階層にあるか」を聞くのがポイントです。
- 商流を浅くするには、どうすればいいですか?
-
商流を浅くするには、「案件の選び方」と「自分の市場価値」が重要です。
- 商流の浅い案件を扱うエージェントを利用する
- 元請け・エンド直の会社とつながるために人脈を広げる
- スキルと実績を積んで「この人と直接やりたい」と思われる存在になる
商流の浅い案件は競争率も高いため、常にスキルの棚卸しや自己PRを意識することが大切です。
フリーランスエンジニアの案件探しはエンジニアファクトリー

フリーランスとして納得感ある働き方を実現するなら、商流を意識した案件選びが欠かせません。エンジニアファクトリーでは、エンド直・元請け直の案件を多数保有しており、中間マージンの少ない高単価案件や、交渉可能な商流浅めの案件をご提案できます。
実際に、当社経由で参画したエンジニアの継続率は95.6%、年商は最大300万円アップという実績も。案件紹介だけでなく、面談や条件交渉も丁寧にサポート。自分の市場価値を理解し、より納得のいく契約で働きたい方にこそ選ばれています。
\ 遠回りせずに、納得できる仕事へ! /
まとめ
IT業界における「商流」は、契約や所有権の流れを意味し、エンジニアにとっては「誰とどんな関係で働いているか」を示す重要な構造です。
とくにフリーランスやSESで働くエンジニアにとって、商流は単価・裁量・働きやすさを左右する要因になります。
この記事では、商流の基本から、商流が深いことによるリスク、商流を浅くする方法、そして「商物分離」の考え方までを解説しました。自分がどこに位置し、どのような契約構造の中で働いているかを把握することは、キャリアや案件選びの判断軸にもなります。
「なんとなく働いている」状態から抜け出し、「なぜこの案件なのか」「もっとよい働き方はないか」を考えるきっかけとして、商流への理解をぜひ活かしてください。
ライター:にのまえ はじめ
大手精密部品メーカーで社内SE・PGを経験。その後、国内のSIerに転職し生産管理システムの開発・導入・保守・運用を担当。現在は自らIT企業を立ち上げ、顧客企業のDX化やIT化による業務改善の支援を行っている。並行して企業サイトやWebメディアでライターとしても活動中。趣味は筋トレ・プロレス観戦。
Website:https://writer.yui-road.com/