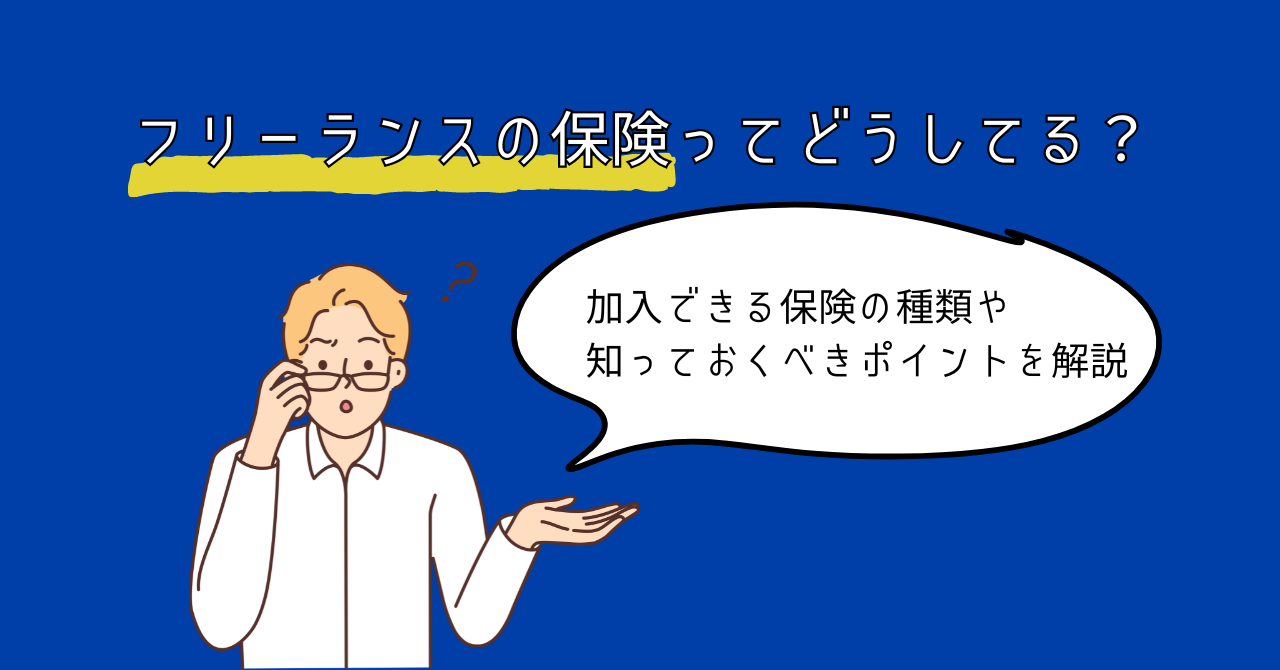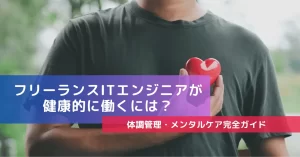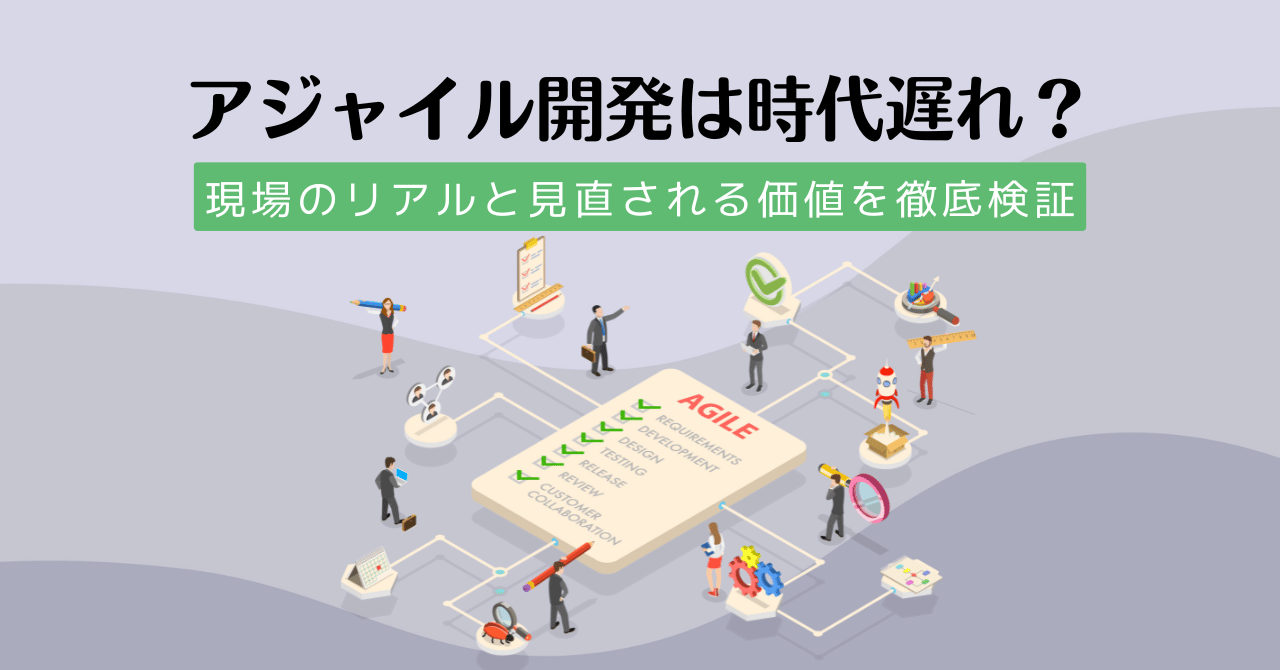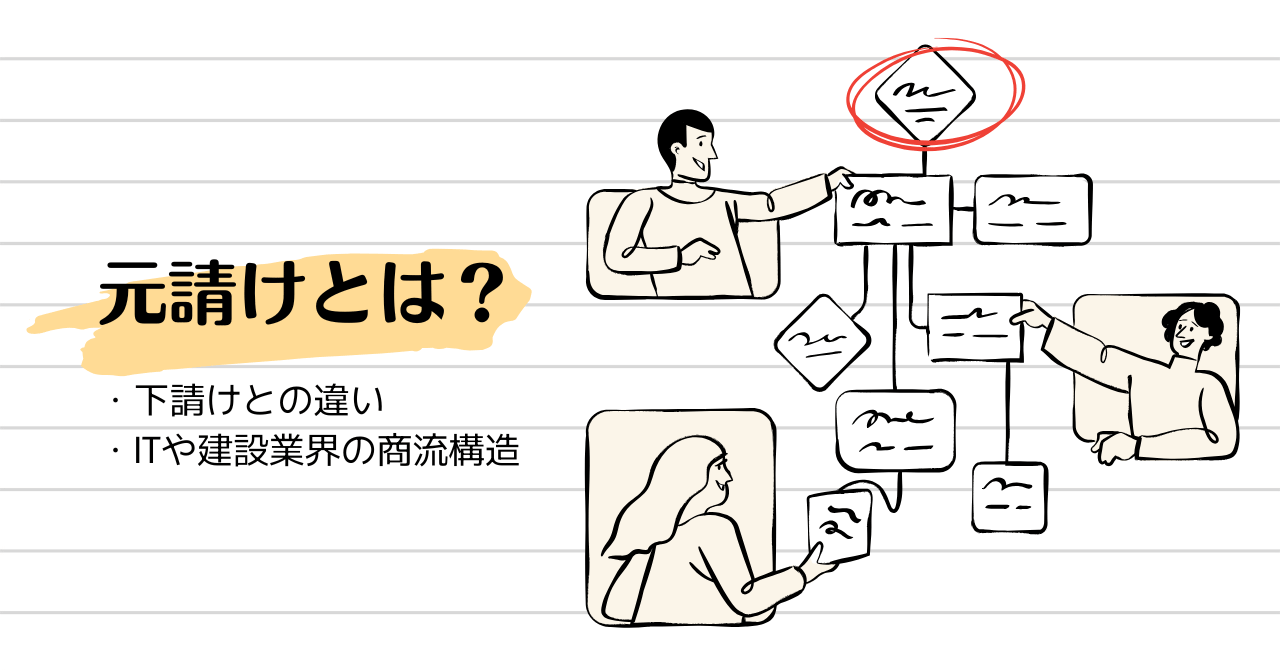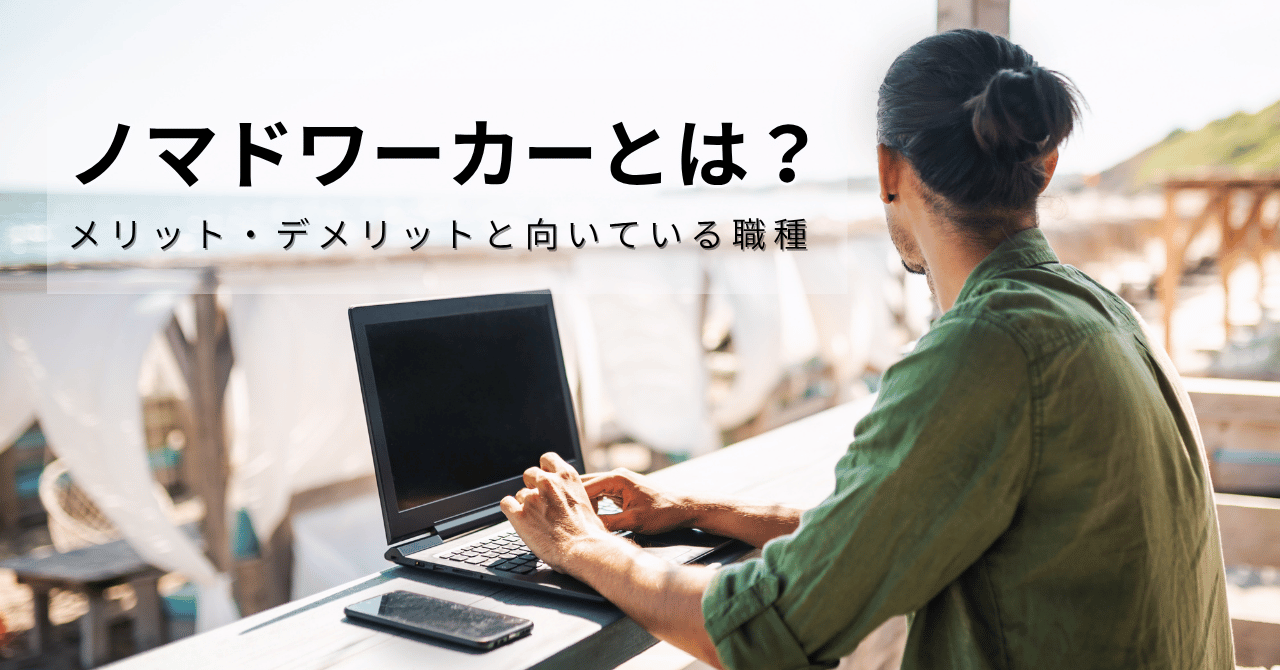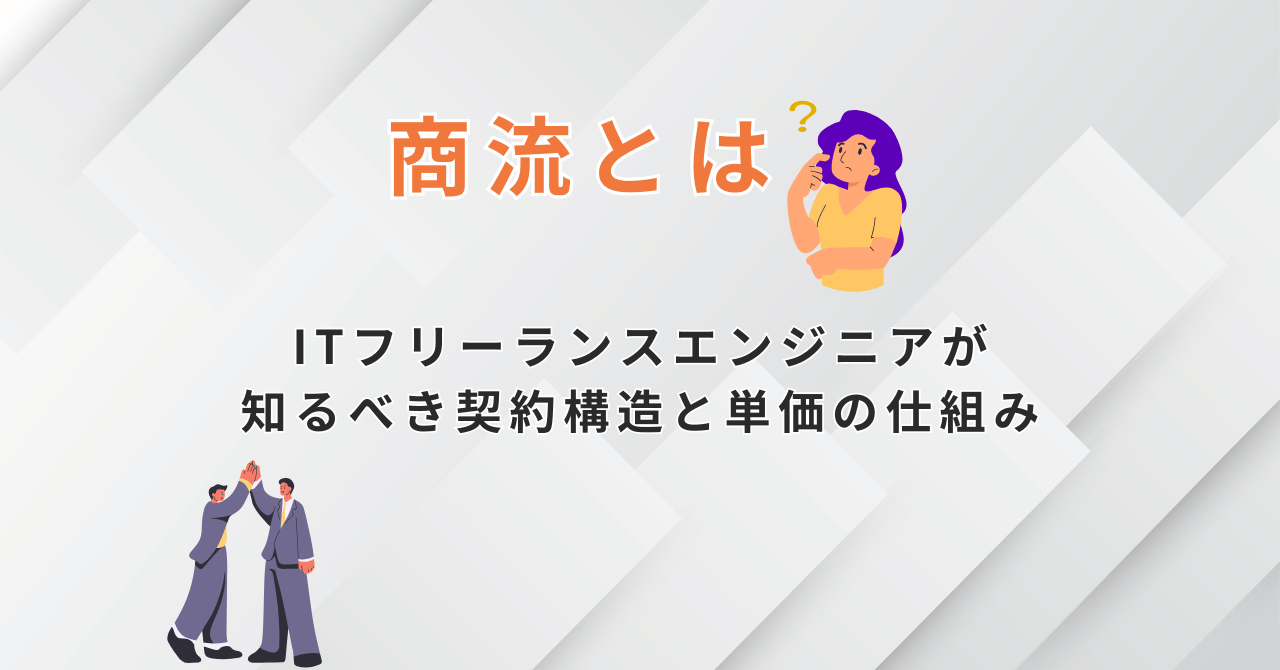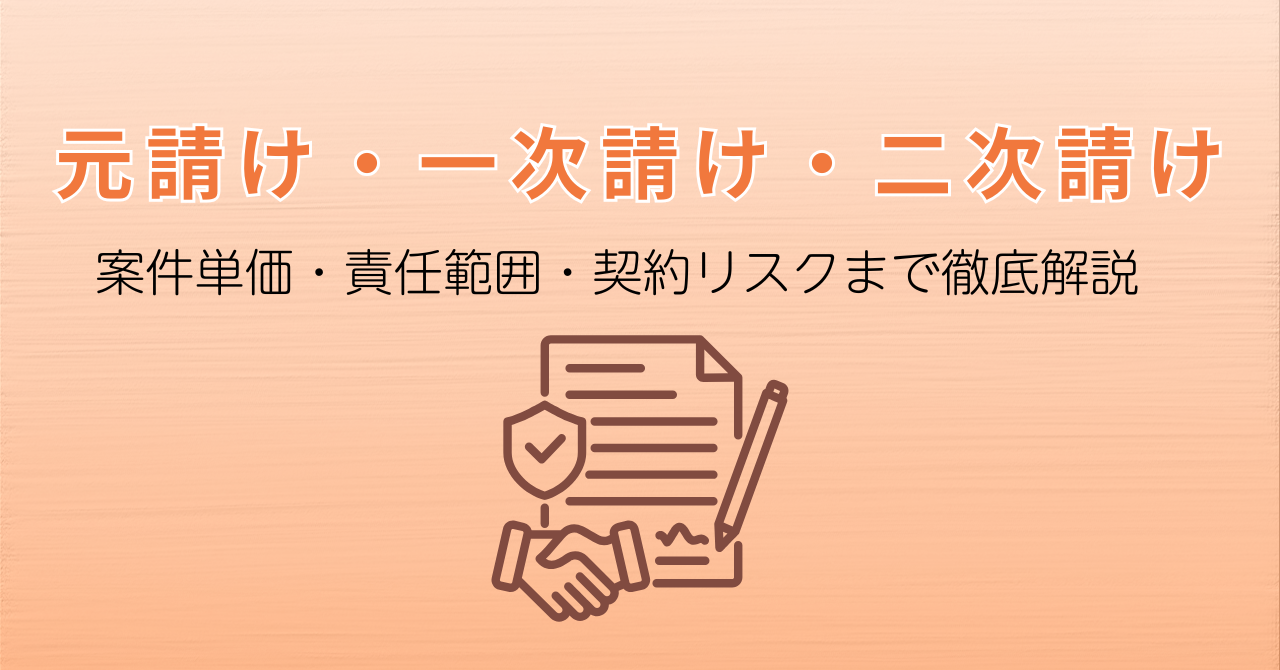フリーランスとして働くと、会社員時代とは大きく異なる公的保険の仕組みを理解する必要があります。特に「社会保険」という言葉が、会社員向けの制度を指すことが多い中で、フリーランスが利用できる保険制度との違いを正しく知っておくことが重要です。
この記事では、フリーランスが加入できる社会保険について、会社員との違いを明確にしながら、健康保険や年金、さらにはフリーランスエンジニア特有のリスクに対応する保険についても解説します。
これからフリーランスを始める方や、既に働いている方が安心してキャリアを築けるよう、必要な知識をわかりやすくまとめました。

エンジニアファクトリーでは、フリーランスエンジニアの案件・求人をご紹介。掲載中の案件は10,000件以上。紹介する案件の平均年商は810万円(※2023年4月 首都圏近郊のITエンジニア対象)で、ご経験・志向に合った案件と出会えます。
簡単なプロフィール入力ですぐにサポートを開始。案件にお困りのITフリーランスの方やより高条件の案件と巡り合いたいと考えている方は、ぜひご登録ください。
フリーランスと会社員の社会保険の違い
「社会保険」という言葉から、多くの人は「会社員が加入する健康保険や厚生年金保険」をイメージするでしょう。しかし実際には、「社会保険」は公的な保険制度全体を指す言葉で、フリーランスもその一部である「国民健康保険」や「国民年金」に加入できます。
会社員とフリーランスでは、「社会保険」という言葉が示す内容や適用範囲が大きく異なることを理解しておくことが重要です。
フリーランスになると保険料はどう変わる?
フリーランスとして働く場合、健康保険や年金の仕組みが会社員時代とは大きく変わります。
会社員の場合、健康保険や厚生年金の保険料は雇用主が半額負担してくれるため、自己負担額が抑えられています。しかし、フリーランスになると保険料の負担をすべて自分で背負うことになります。
特に国民健康保険は、住んでいる地域や所得額によって保険料が大きく異なり、会社員時代と同じ収入だと負担が増える可能性が高まります。年金は厚生年金の加入資格がなくなることで国民年金のみの加入へと移行し、将来の年金受給額が減少する点にも注意が必要です。
負担が増える背景には、雇用主が負担していた保険料がなくなることや、フリーランス特有の制度が影響しています。
フリーランスが加入すべき保険と追加で検討すべき保険
フリーランスとして働く際、法律で加入が義務付けられている保険と、自分の働き方やリスクに応じて追加で検討できる保険があります。ここでは、それぞれをわかりやすく分類して解説します。
フリーランスが必ず加入する保険
フリーランスとして働く上で、加入が法律で義務付けられている保険は次の2つです。
国民健康保険(国保)
国民健康保険は、フリーランスが必ず加入する公的医療保険制度です。会社員時代に雇用主が負担していた保険料がなくなるため、全額自己負担となります。市区町村が運営しており、保険料は所得や世帯構成、住む地域によって異なります。40歳以上になると、介護保険料が上乗せされます。
保障内容としては、医療費の一部負担(原則3割)や高額療養費制度があります。また、所得が低い場合は減免措置を申請することも可能です。
国民年金
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する基礎的な公的年金制度です。保険料は定額で、2025年度は月額約17,000円です。受給額は保険料の納付月数によって決まり、老齢基礎年金として支給されますが、厚生年金に比べて少額です。そのため、老後の生活資金を補う追加的な対策が重要です。
フリーランスが追加で検討すべき保険
次に、加入が必須ではないものの、リスクや老後の保障を強化するために検討できる保険を紹介します。
老後資金を補強する年金保険
付加年金
国民年金に追加で加入できるオプションで、月額400円を国民年金保険料と一緒に支払うことで将来の年金額が年間200円×加入月数増えます。負担額が少ないながらも年金の受給期間が2年を超えると支払った保険料を回収できるため、コストパフォーマンスが非常に高い制度として知られています。老後の収入を少しでも増やしたい方におすすめです。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、自分で積み立てる私的年金制度で、老後資金を計画的に準備するための有力な選択肢です。掛け金は全額所得控除の対象となり、節税効果が大きい点が特徴です。また、運用益も非課税となるため、長期的な資産形成に適しています。
ただし、原則として60歳まで積み立てた資金を引き出せないため、生活費や緊急資金とは別に積立資金を確保する必要があります。さらに、自分で投資信託や定期預金などの運用商品を選ぶ必要があり、運用結果に応じて受け取れる年金額が変動します。フリーランスの場合、加入条件は20歳以上60歳未満の国民年金保険料を納付している方で、掛け金の上限は月額68,000円です。
業務リスクに備える保険
就業不能保険・所得補償保険
就業不能保険や所得補償保険は、病気やケガで働けなくなった場合に、収入減少を補うための保険です。フリーランスは雇用保険や労災保険の対象外で傷病手当金を受給できないため、長期間仕事ができない状況が発生すると収入が途絶え生活に大きな影響が出ます。この保険は、そのようなリスクに備えるための重要な選択肢です。
補償内容は契約時に設定した金額に基づき、一定期間の収入をカバーします。たとえば、毎月30万円の補償を設定している場合、病気やケガで働けない間、この金額が支払われます。保険料は補償額や補償期間によって異なりますが、手ごろな価格で安心を得られる点が魅力です。また、保険によっては、精神的な疾患や産前産後の休業にも対応している商品があります。
賠償責任保険
賠償責任保険は、業務中のトラブルによって発生する損害賠償に対応する保険です。特に、ITエンジニアやコンサルタントなどの職種では、納期遅延や情報漏洩、システム障害による損害など、業務上のリスクが高い場合が多くあります。
この保険は、以下のような場面で役立ちます。
- 情報漏洩によって取引先に損害が発生した場合
- 納品物に欠陥があり、修正や再納品が必要になった場合
- 顧客が業務の遅延によって金銭的損害を被った場合
契約内容によって補償範囲が異なるため、業務内容や想定されるリスクに応じた保険を選ぶことが重要です。保険料は補償内容や補償額に応じて変動しますが、フリーランスのようにリスクを直接負う働き方では、特に重要な保険といえます。
自分に合った保険を選ぶポイント
フリーランスとして働く際には、まず国民健康保険と国民年金に確実に加入しましょう。その後、自分の働き方やライフスタイル、将来の目標に応じて、付加年金やiDeCoを活用して老後資金を補強するのがおすすめです。
また、業務内容にリスクが伴う場合は、賠償責任保険や就業不能保険・所得補償保険の加入を検討することで、安心して働ける環境を整えることができます。
よくある質問と回答
Q1. フリーランスになると必ず国民健康保険に加入しなければなりませんか?
はい、フリーランスとして働く場合、国民健康保険またはそれに代わる保険(例えば、前の勤務先の任意継続健康保険)に加入する必要があります。会社員時代と異なり、雇用主の保険料負担がなくなるため、保険料は全額自己負担となります。国民健康保険は収入や住む地域に応じて保険料が異なるため、事前に市区町村で確認することをおすすめします。
Q2. 国民健康保険と任意継続健康保険はどちらが良いですか?
どちらが適しているかは、扶養家族の有無や収入によります。扶養家族が多い場合や収入が高い場合、任意継続健康保険の方が保険料を抑えられることがあります。一方、任意継続健康保険は退職後20日以内に申請が必要で、最大2年間しか利用できない点に注意してください。長期的に考えるなら、国民健康保険に移行する準備を進めるのも一つの選択肢です。
Q3. 国民年金だけで老後の生活資金は十分ですか?
国民年金の受給額は、老齢基礎年金として満額受け取れる場合であっても月額約65,000~70,000円程度です。加入期間が短ければ受給額も減ります。これだけでは十分な生活資金を確保するのが難しいため、付加年金やiDeCoなどの老後資金対策を検討することをおすすめします。これらを併用することで、将来の生活に余裕を持たせることができます。
Q4. フリーランス特有のリスクに備える保険はありますか?
あります。フリーランス協会の保険や民間の就業不能保険・所得補償保険が代表的です。フリーランス協会の保険は、所得補償や業務中のトラブルによる賠償責任補償が含まれており、病気やケガで働けなくなった場合や情報漏洩などのリスクに対応できます。業務内容に応じた保険を選ぶことが重要です。
Q5. 健康保険料や年金の負担を軽減する方法はありますか?
はい、いくつかの方法があります。国民健康保険の場合、収入が減少した場合は市区町村に申請することで保険料の減免措置を受けられることがあります。また、一定の条件を満たせば、配偶者や親の健康保険に扶養家族として加入することで負担を軽減できる可能性があります。年金については、付加年金やiDeCoを活用することで、将来の受給額を増やすことができます。
フリーランスエンジニアのキャリア構築ならエンジニアファクトリー

フリーランスとして働くなら、高単価・安定した案件を確保することが重要です。エンジニアファクトリーでは、エンド直案件を中心に7,000件以上の公開案件を掲載。経験豊富なエージェントがあなたのスキルや希望に合った案件を厳選し、提案します。
さらに、契約手続きや報酬交渉、参画後のフォローまでしっかりサポート。フリーランスの不安を最小限に抑え、安心して働ける環境を整えます。案件検索は登録不要。まずはどんな案件があるのか、ぜひチェックしてみてください。
まとめ

フリーランスとして働く際には、収入の不安定さがつきまとうものです。しかし保険について十分検討し、自分や家族に最適な保険を選ぶことで、少しでも経済的な不安を軽減できます。
本記事で紹介した保険や任意継続の仕組みを利用して、フリーランスとしての仕事始めがスムーズになるよう、検証することをおすすめします。
監修:水野崇
水野総合FP事務所代表。相談、執筆・監修、講演・講師、取材協力、メディア出演など多方面で活躍するファイナンシャルプランナー。主なテレビ出演は、テレビ朝日『グッド!モーニング』、BSテレ東『マネーのまなび』、TOKYO MX『日曜はカラフル2』など。NHK土曜ドラマ『3000万』の家計監修・考証を担当。学校法人専門学校「東京ビジネス・アカデミー」非常勤講師。
<資格>1級ファイナンシャル・プランニング技能士|CFP認定者|宅地建物取引士|日本証券アナリスト協会検定会員補|証券外務員1種 ほか
<URL>水野総合FP事務所 水野崇HP:https://mizunotakashi.com/

ライター:前嶋 翠(まえじま みどり)
COBOLが終わろうとする時代にプログラマのキャリアをスタートし、主にJavaエンジニアとして経験を積みました。フリーランスエンジニアとして活動していたとき、リーマンショックが起こったことをきっかけに家庭に入りました。出産を経て在宅でできる仕事として、ライターに。ITエンジニア経験のあるライターとして、IT業界のあれこれを皆さまにわかりやすくお伝えしていきます。