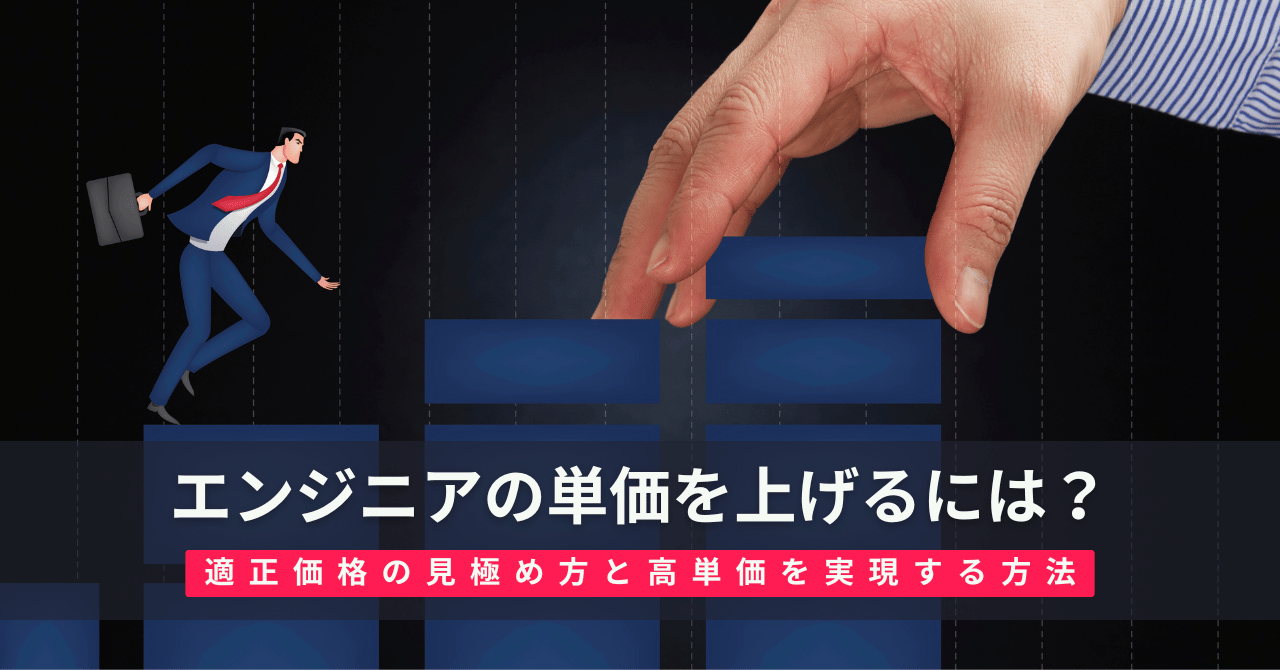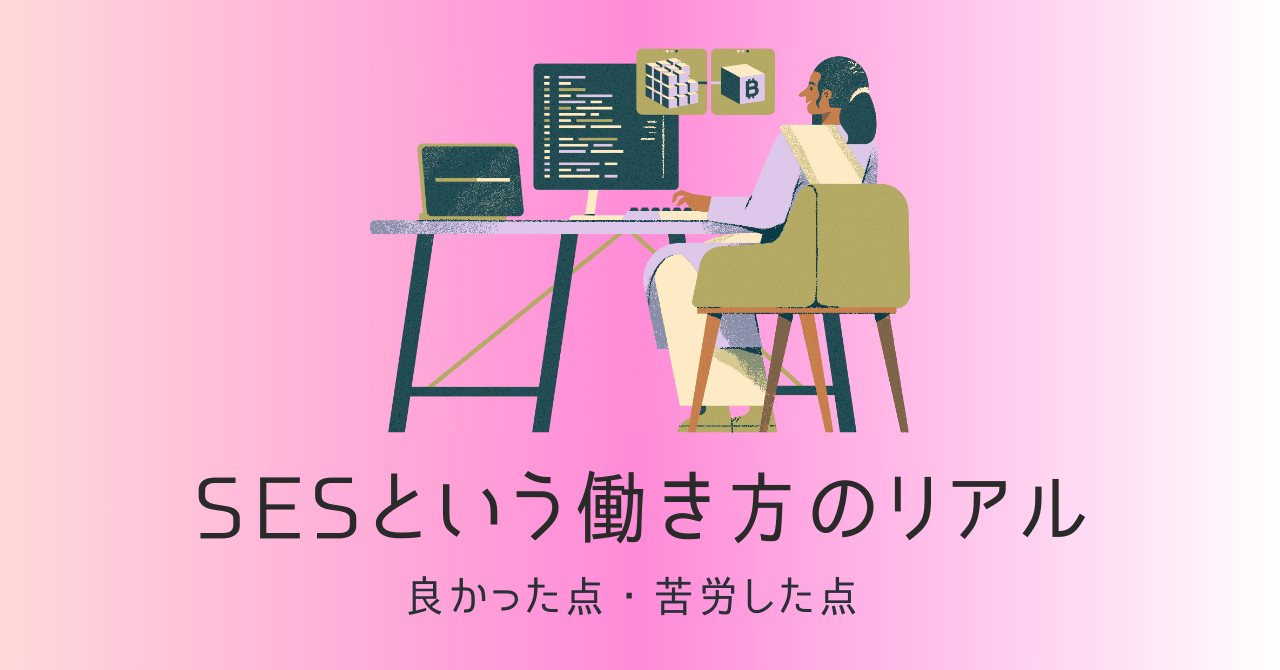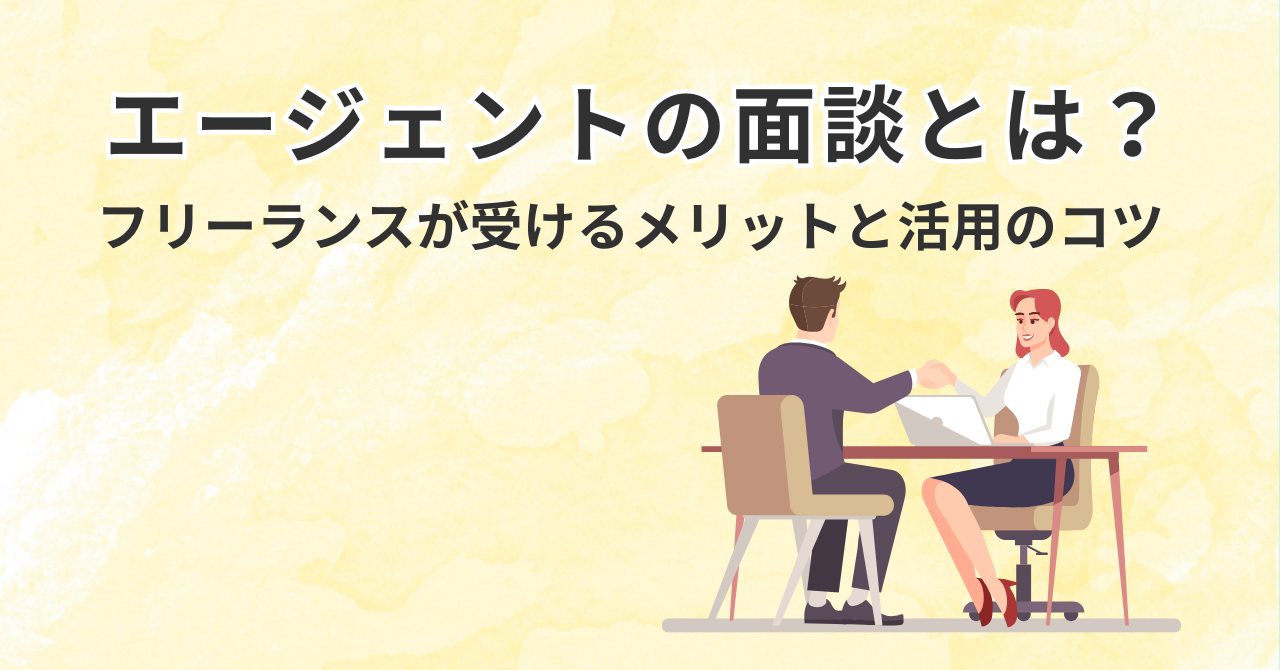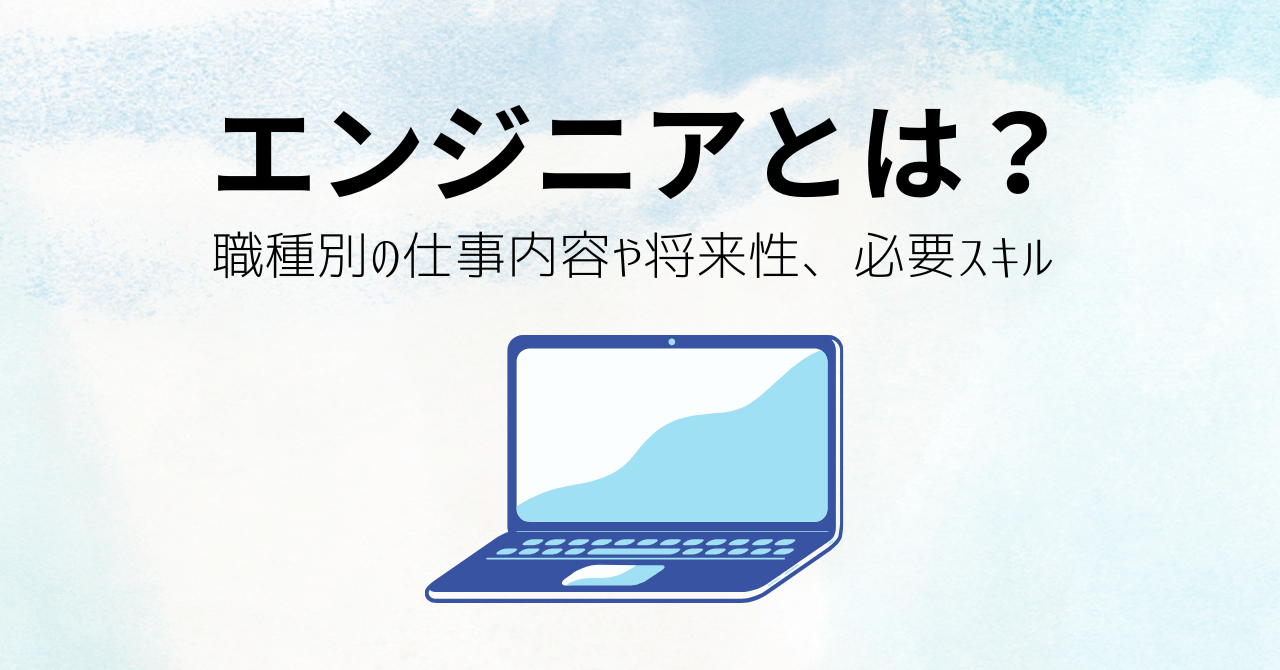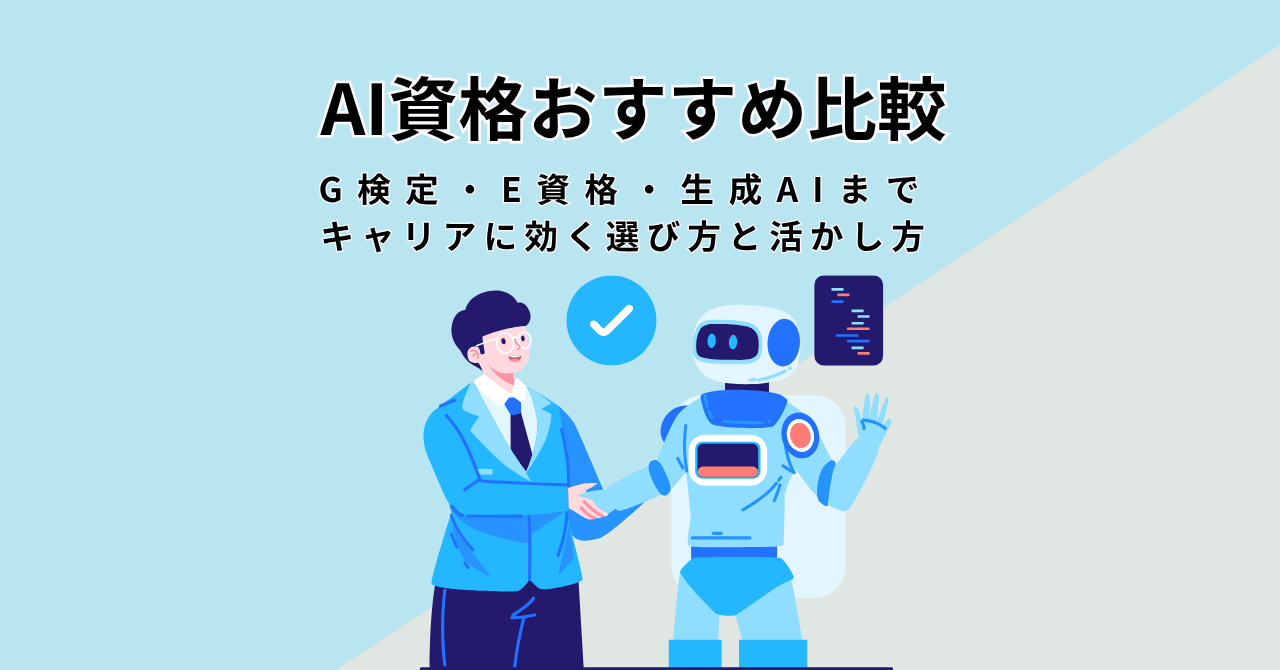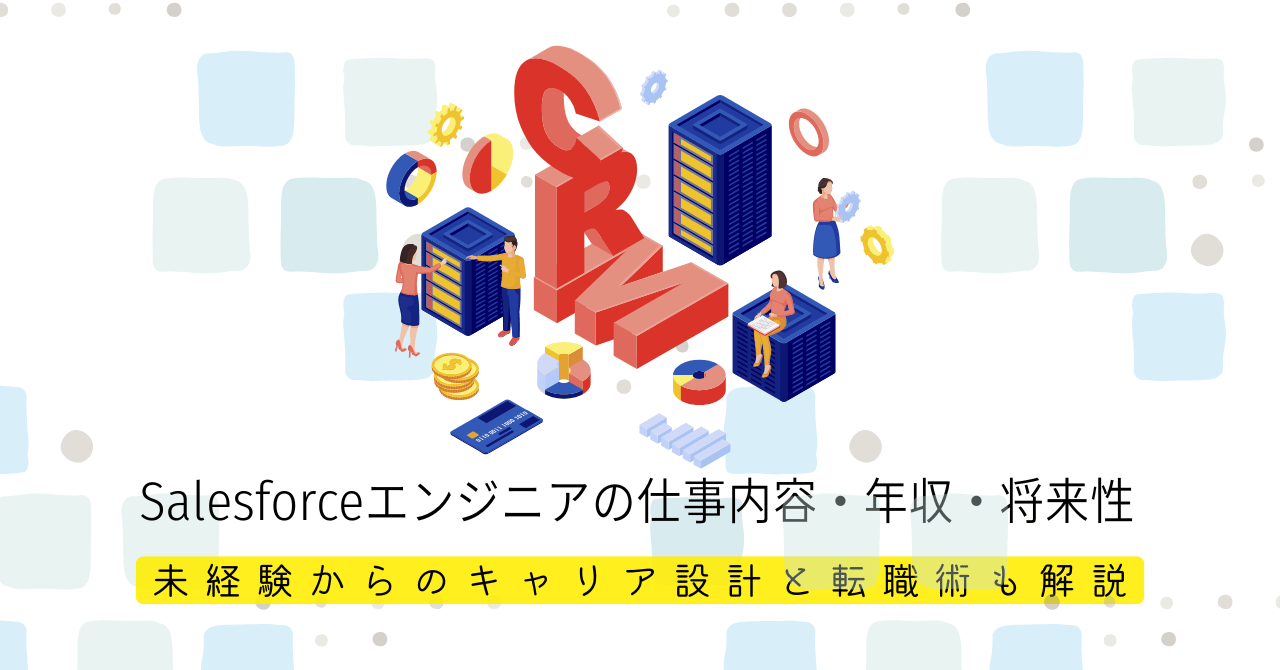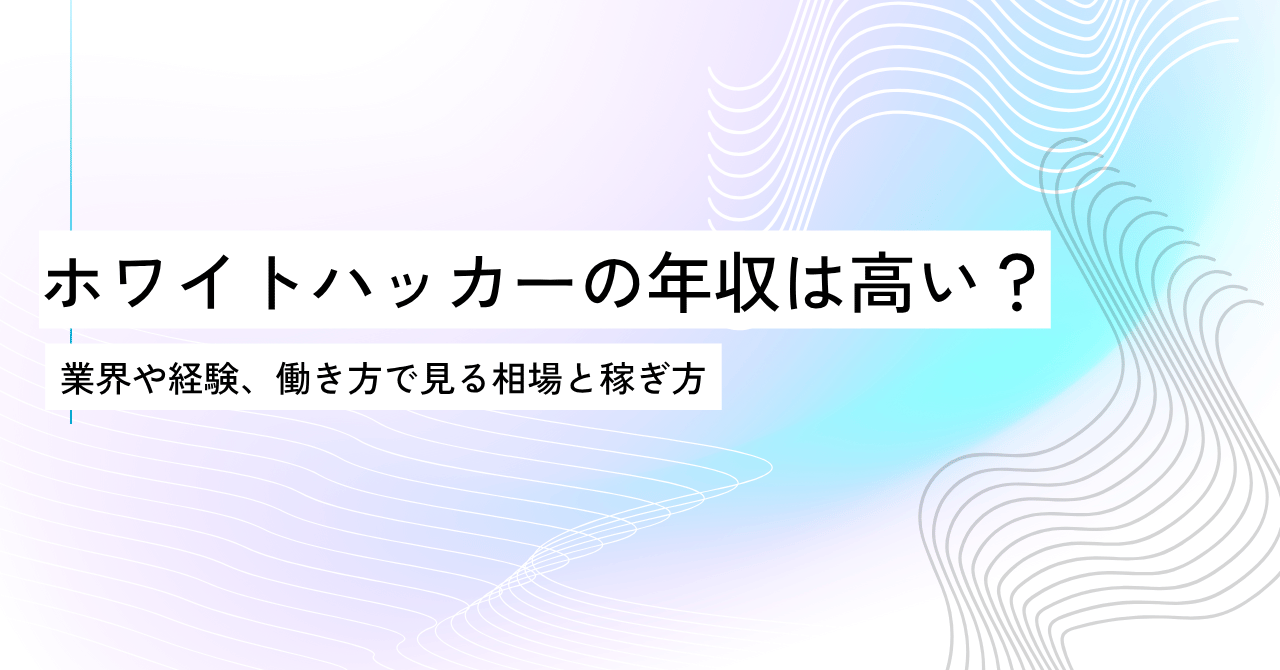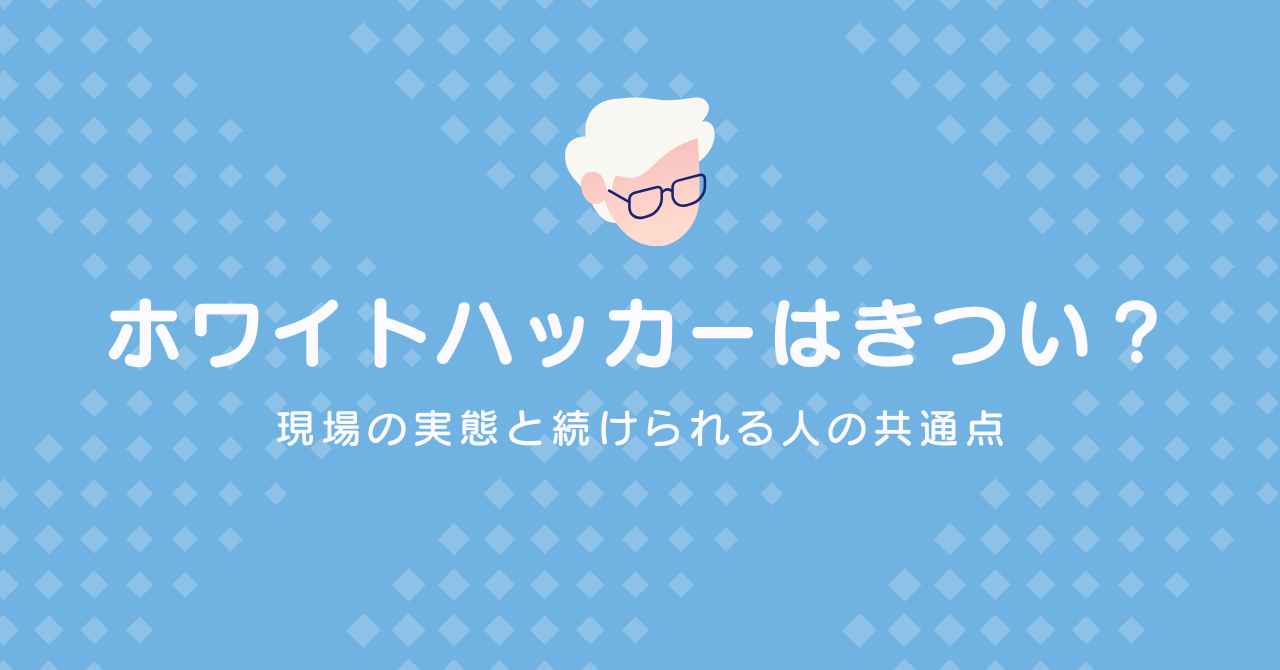「この単価、妥当なんだろうか?」エンジニアとして働いていると、ふとそんな疑問が浮かぶことはありませんか。
案件やポジションによって大きく変動する単価ですが、仕組みや相場を正しく知っている人は意外と少ないかもしれません。本記事では、単価の決まり方や適正価格の見極め方、単価を上げるための具体的な方法を紹介しています。
フリーランスと正社員の違いや、実際に単価アップを実現した人のケースも取り上げています。

エンジニアファクトリーでは、フリーランスエンジニアの案件・求人をご紹介。掲載中の案件は10,000件以上。紹介する案件の平均年商は810万円(※2023年4月 首都圏近郊のITエンジニア対象)で、ご経験・志向に合った案件と出会えます。
簡単なプロフィール入力ですぐにサポートを開始。案件にお困りのITフリーランスの方やより高条件の案件と巡り合いたいと考えている方は、ぜひご登録ください。
- エンジニアの単価はどう決まる?
- 適正価格で案件を受注するためのポイント
- エンジニアが単価を上げるための戦略
- フリーランスと正社員の単価比較!どちらが高単価を狙いやすい?
- エンジニアの単価交渉のコツと成功事例
- エンジニアの単価に関するよくある質問
- ITエンジニアの案件探しならエンジニアファクトリー
- まとめ
エンジニアの単価はどう決まる?
エンジニアの単価は、スキル、経験、契約形態、市場の需要など複数の要素によって決まります。ここでは、以下のポイントを詳しく解説します。
- エンジニアの案件単価はどのように決まるのか?
- 適正価格とは?安すぎる案件を避けるポイント
- 職種ごとの単価相場を調べる方法
エンジニアの案件単価はどのように決まるのか?
案件単価は、スキルや経験年数に加え、契約形態や市場の需要、クライアント側の予算など、複数の要素によって決まります。スキルの高いエンジニアが高単価案件を受注しやすいのは確かですが、職種やタイミングによってはそう単純ではありません。
たとえば、同じスキルセットでも、大手企業での就業経験やマネジメント実績があるかどうかで、評価が分かれることもあります。また、予算が潤沢なクライアントであれば、提示単価が相場より高くなることもあります。
市場で「選ばれる側」に回るには、技術力だけでなく、案件文脈に応じた実績やアピールの仕方が重要です。
伝え方次第で、単価は大きく変わってくるのが現実です。
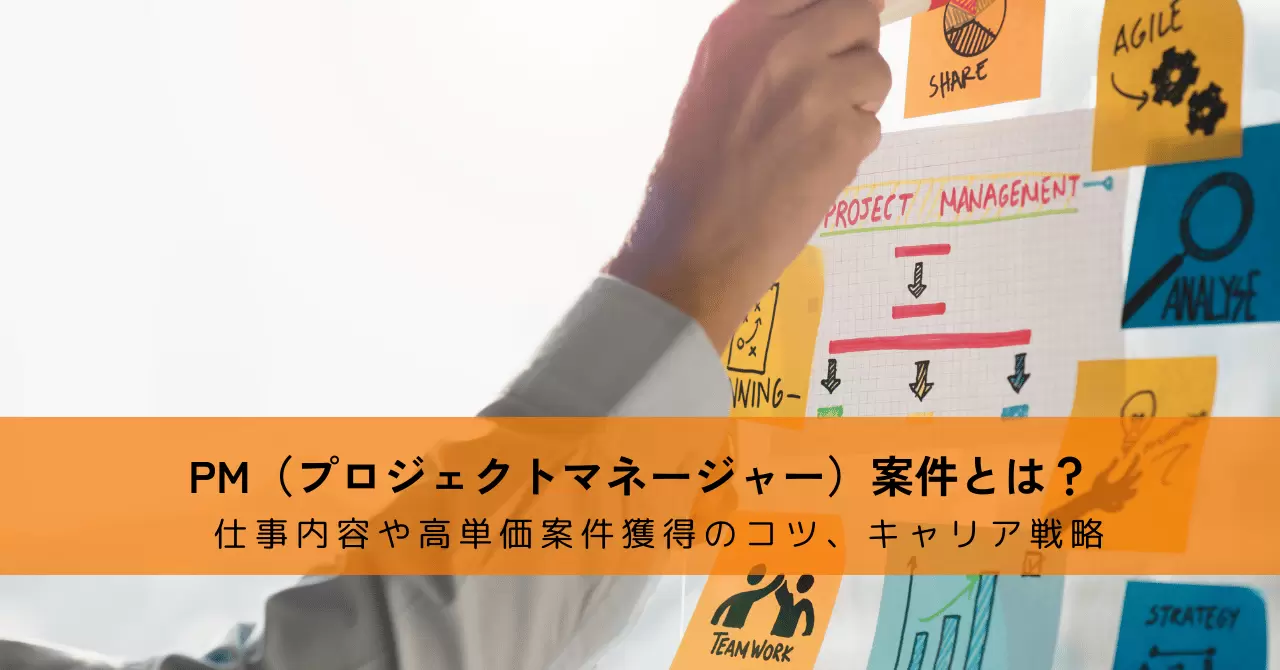
適正価格とは?安すぎる案件を避けるポイント
エンジニアにとっての「適正価格」とは、市場相場をベースにしつつ、自身のスキル・経験・成果に見合った金額が提示されているかどうかが鍵になります。
たとえば、Web系なら月60〜80万円、スマホアプリ開発では月50〜70万円前後が目安ですが、言語やフレームワークの選定、過去のプロジェクト規模、マネジメント経験の有無によっても大きく変動します。
安すぎる案件を避けるには、「今の単価は適切か?」を定期的に見直す視点が必要です。
そのうえで、稼働内容に対して金額が見合っているか、業務範囲が契約内に収まっているかも要確認です。特に業務が拡張しやすい現場では、契約前にタスクの範囲や対応ラインを明文化しておくことで、後からの“単価据え置きの負担増”を防げます。
職種ごとの単価相場を調べる方法
「今の単価、周りと比べてどうなんだろう?」そんなときは、複数の情報源を組み合わせて相場感をつかみましょう。
まず参考にしたいのが、エンジニア向けのエージェントサービス。公開案件の単価情報から、最新の水準が把握できます。特定の職種やスキルセットごとの傾向もつかみやすく、実務と結びついた情報を得やすいのが特長です。
エンジニアファクトリーでは職種別に案件を検索すると月額の単価相場目安が表示されるため、単価を比較しながら案件選びが可能です。

次に、業界レポートや調査資料も有益です。IT系の求人動向や職種別平均単価などが数値でまとめられているため、定量的に比較したいときに役立ちます。
加えて、SNSやエンジニアコミュニティでの情報交換も見逃せません。公式な情報には出にくい実体験ベースの話や、特定案件でのリアルな単価感覚を知ることができます。
情報の精度にはバラつきがあるため、複数の視点から確認して、自分の市場価値を見直すきっかけにしてみてください。
適正価格で案件を受注するためのポイント
適正な単価で案件を受注するには、市場相場の理解や契約形態の違い、エージェントとの付き合い方など、複数の視点を持つことが欠かせません。
ここでは以下の3つのポイントから、現場で気をつけたい判断軸を整理します。
- 低単価案件を避けるために知っておくべきこと
- 案件ごとの単価設定の違い(SES・受託開発・フリーランス・正社員)
- エージェントを活用する場合の適正価格の見極め方
低単価案件を避けるために知っておくべきこと
単価が低くなってしまう理由には、いくつかの傾向があります。よくあるのが、「工数に対して報酬が見合っていない」ケース。一見すると高単価に見えても、稼働時間が想定より多ければ、実質の時給は下がります。契約前にざっくりでも稼働想定を確認し、時給ベースで単価を計算しておくことが大切です。
また、「誰でもできる作業」や「属人性が低いタスク」が多い案件は、競争が激しく、単価が下がりやすい傾向にあります。工数を増やして稼ぐ方法もありますが、長期的には非効率です。技術力はもちろん、「誰にでもできる仕事ではない」と認識してもらえるような専門性や提案力が、高単価案件への入口になります。
案件ごとの単価設定の違い(SES・受託開発・フリーランス・正社員)
契約形態によって、単価の決まり方や報酬の見え方には大きな違いがあります。単価だけを見るのではなく、稼働条件や責任範囲、報酬の安定性なども含めて比較することが大切です。
| 契約形態 | 単価の決まり方 | 相場 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| SES | 人月単価方式(1ヶ月フルタイム稼働基準) | 60~120万円/月 | 時間ベースの稼働単価 スキル・経験で変動 |
| 受託開発 | 成果物ベースの契約 | 実働換算で月60〜100万円前後 ※ | 高単価でも工数が膨らみがち。要件定義と契約内容の明確化がカギ。 |
| フリーランス | 案件ごとに設定 | 60〜80万円/月(上流は100万円超も) | スキル・交渉力・タイミング次第で大きく変動。 |
| 正社員 | 企業の給与体系に基づく | 年収ベース(例:500〜800万円) | 単価は見えづらいが、安定性と福利厚生が強み。市場とのギャップ確認も大事。 |
参考:
SES費用相場|Lancers Agent
受託開発の費用相場|コンサル&システム発注依頼.com
フリーランスエンジニア単価相場|WEBLANCE
エージェントを活用する場合の適正価格の見極め方
エージェント経由で案件を受ける際は、提示された単価が自分にとって適正かどうかを判断する必要があります。とはいえ、市場の相場や交渉余地をすべて一人で把握するのは簡単ではありません。
信頼できるエージェントであれば、これまでに扱ってきた類似案件やスキル構成の事例から、相場感や想定単価の目安を提示します。「このスキルセットなら◯万円前後が狙える」といった実践的なアドバイスが得られるのは大きな助けとなるでしょう。
また、単価交渉が必要な場面でも、第三者としてクライアントとやりとりしてもらえるため、自分では言い出しにくい条件面の調整も進めやすくなります。数字の裏にある背景や意図まで丁寧に説明してくれるエージェントと組めば、より納得感のある条件で案件に参画しやすくなるはずです。
エンジニアが単価を上げるための戦略
単価を上げたいと思ったとき、ただ「スキルを磨こう」と考えるだけでは足りない場合もあります。現場の選び方やアピールの仕方次第で、同じスキルでも単価が数万円変わることも珍しくありません。
ここでは、実際に多くのエンジニアが取り入れている「単価アップの打ち手」を5つに分けてご紹介します。今すぐできることから、中長期で考えるべき視点まで。自分に合いそうな方法から、ぜひ参考にしてみてください。
- 長期参画による単価アップのメリットとデメリット
- スキルアップして高単価案件を狙う方法
- 資格を取得し、市場価値を高める
- 業務範囲を広げて単価を上げる(フルスタック・マネジメントスキル)
- 需要の高い分野にシフトする(AI・クラウド・セキュリティなど)
長期参画による単価アップのメリットとデメリット
「長く同じ現場にいると、単価は上がるのか?」現場に長くいることで評価され、単価が上がるケースは確かにあります。業務理解が深まり、クライアントとの信頼関係ができれば、「継続のために報酬を上げたい」と言われることもあります。特に、立ち回りや提案力まで評価されるようになれば、ポジション変更や条件アップの打診が来ることも。
また、長期案件は収入の安定という点でもメリットがあります。特に独立直後や家庭の事情がある場合など、「しばらく動かずに済む安心感」は無視できません。一方で、アサイン内容が想定とずれていたり、成長実感が持てなかったりする場合は要注意。契約を継続するうちに、単価も仕事内容も固定されてしまい、動きづらくなるパターンもあります。
スキルアップして高単価案件を狙う方法
同じ職種でも、スキルや扱える技術によって単価には大きな差が生まれます。たとえば、汎用的な実装スキルだけでなく、設計や要件定義といった上流工程まで対応できる人材は、クライアントから高く評価されやすくなります。
また、市場で扱える人材が限られている技術領域(クラウド基盤、セキュリティ、機械学習、データエンジニアリングなど)では、希少性の高さが単価に直結することもあります。
当然ながら、スキルは磨けばすぐに単価が上がるとは限りませんが「対応できる領域が広い」「今後もニーズが続く技術に強い」という条件を満たせば、提案の幅も大きく広がります。トレンドは変化しますが、「必要とされる技術に、今の自分が対応できるか」を定期的に見直すことが、高単価案件を選べる状態につながっていきます。
資格を取得し、市場価値を高める
スキルの証明は、実績やポートフォリオだけではありません。特定の資格を持っていることで、「一定の専門知識がある人材」として評価されやすくなる場面もあります。
たとえば国家資格の中でも、応用情報技術者やネットワークスペシャリスト、システムアーキテクトなどは、上流工程や専門領域への理解をアピールできる材料になります。特に金融・公共系など、資格を重視する業界や企業では、単価設定にも影響するケースがあります。
一方で、ITパスポートや基本情報技術者などの初級資格は、すでに実務経験のあるエンジニアにとっては単価面での直接的な効果は限定的です。とはいえ、知識の整理やキャリアの方向性を見直すきっかけにはなり得ます。
資格は「取ればすぐ単価アップ」とは限りませんが、市場のどこで自分が評価されるかを考える材料として、適切なものを選ぶことが大切です。
業務範囲を広げて単価を上げる(フルスタック・マネジメントスキル)
「自分は、どこまでを任される人材だろうか?」スキルアップだけでなく、任される業務の幅によって単価は大きく変わります。たとえば、開発だけでなく設計や運用にも対応できるフルスタック型のエンジニアは、チームの中での使われ方が変わり、単価が上がるケースもあります。
ただし、「なんでも屋」になることが目的ではありません。強みのある領域をベースに、隣接分野に手を伸ばすことで、現場内での替えがききにくいポジションを築いていく。それが単価アップにつながります。
マネジメントも同様です。プロジェクトを動かす力、チームの進行を担う力は、技術とは別の評価軸として見られます。現場で「この人がいると助かる」と思われる人ほど、長期的に高い単価を維持しやすい傾向があります。
すべてを完璧にこなす必要はありません。「技術の幅」だけでなく、「役割の幅」に目を向けられると、報酬のステージは変わっていきます。
需要の高い分野にシフトする(AI・クラウド・セキュリティなど)
同じスキルでも「どの分野で、どう使うか」によって単価は大きく変わります。AI、クラウド、セキュリティなどの分野は今も高い需要があり、これらに対応できるエンジニアは比較的高単価で評価されやすい傾向があります。
ただし、最新技術だけが市場価値につながるわけではありません。実際、大手SIerをはじめとするエンタープライズ領域では、今もJavaの需要が根強く、業務システムやインフラ系案件でスキルが活かされる場面は多くあります。また、COBOLなどレガシー環境で広く使われてきた技術にも一定のニーズはあり、刷新プロジェクトや保守案件などで経験者が求められるケースもあります。
大事なのは、自分のスキルを市場が求める形にどう結びつけるか。いま持っている強みを活かしながら、評価されるポジションに寄せていく視点が、着実な単価アップにつながります。
フリーランスと正社員の単価比較!どちらが高単価を狙いやすい?
「収入を上げたいならフリーランス」という声を聞く一方で、「安定性も捨てがたい」というのが本音。単価に着目すると、両者にはどう違いがあるのか?それぞれの特徴と、どうすれば収入を伸ばせるかを整理します。
- フリーランスと正社員、それぞれの単価の特徴
- 案件単価の決まり方の違い(直接契約 vs エージェント vs 企業雇用)
- フリーランスエンジニアが高単価を実現する方法
- 正社員エンジニアが昇給・昇格で単価を上げる方法
フリーランスと正社員、それぞれの単価の特徴
フリーランスと正社員では単価の決まり方が異なります。
フリーランスの場合、エンジニアが持つスキルや実績、市場の需要によって単価が変わるのが特徴です。単価は案件ごとに交渉でき、高いスキルを持っていれば短期間で収入を増やせるというメリットがあります。
一方、正社員の単価は、企業の給与体系に基づいて決められます。企業によっては、年功序列や社内評価制度の影響を受けやすいため、単価アップ(昇給)には一定の時間がかかるのが一般的です。
フリーランスと正社員は雇用形態により単価の違いが生まれるため、どちらを選ぶかはキャリアステップや安定性などで判断するのが良いでしょう。
案件単価の決まり方の違い(直接契約 vs エージェント vs 企業雇用)
フリーランスと正社員の単価は、単純に「高い・低い」で語れるものではありません。その背景には、報酬がどう決まり、どこにお金が流れているかという構造の違いがあります。
直接契約(フリーランス × クライアント)
クライアントとフリーランスが1対1で契約するスタイル。
仲介がない分、提示された金額がそのまま報酬になるのが最大の特徴です。
営業や契約周りの手続きも自分で行う必要はありますが、スキルと信頼関係があれば最も高単価を狙いやすい方法です。
エージェント経由(フリーランス × エージェント × クライアント)
エージェントが間に入り、クライアントとの契約や条件交渉、案件紹介などを担うスタイルです。
案件単価にはエージェントのマージンが含まれますが、このマージンは基本的にクライアント企業が支払うため、エンジニアの手取り報酬が直接減るわけではありません。そのため、フリーランスとしての報酬を確保しながら、営業や契約周りの手間を任せられる点が大きなメリットです。
また、エージェントによっては相場をふまえた単価交渉や、キャリアに合わせた案件の提案も受けられるため、長期的に見て単価アップにつながるケースもあります。また、信頼できるエージェントであれば、相場に見合った単価で交渉し、継続的に条件を見直すことも可能です。
企業雇用(正社員)
月給制の給与として支払われる形です。エンジニア個人の市場価値よりも、企業の評価制度や人事制度が優先されるため、短期間での単価上昇は難しい場合もあります。その代わり、福利厚生や社会保障などが整っており、安定性を求める人には合っています。
フリーランスエンジニアが高単価を実現する方法
フリーランスとして高単価を実現するには、スキルや実績をただ積み重ねるだけでなく、「どこで・どう評価されるか」を意識して動く必要があります。
たとえば、開発だけでなく要件定義や基本設計など、上流工程の経験がある人は単価のベースが上がりやすくなります。技術力に加えて、クライアントとの折衝や進行管理まで対応できる人材は、現場で重宝されやすいためです。
また、特定の分野に特化するだけでなく、隣接する技術を習得して対応範囲を広げていくことも単価アップにつながります。フロントエンドからバックエンドへ、アプリ開発からインフラやクラウド構成へ、といった広がりは提案できる案件の幅にも直結します。
そしてもうひとつ重要なのが「単価交渉のタイミング」です。実績や評価がついてきた段階で、現状の単価が見合っていないと感じる場合は、遠慮せず相談してみましょう。エージェントを活用している場合は、過去の交渉事例などをもとに、適切なタイミングや言い回しもサポートしてもらえるはずです。
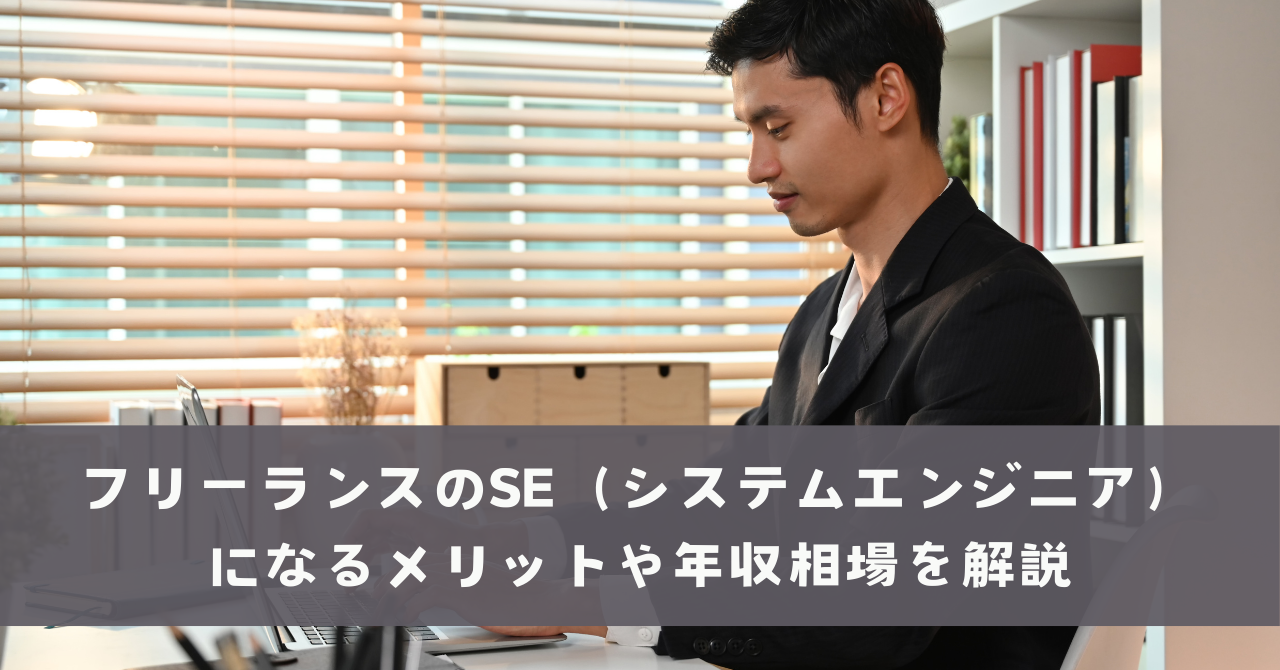
正社員エンジニアが昇給・昇格で単価を上げる方法
正社員として収入を上げるには、社内評価に基づく昇給や昇格を目指すのが基本です。プログラマーからSE、リーダー職やPMなど、職域を広げることで評価が上がり、報酬も上がっていきます。
また、企業が注力している分野や新技術のキャッチアップが早い人材は、昇進や抜擢の対象になりやすく、結果的に年収も上がっていく傾向があります。
ただし、スキルが上がってもすぐに報酬へ反映されるわけではなく、社内制度や評価サイクルに乗って進んでいくのが特徴です。こうした構造の違いが、フリーランスと正社員の単価上昇スピードに差が出る一因となっています。
エンジニアの単価交渉のコツと成功事例
エンジニアの単価交渉のコツと成功事例を以下の4点に分けて解説します。
- 単価交渉の適切なタイミングとは?
- 単価交渉の成功事例と失敗事例
- エージェントを活用した単価交渉の進め方
- 単価交渉の際に必要なポートフォリオと実績の示し方
単価交渉の適切なタイミングとは?
単価交渉は、タイミングを間違えると相手に不信感を与えかねません。
一方で、現場や成果、条件の変化をうまく捉えれば、自然な流れで単価アップを提案することも可能です。
単価交渉を持ちかけやすいのは、こんなタイミングです。
契約更新時
これまでの実績や信頼関係をもとに、次の条件を見直しやすいタイミングです。
仕事の幅が広がっている場合は、役割の変化を交渉材料にすることも可能です。
新プロジェクトの提案や参画時
契約前のフェーズでは、仕事内容・作業時間・単価をまとめて確認できます。
「この業務内容なら、単価はこのくらい必要です」と話を切り出しやすい場面です。
※エージェント経由の場合は、新案件の提案を受けたタイミングがこれに該当します。
成果を出した直後
目に見えるアウトプットや価値提供があった直後は、クライアント側の満足度も高く、単価アップが受け入れられやすいタイミングです。
単価交渉の成功事例と失敗事例
単価交渉の成功事例と失敗事例にはそれぞれ特徴があります。
成功する場合は、実績を示せるタイミングであるプロジェクト成功後や納品後の契約更新時に交渉する場合が多いです。成果物やスキルが向上した証拠などを提示した上で交渉すると、相手も納得しやすくなります。
一方、失敗事例では、クライアントがプロジェクトで忙しい時期や予算が確定した後など、交渉するタイミングがずれているケースが多いです。また、相手の予算や状況を考えずに一方的に金額を提示する場合も、受け入れられる可能性は低くなります。
単価交渉をする際は、自分の都合ばかりを考えるのではなく、相手の立場を理解してWin-Winな関係を提案できるかが鍵となるでしょう。
エージェントを活用した単価交渉の進め方
単価交渉に不安があるなら、エージェントの力を借りるのもひとつの手です。相場観や過去の事例をふまえて、どのくらいの単価が妥当かを客観的に整理してもらえるため、交渉の精度が上がります。
また、エージェントが企業との交渉窓口になるため、金額の話を自分で切り出す必要はありません。伝えにくい内容でも、プロの視点で条件交渉してもらえるのは大きなメリットです。
交渉の際には、自分の実績や担当業務の変化などをエージェントに共有しておくと、話がスムーズに進みやすくなります。「自分では言いづらいけど、今の単価は見直したい」と感じたら、一度相談してみるのがおすすめです。
単価交渉を進めるうえでは、自分の実績や担当業務の変化をエージェントに共有しておくのが大切です。成果や工夫を数値で説明できると、説得力が増します。
エンジニアの単価に関するよくある質問
最後に、エンジニアの単価に関するよくある質問7つに回答します。
- エンジニアの単価はどうやって決まるの?
- 適正価格の案件を選ぶ基準は?
- 単価交渉はどうすれば成功しやすい?
- エージェントを使うと単価は下がる?
- 未経験から高単価エンジニアになるにはどうすればいい?
- フリーランスと正社員、どちらの方が単価を上げやすい?
- リモート案件と常駐案件、どちらが単価が高い?
エンジニアの単価はどうやって決まる?
単価は、スキル・経験年数・契約形態・業界の需要によって決まります。
フリーランスの場合は案件ごとに報酬が設定されるため、同じ技術でも参画先や契約内容によって単価に差が出ます。一方、正社員は企業の給与制度に基づくため、市場価値よりも社内ルールに左右されることが多いです。
希少性のある言語や高需要の分野に強みを持つエンジニアは、単価が高くなる傾向があります。たとえば、GoやScala、Rustといった実務経験者が少ない言語に対応できるエンジニアは、特定分野での引き合いが強くなります。
また、クラウド(AWS・GCP)やセキュリティ、データ基盤構築やAI開発(LLMや自然言語処理など)といった領域も、継続して人材不足が続いているため、これらのスキルを活かせる案件では高単価が期待しやすくなります。
適正価格の案件を選ぶ基準は?
適正価格の案件を選ぶためには、市場の相場を把握することが大切です。エンジニアの単価は、スキルや経験年数、作業内容のボリューム、契約形態などによって変わります。
例えば、SESエンジニアの場合は経験に応じて単価が決まることが多く、未経験者と5年以上のベテランでは大きな差があるのが一般的です。自分と同じ条件のエンジニアの相場を知ることで、提示された価格が適正かどうかを判断する基準となります。
また、単価が適正かどうか決める際は、自分の価値と照らし合わせることも大切です。求められる業務内容や作業量が自分のスキルに見合っていない場合は、交渉するか別の案件を探すことも検討しましょう。
単価交渉はどうすれば成功しやすい?
実績や信頼関係が築けている状態であれば、契約更新や新規案件参画のタイミングが交渉の好機です。スキルや成果を客観的に伝えつつ、相手企業の事情や予算感も踏まえて話を進めることが大切ですが、それには日頃からのコミュニケーションを通じて相手のスタンスを把握しておくことも重要です。
「要求」ではなく「提案」の姿勢で臨むことが、相手に受け入れられやすく、交渉成功のポイントになります。
交渉が苦手な場合は、エージェントを通じて調整してもらうのも有効です。
エージェントを使うと単価は下がる?
エージェントを使うからといって、単価が下がるとは限りません。案件によっては、エージェントが間に入ることで交渉の余地が生まれ、スキルに見合った報酬を引き出せるケースもあります。特に実績のあるエンジニアには、エージェント側が企業と調整し、相場以上の単価が提示されることも珍しくありません。
さらに、営業活動や契約交渉の代行、トラブル時のフォローなど、金額以外の価値も多く含まれているため、総合的に見てメリットの大きい選択肢といえるでしょう。
未経験から高単価エンジニアになるにはどうすればいい?
いきなり高単価を狙うのは難しくても、計画的に経験を積めば十分実現可能です。
まずは基礎スキルの習得とポートフォリオ作成、次に小規模な実務経験を積み、徐々に専門性をつけていくのが王道ルートです。特定の分野に強みを持ち、上流工程やフルスタックに対応できるようになれば、フリーランスとして高単価の案件にも手が届くようになります。
フリーランスと正社員、どちらの方が単価を上げやすい?
短期的に単価を上げやすいのは、フリーランスです。案件ごとに単価交渉ができるため、スキルや実績に応じてすぐに反映されやすく、交渉次第で報酬条件を改善できる可能性があります。
一方、正社員は企業の評価制度に基づいて年1回程度の昇給が一般的です。昇格や転職を経ないと大幅な給与アップは難しく、即時的な収入の変化は得にくい構造です。
収入面での柔軟性や上限のなさではフリーランスに軍配が上がりますが、安定性や福利厚生といった面では正社員に利があります。「リスクをとって収入を上げたいか」「安定を重視しながらキャリアを築きたいか」で選ぶのがよいでしょう。
リモート案件と常駐案件、どちらが単価が高い?
単価の高さは、働き方よりも担当する工程やスキルレベルによって決まるケースがほとんどです。常駐だから高単価、リモートだから低単価という明確な傾向はなく、どちらの形態にも高単価案件は存在します。
ただし、ITコンサルのように経営層との連携が密に発生する職種では、信頼関係を築きやすい常駐が選ばれることもあります。とはいえ、これは一部の例にすぎません。
現在は「完全常駐」よりも週2〜3日リモートを含む柔軟な働き方が主流です。単価だけでなく、どんな働き方が自分にとって無理なく続けられるかも判断材料にしていくのが現実的です。
ITエンジニアの案件探しならエンジニアファクトリー

フリーランスとして適正単価で働きたい方は、ITエンジニア専門エージェント「エンジニアファクトリー」の活用がおすすめです。公開案件数は8,000件以上(2025年4月時点)、スキルや希望条件に応じて月単価100万円以上の高単価案件も提案可能です。
エージェントが相場感を踏まえて交渉もサポートするため、初めての方でも安心して単価調整ができます。さらに、契約継続率は95.6%と、参画後のフォロー体制にも定評があります。適正単価で納得感のある働き方を実現したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
エンジニアの単価は、スキルや経験だけでなく、職種や契約形態、市場の需要によって大きく変わります。フリーランスは交渉やスキルの活かし方次第で短期的に単価アップが狙えますが、正社員は安定した環境で着実に成長できるという強みがあります。
単価を上げたいと感じたときは、今の働き方を見直すタイミングかもしれません。どんなスキルを身につけ、どんな案件に関わりたいのか。自分のキャリアに合った形で、無理なく続けられる選択肢を見つけていくことが大切です。