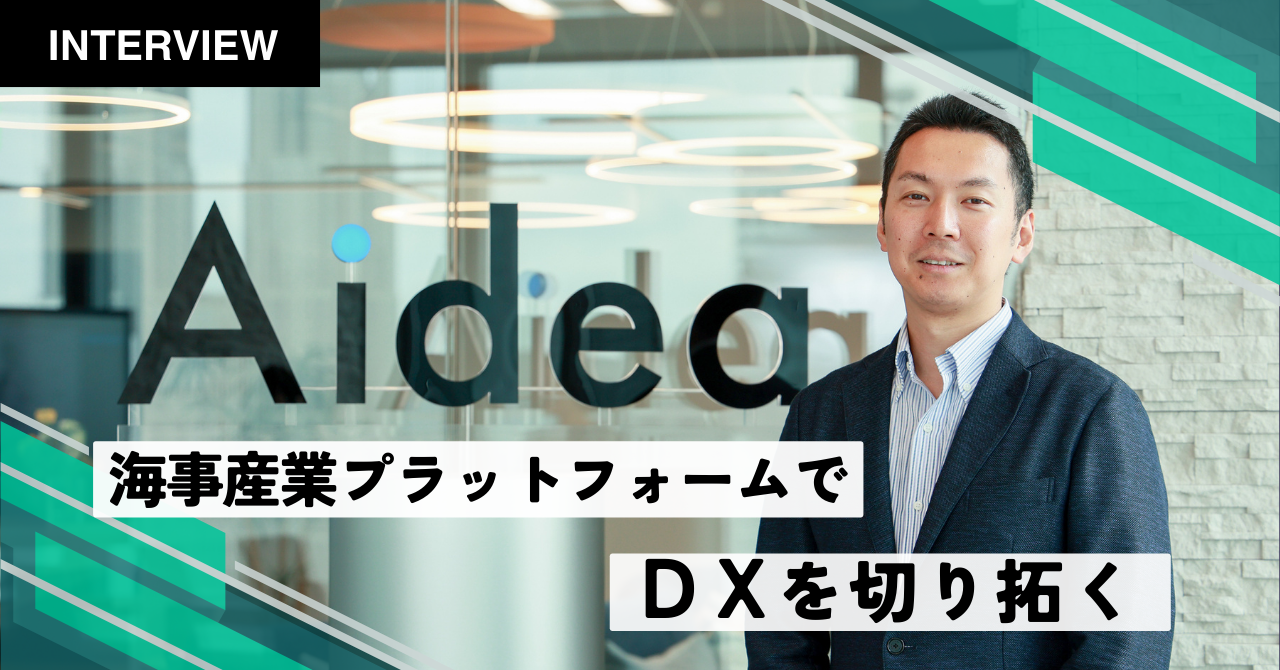会社紹介
社名:株式会社ecbeing
代表:林 雅也
事業内容:
・ECサイト構築
・コーポレートサイト、サービスサイトなどの各種サイト構築
・ECビジネスコンサルティング
・ECサイトデザイン制作
・ECプロモーション・マーケティング
・EC専用インフラサービス
株式会社ecbeingは東京・渋谷に拠点を構え、EC分野で国内シェアNo.1の構築実績を誇る企業です。1982年にパソコンショップ「ソフトクリエイト」として創業し、1997年にはインターネット通販へ参入。そこで培った豊富な販売・運営ノウハウを活かし、ECサイト構築パッケージ「ecbeing」を開発・提供してきました。2022年度には累計1,600件を超える導入実績を達成しています。今回は、ゼクスタント統括部 統括部長代理の鈴木 盛士(すずき せいじ)さんに、同社の事業や社風、採用計画について伺いました。
ゼクスタント統括部 統括部長代理 鈴木 盛士さん
2005年に新卒で株式会社ecbeingへ入社。自社パッケージ「ecbeing」を基盤としたEC構築プロジェクトにおいて、プログラマー/SE/PL/PMとして下流から上流まで15年間携わり、チームマネジメントも経験。その後、製品開発部門へ異動し、組織運営や人材育成を中心に従事。2025年4月よりゼクスタント統括部の統括部長代理に就任し、機能品質の安定化・向上をミッションに、課題解決や仕組みづくりに取り組んでいる。
組織としては国内シェアNo.1のEC構築パッケージを強みに、ワンストップのソリューション提供を展開。人材育成やナレッジ共有に積極的に取り組み、新卒メンバーの増加とともに成長を実感できる環境を整えている。
日常で目にするサービスの裏側を支えるしごと

ーー御社の事業やサービスについて教えてください。
鈴木 盛士様(以下、鈴木):
当社の主力は、社名と同じ「ecbeing」というECサイト構築パッケージです。国内シェアNo.1を誇り、中堅・大手企業様を中心に1,600サイト以上の導入実績があります。
特徴は「お客様の声を重視したマーケットイン型の開発」と「インフラからアプリケーション、保守・運用まで自社リソースで提供できるワンストップ体制」です。単なるシステム提供にとどまらず、事業成長を支えるパートナーとしてサービスを展開しています。
ーー御社の事業にかかわる魅力を教えてください。
鈴木:例えば、誰もが知る企業様と一緒に仕事を進め、そのオンライン販売やビジネスの仕組みを支えられる点は非常にやりがいがあります。普段の生活で消費者として接しているブランドの裏側に関わることができるのは、この仕事ならではの魅力ですね。
私自身、結婚式の場で社長にスピーチをいただいた際、当時担当していたプロジェクトに触れてもらえました。仕事で取り組んでいたことを家族や友人にも共有でき、プライベートでも自分の仕事を胸を張って語れる瞬間になったのは、とても印象深い経験です。
また、ecbeingは「世の中をリードするような取り組み」「形に残る仕事」が多く、成果が目に見えることも大きなモチベーションになります。さらに、会社全体として人材育成やナレッジ共有に力を入れており、新卒で入社した若手がどんどん成長していくのを間近で見られるのも特徴です。マネジメントの立場としても、事業の成長と人材育成を同時に実感できる環境は大きなやりがいだと感じています。
未来をつくる、新しい挑戦 ― BtoB市場へのシフト

ーー今後、御社が注力されていく事業や領域について教えてください。
鈴木:BtoC、つまり一般消費者向けのネットショップやサービスは、これまで当社の強みとして数多く手がけてきました。ですが、DXの流れもあり、今後はECの活用がBtoB領域へ広がっていきます。そこで、これまでに培ってきたBtoCでのノウハウをBtoBにも活かし、事業領域を拡大すべく注力しているところです。
ーーBtoB市場に参入するにあたり、御社のサービスはどのように変化するのでしょうか?
鈴木:これまでは一般消費者がターゲットでしたが、それを企業間取引に置き換えると大きく変わります。たとえば部品の発注やサプライ品の手配といった、より大規模で複雑なプロセスが追加されます。商流や発注タイミング、数量など、BtoBならではの要件が数多く発生するのです。
一方で「人が使うサービスである」という本質は変わりません。たとえBtoBであっても、使いづらい仕組みや洗練されていないUIでは、利用者に浸透せず、結果的に事業価値を生み出せません。発注や取引の現場においても、直感的に操作でき、ストレスなく使える設計が求められます。
私たちはこれまでBtoCの領域で、消費者に選ばれ続けるUIやデザインを数多く提供してきました。その知見は、BtoBにおいても大きな強みになります。単に「機能する」だけでなく、「気持ちよく使える」体験を設計することこそ、サービスを根付かせる鍵だと考えています。
ーーBtoB向けの製品では、業界ごとのニーズに合わせたカスタマイズも検討されているのでしょうか?
鈴木:はい。カスタマイズは個別のご要望にも対応していく予定です。これまでに蓄積してきたナレッジとBtoB特有の要件を融合させながら、新しい価値を提供していきたいと考えています。
プロダクトと現場を結ぶ、2つのエンジニア像

ーー現在募集されている具体的なポジションについて、教えてください。
鈴木:私が所属しているのは「ゼクスタント統括部」という、自社の製品・サービスそのものを手がけるチームです。いわゆる自社プロダクトに専念できる部署ですね。
この部署で活躍するメンバーには、大きく二つの役割があります。ひとつは「製品開発」と呼んでいるポジションで、サービスを強化しながらプロダクト自体を進化させていくエンジニア。もうひとつは、お客様向けにソリューションを提供するコンサルタントです。
別部門では、主力製品である「ecbeingパッケージ」をお客様に納品し、カスタマイズ要件をヒアリングして実装していく、いわばフロントサイドエンジニアの役割もあります。
イメージで言えば、家電量販店で販売されている製品を“つくる”エンジニアと、その製品をお客様の環境に合わせて“調整し、使えるようにする”エンジニア。その二本柱がecbeingを支えています。
ーーそれぞれのポジションの魅力ややりがいを教えてください。
鈴木:お客様側を担当するPMは、上流工程から下流工程まで一貫して対応しています。お客様と直接やり取りしながら要件を固めていくところから始まり、私自身も15年その領域を経験してきました。
人と話すのが好きで、ものづくりだけでなくニーズを汲み取って形にすることにやりがいを感じる方に向いています。要望を丁寧に拾い上げ、それをプロダクトに反映していく過程を楽しめるタイプには、ぴったりの環境です。
一方、製品開発を担当するエンジニアは、新しい技術を取り入れながら、製品を磨き続ける役割を担います。常にチャレンジできる環境があり、次々と新しい取り組みに挑戦できるのが魅力です。「プロダクトを進化させたい」と考える方には、大きなやりがいを感じられるはずです。
事業の成長は、人の成長とともに。挑戦を後押しするカルチャー

――チームとして働き方の指針や、大切にしていることを教えてください。
鈴木:弊社では「事業の成長に合わせて、人も一緒に成長していく」という考え方を強く意識しています。
具体的には、社内勉強会や外部セミナーへの参加を積極的に推奨し、資格取得には全社で支援金を用意しています。特に製品開発部門では、学びの文化づくりを10〜20名だった頃から積極的に取り組んでいました。組織規模が大きくなってもなお、学び続ける文化が根付いているのは非常に良い傾向だと感じています。
――会社や部署の規模が大きくなる過程で、今までの良さを失わないためにしている工夫があれば、教えてください。
鈴木:通常の業務とは別に「委員会制」を設けています。例えば「図書委員会」では書籍を紹介する会を主催したり、社内の本棚を管理したりしています。備品管理委員会もあり、社内備品の管理や共有をスムーズに進める役割を担っています。
委員会メンバーは1年ごとに入れ替え、前期の委員長がオブザーバーとしてサポートに入る仕組みです。役割を循環させることで、文化を継続的に守れる体制を整えています。そのほか「ポータル委員会」もあります。部門のポータルサイトを運営し、社内情報を共有・見える化するのが役割です。いわば社内報やナレッジ蓄積の場で、勤怠ルールの整備や周知もここで行っています。
――社内でドキュメントを作成するにあたって意識していることはありますか?
鈴木:提供しているサービスはパッケージベースのシステムが中心となります。そのためドキュメントは「とにかく書く」のではなく、要点を押さえることが重要です。必要なものは作る、一方で不要なものは思い切って作らない。そのバランスを大事にしています。まず「何が重要か」をチームで言語化できることが、最も大切だと考えています。内コミュニティで得られたアイデアが実際のサービスに反映されることも出てくると思います。
受け継がれるベンチャーマインド
――会社の雰囲気や働きやすさについて教えてください。
鈴木:社内にいると当たり前に感じてしまうのですが、転職してきた社員からは「人間関係がとても良い」という声をよく聞きます。困ったときにはすぐに相談できたり、親身になって答えてくれる人が多いのが特徴です。
受け入れ態勢としては、その時々で工夫は変わりますが、基本的にはメンターをつけてOJTでサポートしています。加えて、ウェルカムランチを開いたり、ウェルカムボードを作って自己紹介を共有したりしています。
社員一人ひとりがオンラインのホワイトボードにプライベートも含めた自己紹介を書き込み、それを全員でシェアします。仕事だけでなくプライベートの共通点が見つかることで、日々のコミュニケーションも取りやすくなっています。
――働きやすさや受け入れ体制に加え、御社ならではのカルチャーとして大事にしている考え方はありますか?
鈴木:弊社の前身は「ソフトクリエイト」というパソコンショップで、現会長が立ち上げました。そこからEC事業をスタートさせ、いわばベンチャーの歩みを続けてきました。
私が入社した頃も、まだこれから成長していく段階で、いわゆるベンチャー企業の雰囲気がありました。その後、上場を果たし、グループ会社化が進み、事業会社としても大きく成長しましたが、創業以来のベンチャーマインドはずっと大切にされています。
社是である「Speed&Change」は、組織全体で意識している文化だと思います。
――今後、アイムファクトリーにはどのようなことを期待されますか?
鈴木:弊社は人材獲得においても、マーケットインの姿勢を重視しています。 こちらの要件だけでなく、市場の動きを踏まえたご提案や、募集要件に対する改善点のご指摘などをいただけると大変助かります。人材のプロとして最新の知見を共有いただけることを期待しています。
実際に、アイムファクトリーからご紹介いただいた方は外部パートナーとして大きく貢献してくださり、社内で表彰させていただきました。こうしたご縁を通じて優秀な人材と出会えることも、私たちにとって非常に価値のあることだと感じています。
鈴木さん、お話ありがとうございました。
業界をリードするEC構築パッケージ「ecbeing」を展開し、進化を重ねる株式会社ecbeing。挑戦を後押しし、人と事業の成長を同時に描ける環境があります。自社プロダクトの開発を通じて、大きな成長を実感したい方は、ぜひご応募ください。
担当エージェント紹介

担当エージェント:Usami
◆フリーランスのキャリアに“寄り添う”エージェント
フリーランスエンジニアにとって、案件の選択はキャリアを左右する重要な決断です。私は単なる案件紹介にとどまらず、将来的なキャリアプランまで考えた提案を大切にしています。
また、参画後も継続してサポートし、プロジェクトの状況や働き方の変化に合わせたフォローを実施。フリーランスだからこそ、安定して働き続けられる環境を一緒に考えていきます。