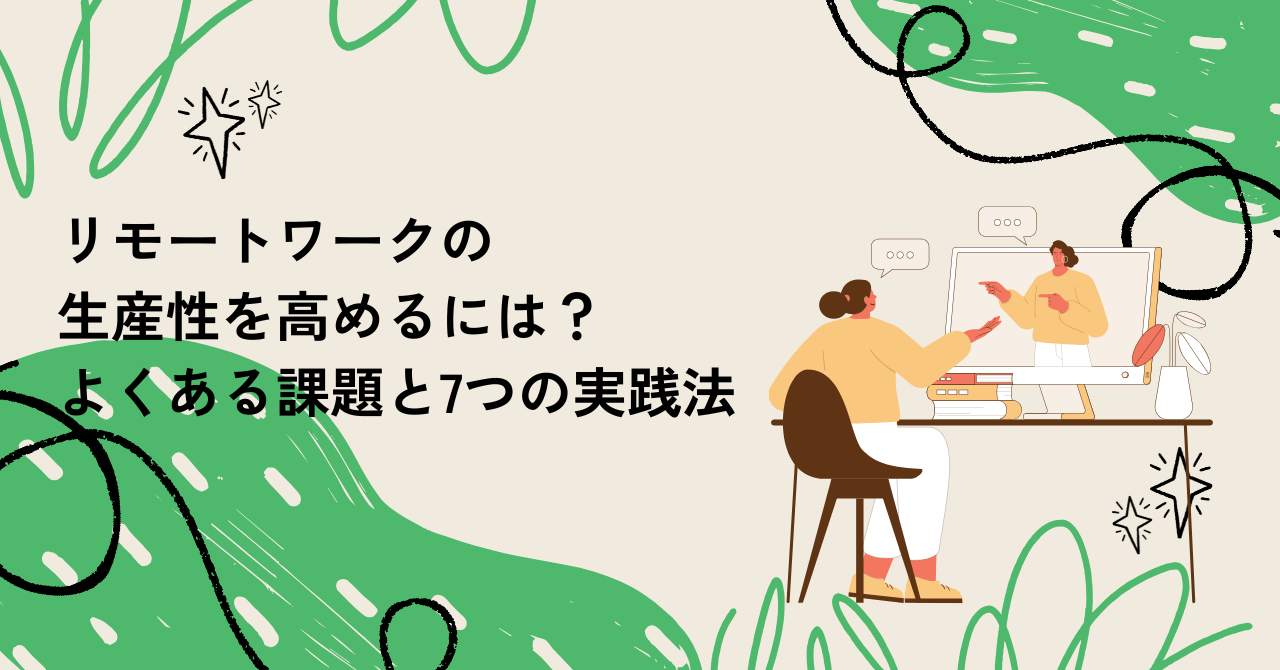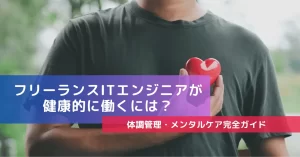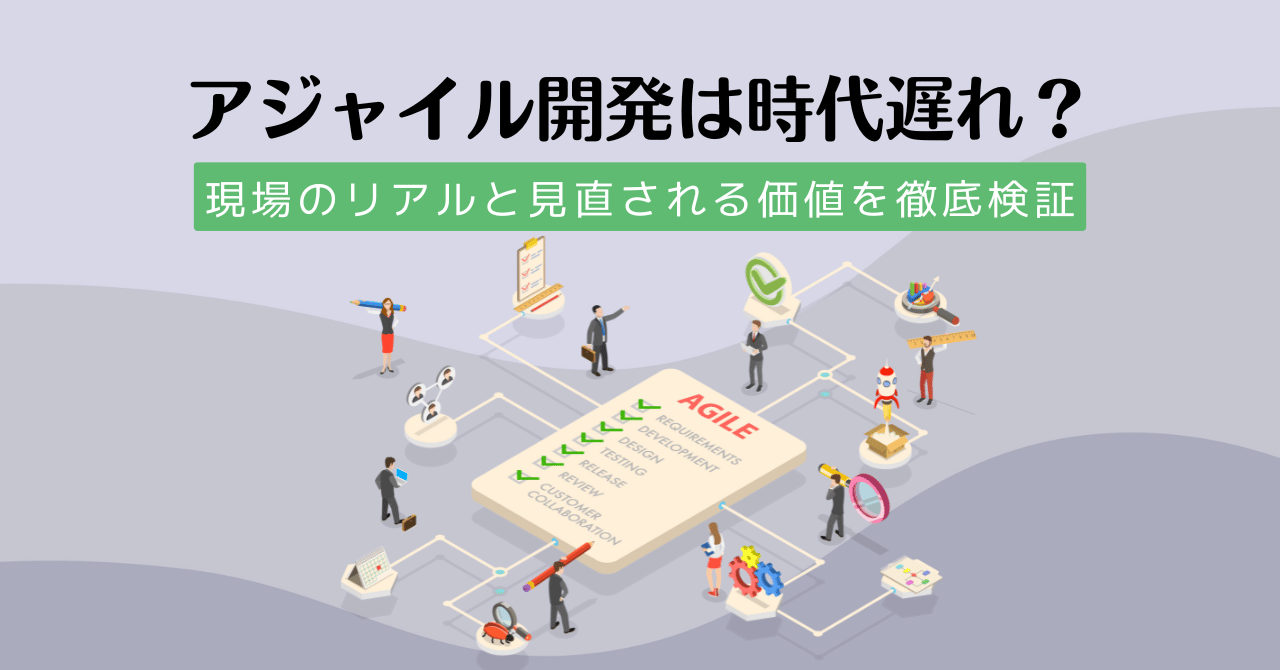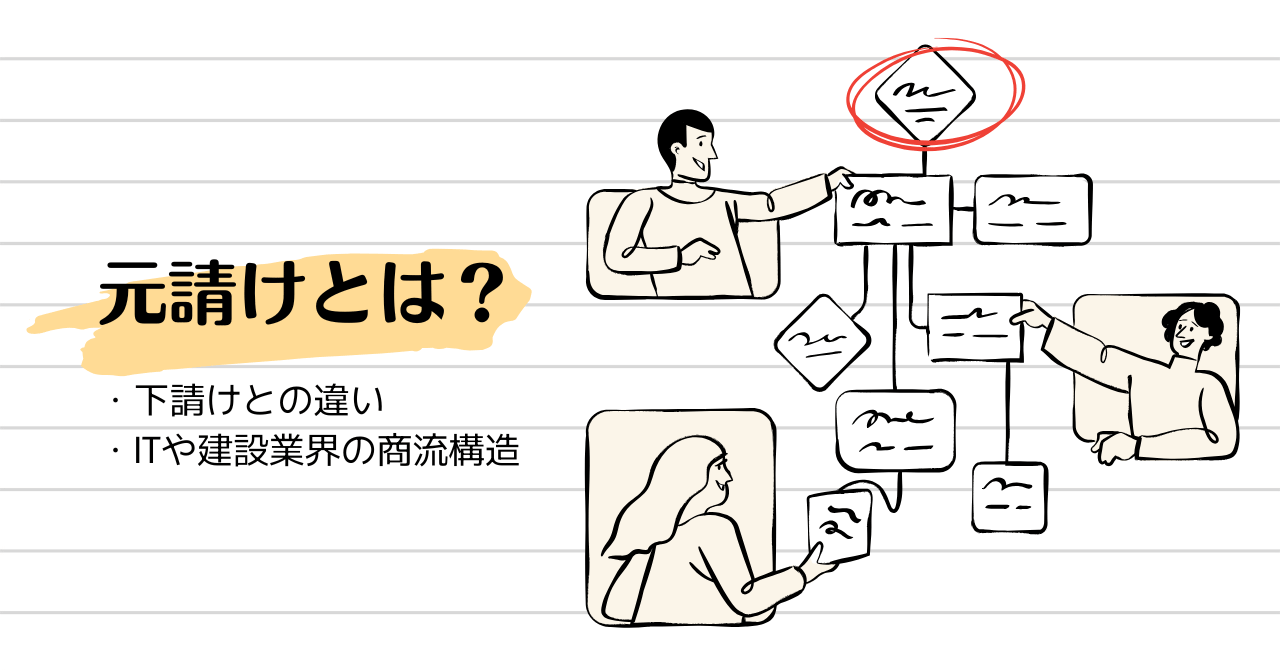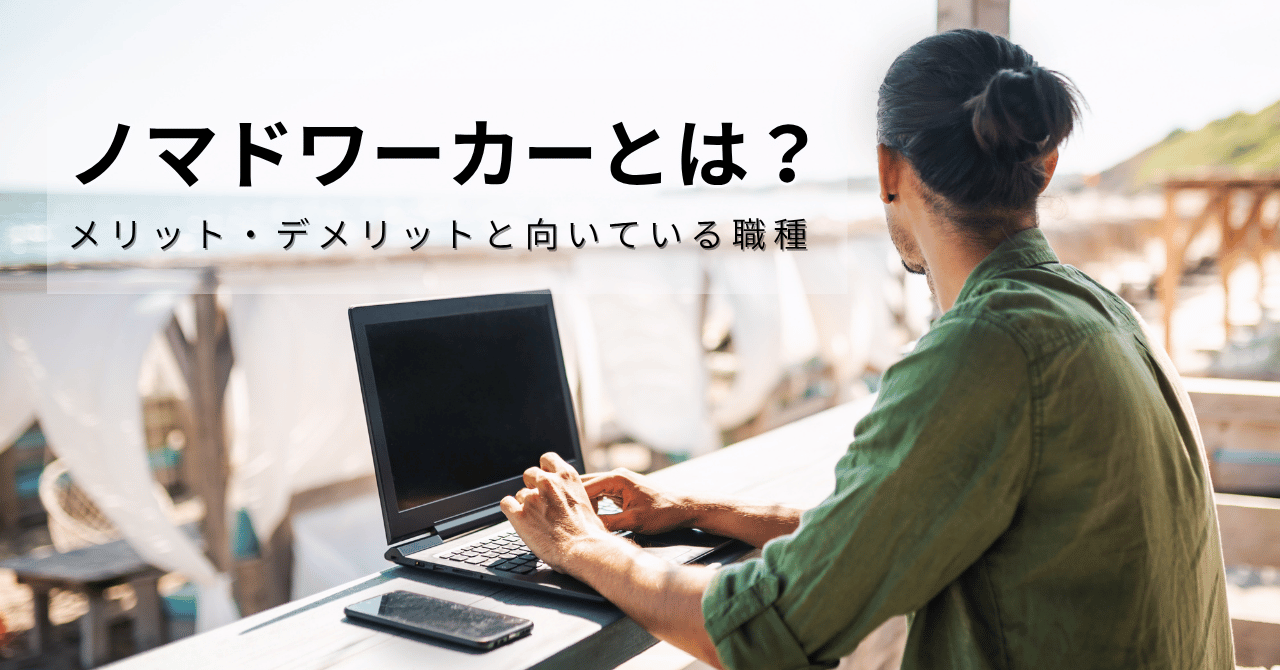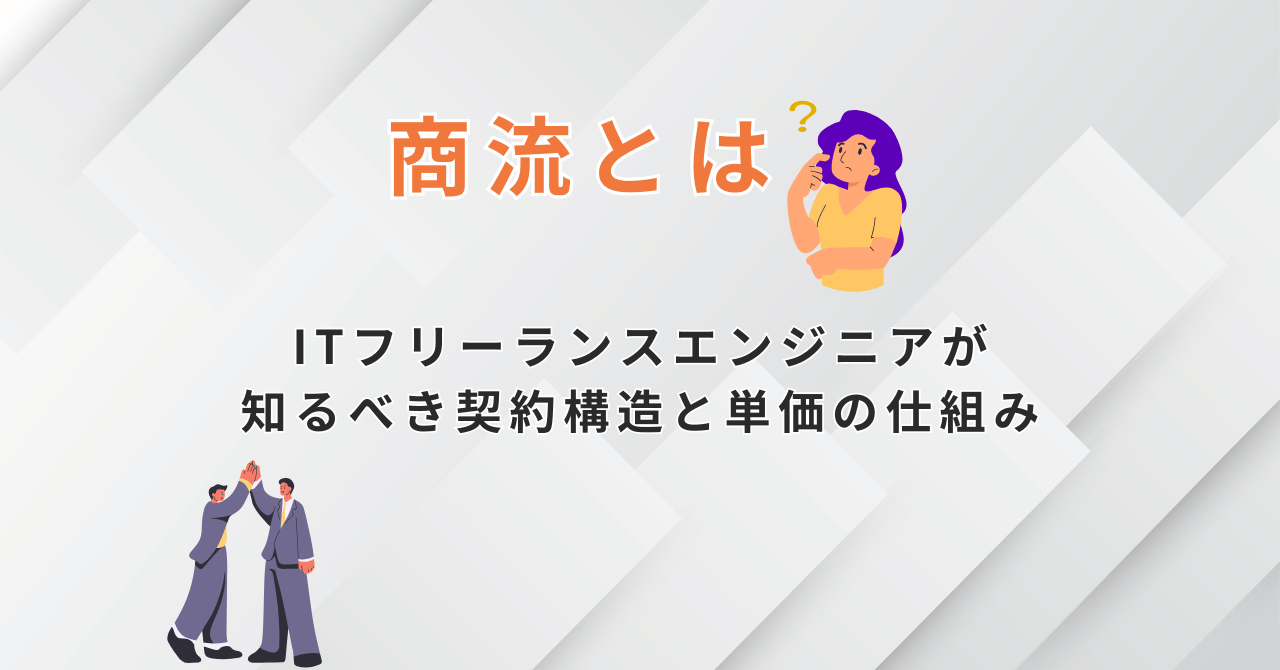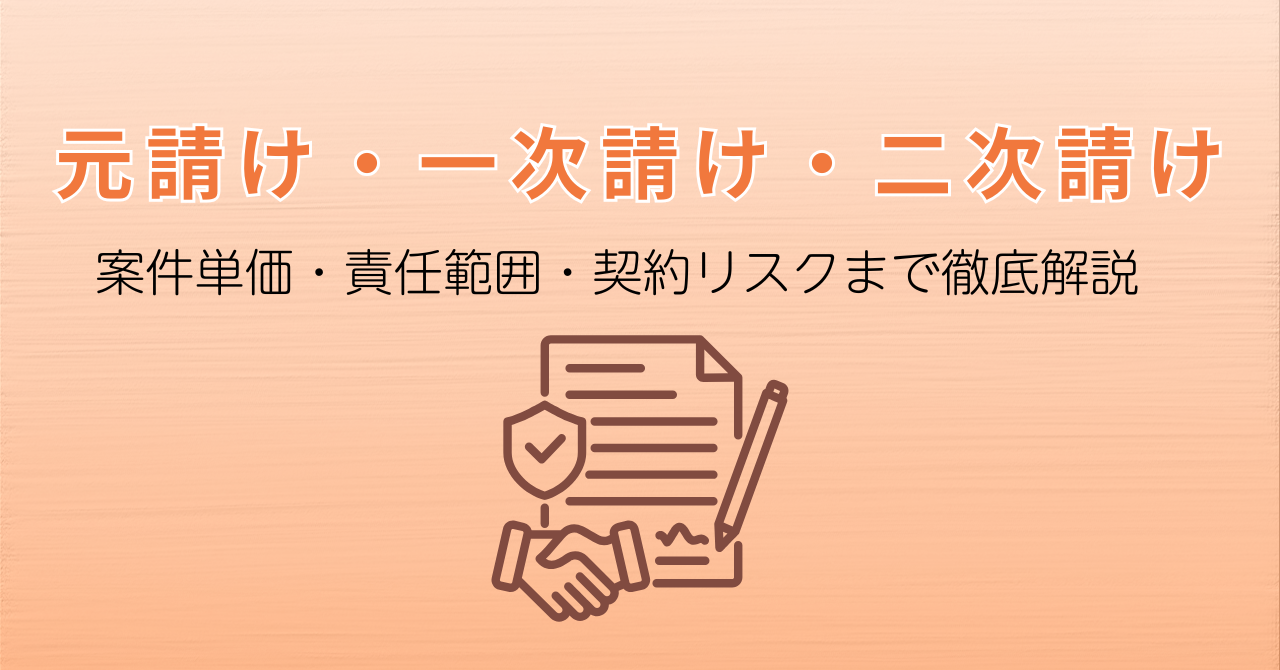新型コロナウイルスの感染拡大以降、自宅などで働くリモートワークが普及しています。リモートワークは柔軟な働き方が実現できる一方、生産性の低下が懸念される点も否めません。
本記事ではリモートワークで生産性が低下する原因、実践的な改善策や成功事例を紹介します。自宅でもパフォーマンスを最大化したい方は、ぜひご覧ください。

エンジニアファクトリーでは、フリーランスエンジニアの案件・求人をご紹介。掲載中の案件は10,000件以上。紹介する案件の平均年商は810万円(※2023年4月 首都圏近郊のITエンジニア対象)で、ご経験・志向に合った案件と出会えます。
簡単なプロフィール入力ですぐにサポートを開始。案件にお困りのITフリーランスの方やより高条件の案件と巡り合いたいと考えている方は、ぜひご登録ください。
リモートワークで生産性は下がるのか?
結論から言えば、リモートワークは運用次第で「生産性が上がる場合」と「下がる場合」の両方があり得ます。たとえば、集中できる作業環境が整っていたり、ツールやルールが明確であれば、オフィス勤務以上に効率よく働けるケースもあります。一方で、コミュニケーション不足や仕事とプライベートの切り替えがうまくできない環境では、生産性の低下が起こることも事実です。
まずは、オフィス勤務とリモートワークの主な違いを整理し、そのうえでリモートワーク特有のメリット・デメリットについて見ていきましょう。
オフィス勤務とリモートワークの比較表
| 観点 | リモートワーク | オフィス勤務 |
|---|---|---|
| 通勤 | 不要。時間・体力を節約できる | 通勤が必要。時間とストレスが発生 |
| 集中環境 | 個人最適だが生活音・誘惑の影響あり | 周囲に人が多く、集中を妨げられることも |
| コミュニケーション | チャット・ビデオでタイムラグあり | 対面で即時にやりとりが可能 |
| 作業の可視化 | ツール導入が前提。管理しづらい場合も | 上司や同僚に見える形で進行可能 |
| 柔軟性 | 働く時間・場所に自由度がある | 就業時間・場所が固定されがち |
| プライベートとの切り替え | オンオフの切り替えが難しいことも | 明確に切り替えやすい |
リモートワークのメリット
リモートワーク最大の利点は、通勤時間がなくなることです。移動にかかっていた1〜2時間を自己研鑽や業務に充てられるため、時間の使い方に大きな変化が生まれます。また、働く環境を自分で調整できる柔軟性も大きな魅力です。集中しやすい空間で仕事に取り組めることは、パフォーマンスの向上にもつながります。
さらに、ライフスタイルに応じた働き方が可能になる点もメリットです。育児や介護など、これまで働き続けることが難しかった状況でも、仕事と家庭を両立しやすくなります。こうした柔軟な環境は、離職率の低下や社員満足度の向上にも寄与します。
リモートワークのデメリット
一方で、リモートワークには克服すべき課題も存在します。コミュニケーションの取りづらさはその一つで、テキスト中心のやり取りではニュアンスが伝わりづらく、誤解や遅延が生じやすくなります。加えて、進捗や勤怠の把握が難しくなるため、マネジメント側の負担が増える傾向があります。
また、生活空間と仕事場の境界が曖昧になりやすいため、オンオフの切り替えがうまくいかず集中力が続かないといった悩みも。逆に、常に仕事ができる環境ゆえに働きすぎてしまうケースもあり、バーンアウトのリスクにも注意が必要です。
リモートワークで生産性が下がる場合の原因と対策
リモートワークでも成果を出している人がいる一方で、思うようにパフォーマンスを発揮できない人もいます。その差は、環境や働き方の工夫だけでなく、見落としがちな課題に気づいているかどうかにもあります。
生産性が落ちやすい場面には共通点があります。ここでは、よくある5つの要因を取り上げ、それぞれがどのようにパフォーマンスに影響するのかを見ていきます。
コミュニケーション不足
リモートワークでは、コミュニケーションの取りづらさが生産性低下の一因となります。対面のやり取りがないことで、情報の行き違いや認識のズレが発生しやすく、進捗が見えにくいため、チーム内の連携がうまくいかない場面も出てきます。
たとえば、メールやチャットの未読が長く続けば、返信が遅れ、意思決定までのスピードも落ちてしまうでしょう。また、テキストのみのやり取りでは、指示の細かなニュアンスまで正確に伝えるのが難しいという課題もあります。
こうした問題を放置すれば、認識のズレや手戻りが増え、全体の業務効率にも影響します。だからこそ、早い段階での改善が求められます。
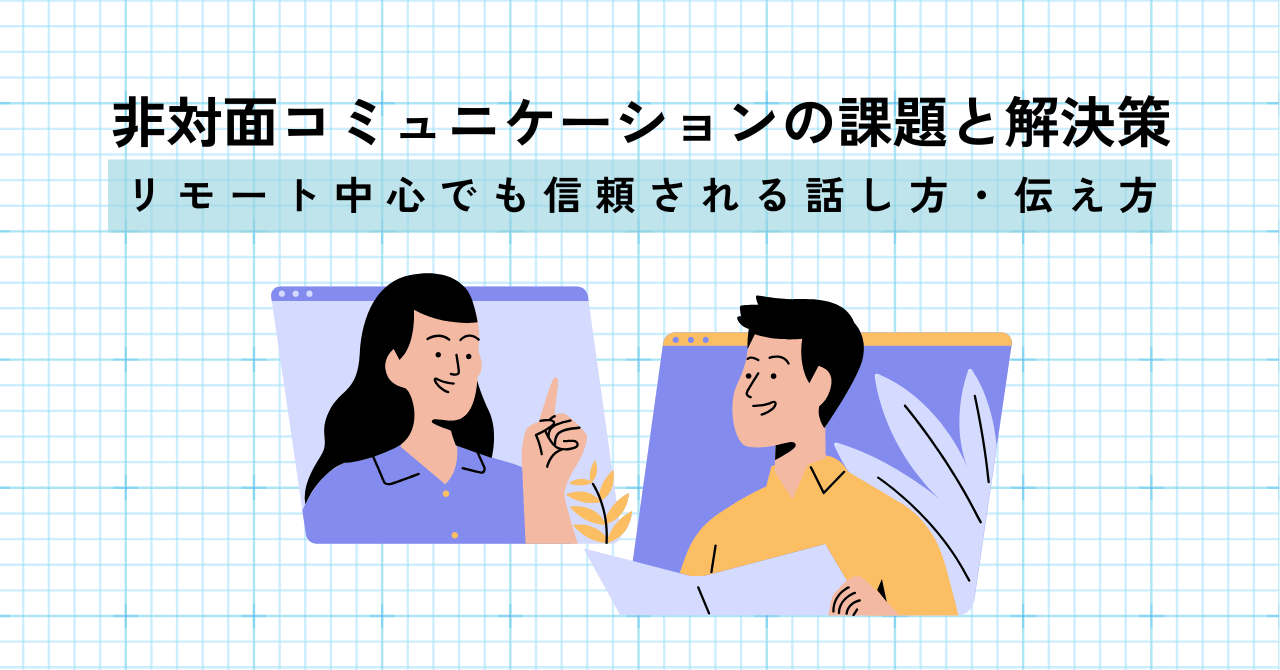
進捗管理・労務管理の難しさ
リモートワークでは、メンバーの作業状況や勤務時間が見えにくくなるため、進捗や労務の管理に課題が生じやすくなります。
特に、タスクの遅れに早期気づけないことが原因で、対応が後手に回るケースも少なくありません。進捗が不透明なままだと、サポートが遅れ、納期の遅延やチーム全体の足並みの乱れにつながる恐れがあります。
また、勤務時間の自己管理に任される環境では、長時間労働や業務密度のばらつきも起こりがちです。目に見えない過重労働が習慣化してしまうと、チームのパフォーマンスに悪影響を及ぼすリスクも高まります。
こうした状況を防ぐためには、タスク管理ツールを活用した進捗の可視化や、報告・確認のルール整備が不可欠です。働き方の透明性を高める仕組みづくりが、リモート下でも安定した生産性を支える土台になります。
仕事とプライベートの切り替えが困難
自宅で仕事を行うリモートワークでは、生活空間と業務空間の境界が曖昧になりがちです。オンとオフの切り替えがうまくできず、集中力が続かないといった声も多く聞かれます。
特に、家族と同居している場合には、会話や生活音が気になり、業務への没入が難しくなることもあるでしょう。一方で、「いつでも働ける」という状況が、逆に休憩を後回しにしてしまう原因になることもあります。
こうした状況が続くと、無意識のうちに疲労が蓄積し、パフォーマンスの低下につながる恐れがあります。リモートワークでは、時間や空間にメリハリを持たせるための工夫が欠かせません。
たとえば、業務専用のスペースを設ける、就業時間を固定する、朝のルーティンを作るといった取り組みは、オン・オフの切り替えに効果的です。自律的に働く環境を整えることで、持続可能な働き方を実現しやすくなります。
作業環境が整っていない
リモートワークでは、オフィスと比べて作業に適した環境が確保されていないことが少なくありません。こうした状況が続くと、業務効率や集中力に悪影響を及ぼす恐れがあります。
たとえば、通信環境が不安定な場合には、Web会議が途切れたり、クラウドサービスへのアクセスが遅れたりと、仕事の進行に支障が出る場面もあります。また、長時間作業に適さないデスクや椅子を使用していると、姿勢が崩れやすくなり、集中力の低下や身体への負担が蓄積しやすくなるでしょう。
そのため、作業環境の見直しは後回しにせず、優先的に取り組みたいポイントです。通信機器や家具の改善だけでなく、照明や室温、騒音対策といった要素にも目を向けることで、より快適なリモートワーク環境を実現できます。こうした基盤整備を進めることが、継続的なパフォーマンス向上につながる鍵となります。
長時間労働が増えやすい
リモートワークでは、勤務時間の境界があいまいになりがちです。明確な始業・終業の区切りがないため、知らず知らずのうちに働きすぎてしまうケースも珍しくありません。
特に自宅での作業では、つい時間を忘れて作業を続けてしまったり、仕事とプライベートの切り替えがうまくいかず、休憩を後回しにしてしまうことがあります。結果として、業務の効率は下がり、心身への負担が増える一因となります。
また、「成果を出さなければならない」というプレッシャーから、自主的に作業時間を延ばす人も見受けられます。こうした状況が続くと、バーンアウトのリスクが高まり、生産性をかえって損なうことにもなりかねません。
長時間労働を防ぐには、スケジュールに明確な区切りを設け、オン・オフを意識的に切り替える工夫が必要です。業務開始・終了のタイミングを決めておくだけでも、働き方にメリハリが生まれ、長期的なパフォーマンス維持につながります。
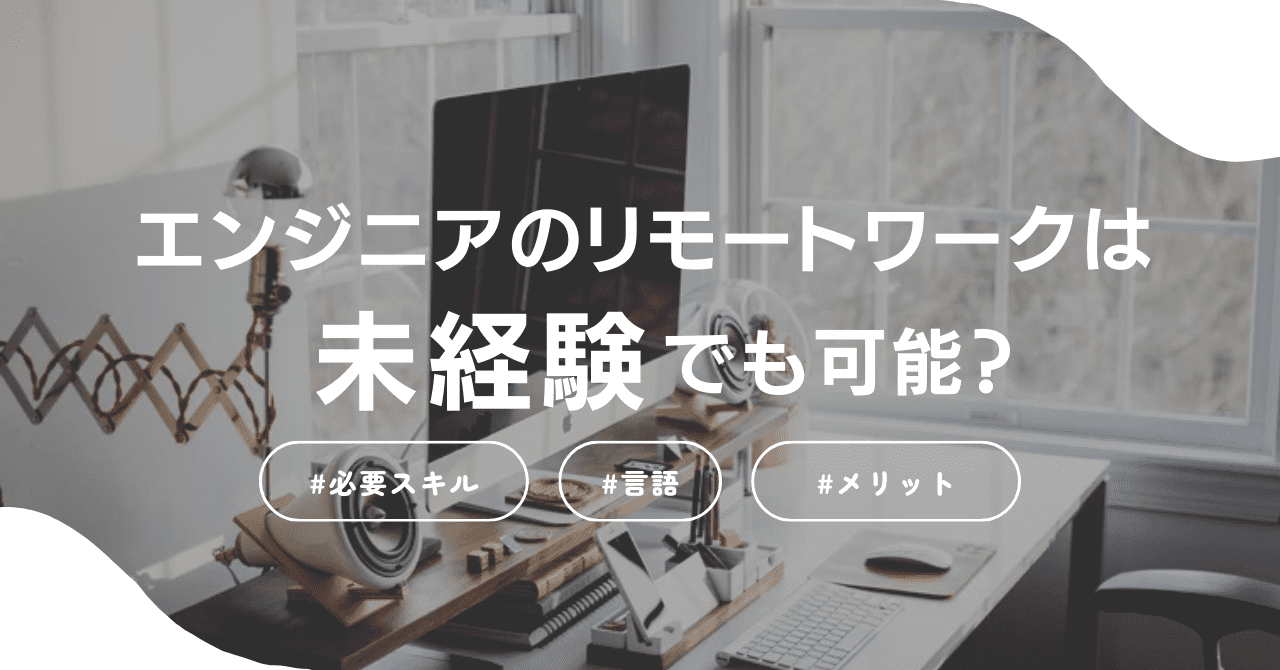
リモートワークの生産性を向上させる7つの実践法
リモートワークで成果を上げ続けるには、単なる業務の効率化だけでなく、働く環境やチーム運営の見直しも欠かせません。ここでは、リモート環境下で生産性を保ち、高めるための具体的な方法を紹介していきます。
業務プロセスの可視化と効率化
リモートワークで業務が滞る主な原因は、誰がどの仕事をしているかが見えづらくなる点にあります。タスクの可視化を徹底することで、情報の行き違いや業務の重複といった無駄を減らすことが可能です。
たとえば、タスク管理ツールやプロジェクトボードを使えば、各自の作業内容や進捗状況を一目で把握できます。こうした仕組みを導入するだけでも、チーム全体の業務連携が格段にスムーズになります。
また、定期的な進捗報告やミーティングの場を設けておけば、小さな課題にも早い段階で気づけるでしょう。結果として、トラブルを未然に防ぎ、生産性の底上げにつながります。
ITツールの活用(コミュニケーション・タスク管理・勤怠管理)
リモートワークでは、業務の可視化や情報共有の円滑化が求められるため、ITツールの活用は欠かせません。たとえばSlackやMicrosoft Teamsは、チャンネルやスレッドを活用することで、情報の整理と即時共有を両立できます。Zoomなどのビデオ会議ツールと併用することで、感情やニュアンスを伴うやり取りもカバーでき、信頼関係の構築にも効果的です。
タスクやプロジェクト管理においては、Trello(ボード形式)、Asana(進捗・期日管理)、Jira(詳細な課題管理に強み)などが代表的です。これらを導入することで、タスクの見える化・優先順位付け・情報共有がスムーズに行えます。
また、勤怠管理には「ジョブカン勤怠管理」や「KING OF TIME」などのツールが有効です。リアルタイムでの出退勤記録や申請・承認が行えるため、長時間労働の是正や人事・労務との連携にも役立ちます。
各ツールは導入後のルール設計と継続的な運用が成果を左右するため、「目的に応じた選定」と「チーム内での使い方の統一」がポイントです。代表的なITツールをカテゴリ別に整理した一覧は以下の通りです。
| ツールカテゴリ | ツール名 | 主な特徴・用途 |
|---|---|---|
| コミュニケーション | Slack | チャットによるリアルタイムな情報共有。チャンネルごとの管理が可能。 |
| コミュニケーション | Zoom | ビデオ会議で対面に近いコミュニケーションが可能。画面共有や録画にも対応。 |
| タスク管理 | Trello | ボード形式でタスクの可視化・整理ができ、進捗管理が直感的。 |
| タスク管理 | Asana | プロジェクト単位での管理がしやすく、担当者・期限の設定が可能。 |
| 労務管理 | KING OF TIME | 多様な打刻方法とリアルタイム集計、過重労働のアラート通知機能もあり。 |
| 労務管理 | ジョブカン勤怠管理 | 勤怠だけでなく給与・人事連携も可能。柔軟な申請・承認フローが魅力。 |
コミュニケーションの質を向上させる
リモートワークでは、対面のコミュニケーションに代わる手段として、テキスト・音声・ビデオ会議など複数のコミュニケーションツールが活用されます。これらの適切な使い分けが、情報伝達の正確性と業務効率を高める鍵となります。
たとえば、簡単な確認や報告はテキストチャット、細かなニュアンスを伝えたい場合は音声通話、そして意思決定や議論が必要な場面ではビデオ会議の使用が効果的です。状況に応じた最適なツールの選択が、誤解を防ぎ迅速な対応へとつながります。
リモートワークはテキストでのやり取りが多くなりがちですが、適切なツールの使用とわかりやすい言葉での情報伝達が、コミュニケーションの質の向上につながるでしょう。
労務管理と評価制度の見直し
リモートワークにおける生産性向上には、従来の評価基準を見直す必要があります。オフィス勤務では「勤務時間」や「勤務態度」なども評価対象の1つになりますが、リモートワークでは適応できません。そのため、成果やプロセスに基づくリモートワーク向けの評価制度の導入が求められます。
たとえば、タスクの達成度や目標に対する進捗、チームへの貢献度などを明確に設定し、定期的にフィードバックを行うことで、個々のモチベーション向上につながります。
また、柔軟な労働時間制度や、成果に応じたインセンティブ設計も有効です。これにより、従業員は自身のペースで効率的に働きながら、生産性を高めることができます。
快適な作業環境を整備する(デスク・椅子・通信環境など)
リモートワークにおいて、作業環境の整備は生産性の維持・向上に直結するため重要です。業務効率を高めるためにも、身体への負担が少ないチェアやデスクの導入は欠かせません。腰痛や疲労を防ぐことで、集中力や作業時間に好影響を与えます。また、適切な高さの机や人間工学に基づいたチェアの導入により、姿勢の乱れや疲労の蓄積を防げます。
さらに、スムーズな業務遂行のためには安定した通信環境も欠かせません。通信トラブルを防ぐためには、ルーターの位置やWi-Fi中継機の設置も視野に入れましょう。特にWeb会議が多い職種では、通信品質がパフォーマンスに直結します。
さらに照明や室温、そして周囲の音環境なども集中力に影響する要素の一つであるため、これらを総合的に整えるとより快適で効率的なリモートワーク環境が実現できるでしょう。
モチベーションを維持する工夫
リモートワークでは人との接点が減ることで、孤独感や単調さからモチベーションが下がりやすくなります。そのため、意識的にやる気を維持する工夫が必要です。
たとえば、定期的にオンラインでのチームミーティングなどを設けると、チームの一体感を高めることができます。また、成果を正当に評価する制度があることで、目標達成に向けた自発的な行動を引き出しやすくなります。とくに表彰やインセンティブの仕組みは、心理的な充足感にも寄与するでしょう。
さらに、自身で仕事の始業・終業のルーティンを決める、目標を細かく設定するといったセルフマネジメントの工夫も効果的といえます。モチベーションの低下は生産性に直結するため、組織全体で取り組むことが重要になります。
ワークライフバランスを保つためのルール策定
リモートワークでは時間や場所に縛られずに働ける反面、仕事と私生活の境界が曖昧になり、長時間労働や長めの休憩をとってしまう状況に陥りやすくなります。
長時間労働を防ぐには、始業・終業時間をチームで共有し、休憩のタイミングもあらかじめ設定しておきましょう。曖昧な境界を明文化することで、働きすぎの抑止にもなります。
また、業務中は一定時間ごとに短い休憩時間の設定も重要です。たとえば「25分作業+5分休憩」を1セットとするポモドーロ・テクニックは、集中力の維持と疲労防止の両立に効果的です。リズムある働き方を意識することで、日々のパフォーマンスが安定します。
このように、業務時間と休息のメリハリをつけることで、ワークライフバランスの向上と生産性の維持・向上が期待できます。
リモートワークの成功事例
ここでは国内・海外におけるリモートワーク導入による成功事例を紹介します。また、リモートワーク導入後に生産性がどう変わったのかデータを用いて解説します。
- 国内企業の成功事例
- 海外企業の成功事例
- リモートワーク導入後の生産性向上データと分析
国内企業の成功事例
日本国内において、リモートワークの導入により業績が向上した企業がいくつかあります。たとえばIT企業のサイボウズ株式会社は、リモートワークをいち早く導入し、柔軟な運用により社員の働きやすさを向上しました。その結果、離職率が減少しチームの生産性向上にもつながっています。
また、リモートワークでも円滑なコミュニケーションを維持するために、オンライン会議やチャットツールの活用を積極的に進めた結果、社内外の連携もスムーズに行われています。
さらに富士通株式会社では、2020年4月より全社一丸となって社内のリモートワーク化プロジェクトを進めています。資料はほぼ電子ファイルでのやり取りになるため、紙の削減や業務の効率化を両立させました。
これらの事例は、リモートワークが単なる一時的措置ではなく、持続可能な働き方として機能していることを示しています。
海外企業の成功事例
リモートワークを積極的に導入し、成果をあげた海外企業を紹介します。たとえば、アメリカのソフトウェア開発企業「GitLab」は、創業当初からフルリモート体制を採用しています。世界中に2,000人を超える従業員を抱えながら、成果を出し続けている理由の一つが「ドキュメント文化の徹底」です。業務マニュアルや社内ルールをすべて明文化・共有し、誰もがアクセスできる状態に保っています。
また、ビデオ会議や1on1ミーティングを定期的に実施し、物理的な距離を超えた心理的なつながりを重視しています。社員同士のコミュニケーションを促進する工夫として「雑談専用チャンネル」を設けるなど、柔軟な仕組みづくりが特徴です。
このような取り組みは、国内企業にとっても参考になるポイントが多く、リモート環境でもチームの一体感と生産性を両立できる好例といえるでしょう。
リモートワーク導入後の生産性向上データと分析
実際にリモートワークを導入した企業の中には、生産性の向上を実感しているケースも多く見られます。たとえば、総務省が2020年に実施した調査によると、テレワークを導入している企業の従業員1人あたりの労働生産性は759万円で、未導入企業の517万円に比べて約1.5倍の差があったと報告されています。
また、ハーバード・ビジネス・スクールの研究では、米国特許商標庁の審査官がリモート勤務を選択したことで、生産性が4.4%向上したとされています。これは、業務時間の自己管理や作業環境の最適化が成果に直結していることを示すデータです。
こうした実例やデータは、リモートワークが単なる「一時的な働き方」ではなく、継続的な成果を生む選択肢であることを裏付けています。
参考:kyozon
リモートワークの生産性を維持・向上するためのチェックリスト
リモートワークで安定した成果を出し続けるには、働く環境や業務の進め方を定期的に見直すことが欠かせません。ここでは、実際の現場で使えるチェックポイントを「環境」「管理」「コミュニケーション」「健康・モチベーション」の4つに分類して紹介します。
リモートワーク環境の整備状況
作業環境の質は、集中力や作業効率に直結します。特にリモートワークでは、オフィスと違い環境整備がすべて自己責任になるため、ちょっとした不備が生産性を左右しかねません。
たとえば、長時間座っていても疲れにくい椅子や、目線と手元の位置が合ったデスクを使っているかどうかで、仕事への集中度は大きく変わります。通信速度が遅かったり、必要なソフトがすぐ使えなかったりすると、タスクが停滞する原因にもなります。
今の環境に不満がなくても、あらためて以下のような点をチェックしておくと安心です。
- 最適な姿勢を維持できる高さ・硬さのデスクとチェアを使用している
- Wi-Fi接続が安定しており、通信速度も問題ない
- 業務に必要なソフトウェアがすべてインストールされ、すぐに使える状態になっている
- 作業スペースが整理され、集中できる環境が保たれている
快適な空間づくりは、一度整えれば終わりではなく、定期的な見直しがカギになります。習慣化することで、コンディションの安定やパフォーマンスの維持につながります。
労務管理・進捗管理の適切な運用
リモートワークでは、メンバーの勤務状況や業務の進み具合が見えにくくなりがちです。出勤・退勤が曖昧になり、タスクの進捗も「なんとなく」で把握している状態が続けば、チーム全体の足並みが乱れ、成果にばらつきが出てしまいます。
特に危険なのは、遅れやボトルネックに早く気づけないこと。対応が後手に回り、納期の遅延や関係者間のストレスにつながります。また、本人に自覚がないまま長時間働き続けてしまうケースもあり、健康面やモチベーションへの悪影響が見過ごされがちです。
こうしたリスクを防ぐには、進捗と勤怠を「見える化」することが前提になります。次のような状態が保たれているか、定期的に確認しておくと安心です。
- 勤怠の打刻が毎日正確に行われている
- タスクがツールで可視化され、進捗状況が明確になっている
- 各メンバーの作業内容や成果が定期的に共有されている
- 優先順位や期日が明示され、遅延リスクが把握できる状態にある
- 日報や週報などによる定期的な報告が継続されている
個人任せではなく、チーム全体で共通ルールとして運用することがポイントです。報告の仕方や頻度、管理ツールの使い方を統一することで、進捗の見落としや認識のズレを最小限に抑えることができます。
チームコミュニケーションの円滑化
リモートワークでは、雑談やちょっとした声かけが減る分、情報共有や相互理解の機会も自然と少なくなります。
「言ったつもり」「聞いていない」「誰に聞けばいいかわからない」そんなすれ違いが続くと、チームとしての一体感が薄れ、連携にも支障が出てきます。
業務上のやりとりだけでなく、人と人との関係性を保つための仕掛けが重要です。情報伝達の質を上げるだけでなく、安心して相談できる空気や、チーム内の心理的な距離を近づける工夫が欠かせません。
以下のようなコミュニケーション設計が継続できているか、一度見直してみましょう。
- 定例のオンラインミーティングが毎週実施されている
- チャットツールで日常的に情報共有が行われている
- メンバー同士の1on1が定期的に組まれている
- 雑談やカジュアルな交流の場が意図的に用意されている
- チーム内の連絡ルールや返信タイミングが明文化されている
形式的なやりとりではなく、関係の「質」を維持するための仕掛けがあるかがポイントです。オンラインでも、「顔が見える・声が聞こえる」機会があるだけで、チームの一体感は大きく変わります。、チーム全体のパフォーマンスが向上します。
従業員の健康管理とモチベーション維持策
リモートワークでは、自分のペースで働ける一方で、体調の変化や気持ちの落ち込みに気づきにくくなります。運動不足、生活リズムの乱れ、孤独感といった課題が、少しずつ蓄積し、気づかぬうちにパフォーマンスを下げてしまうこともあります。
特に、誰にも相談せずにひとりで抱え込んでしまう状態が続くと、心身のコンディションだけでなく、仕事への意欲や判断力にも影響が出てきます。日々の業務を安定してこなすためには、健康とモチベーションを保つための小さな仕組みを、チームや会社全体で設けておくことが大切です。
次のような取り組みが実施されているかを振り返ってみましょう。
- 月1回以上の健康チェックやセルフケアアンケートを実施している
- 定時での退勤や適切な休憩時間の確保がルールとして浸透している
- 運動やストレッチを習慣化するような促しがある
- メンタルヘルスの相談窓口やカウンセリング体制が整っている
- 業務負荷が特定のメンバーに偏っていないか、定期的に確認されている
調子がいいときには気づきにくい部分だからこそ、仕組みとして“当たり前”にしておくことが重要です。気軽に話せる関係性や、無理をしなくていい空気があるだけでも、日々の安心感が変わります。
リモートワークの案件探しはエンジニアファクトリー

リモートワークの課題と解決方法を理解した今、次のステップとして、あなたに合ったフリーランス案件で理想的な働き方を実現しませんか?
エンジニアファクトリーでは、公開案件数8,000件以上を誇り、幅広い選択肢から最適な案件を見つけることができます。さらに、継続率95.6%、年商最大300万円アップを実現したエンジニアも。リモート環境でもスキルを存分に発揮し、さらなる成長と収入アップを目指したい方は、ぜひエンジニアファクトリーをご活用ください!
まとめ
リモートワークはオフィス勤務と比較して柔軟な働き方が可能となる一方で、コミュニケーション不足や進捗管理の難しさ、オン・オフの切り替えの曖昧さなどの課題がある点は否めません。ただし、適切な作業環境の整備や運用次第で十分に成果を上げられます。
課題解決のためには、業務の可視化やITツールの活用、そして労務管理の見直しなど作業環境の整備を行うと良いでしょう。また、健康管理やモチベーション維持に向けた取り組みも重要です。さらに、ツールの適切な導入や成功事例を参考にするなど多角的に対策を講じることで、リモートワークにおける生産性を高めることができるでしょう。