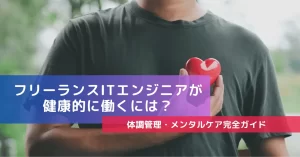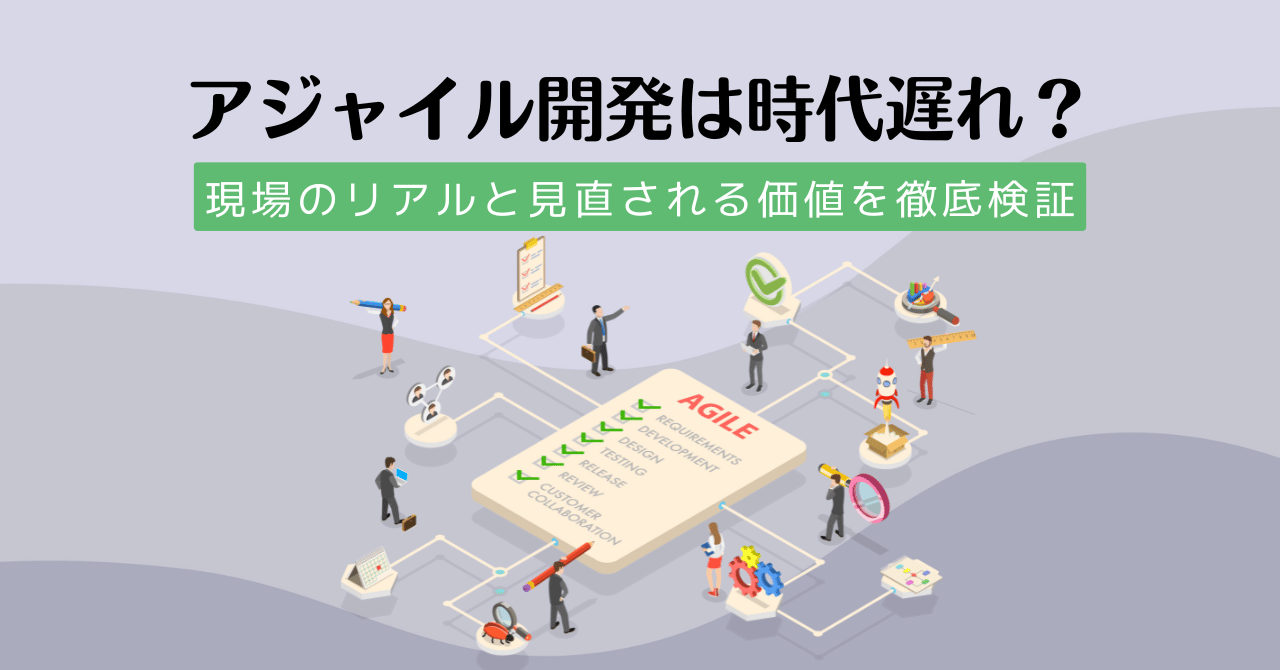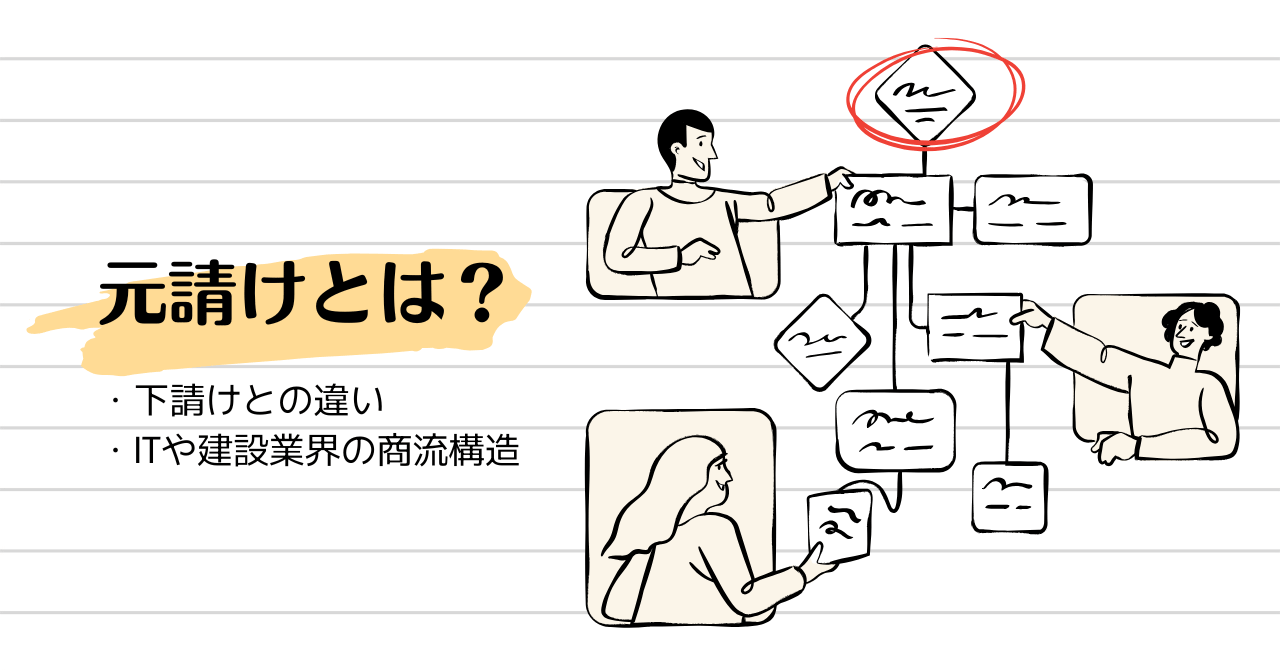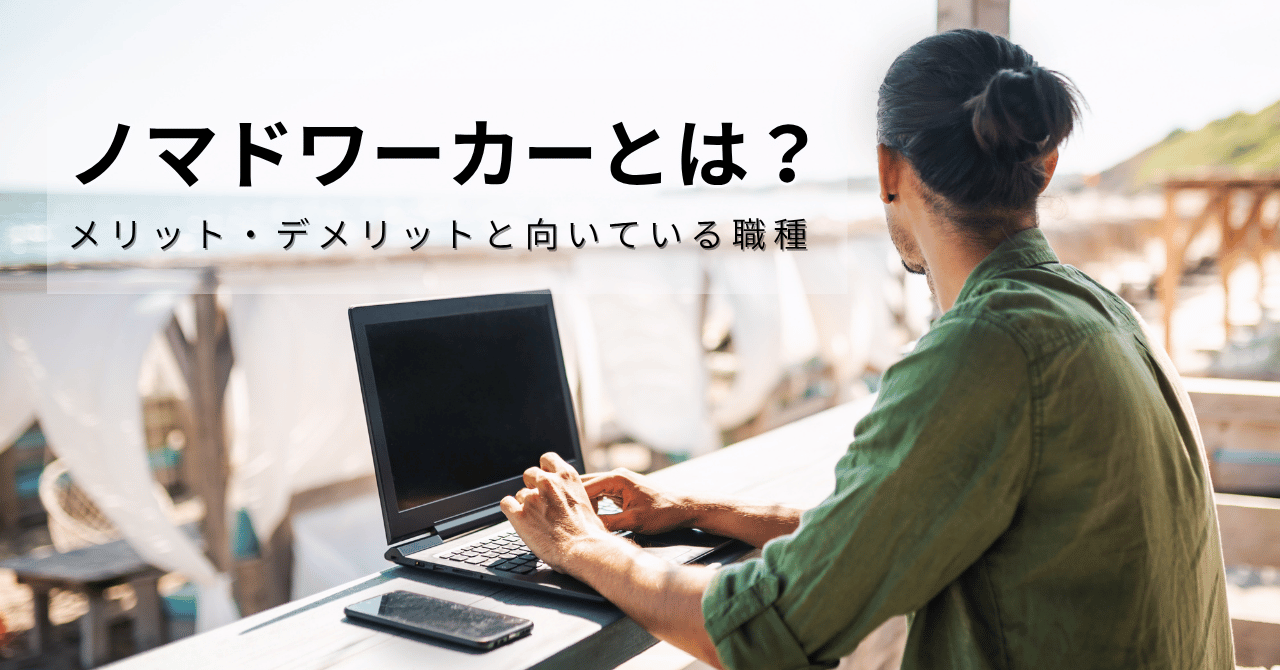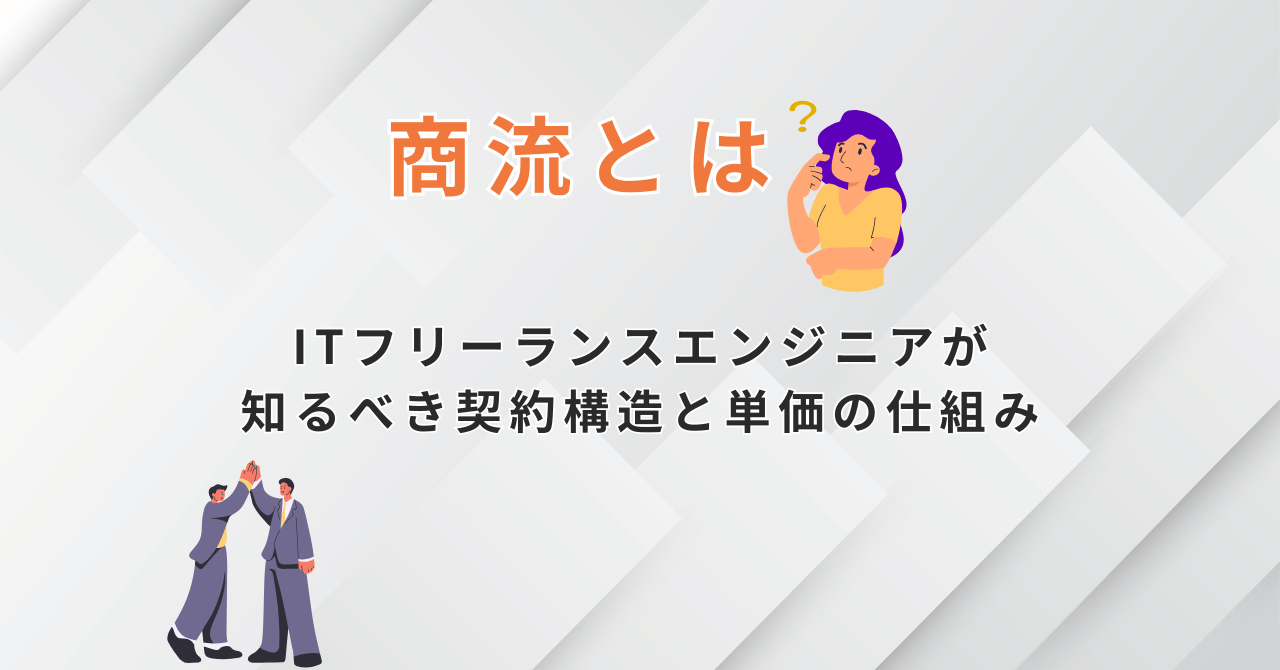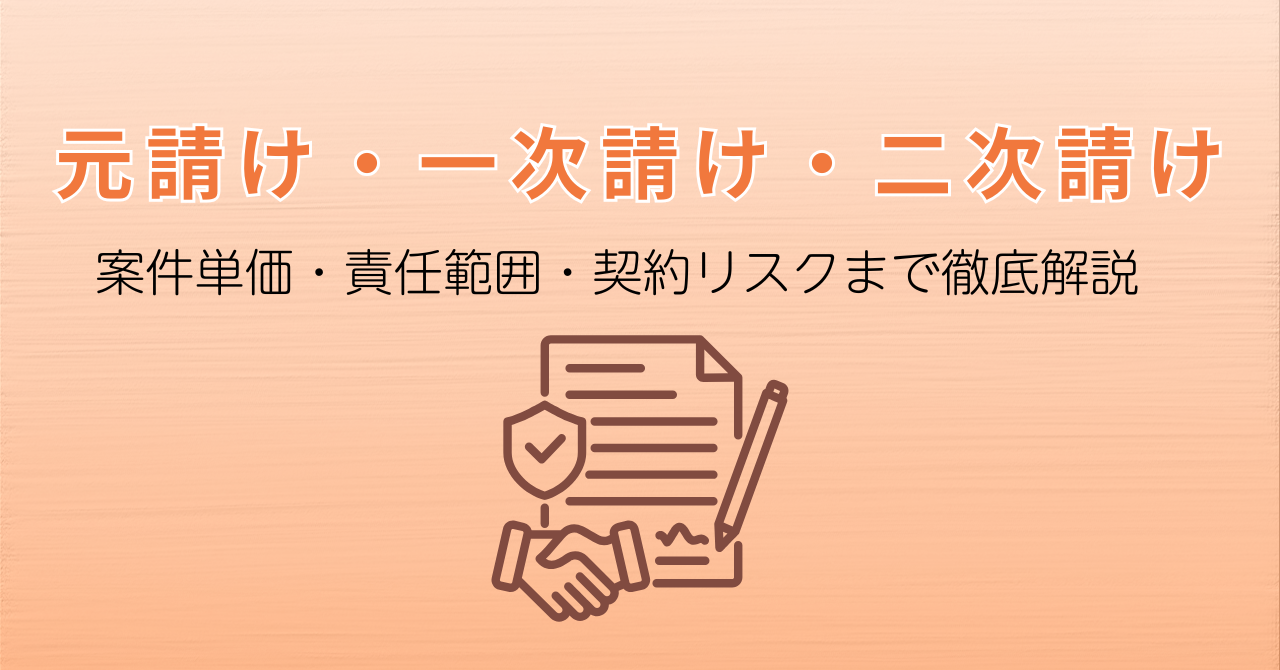「医療費控除の確定申告を簡単に済ませたい」と思っていませんか?実は、スマホを使えば自宅で手軽に申請できます。本記事は、申請に必要な書類の準備からスマホの操作手順、便利なアプリまで分かりやすく解説します。
特に、手間をかけずにスムーズに確定申告を完了させたい方に今すぐ使える情報をお届けしますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

エンジニアファクトリーでは、フリーランスエンジニアの案件・求人をご紹介。掲載中の案件は10,000件以上。紹介する案件の平均年商は810万円(※2023年4月 首都圏近郊のITエンジニア対象)で、ご経験・志向に合った案件と出会えます。
簡単なプロフィール入力ですぐにサポートを開始。案件にお困りのITフリーランスの方やより高条件の案件と巡り合いたいと考えている方は、ぜひご登録ください。
医療費控除を確定申告でスマホから申請する流れ
ここでは、医療費控除を確定申告でスマホから申請する流れを5つのステップで解説します。
ステップ1:医療費通知や領収書データをスマホで準備する
まずは、医療費控除の確定申告をスマホで申請するために必要な書類を準備します。以下の流れを参考に準備していきましょう。
【必要な書類とその入手方法】
| 必要な書類 | 補足 |
|---|---|
| 1年間の医療費領収書(1月~12月分) | 医療費通知に記載されない11月~12月の領収書は必須準備 |
| 医療費通知(医療費のお知らせ) | ・会社員:勤務先から配布される・個人事業主:健康保険組合から送られてくる |
| 源泉徴収票または確定申告書 | ・会社員:源泉徴収票・個人事業主:確定申告書 |
【確定申告をスマホで申請するための準備方法】
- 書類がそろったら、1枚1枚撮影する
- スマホのアルバムやクラウドサービスに保管する
保管は、時系列にしたり「歯医者」「内科」など診療科目ごとに分けて撮影しておくと後から探すのに苦労しないでしょう。
ステップ2:確定申告書等作成コーナーにスマホからアクセスする
つぎに、国税庁の確定申告書等作成コーナーに、スマホからアクセスします。以下の手順に沿って進めてください。
【アクセス方法】
- マイナポータルアプリをインストール
- 利用者登録してログイン
- 「おかね」カテゴリーの「確定申告」をタップ(上から3つ目)
- 画面下にある「確定申告書等の作成」からアクセス
【ログイン方法】
ログインには「マイナンバーカード」と「利用者証明用電子証明書のパスワード(4桁)」が必要です。
- ログインボタンをタップ
- 利用者証明用電子証明書のパスワードを入力して「ログインする」をタップ
- スマホにマイナンバーカードを密着させて読み取り
読み取り時のカードは、スマホにしっかり密着させましょう。読み取りは、少し時間がかかることもあります。
ステップ3:スマホで医療費控除明細書を入力する
つぎに、「作成開始」ボタンをタップして、医療費控除明細書の入力をします。
【医療費控除の入力方法】
作成する申告書等:所得税・作成する年分:該当年度(2025年の場合は令和6年分)
【「マイナポータル」と連携している場合】自動入力されてない11月〜12月分は「追加入力分の医療費」箇所から入力
計算結果の確認画面が表示されたら、控除の入力は完了です。
ステップ4:確定申告書をスマホで確認・修正する
医療費控除の入力が完了したら、入力した内容を確認していきましょう。
【入力内容の確認方法】
確定申告後の還付金または追納金の確認
・受け取り方法(還付金がある場合)
・納付方法(追納がある場合)・住所・氏名 など
【確認ポイント】
①収入金額に誤りはないか
②控除に書いた内容と金額に誤りはないか
③本人情報、振込先口座に誤りはないか
「⑤表示された画面で入力した内容」は、確認ポイントを参考に入念にチェックしましょう。誤りがあった場合は「申告内容の確認・訂正」から入力内容を訂正できます。
ステップ5:スマホを使ってe-Taxで提出する
最後は「送信」をして申告完了です。以下の手順に沿って完了させてください。
【確定申告書の送信と完了方法】
「帳票表示・印刷」画面
「申告書を送信した後の作業について」画面
税務署に提出すべき書類がある場合は、送信実行後の画面に詳細が表示されますので、対応しましょう。
その後「④申告書データを保存」でデータを保存しておくと、翌年以降の作成に活用できます。「翌年のことはまだ分からない」という方も、保存しておくことをおすすめします。
医療費控除を確定申告でスマホから申請できるメリット
医療費控除の確定申告は、スマホで行うと申請や移動にかかる時間を減らし、自宅で好きな時間に手続きを完了できます。
スマホを使えば申請の手間を減らせる
スマホを使って医療費控除の確定申告を行うことで、書類を郵送したり窓口に行ったりする手間を減らせるのは大きなメリットです。郵送費や税務署までの交通費も節約できるため一石二鳥です。
確定申告の時期には税務署は非常に混雑するため、窓口で約1時間以上待つこともあります。しかし、慣れていない人でもスマホを使えば確定申告を完了できるため、本当に大きなメリットです。
自宅で簡単に医療費控除が完了する
スマホなら税務署の開庁時間を気にせず、自分の都合に合わせて申告できます。
例えば、平日忙しい会社員なら休日の朝に少し時間を取って申請したり、育児や家事の合間に領収書を整理し、マイナポータル連携で自動入力項目を確認するだけで済ませたりできます。
税務署での長時間の待ち時間を削減し、その時間を家族との時間や趣味に充てられるのも、スマホ申請の大きなメリットです。
医療費控除はいくら以上ならやる意味ある?
医療費控除は、所得税と住民税の節税にも繋がるため、たとえ少額であってもやる意味があります。
医療費控除の基準額と判断ポイント
医療費控除の基準額は、所得金額によって異なります。
| 所得金額 | 控除基準額 |
|---|---|
| 200万円以上 | 医療費合計10万円を超えた金額 |
| 200万円未満 | 医療費合計が所得金額の5%を超えた金額 |
また控除の対象となる金額は、以下のような計算式になります。
計算式医療費控除の対象額=1年間の医療費合計-控除基準額
つぎに、具体的な例を見てみましょう。
具体例①所得金額200万円以上
所得金額:300万円医療費:15万円
控除基準額:医療費合計10万円を超えた金額1年間の医療費合計:15万円
医療費合計15万円ー控除基準額10万円=5万円
医療費控除の対象額:5万円
具体例②所得金額200万円未満
所得金額:180万円医療費:15万円
控除基準額:所得金額180万円×5%=9万円1年間の医療費合計:12万
医療費合計15万円ー控除基準額9万円=6万円
医療費控除の対象額:6万円
このように、所得金額によって控除を受けられる基準額が異なります。
少額でも控除するメリットがあるケース
医療費控除の金額が少額の場合、「手間がかかるし、申請しなくてもいいかな」と考える方もいるかもしれません。
しかし、医療費控除には節税効果があり、さらに過去5年分までさかのぼって申請できるため、少額でも申請するメリットがあります。
具体例な例を見てみましょう。
具体例①所得税・住民税の軽減
(仮定)所得税・住民税率:10%年間売上:600万円医療費:20万円
控除対象額:1年間の医療費20万円ー控除基準額10万円=10万円
所得税の軽減額:控除対象額10万円×10%=1万円住民税の軽減額:控除対象額10万円×10%=1万円
このように、翌年の所得税・住民税が合計で2万円も軽減されるため、大きなメリットになると言えます。
具体例②複数年まとめて申請
(仮定)所得税・住民税率:10%年間売上:600万円医療費:毎年11万円
控除対象額:1年間の医療費11万円ー控除基準額10万円=1万円
5年分まとめた控除対象額:1万円×5年=5万円
所得税の軽減額:控除対象額5万円×10%=5,000円住民税の軽減額:控除対象額5万円×10%=5,000円
医療費控除は、過去5年分まで遡って申請できるため、1年毎に申請するよりもまとめることで多くの還付を受けられる可能性があります。
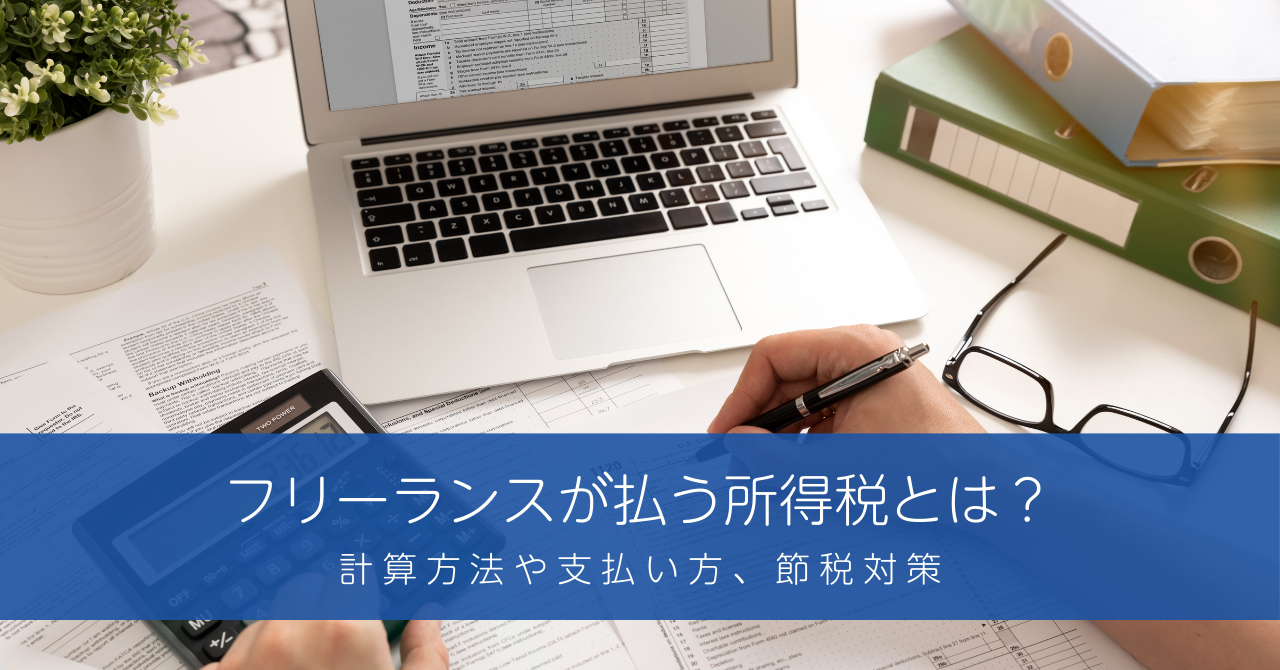
医療費控除でいくら戻って来る?
医療費控除を申請すると、所得税や住民税の負担が軽減され、支払った医療費の一部が還付される可能性があります。ここでは、具体的な還付額の計算方法やシミュレーションを交えて、どのくらい戻ってくるのかを分かりやすく解説します。
また、所得税と住民税の還付タイミングの違いについても詳しく説明するので、医療費控除を最大限活用するための参考にしてください。
還付額の計算方法とシミュレーション
医療費控除で還付される金額は、次の計算式を使って求めます。
計算式個人事業主の所得=売上ー経費還付金=医療費控除額×所得税率
還付される金額の例を見てみましょう。
具体例①年間売上600万円、医療費11万円の個人事業主
(条件)経費:360万円所得税率:10%
所得:600万円ー360万円=240万円
医療費控除の基準額:10万円(所得金額200万円以上のため)
控除対象額:1年間の医療費11万円ー10万円=1万円
還付金:医療費控除額1万円×所得税率10%=1,000円
年間売上600万円、医療費11万円の個人事業主が、医療費控除の確定申告をした場合に得られる還付金は1,000円です。
ただし、これは所得税の還付額であり、住民税にも影響を与えるため、合計でさらに軽減される可能性があります。
所得税と住民税の還付タイミングの違い
所得税と住民税は、還付のタイミングに違いがあります。
| 所得税 | 住民税 |
|---|---|
| 確定申告手続き後に還付 | 翌年度の住民税が減額 |
所得税は、申告後約1~2ヶ月程度で銀行口座に振り込まれます。それに対して住民税は、6月以降に届く住民税の納税通知書に減額された金額が反映されます。これは、税務署が住民税を計算する際に、医療費控除で減額された課税所得を基に新しい住民税額を算出するためです。
たとえば、その年の本来の住民税が12万円(1万円×12か月)で、医療費控除により課税所得が減額となり、住民税から2万円減額になったとします。
1カ月あたりの住民税額=(本来の住民税額12万円ー2万円)÷12ヶ月=約8,333円
このように、医療費控除を適用することで住民税が毎月約1,667円減額され、1年間を通じて毎月の納税額が少なくなる仕組みです。そのため、所得税のように還付金として一括で貰えるわけではないですが、結果的に節税効果が大きくなります。
医療費控除を確定申告でスマホから申請する際の注意点
医療費控除を確定申告でスマホから申請する際は、事前準備の大切さとトラブルに遭ったときの対処法を知っておく必要があります。
医療費通知や領収書データをスマホで管理する
医療費控除の申請をスムーズにするためには、スマホを活用して医療費通知や領収書を整理・管理することが重要です。
確定申告の時期には、多くの領収書を整理しなければならず、紙のままだと紛失や手間がかかる可能性があります。スマホで管理すれば、いつでもどこでもデータを確認でき、申請時の負担を軽減できます。
例えば、Google DriveやiCloudに「医療費控除2025」というフォルダを作成し、領収書を撮影して保存しておけば、申請時にすぐに取り出せます。また、OCR機能付きのスキャンアプリを使えば、領収書の検索も簡単になります。
スマホを活用して医療費データを整理することで、確定申告時の作業負担を減らし、スムーズに申請を完了できるでしょう。
スマホで起きやすいトラブルに対応する
スマホで医療費控除を申請する際、マイナンバーカードの読み取りエラーやアプリの不具合がよく発生するため、適切な対処法を知っておくことが重要です。
マイナンバーカードが正しく読み取れない原因は、かざす位置のズレやスマホケースの影響、カードの傷などが考えられます。また、アプリの不具合はバージョンが古いことや一時的なエラーが原因であることが多いでしょう。
マイナンバーカードの読み取りエラーが起きた場合、スマホとカードを密着させ、スマホケースを外して試すと解決することがあります。それでもダメなら、カードの傷が原因かもしれないため、早めの再発行を検討しましょう。アプリの不具合が発生した場合は、アプリのアップデートや再インストール、スマホの再起動を試すことで改善するケースが多いです。
スマホで確定申告を行う際は、マイナンバーカードの読み取り方やアプリの更新に注意し、事前に対処法を知っておくことでスムーズに申請を完了できます。
申請前に重要なポイントを確認する
スマホで医療費控除を申請する前に、確認しておくべき重要なポイントについて見てみましょう。
【申請前のチェックポイント】
| 確定申告の期限 | 毎年2月16日から3月15日までこの期間内に手続きを完了しないと還付されません。スマホの確定申告は、窓口の混雑を避けられますので早めに終わらせましょう。 |
| マイナポータル利用の準備と連携設定 | 確定申告期間の前に終わらせておくと、申請時は申告内容の入力だけに集中できます。 |
初めて申請する人は、マイナポータルのログインと確定申告書等作成コーナーへのアクセスを申請前に試しておくことをおすすめします。
確定申告をスムーズに進めるためには、期限の把握と事前のシミュレーションが重要です。申請前に必要な準備を整え、安心して手続きを進められるようにしましょう。
医療費控除を確定申告でスマホから申請するのに役立つアプリ
スマホを活用した医療費控除の確定申告をスムーズに進めるために、便利なアプリを活用しましょう。ここでは、freee会計・マネーフォワード確定申告・国税庁の確定申告書等作成コーナーの特徴や利便性を紹介します。
freee会計
freee会計は、直感的な操作で初めて会計アプリを使う方や確定申告を行う方にも簡単に利用できるアプリで、以下のような特徴があります。
【freee会計の特徴】
- スマホで簡単に操作できる
- 領収書の撮影と入力項目をチェックするだけでアップロードが完了
- 質問に答えるだけで医療費控除の明細書が自動作成
- マイナポータルとの連携機能により、医療費データを自動取り込み
freee会計は、自動計算機能や自動チェック機能などにより、計算方法や入力に不安がある確定申告初心者でも安心して使えます。
また、マイナポータル連携機能がある点は、確定申告を早く終わらせたい人にとって強い味方となるでしょう。連携機能で医療費データを自動で取り込み、自動で作成された医療控除の明細書を使えば、アプリから直接電子申告ができます。
「初めての確定申告を早く終わらせたいけど、入力が難しいのは困る」といった方におすすめのアプリです。
マネーフォワード確定申告
マネーフォワード確定申告アプリは、家計簿アプリ「マネーフォワードME」を使用している方に特におすすめのアプリで、以下のような特徴があります。
【マネーフォワード確定申告の特徴】
- 初心者にも分かりやすいガイド付き
- マイナポータルとの連携で医療費データを取得可能
- 家計簿アプリ「マネーフォワードME」との連携が可能
- AIによる最適な控除方法の提案
マネーフォワードMEを使っている方は、医療費が「マネーフォワード確定申告」に自動反映されるため、確定申告の手間を大幅に削減できます。さらに、複数の領収書をまとめて撮影しアップロードできるため、食費や光熱費などと一緒にまとめて管理することも可能です。
また、初めて確定申告をする方にとって安心材料となる機能が備わっています。
- 画面の指示に従うだけで申告書が完成
- 分かりやすい用語説明と入力ガイド
- 24時間対応のチャットボット
そのため、確定申告に不慣れな方でもスムーズに申請でき、医療費控除の手続きを簡単に完了できる便利なアプリです。
国税庁 確定申告書等作成コーナー
国税庁の確定申告書等作成コーナーは、医療費控除を申告する公的サービスとして安心感とスマホで利用できる利便性を備えており、以下のような特徴があります。
【国税庁確定申告書等作成コーナー】
- 無料で利用できるため、費用を気にせず使える
- マイナポータルを連携すれば、面倒な入力作業は自動化
- 医療費通知データの読み込みで、簡単に控除額を計算
- 動画やマニュアル完備で、申告方法が分かりやすい
ご紹介した2つのアプリは有料ですが、国税庁の確定申告書等作成コーナーは無料で利用できます。そのため、コストを抑えたい方にとって大きなメリットです。
また、個人情報の取り扱いが厳重で、データの漏洩リスクが低いことから安心して利用できます。確定申告書等作成コーナーにあるスマホ用の操作マニュアルで簡単に利用登録から申告までをおこなえるのも利点です。
「国税庁のものだから難しく書いてありそう…」と感じるかもしれませんが、イメージ図と分かりやすい解説で想像以上に簡単に申告を完了できるおすすめの方法です。
医療費控除を確定申告でスマホから申請する際のよくある質問
スマホで医療費控除を申請する際に、多くの人が疑問に思うポイントを質問形式で解説します。
申請にかかる時間はどのくらい?
スマホで医療費控除を申請する場合の所要時間は、2時間前後を見込んでおくとよいでしょう。領収書の整理と確定申告内容の入力には、それぞれ約1時間が必要です。ただし、マイナポータル連携やアプリの自動入力機能を活用することで、上記の時間は大幅に削減できます。
さらに所要時間を削減するためのコツとして、以下の3つがおすすめです。
【所要時間削減のコツ】
- 領収書を事前にスマホ内に管理しておく
- 医療費をアプリやエクセルで集計しておく
- マイナポータルとe-Taxを連携させる
これをしておくだけでも30分前後の時間を削減できるはずです。特に初めての方は、確定申告時期の差し迫った時期にまとめてやるよりも、日々の入力をコツコツ進めておくことで焦らずに申告できるでしょう。
医療費控除の対象になる費用とならない費用は?
医療費控除の対象となる費用は、以下のとおりです。
【医療費控除の対象になる費用】
| 病院の診療費 | 処方箋で購入した薬代 |
| 入院費用 | 妊娠・出産関連の費用 |
| 通院にかかった交通費 | 治療に必要な医療器具の購入費(松葉杖、車いすなど) |
それに対して、医療費控除の対象とならない費用は以下のとおりです。
【医療費控除の対象にならない費用】
| 美容整形の費用 | 通院時のタクシー代(急を要する場合を除く) |
| 健康診断や人間ドックの費用 | 美容目的の歯列矯正(見た目を良くするため) |
| 予防接種の費用 | 健康維持や予防のための費用(ビタミン剤やサプリメントなど) |
医療費控除の基準は『治療を目的として支払った費用か』どうかがポイントです。そのため、対象外の費用は、申告しないように十分注意しましょう。
家族全員分の医療費をまとめて申請できる?
家族全員分の医療費は、まとめて申請することが可能です。医療費控除は、生計が同じ家族の医療費を合算して申請できる制度だからです。具体的な例を挙げてみます。
- 申請者本人の医療費:50,000円
- 妻の医療費:40,000円
- 子どもの医療費:30,000円
医療費合計:120,000円
それぞれの医療費は基準の10万円を超えていなくても、合算することにより超えるため医療費控除を受けられます。
ただし、まとめて申請するには2つの条件があります。
- 申請者と同一世帯で生計を同一にしている家族
- 家族の医療費を申請者が支払っている
条件に当てはまる場合は、まとめて申請して還付金の受け取りや節税をしっかりやっていきましょう。
フリ-ランスの案件を探すならエンジニアファクトリー

エンジニアファクトリーは、フリーランスエンジニア向けに最適な案件をご紹介するサービスです。公開案件は7,000件以上、IT業界専門歴16年の実績を誇り、80%以上の方がエンジニア歴10年以上と、経験豊富なプロフェッショナルに選ばれ続けています。
また、案件の継続率は95.6%と高く、安定した仕事環境を提供しています。さらに、案件紹介後も丁寧なサポートを行い、エンジニア一人ひとりのキャリア形成をしっかりとサポート。信頼できるパートナーとして、あなたの成長を後押しします。フリーランスとしての活動をより充実させたい方、エンジニアファクトリーで新たな一歩を踏み出してみませんか?
まとめ
医療費控除の確定申告をスマホから申請する方法は、思っているよりも簡単でスムーズに終えられます。
「確定申告ってなんとなく難しそう」「税務署に行く時間がない」「どうにか楽にできる方法はないだろうか」こんな悩みを持つ方でも、スマホなら窓口に行かずに手間や時間を削減しながら確定申告が可能です。
また、マイナポータルの連携設定や日々の領収書管理を日頃から工夫することで、さらにスムーズに申請を進められます。毎日使っているスマホを活用し、本記事を参考にしながら、確定申告を効率よく完了させましょう。

-31.jpg)