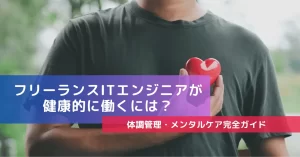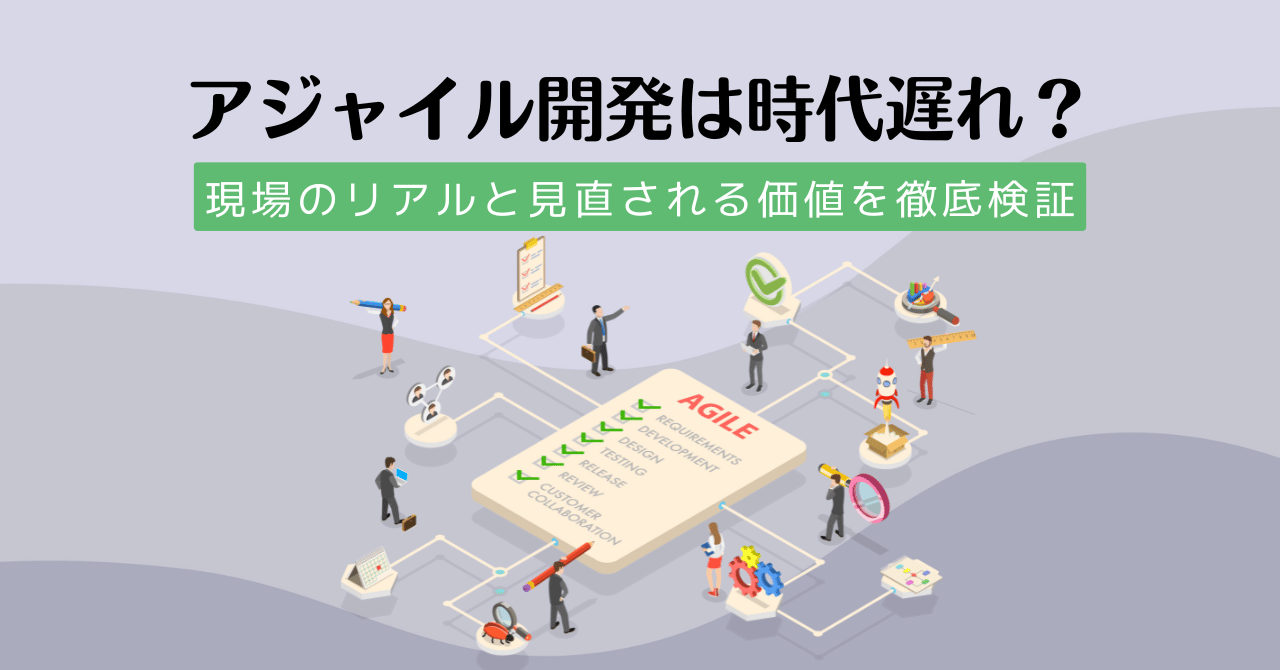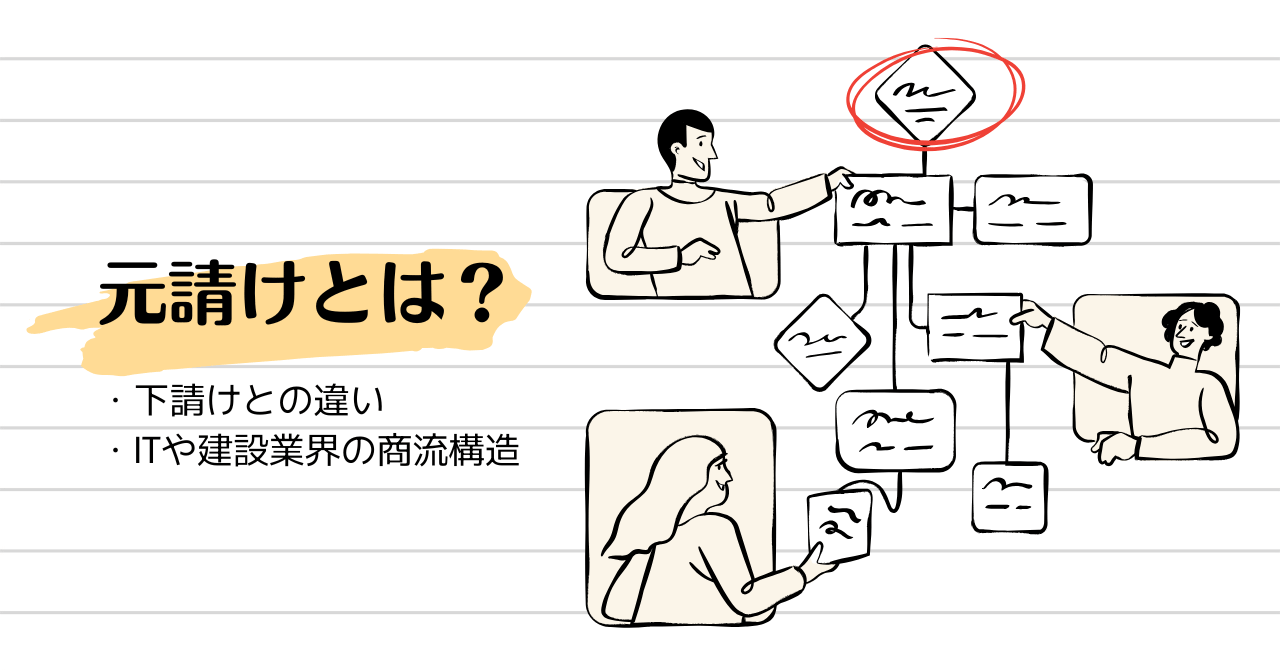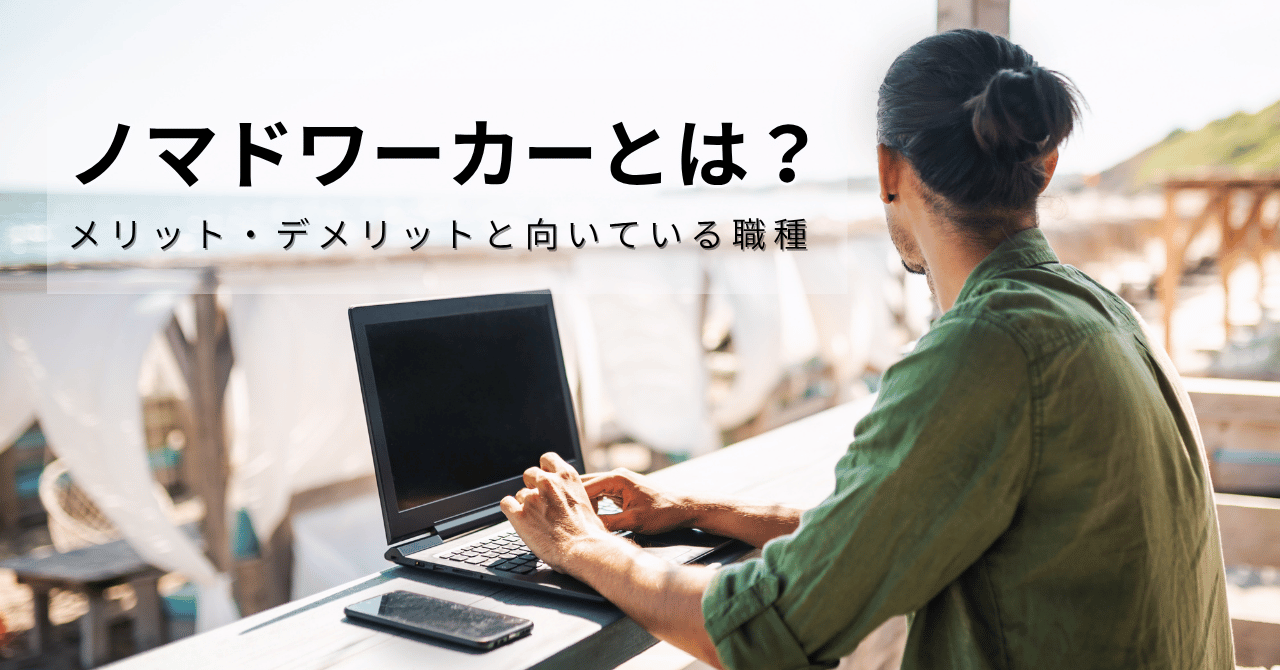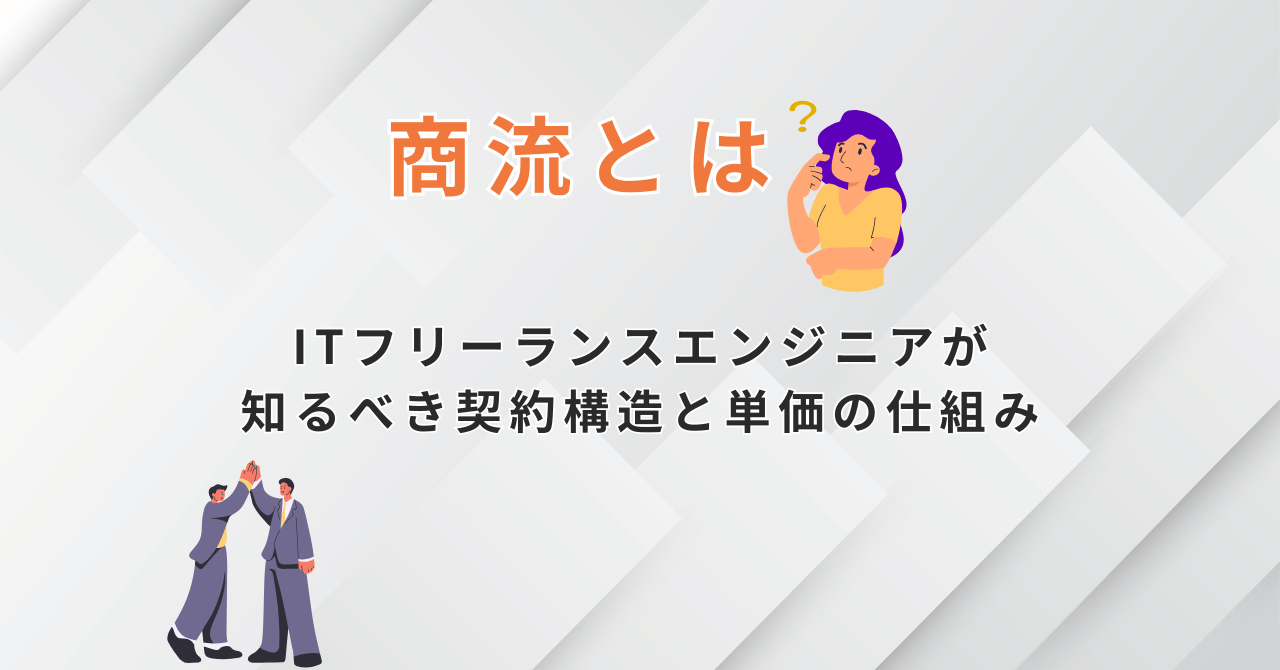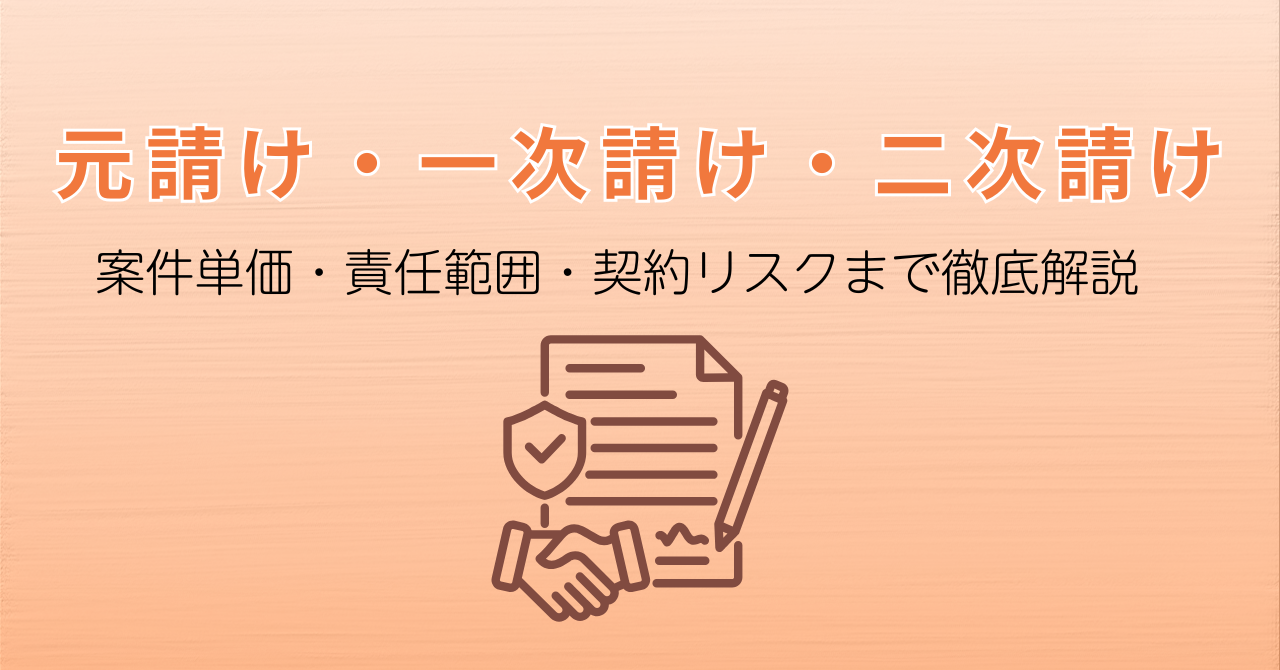フリーランスをされている方のなかには、消費税の仕組みやインボイス制度など複雑でわかりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、自分の業務に必要な税務知識を確認したい駆け出しフリーランス向けに、消費税の計算方法や納税手続きについて初心者にも分かりやすく解説します。
さらに、インボイス制度の影響や対応策、消費税の課税対象や免税事業者としての条件まで詳細に解説します。ぜひ最後までご覧いただき、必要な税務知識に対する理解を深めてください。

エンジニアファクトリーでは、フリーランスエンジニアの案件・求人をご紹介。掲載中の案件は10,000件以上。紹介する案件の平均年商は810万円(※2023年4月 首都圏近郊のITエンジニア対象)で、ご経験・志向に合った案件と出会えます。
簡単なプロフィール入力ですぐにサポートを開始。案件にお困りのITフリーランスの方やより高条件の案件と巡り合いたいと考えている方は、ぜひご登録ください。
フリーランスと消費税の基礎知識
フリーランスに関係する消費税の基礎知識について解説します。
消費税とは?フリーランスに関係する仕組みを解説
消費税とは、商品やサービスの購入時に課される税金を意味します。2025年2月現在における税率は、標準税率で10%、軽減税率は8%です。
フリーランスに関わる消費税として「間接税」という仕組みが取られています。間接税とは、消費者が支払った消費税を一旦フリーランスが預かり、その後消費者に代わってフリーランスが間接的に税務署へ納付する仕組みです。
基本的にフリーランスは消費税を納税する義務がありますが、国が定める一定の条件を満たされた場合に限り納税義務が免除されます。
フリーランスとして事業を続けていくためには、消費税の仕組みを理解することが重要です。
免税事業者と課税事業者の違い
フリーランスを含めるすべての事業者は、「免税事業者」と「課税事業者」のどちらかに分けられます。
両者の大きな違いとして、免税事業者は納税の義務はなく、課税事業者には納税の義務がある点が挙げられます。したがって、免税事業者は消費税を受け取っていても納税する義務は発生しませんが、課税事業者は消費税の申告を行い適切な額を納めなければなりません。
下表に免税事業者と課税事業者のメリット・デメリットを記載します。
| 事業者 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 免税事業者 | 消費税の申告・納付義務なし | 消費税の還付を受けられない |
| 課税事業者 | 消費税の還付を受けられる | 消費税の申告・納付義務あり |
一般的には、免税事業者の方が手続きが簡単で、納税義務がないため負担が軽くなります。しかし、多額の設備投資などにより仕入れにかかる消費税が売上にかかる消費税を上回る場合は、課税事業者を選択した方が有利になることがあります。
免税事業者と課税事業者の選択は、手続きや税負担だけでなく収益にも影響を及ぼすため、適切な判断が求められるでしょう。
消費税が発生する条件と基準期間の考え方
消費税の納税義務が発生する条件は、売上高とその売上を計上した期間によって決まります。
期間は「基準期間」と「特定期間」があり、それぞれの違いを下表に記載します。
| 項目 | 基準期間 | 特定期間 |
|---|---|---|
| 期間 | 前々年または前々事業年度 | その年の前年1月1日から6月30日、または前事業年度開始の日以後6ヶ月 |
| 判定基準 | 課税売上高 | 課税売上高または給与等支払額 |
| 課税判定 | 課税売上高が1,000万円超で課税事業者 | 基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高または、給与等支払額のいずれかが1,000万円超なら課税事業者 |
なお、開業から2年以内のフリーランスでも、特定期間の課税売上高または給与等支払額が1,000万円を超える場合は、課税事業者となる可能性があります。
基準期間と特定期間は、対象期間や判定基準がそれぞれ異なります。自身の状況に合わせて、どちらの期間の売上高が課税判定に影響するかを確認し、適切に消費税の申告・納付を行いましょう。
フリーランスが知っておくべき消費税の計算方法
フリーランスの方が消費税を納める際には、主に「本則課税方式」と「簡易課税方式」の2つの方法があります。これらの違いを理解し、適切な方法を選択することが重要です。
本則課税方式の計算方法
本則課税方式は、売上にかかる消費税額から、仕入れや経費にかかる消費税額を差し引いて納税額を算出する方法です。具体的には、以下の計算式で求められます。
「納付消費税額 = 受取った消費税額(仮受消費税) - 支払った消費税額(仮払消費税)」
具体的な計算例:
- 売上高(税抜): 2,000万円
- 売上にかかる消費税額(10%): 200万円
- 仕入れや経費(税抜): 1,000万円
- 仕入れや経費にかかる消費税額(10%): 100万円
- 納付消費税額: 200万円 - 100万円 = 100万円
この方式では、実際に支払った消費税額を正確に控除できるため、公平な納税が可能です。
簡易課税方式の特徴と計算の仕組み
簡易課税方式は、中小事業者の消費税計算の負担を軽減するための制度で、基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者が適用可能です。この方式では、仕入れにかかる消費税額を業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて算出します。
納付消費税額 = 売上にかかる消費税額 -(売上にかかる消費税額 × みなし仕入率)
また、みなし仕入率は事業の種類に応じて以下のような違いがあります。
| 事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業内容 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に販売する事業) |
| 第2種事業 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの) |
| 第3種事業 | 70% | 農業、林業、漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業 |
| 第4種事業 | 60% | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業(具体的には、飲食店業など) |
| 第5種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く) |
| 第6種事業 | 40% | 不動産業 |
フリーランスのITエンジニアの場合、サービス業に該当し、第5種事業(みなし仕入率50%)が適用されます。ただし、業務内容によっては異なる事業区分に該当する可能性もあります。詳細な判定には国税庁の「簡易課税の事業区分について(フローチャート)が参考になります。
具体的な計算例として、ITエンジニア(第5種事業、みなし仕入率50%)で年間の売上高が税込1,100万円(税抜1,000万円、消費税率10%)の場合で考えてみましょう。
具体的な計算例:
- 年間売上高(税抜): 1,000万円
- 消費税率: 10%
- 売上に含まれる消費税額: 1,000万円 × 10% = 100万円
- みなし仕入率(第5種事業): 50%
- 仕入控除額: 100万円 × 50% = 50万円
- 納税額: 100万円 – 50万円 = 50万円
納めるべき消費税額は50万円となります。
最終的な判断は、具体的な業務内容や契約形態によって異なる場合がありますので、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
どちらを選ぶべきか?事業内容に応じた判断基準
本則課税方式と簡易課税方式のどちらを選ぶか判断するには、まず両者の違いを知る必要があります。
| 項目 | 本則課税 | 簡易課税 |
|---|---|---|
| 選択するための税務手続き | 不要 | 前期末日(個人事業主の場合は前年末)までに届け出が必要 |
| 強制継続期間 | なし | 2年間強制継続 |
| メリット | 消費税の過不足が発生せず、適正な納税ができる | 計算が簡単で、税務処理の負担が軽減される |
| デメリット | 仕入税額控除の計算が必要で、手続きの負担が大きい | 実際の仕入れ額によっては納税額が増える可能性がある |
| 計算負担 | 手間がかかる | 手間がかからない |
| 選択できる事業規模 | 事業規模に関係なく選択できる | 2期前の売上5,000万円以下の事業者しか選択できない |
本則課税は、売上にかかる消費税から仕入や経費にかかる消費税(仕入税額控除)を差し引いて納税額を計算します。これにより、実際に支払った消費税分が正しく控除されるため、公平な納税が可能です。
一方、簡易課税は、売上にかかる消費税に業種ごとの「みなし仕入率」を適用し、仕入控除額を一律に計算する方式です。計算がシンプルになる反面、実際の仕入額によっては損をする可能性もあります。
| 項目 | 本則課税 | 簡易課税 | |
|---|---|---|---|
| 事業規模 (年間課税売上高) | 5,000万円以下 | どちらでも選択可 | |
| 5,000万円以上 | 本則課税のみ適用 | 選択不可 | |
| 仕入れや経費 | 少ない | 仕入控除が少ないため簡易課税の方が有利になる可能性あり | みなし仕入率の影響で損をする可能性あり |
| 多い | 仕入控除の恩恵を受けられるため本則課税が有利 | みなし仕入率次第で有利になることも | |
| 事業負担 | | 計算負担が大きい(仕入控除の計算が必要) | 計算負担が少ない(売上に応じた簡単な計算で済む) |
フリーランスエンジニアは、一般的に仕入れや経費が多い業種ではないため、簡易課税(第5種事業・みなし仕入率50%)を選んだ方が有利になることが多いです。ただし、経費の割合が売上の50%以上になる場合は、本則課税を選ぶ方が節税につながる可能性もあるため、一度シミュレーションしてみるのがおすすめです。
事業規模や必要経費などでどちらにするか判断が変わってきますので、自身の事業状況に合わせてシミュレーションをしてみるとよいでしょう。
消費税の申告と納税の手続き
ここからは、消費税の申告と納税の手続きについて、詳しく解説します。
消費税の申告・納付の流れ
消費税の課税対象となったフリーランスは、対象となった年の売上から消費税額を計算し、消費税の申告と納付を行わなければなりません。
申告から納付までの手順は、下表1〜4になりますので、参考にされてください。
| 手順 | 詳細 |
|---|---|
| 消費税の課税対象となるかを判断 | 事業の売上や経費にかかる消費税を集計本則課税方式の場合、仕入税額控除(仕入れ時に支払った消費税)を考慮 |
| 消費税の納税額を計算 | 本則課税方式と簡易課税方式のそれぞれの計算式に則り算出 |
| 申告書類を入手・申告 | ・税務署で入手・申告・国税庁のホームページからダウンロード・国税庁のe-TAXで申告(電子申告) |
| 消費税を納付 | ・納付書にて金融機関や税務署窓口、またはコンビニなどで支払う・インターネットにて支払う |
消費税の申告・納付は、従来の紙による申告の他にe-TAXなどを使用してネット上でも行えます。利便性や手間を考慮した上で、どちらで行うか決めるとよいでしょう。
申告と納付のスケジュールと注意点
課税期間
毎年1月1日から12月31日までの1年間。
申告・納付期限
翌年の3月31日まで。
フリーランスの場合、消費税の課税期間は毎年1月1日から12月31日までの1年間です。この期間における消費税申告書の提出および納付の期限は、翌年の3月31日となります。
例えば、2024年の課税期間に対する申告・納付期限は、2025年3月31日となります。ただし、3月31日が土日祝日に当たる場合は、翌営業日が期限となります。
振替納税を利用すると、口座からの引き落とし日は納付期限の約1ヶ月後となります。例えば、2025年3月31日が納付期限の場合、引き落とし日は2025年4月下旬になります。振替納税を希望する場合は、事前に税務署への手続きが必要です。
【注意したいポイント】
期限内の申告・納付
期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。特に、消費税額が大きい場合、延滞税も高額になる可能性があるため、注意が必要です。
資金管理
消費税の納付額は事業収入に応じて増減するため、日頃から適切な資金管理を行い、納付時に資金不足とならないよう心掛けましょう。
適切なスケジュール管理と資金管理を行うことで、申告・納付をスムーズに進められ、事業運営の安定にもつながります。
申告時に必要な書類と記載方法
フリーランスが消費税の申告・納付を行う際には、以下の各書類が必要となります。どのような書類が必要なのか見ていきましょう。
| 方式 | 書類 | 記載内容 |
|---|---|---|
| 本則課税方式 | 税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表 | 標準税率(10%)および軽減税率(8%)が適用された取引に関する課税標準額や消費税額を税率別に詳細に計算・記載 |
| 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 | 課税売上割合の計算や、控除対象となる仕入税額の詳細を記載 | |
| 第一表 消費税および地方消費税の確定申告書<一般用> | 課税期間の消費税額や地方消費税額を記載 | |
| 第二表 課税標準額等の内訳書<一般用> | 課税標準額等の内訳を詳細に記載 | |
| 簡易課税方式 | 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表(簡易課税用) | 簡易課税方式における標準税率および軽減税率が適用された取引に関する課税標準額や消費税額を税率別に計算・記載 |
| 控除対象仕入税額等の計算表(簡易課税用) | 簡易課税方式における控除対象となる仕入税額の詳細を記載 | |
| 第一表 消費税および地方消費税の確定申告書<簡易用> | 課税期間の消費税額や地方消費税額を記載 | |
| 第二表 課税標準額等の内訳書<簡易用> | 課税標準額等の内訳を詳細に記載 |
記載方法は、課税期間中の売上高や仕入高を基に消費税額を計算し、所定の欄に記入になります。記載方法や計算に不明な点がある場合は、税務署や専門家への相談をおすすめします。
インボイス制度の概要とフリーランスへの影響
インボイス制度の概要と、フリーランスにどのような影響があるのか解説します。
インボイス制度とは?適格請求書の基本を理解しよう
インボイス制度(適格請求書制度)とは、売り手が買い手に対し、適用税率や消費税額などを正確に記載した請求書を発行・保存するための仕組みです。これにより、消費税の計算を明確化し、公平な税負担を実現することを目的としています。
適格請求書として認められるには、以下の6つの要件を満たす必要があります。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
注意点として、適格請求書を発行できない売り手との取引においては、買い手側は仕入税額控除を受けられない状況になってしまいます。
例えば、A店(課税事業者)がB店(インボイス未登録)に仕事を依頼し、10万円(+消費税1万円)を支払った場合、 B店は適格請求書を発行できないため、 A店はB店に支払った1万円の消費税を仕入税額控除できず、税負担が増えることになってしまいます。
そのため、フリーランスや事業者はインボイス制度の影響を理解し、取引先との契約・請求書に注意を払うことが重要です。
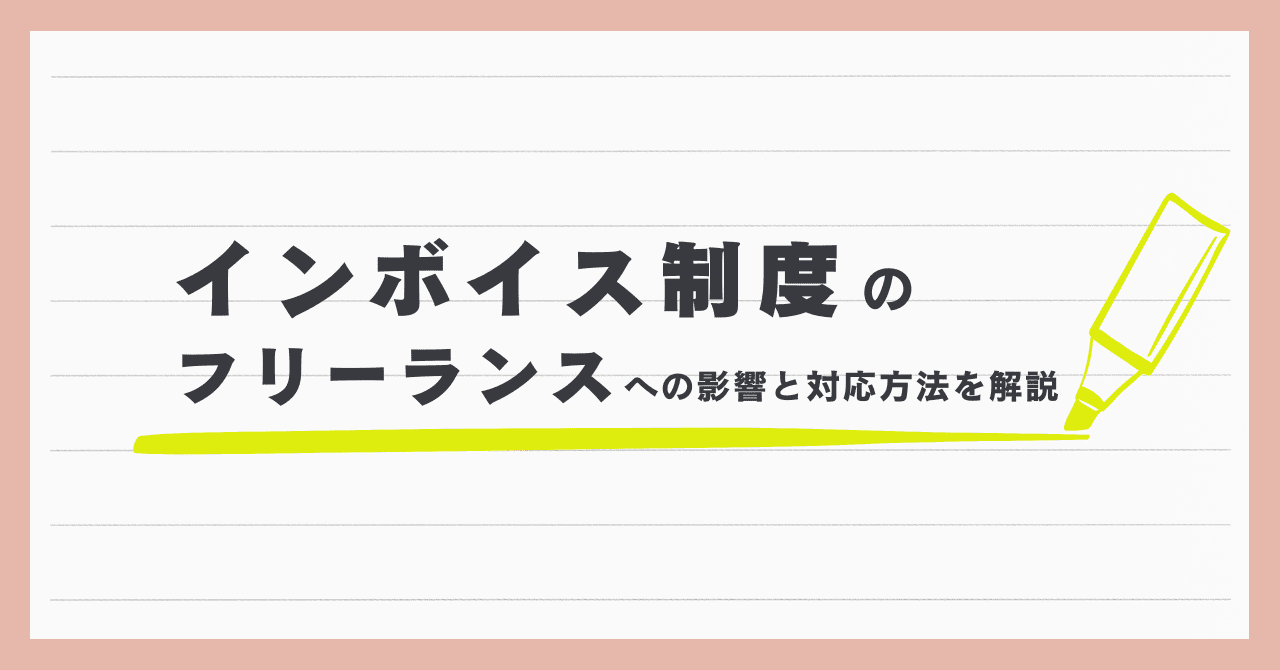
インボイス制度がフリーランスに与える影響
インボイス制度の導入に伴い、フリーランスにどのような影響があるのでしょうか?
下表に免税事業者(インボイス未登録者)が適格請求書発行事業者(インボイス登録者)になった際のメリット・デメリットを記載します。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 適格請求書発行事業者になる場合 | 取引先からの信頼を維持し、継続的に仕事を受けられる | 消費税の納税義務が発生する |
| 適格請求書発行事業者にならない場合 | 消費税の納税義務はない | ・取引が減る、あるいは停止のリスクがある・報酬を消費税分値引きしてほしいと交渉される |
免税事業者が適格請求書発行事業者に登録すれば、適格請求書を発行できるようになり、売上減少のリスク回避につながります。ただし、課税事業者としての納税義務が発生する点には注意が必要です。
事業者側からの視点と今後の事業運営を考えたうえで、適格請求書発行事業者になるかを検討することが重要です。
適格請求書発行事業者になるための手続きと条件
免税事業者のフリーランスが適格請求書発行事業者(インボイス登録者)として登録する方法は、書面・パソコン・スマートフォンの3種類があります。
下表において、各媒体での手続き方法を解説します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 書面 | ①国税庁のWebサイトから「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」をダウンロード |
| ②必要事項を記入 | |
| ③インボイス登録センターへ郵送(税務署への直接申請は不可) | |
| PC | ①マイナンバーカードを準備し、e-Taxソフトまたはe-Taxソフト(WEB版)をインストール |
| ②登録申請データを作成(e-Taxソフトは帳票形式、WEB版は問答形式) | |
| ③登録申請データを送信 | |
| スマートフォン | ①マイナンバーカードを準備し、マイナポータルアプリをインストール |
| ②登録申請データを作成 | |
| ③登録申請データを送信 |
注意点として、免税事業者がインボイス登録をする場合、事前に「課税事業者の選択届出」を提出する必要があります。 インボイス制度に対応するためには、課税事業者としての登録が前提となるため、申請前に手続きを行いましょう。
契約時に注意すべき消費税のポイント
フリーランスが契約時に注意すべき消費税のポイントについて解説します。
報酬設定時に消費税を考慮する方法
フリーランスが仕事を契約する際、消費税を考慮した報酬設定は、収益管理や消費税の申告・納税において重要なポイントの一つです。
報酬の設定方法には 「税抜価格(外税)」と「税込価格(内税)」 の2種類があり、それぞれの違いを理解することが大切です。
以下に、それぞれの特徴をまとめました。
| 項目 | 方式 | 例 |
|---|---|---|
| 税抜価格(外税) | 報酬金額に消費税を別途加算 | 50,000円の報酬に対して消費税(10%)を加え、請求額は55,000円 |
| 税込価格(内税) | 報酬金額に消費税が含まれている | 50,000円の税込報酬の場合、実際の手取りは45,454円(税抜) |
税抜価格(外税)で請求すると、消費税を別途受け取れるため手取り額が増えるメリットがあります。
また、企業との取引では一般的に税抜価格(外税)が使われる一方で、消費者向けのサービスでは税込価格(内税)が用いられることが多いです。取引先に応じて、適切な価格設定を行いましょう。
請求書に消費税を記載する際の注意点
フリーランスが請求書を作成する際、消費税に関する記載内容には注意しなければなりません。クライアントとの報酬金額における認識違いを防ぐためにも、税抜価格・消費税額・税込価格を明確に記載し、正確な金額を伝える必要があります。
請求書に記載する消費税関連の4つの項目と、記載例を以下に記します。
- 取引内容(例:ウェブサイト作成)
- 税抜価格(例:100,000円)
- 消費税額(例:10,000円)
- 税込価格(例:110,000円)
軽減税率(8%)の対象となる取引がある場合は、税率ごとに金額を分けて記載する必要があるので注意が必要です。また、ライターやデザイナーなどの仕事では源泉徴収(10.21%)が発生するケースもあるため、その金額を控除し請求書に明記しなければなりません。
さらにクライアントとの契約時において、税込・税抜どちらで請求するかを事前に確認することが大切です。くわえて、適格請求書(インボイス)の発行義務があるかどうかも把握しておくと、今後の取引をスムーズに進めることができるでしょう。
取引先との交渉で損しないためのコツ
フリーランスが取引先との交渉時に消費税に関する誤解を防ぐためには、以下3つのポイントが重要になります。
自身の課税ステータスの明確化
自身が課税事業者か免税事業者かを取引先に伝えましょう。免税事業者の場合、インボイスを発行できず、取引先が仕入税額控除を受けられない可能性があるため、契約時に明確にしておくことが重要です。
取引条件の明確化
報酬額が税込みか税抜きか、消費税を別途請求するのかを契約書や請求書に明記しましょう。口頭での合意は誤解の元になるため、書面やメールで条件を確認・保存しておくと安心です。
インボイス制度への対応
自身が適格請求書発行事業者に登録しているかを取引先に伝え、インボイス発行の可否を明確にしましょう。免税事業者の場合、取引先がインボイスの発行を求めているか確認し、必要に応じて登録を検討するのも一つの方法です。
契約時にインボイス登録・未登録を伝え、取引先との円滑な関係を築き事業拡大につなげましょう。
消費税の手続きに関するよくある質問
ここでは、消費税の手続きに関するよくある質問にお答えします。
還付を受けるための条件と手続き
フリーランスが消費税の還付を受けるには、一定の条件を満たし、正しい手続きを行うことが必要です。
消費税還付を受けるためのおもな条件は、以下の3つです。
- 課税事業者であること(免税事業者は対象外)
- 本則課税方式を選択していること(簡易課税方式は原則対象外)
- 支払った消費税額が、受け取った消費税額を上回っていること
還付の手続きの流れは、以下の表にまとめています。
| 項目 | 必要書類 | 記載内容/注意事項 |
|---|---|---|
| 申告書の作成 | 消費税及び地方消費税確定申告書(第一表)(一般用)消費税及び地方消費税確定申告書(第二表) | 事業者の基本情報と計算した消費税の金額などを記載 |
| 明細書の作成 | 消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用) | 申告する理由や、主な課税資産の譲渡等の明細などを記載 |
| 計算書の作成 | 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 | 課税・免税のそれぞれの売上高などから、課税売上割合や控除対象仕入税額を計算 |
| 申告書と明細書の提出 | ー | ・所轄の税務署へ提出・申告期限は翌年の3月31日まで |
| 還付金の受け取り | ー | 申告から約1〜2ヶ月後に指定の銀行口座へ入金 |
課税事業者かつ本則課税を適用している場合、還付を受けられます。手続きを正しく行い、適切な還付を受けましょう。
免税事業者が課税事業者に切り替える際の手続き
免税事業者であるフリーランスが課税事業者へ移行する際には、以下の手続きを行う必要があります。
| 手続き | 書類 | 提出先/期限 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 登録申請 | 適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用) | 提出先:所轄の税務署提出期限:適格請求書発行事業者としての登録を希望する日の原則として前日まで | 2023年10月1日~2029年9月30日までの間に登録を受ける場合「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要 |
| 書類提出(任意) | 消費税簡易課税制度選択届出書 | 提出先:所轄の税務署提出期限:適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで | ー |
課税事業者になる際の注意点は以下2つです。
- 一度課税事業者を選択すると、原則2年間は免税事業者に戻れない
- 事業規模や取引先の状況を考慮し、慎重な判断が求められる
適切な手続きの実施により、課税事業者としての義務を果たし、取引先との円滑な関係を維持できます。不明な点は税務署や専門家に相談し、確実な対応を行いましょう。
消費税の納付が遅れた場合の対応方法
フリーランスが消費税の納付を期限内に行えなかった場合、以下2つのペナルティが発生します。どのようなものなのか見ていきましょう。
1つ目のペナルティとして、以下の延滞税が発生します。
| 税 | 滞在期間 | 率 |
|---|---|---|
| 延滞税 | 納期限の翌日から2ヶ月以内 | 年7.3%または「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い方 |
| 納期限の翌日から2ヶ月経過後 | 年14.6%または「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方 |
延滞税特例基準割合とは、日本銀行の短期金利(政策金利)を基に算出される割合で、毎年3月に発表され、1年単位で更新されます。
2つ目のペナルティとして、以下の無申告加算税が発生します。消費税の申告を期限内に行わなかった場合に対するペナルティです。
| 税 | 条件 | 率 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 納付すべき税額が50万円まで | 15% |
| 50万円を超える部分 | 20% |
万一消費税の納付が遅れた場合、以下の3つを速やかに行いましょう。
- できるだけ早く納付する(延滞期間が長くなるほど負担が増大)
- 自主的に申告する(税務調査前の申告でペナルティが軽減)
- 税務署へ相談する(状況に応じた対応策を確認)
消費税の納付遅延は、事業の資金繰りに大きな影響を及ぼします。日頃からスケジュール管理や資金計画を徹底し、期限内の納付を心掛けましょう。
フリ-ランスの案件を探すならエンジニアファクトリー

エンジニアファクトリーは、フリーランスエンジニア向けに最適な案件をご紹介するサービスです。公開案件は7,000件以上、IT業界専門歴16年の実績を誇り、80%以上の方がエンジニア歴10年以上と、経験豊富なプロフェッショナルに選ばれ続けています。
また、案件の継続率は95.6%と高く、安定した仕事環境を提供しています。さらに、案件紹介後も丁寧なサポートを行い、エンジニア一人ひとりのキャリア形成をしっかりとサポート。信頼できるパートナーとして、あなたの成長を後押しします。フリーランスとしての活動をより充実させたい方、エンジニアファクトリーで新たな一歩を踏み出してみませんか?
まとめ
本記事では、フリーランスに必要な消費税に関する知識や計算方法、そして申告・納税の手続きについて解説しました。
インボイスの登録・未登録は、どちらが良いとは一概には言えません。メリット・デメリットは事業の状況によって変わってくるため、自身の事業に応じた選択を行いましょう。
どちらにするか判断がつかない場合は、税務署などに相談しアドバイスを受けることをおすすめします。

-16.jpg)