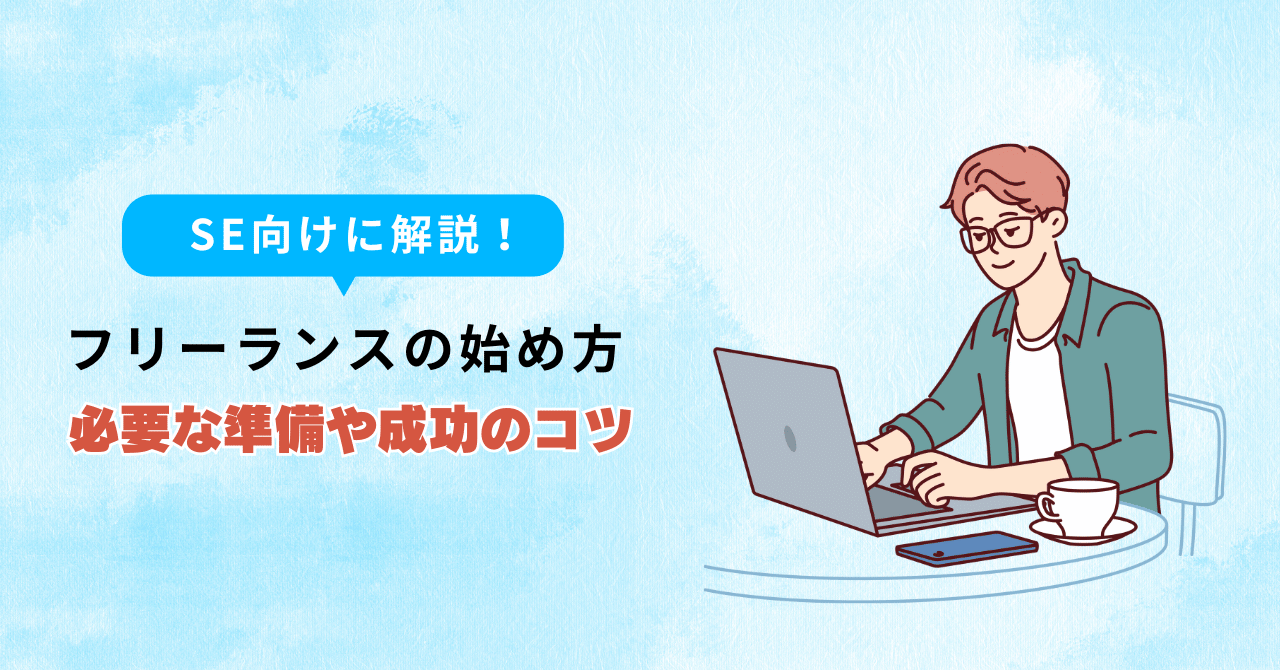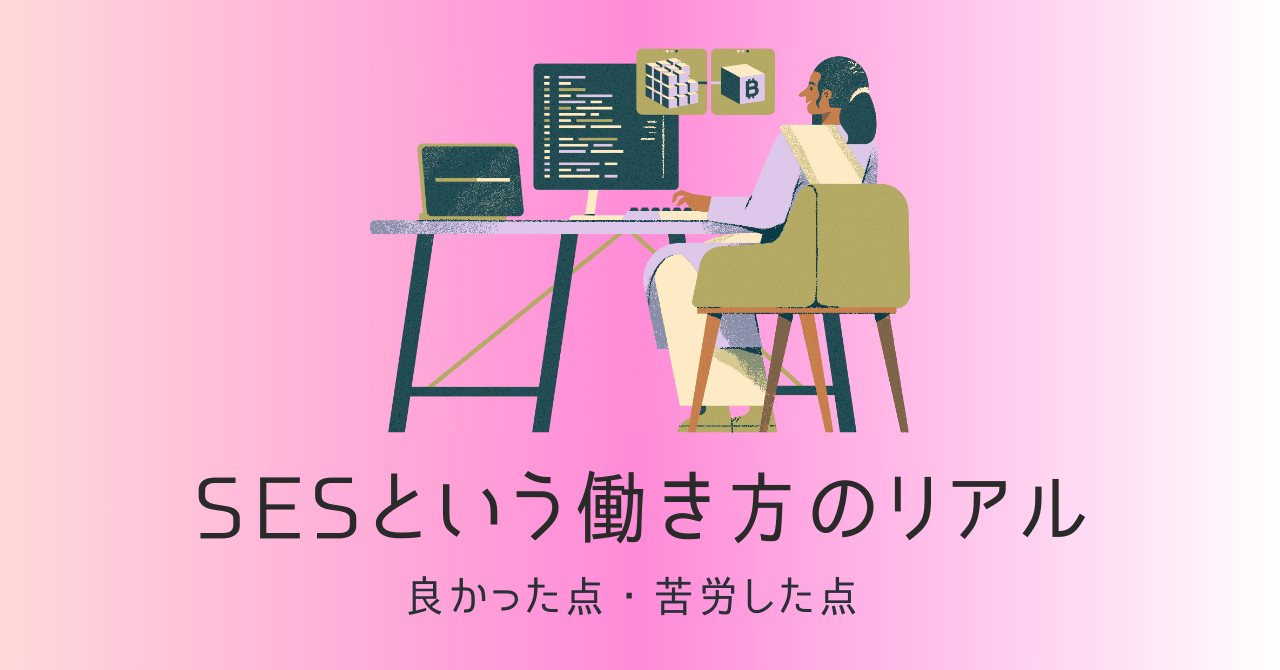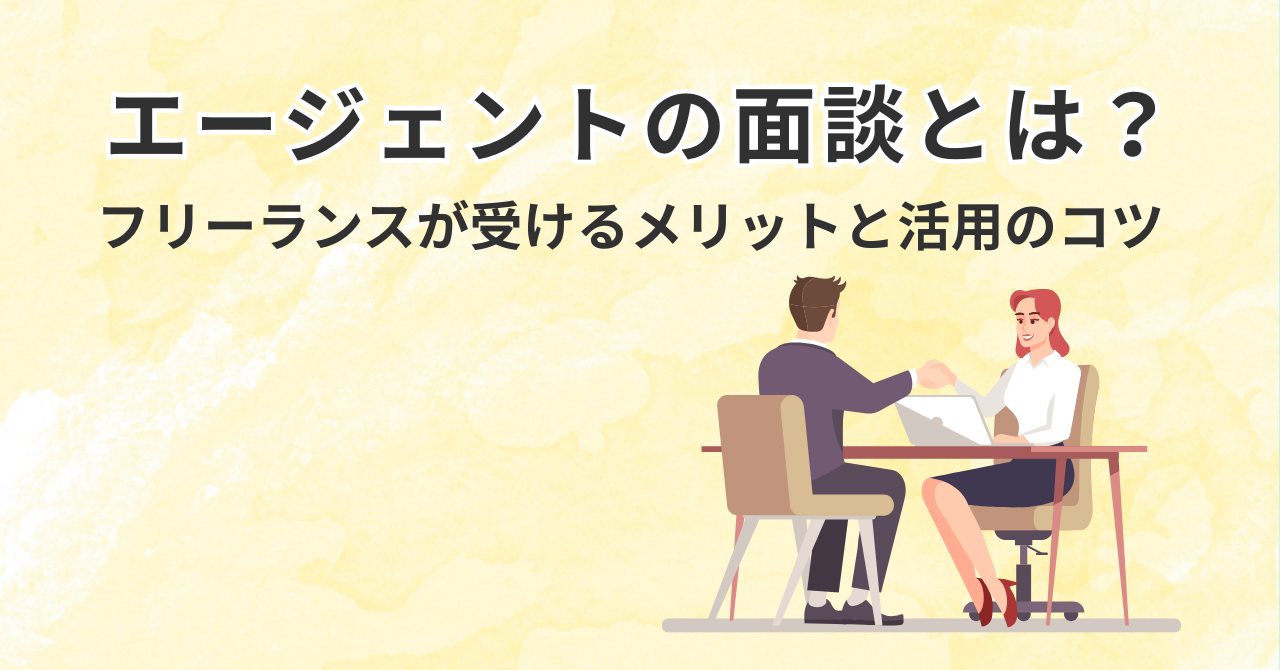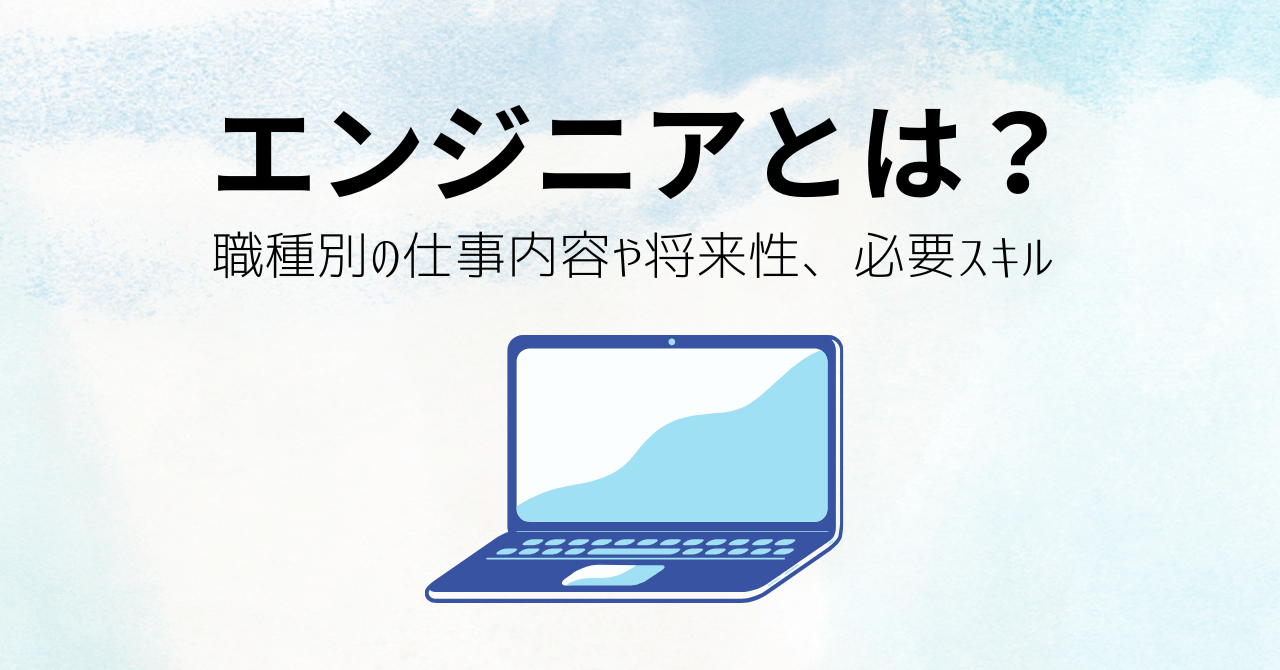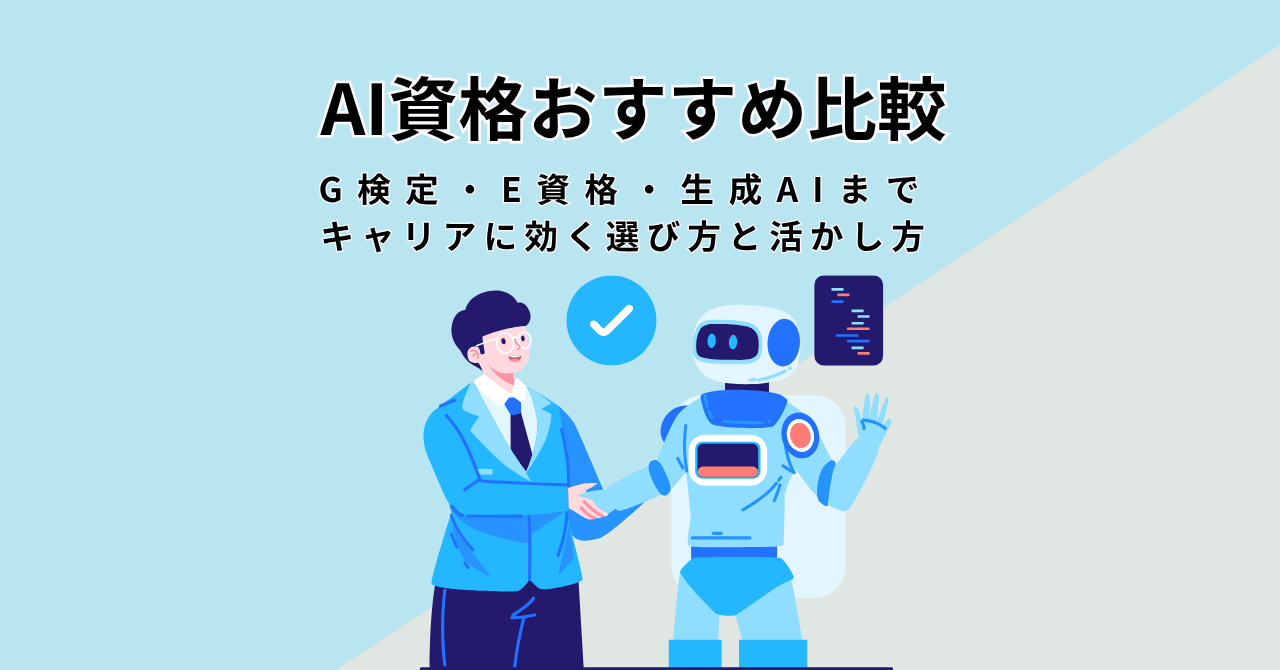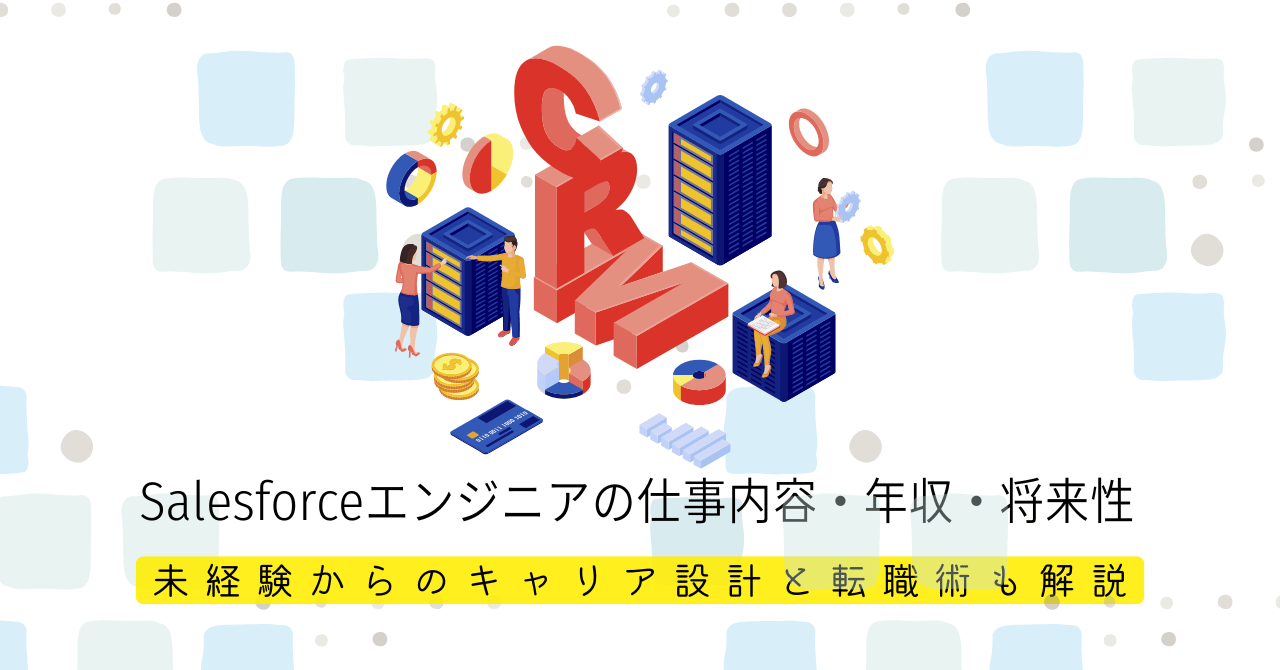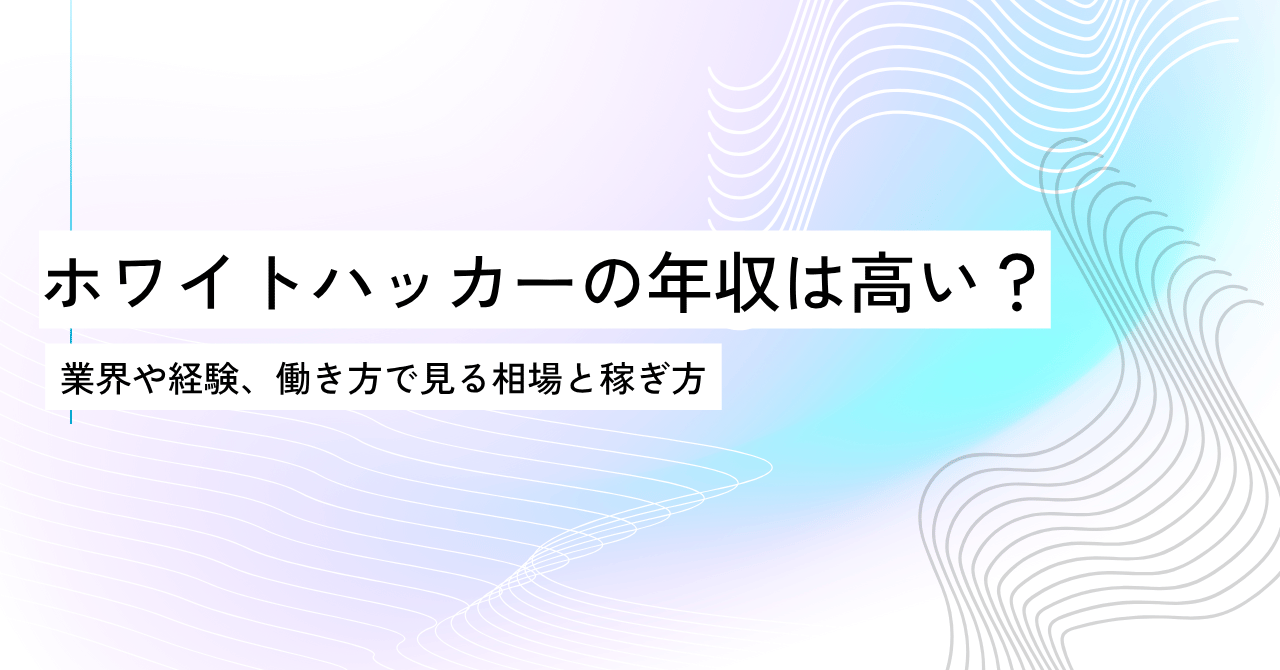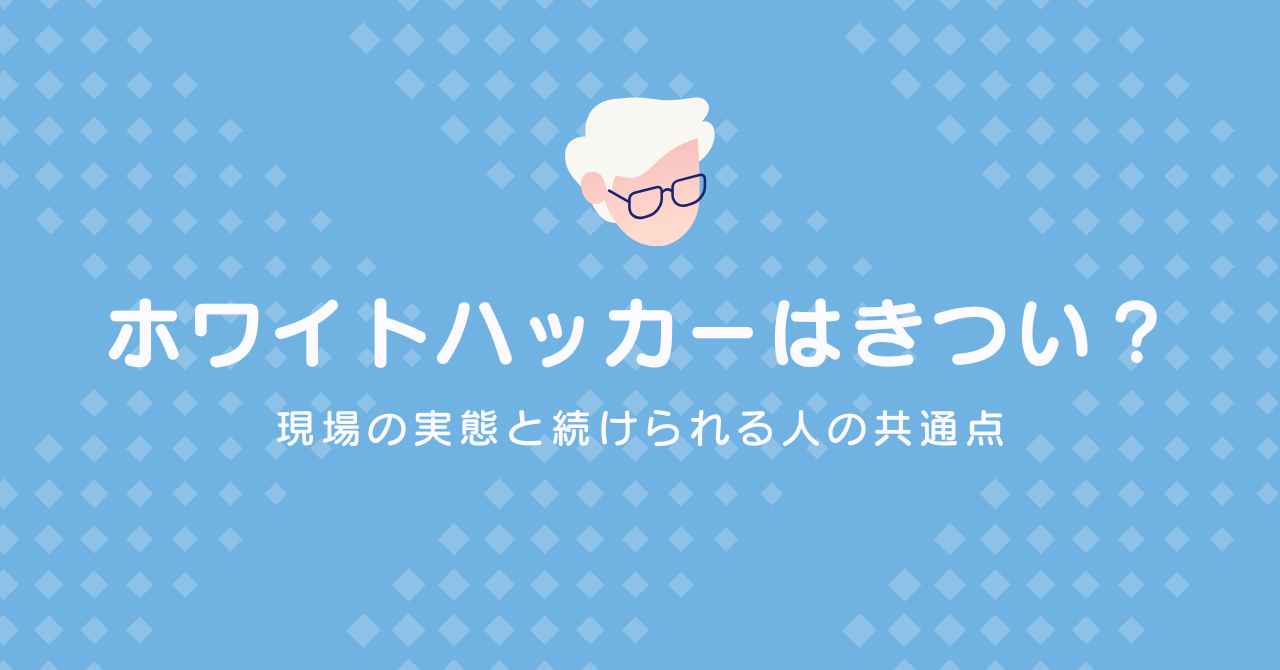「会社員のSEとして働いているものの、フリーランスという働き方に魅力を感じている」という人は多いでしょう。しかし、実際にフリーランスになると思うと、何から始めればよいのかがはっきりしないと動き出すことができません。
そこでこの記事では、フリーランスへのキャリアチェンジを検討しているエンジニアの方に向けて、知っておくべきことや準備を解説します。 しっかりと把握して、安心して一歩を進めましょう。

エンジニアファクトリーでは、フリーランスエンジニアの案件・求人をご紹介。掲載中の案件は10,000件以上。紹介する案件の平均年商は810万円(※2023年4月 首都圏近郊のITエンジニア対象)で、ご経験・志向に合った案件と出会えます。
簡単なプロフィール入力ですぐにサポートを開始。案件にお困りのITフリーランスの方やより高条件の案件と巡り合いたいと考えている方は、ぜひご登録ください。
フリーランスを始める前にやるべきこと
まずはフリーランスを始める前にやるべき3つの準備について詳しく解説します。
フリーランスの働き方を理解する
フリーランスとして独立する前に、まずその働き方を理解することが重要です。
フリーランスは特定の組織に属さず、自身の専門スキルや知識を生かして報酬を得る働き方を指します。業務の選択や、働く場所、時間において自由度が高い反面、収入の不安定さや自己管理の責任が伴います。
例えば案件の獲得から契約交渉、納期の管理、税務処理まですべてを自分で行う必要があります。 そのため会社員よりも高い自己管理能力や営業力、専門スキルの継続的な向上が重要となるでしょう。また、一般的に会社員よりも社会的信用が低くなりやすいため、クレジットカードの審査やローンの申請が難しくなることがあります。
仕事探しと案件の獲得
フリーランスとして独立する前に、仕事の探し方も確立しておきましょう。
仕事探しの方法のひとつが、クラウドソーシングの活用です。クラウドソーシングの利用により企業とフリーランスがオンライン上でマッチングできるため、比較的容易に案件を見つけられます。しかし単発プロジェクトの多さや競争が激しく低単価になりやすい傾向があります。
おすすめの方法としては、エンジニアファクトリーのようなフリーランス就業支援エージェントを活用すること。エージェントはスキルや経験、志向に合った案件を紹介します。エンジニアファクトリーでは7,000件以上の公開案件をご用意しており、IT業界特化のキャリアアドバイザーが長期的な目線で案件をご提案。将来に向けてステップアップできる案件をご紹介します。
行動計画を立てる
フリーランスとして活動を始める前に、明確な行動計画を策定しましょう。
具体的な目標を設定し、それに向けたステップを明確にすることで、効果的な準備と実行が可能になります。
まず、達成したい目標を具体的に定めます。次に現状と目標とのギャップを分析し、必要なスキルやリソースを洗い出すのです。その上で各ステップを時系列で整理し、優先順位を設定します。最後に進捗を定期的に確認し、必要に応じて計画を修正します。
つまり「いつまでにフリーランスとしての収入をいくらにする」「収入を確保するために長期・安定した案件をいつまでに何件獲得する」「収入を上げるためにいつまでに資格を取得する」といったゴールとマイルストーンを、期間を設定して着実に実行できるように計画するのです。
このような体系的なアプローチにより、フリーランスとしての道を着実に進められるでしょう。
フリーランスを始める際に必要な手続きと準備
ここからは、フリーランスを始める際に必要な、以下7つの手続きと準備について、詳しく解説します。
開業届を提出する
フリーランスとして仕事を始める場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届) を税務署に提出します。提出期限は、事業を開始してから1ヶ月以内です。
開業日は、初めて収益を得た日、契約を結んだ日、事業用の設備を整えた日 などから決められます。特に決まりはありませんが、最初の請求書を発行する前には提出しておくと良いでしょう。
開業届を出すメリットとしては、以下の3点があります。
- 青色申告(65万円控除)の申請ができる
- 屋号の銀行口座を作れる
- 事業所得として申告しやすくなり、経費計上の幅が広がる
副業レベルで年間の事業所得が少額の場合は、開業届を出さずに様子を見ることも可能です。しかし、事業所得として申告する場合は、早めに提出しておいたほうが良いでしょう。
青色申告の準備をする
フリーランスの確定申告には白色申告と青色申告があります。青色申告(65万円控除)を利用する場合は、「所得税の青色申告承認申請書」 を開業届と同時に提出する必要があります。
青色申告のメリット
- 最大65万円の特別控除が受けられる
- 赤字を3年間繰り越せる
- 家族への給与を必要経費にできる
ただし、青色申告をするには複式簿記で帳簿をつける必要があるため、会計ソフト(freeeやマネーフォワードなど)の導入を検討すると良いでしょう。
また、収入が少ないうちは白色申告でも問題ありません。控除を受けるメリットよりも、帳簿管理の手間のほうが負担になる場合もあるため、事業の規模に応じて選択してください。メリットよりも、帳簿管理の手間のほうが負担になる場合もあるため、事業の規模に応じて選択してください。
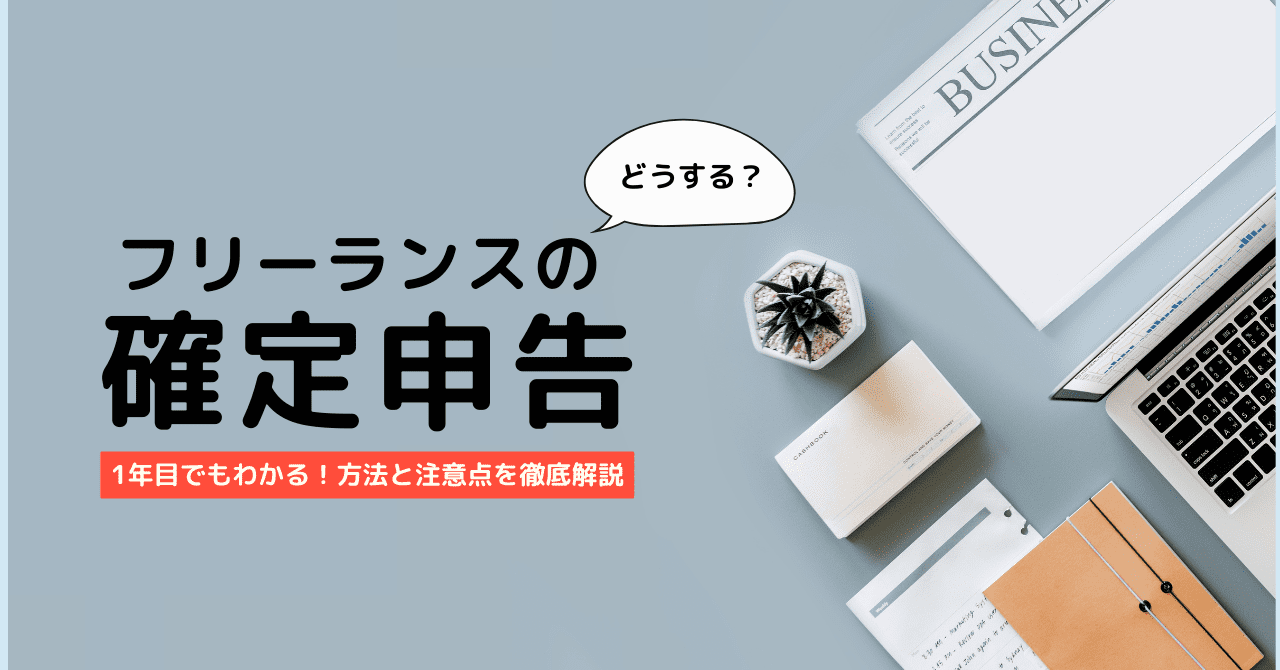
健康保険と年金の切り替えをする
会社員時代は厚生年金と社会保険に加入していましたが、フリーランスになると国民健康保険と国民年金に切り替える必要があります。
国民健康保険は退職後14日以内に、市区町村役場で手続きする必要があります。また国民年金は、年金事務所または市区町村役場で切り替えを行います。健康保険は会社員時代の健康保険を任意継続する選択肢もあります。国民健康保険とどちらが負担が少ないかを比較して決めると良いでしょう。
会計ソフトを導入する
フリーランスは経理業務も自分で行う必要があります。確定申告や日々の記帳をスムーズに進めるために、会計ソフトの導入を検討してください。
主な会計ソフト
- freee:初心者向け、スマホアプリ対応
- マネーフォワード クラウド:機能が豊富、連携サービスが多い
- 弥生会計オンライン:長年の実績があり、サポートが充実
銀行口座やクレジットカードと連携できるため、手入力の手間が減り、確定申告の作業を効率化できます。
必要に応じて保険に加入する
フリーランスは会社員と違い、病気やケガで働けなくなった場合の保障がありません。そのため、所得補償保険や賠償責任保険への加入を検討すると安心です。
所得補償保険は病気やケガで働けなくなった場合の収入を補償するもので、賠償責任保険は仕事のミスで損害を与えた際の賠償リスクをカバーするものです。
こうした保険を活用することで、予期せぬトラブルが起きた際の負担を軽減でき、安心して仕事を続けることができます。特に、長期間の収入減に備えたい場合や、業務上のリスクが気になる場合は、加入を検討すると良いでしょう。
ポートフォリオを作成する
フリーランスとして仕事を獲得するには、自分のスキルや実績を伝えるポートフォリオが重要です。クライアントが仕事を依頼する際の判断材料になるため、しっかり準備しておきましょう。重要なポイントとしては以下の3点です。
- 過去のプロジェクトや成果物を掲載する
- 使用技術や担当した業務を具体的に説明する
- 視覚的に見やすいレイアウトを意識する
エンジニアの場合は、GitHubや個人サイトに実績を掲載すると、クライアントにアピールしやすくなります。定期的に更新し、最新のスキルや取り組みを反映させることも大切です。
フリーランスを始めたら収める税金
ここからは、フリーランスを始めたら収める以下4つの税金について、詳しく解説します。
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
所得税
所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課される税金です。フリーランスは、会社員のように給与天引き(源泉徴収)されないため、自分で確定申告をして納める必要があります。
所得税は、以下の計算式で求められます。
【所得税の計算式】
総収入 - 必要経費 - 各種控除 = 課税所得
課税所得 × 税率 - 税額控除 = 所得税額
税率は累進課税方式(所得が多いほど税率が高くなる仕組み)として、5%~45% の範囲で設定されています。例えば、課税所得が195万円以下なら5%、4,000万円を超える部分には45%の税率が適用されます。
納税の流れとしては、まず確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までです。納付の期限は、基本的に確定申告の締め切りと同じ3月15日ですが、納付方法によっては期限が異なる場合があります。例えば、振替納税を利用すると、実際の引き落としは4月中旬になるため、資金繰りに余裕を持たせたい場合は検討すると良いでしょう。
このように、確定申告と納税の流れは密接に関係しています。申告だけでなく、納付方法や期限も意識しておくことが大切です。申告後は、所得税の納付が必要になることを忘れないようにしましょう。
住民税
住民税は、前年の所得をもとに計算される税金で、所得税の確定申告を行った後に自治体から納付の通知が届きます。課税対象となるのは、1月1日から12月31日までの1年間の所得で、税率は基本的に所得の10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)です。ただし、一部の自治体では税率が異なる場合があるため、住んでいる地域のルールを確認することが重要です。
住民税の納付方法には、一括払いと分割払いがあります。一括払いの場合は6月の納期限までに全額を納めますが、分割払いを選ぶと、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて支払う ことができます。納付書を使って金融機関やコンビニで支払うほか、口座振替を利用して自動引き落としにすることも可能です。
住民税は、会社員時代には給与から自動的に天引きされていたため、納税を意識する機会は少なかったかもしれません。しかし、フリーランスになると自分で納める必要があるため、納付期限を把握し、事前に納税資金を確保しておくことが大切です。もし支払いが遅れると延滞金が発生する可能性があるため、自治体からの通知をよく確認し、計画的に対応しましょう。
個人事業税
個人事業税は、都道府県が課税する税金 で、フリーランスとして一定の所得がある場合に発生します。
個人事業税が発生するのは、「法定業種」に指定されている事業を営む個人事業主 です。フリーランスエンジニアは「請負業」に該当するため、個人事業税の対象になります。ただし、所得が一定額以下の場合は非課税となります。
税額の計算方法
個人事業税は、以下の計算式で算出されます。
(事業所得 - 事業主控除290万円) × 5% = 個人事業税額
例えば、年間の事業所得が500万円の場合、
(500万円 - 290万円) × 5% = 10万5,000円 の個人事業税が発生します。
個人事業税は、確定申告の内容をもとに都道府県が税額を計算し、納税通知書を送付します。自分で申告する必要はなく、自治体からの通知に従って納税します。納税通知の送付時期は毎年8月頃で、8月と11月の2回払い、または一括払いで支払います。
フリーランスエンジニアとして一定の所得がある場合、個人事業税の負担を見越した資金管理をしておくことが大切です。
消費税
消費税は、前々年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、原則として翌々年から課税事業者となり、納税義務が生じます。例えば、2022年の売上が1,000万円を超えた場合、2024年から消費税の納税義務が発生する可能性があります。
また、前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円を超える場合、または支払った給与の合計が1,000万円を超える場合も、翌年から課税事業者となります。そのため、売上が増加した際には、消費税の納税義務がいつから始まるのかを正確に把握することが重要です。
課税事業者となった場合、売上に含まれる消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いた額を納付します。
フリーランスSEの案件探しはエンジニアファクトリー

フリーランスを始めたいけれど、「案件をどう探せばいいのか」「収入が安定するか不安」そんな悩みはありませんか?エンジニアファクトリーなら、公開案件7,000件以上、エンド直案件も多数。あなたのスキルや希望に合った案件を紹介し、契約や単価交渉までサポートします。
さらに、最短2週間で案件参画が可能 なので、スムーズな独立が実現できます。IT業界専門16年の実績 を持つエージェントが、あなたのキャリアをしっかり支えます。まずは無料登録し、あなたに最適な案件をチェックしてみませんか?
まとめ
フリーランスとして成功するためには、綿密な準備と戦略的な行動が求められます。この記事で紹介したいくつかのステップを着実に踏むことで、フリーランスエンジニアとしてのキャリアを着実に築けるでしょう。
もし案件獲得や仕事探し、営業活動に不安がある方は、エンジニアファクトリーに会員登録してどのような求人があるのか、探してみてはいかがでしょうか。