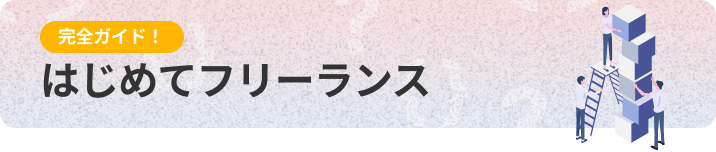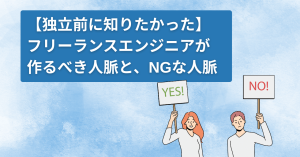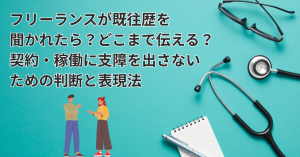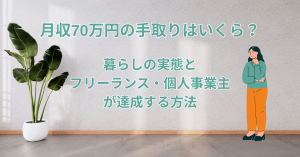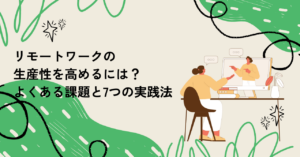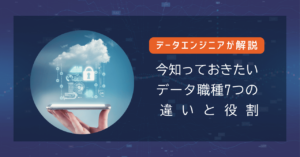「フリーランスや個人事業主だと住宅ローンは組めないの?」「住宅ローンの審査項目と必要な書類はなに?」
フリーランスや個人事業主は、会社員と比較すると社会的信用が低いと捉えられるケースが多々あります。では、住宅ローンを組むことはできないのでしょうか。
この記事では、「フリーランスや個人事業主が住宅ローンを組めるのか」や「ローンを組む際の条件」などについて解説していきます。
- フリ-ランス・個人事業主は住宅ローンが組めない?
- 年収別の住宅ローン借入可能額はどれくらい?
- フリ-ランス・個人事業主は住宅ローンを組むときに必要な書類
- 住宅ローンの審査でチェックされる事とは
- 住宅ローン審査申し込み時の注意点
- フラット35とは?
- フリ-ランスの案件を探すなら「エンジニアファクトリー」
- まとめ
フリ-ランス・個人事業主は住宅ローンが組めない?
フリーランスや個人事業主でも住宅ローンを組むことは可能です。ただし、会社員に比べて審査が厳しくなりやすいです。審査に通るためには、以下の条件をクリアする必要があります。
- 安定した収入があること
- 返済能力があること
- 信用情報に問題がないこと
年収別の住宅ローン借入可能額はどれくらい?
住宅ローン借入可能額は、金融機関や地域によって異なりますが、一般的には「年収の5〜6倍」が無理なく返済できる額といわれています。例えば、年収500万円の場合の借入可能額は2,500〜3,000万円となります。
以下の表が、年収別の住宅ローン借入可能額の目安です。
| 年収 | 借入可能額の目安(年収の5倍) | 借入可能額の目安(年収の6倍) |
| 400万円 | 2000万円 | 2400万円 |
| 500万円 | 2500万円 | 3000万円 |
| 600万円 | 3000万円 | 3600万円 |
| 700万円 | 3500万円 | 4200万円 |
| 800万円 | 4000万円 | 4800万円 |
| 900万円 | 4500万円 | 5400万円 |
ただし、この金額はあくまでも目安であり、実際の借入可能額は、年収以外の下記の条件も考慮して決定されます。
- 勤務先
- 勤続年数
- 家族構成
- 他の借入れの有無
また、住宅ローンの借入上限額は、税金や社会保険料などを差し引く前の年収をもとに計算されます。実際に手元に残る手取り年収はもう少し低くなるため、借入上限額まで借りてしまうと、返済が苦しくなる可能性が高くなるので注意してください。
フリ-ランス・個人事業主は住宅ローンを組むときに必要な書類

フリーランスや個人事業主が住宅ローンを組むには、以下の2点の書類が必要となります。
- 過去3年分の確定申告書
確定申告書とは、1月1日から12月31日までの所得と納税額をまとめた書類です。確定申告書には、A様式とB様式の2種類があります。A様式は会社員などの給与所得者や公的年金等受給者が対象、B様式は個人事業主や給与所得と他の所得を併せ持つ方が対象となります。 - 納税証明書
納税証明書とは納付すべき税額や納付した税額、未納額等を証明する書類です。
未納の税金がある場合は、審査に影響が出るため注意してください。
会社員の場合、勤務先から源泉徴収票や住民税の納税証明書などを提出することで、安定した収入があることを証明することができます。一方、フリーランスや個人事業主は、確定申告書や納税証明書などの書類で、事業の安定性や収入の状況を証明する必要があります。
個人事業主やフリーランスの所得は、収入から経費を差し引いた額になります。中には、節税などの目的で経費を多めに計上して、所得を少なく申告しているケースが見受けられます。所得が少なく申告されている場合、借入可能額が減ってしまう可能性があるため注意が必要です。
会社員であれば、1年分の源泉徴収票で審査が可能です。しかし、フリーランスや個人事業主の場合は、年によって年収が大きく変動することがあるため、金融機関の多くは3年分の源泉徴収票の提出を求めています。
住宅ローンの審査でチェックされる事とは
住宅ローンの審査では、借り入れ希望者の返済能力が十分かどうかを判断するために、以下の6つの項目が確認されます。
- 独立してから何年か
- クレジットカードや公共料金の滞納の有無
- 連帯保証人がいるか
- 自己資金はいくらか
- 住宅用か事業用か
- 事業としての継続性・安定性
ここからは、それぞれの項目について解説していきます。
1. 独立してから何年か
「独立してからの年数」という項目は、フリーランスや個人事業主の場合、収入の安定性や事業の継続性を判断するためにチェックされます。独立してからの年数が短い場合、収入が不安定で事業が継続するかわからない可能性があるため、審査が厳しくなる可能性が高いです。
一般的には、金融機関はフリーランスや個人事業主に対し、3期分の確定申告書の提出を求めます。そのため、独立してから3年程度だと住宅ローンの審査に通ることは難しいでしょう。
しかし、医者や弁護士などの年収水準が高く、社会的地位が確立されている国家資格者の場合は、住宅ローンにおいて優遇される可能性があります。
また、金融機関によって審査の基準は異なります。3期分の確定申告書の提出を求めない金融機関もあるため、独立してから3年程度でも審査が可能な場合があります。
2. クレジットカードや公共料金の滞納の有無
「クレジットカードや公共料金の滞納の有無」という項目は、借り入れ希望者の支払い能力や信用力を判断するためにチェックされます。
金融機関はローンの審査をする際に、個人信用情報を必ず確認しています。そのため、クレジットカードや公共料金の滞納があると、支払い能力に問題がある、信用力が低い、という判断をされてしまい、審査が厳しくなることがあります。
クレジットカードや公共料金の滞納だけでなく、事業用のローンや車のローンも、借り入れ希望者の負債状況に含まれます。そのため、たとえ資金繰りがうまくいっていたとしても、他の借入額が多いと、住宅ローンの借入可能額が減額されたり、審査に通らなくなる可能性があります。
3. 連帯保証人がいるか
連帯保証人とは、借り入れ希望者と連帯して債務を負う人のことをいいます。連帯保証人になると、借り入れ希望者が返済不能になった場合、連帯保証人自身が借金を返済する義務を負うことになります。
「連帯保証人がいるか」という項目は、借り入れ希望者の返済能力が不十分な場合でも、連帯保証人が支払いを保証してくれるかどうかを判断するためにチェックされます。そのため、連帯保証人がいれば、住宅ローンの審査に通過できる可能性が高くなります。
連帯保証人は、配偶者や3親等以内の親族に依頼するのが一般的です。住宅ローンを検討しているのであれば、早めに話しておくことをおすすめします。
4. 自己資金はいくらか
「自己資金はいくらか」という項目は、借り入れ希望者の自己資金の額が、住宅ローンの頭金や諸費用にどの程度充てられるかどうかを判断するためにチェックされます。自己資金が多いほど、住宅ローンの借入額を減らすことができ返済比率も低くなります。
頭金や諸費用を自己資金で賄うことができる場合、返済負担が軽減されるため、審査に有利になります。また、住宅ローンの返済期間を短くすることができるので返済負担の軽減にもつながります。
住宅ローンを検討している場合は、自己資金の準備もすることが大切です。
5. 住宅用か事業用か
フリーランスや個人事業主の方の中には、自宅の一部を事務所や店舗などとして活用している方も多くいます。しかし、住宅ローンはあくまでも生活に必要な住宅の購入を目的とした融資であるため金利が低く設定されており、原則として事業用住宅の購入には利用できません。
近年ではフラット35など、店舗や事務所兼用住宅の融資を行う金融機関も増えてきました。ただし、融資を受けるためには「建物や部屋の床面積の2分の1以上」を居住用に利用しているなどの条件があります。
また、住宅ローン減税を受けるためには「建物や部屋の床面積の2分の1以上」が自己居住用であることが条件となります。
6. 事業としての継続性・安定性
「事業としての継続性・安定性」という項目は、借り入れ希望者の事業が将来にわたって継続的・安定的に収益を上げることができるかどうかを判断するためにチェックされます。事業としての継続性・安定性は、住宅ローンの返済能力に直接影響するため、審査では重要な項目となります。
事業の継続性の有無を判断する材料として、確定申告書の他に「決算報告書」の提出を求められる場合もあります。直近3期の中で赤字がある場合、事業の継続性・安定性に不安があると判断され、審査が不利になるケースもあります。
ただし、赤字が一時的なものであり、今後の収益回復の見込みがあると説明できれば、住宅ローンの審査を通過することも可能です。
住宅ローン審査申し込み時の注意点
住宅ローン控除(減税)の適用条件は下記の通りになります。
- 返済期間が10年以上あること
- 床面積が50平方メートル以上あること
- 自宅で事業を営んでいる場合、床面積の2分の1以上を居住のために使用すること
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 自己居住用の住宅であること
- 住宅取得後6ヵ月以内に入居すること
住宅ローンの審査において、床面積は「登記簿」に記載されている数値で判断されます。マンションの場合は、通路や階段、エレベーターなどの共用部分を除いた専有部分の床面積で判断されます。
中古住宅の場合は、上記に加えて下記2つの条件も満たす必要があります。
- 1982年1月1日以降に建築された住宅であること
- 現行の耐震基準に適合していること
1981年以前の中古住宅を購入する場合は、耐震基準を示す耐震基準適合証明書などが必要になるため、事前に不動産業者に確認するようにしてください。
また、2022年の税制改正により、住宅ローン控除の対象となる新築住宅には、省エネ性能が必須となりました。2024年以降に新築住宅を購入する場合、一定の省エネ性能基準を満たしていない住宅は、住宅ローン控除の適用が受けられなくなります。
フラット35とは?

フラット35とは、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する「全期間固定金利型住宅ローン」です。住宅を購入、リフォーム、改築をする方が利用できます。借入期間は名前の通り最長35年と長く、借入金利が返済期間中ずっと一定であるため、長期にわたるライフプランを立てやすいのが特徴です。
フラット35の特徴は下記の通りです。
- 返済期間は最長35年、最短は15年
- 融資限度額は8000万円
- 連帯保証人が不要
- 団体信用生命保険の加入が難しい方でもローンを利用できる
フラット35は一般的な金融機関の住宅ローンよりも比較的条件が緩めに設定されています。また、直近1期分の確定申告書を提出するだけで審査を受けられるため、フリーランスや個人事業主の方でも申し込みしやすくなっています。
フラット35の利用条件は下記の通りです。
- 申し込み時の年齢が満70歳未満であること
- 日本国籍を有していること(外国人の場合永住許可を受けている、もしくは特別永住者であること)
- フラット35を利用した場合の返済負担率が基準値以下であること
- 住宅金融支援機構が定めた技術水準を満たす住宅であること
- 所得に応じた返済負担率の基準を満たすこと
- 床面積が一戸建ての場合70平方メートル以上、共同住宅の場合30平方メートル以上であること
フラット35の利用条件はどの金融機関でも同じですが、金利や事務手数料などは金融機関により異なるため、事前に調べておくことが大切です。
フリ-ランスの案件を探すなら「エンジニアファクトリー」

フリーランスエンジニアとして案件を探すなら、「エンジニアファクトリー」がおすすめです。
エンジニアファクトリーは、フリーランスエンジニアに特化したエージェントです。エンジニアファクトリーのコンサルタントが一人ひとりの気持ちに寄り添い、希望条件や不安を汲み取り、最適な案件の紹介を行います。
エンジニアファクトリーは、フリーランスエンジニアとして働きたい方におすすめのエージェントです。ぜひ、一度登録してみてはいかがでしょうか。
まとめ
この記事では、フリーランスや個人事業主でも住宅ローンが組めるのかについて解説してきました。
住宅ローンの審査に通るためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 安定した収入があることを証明する
- 複数の金融機関で比較検討する
- 無理のない返済計画を立てておく
- フラット35を活用する
フリーランスや個人事業主でも、住宅ローンを組むことは可能です。ただし、会社員と比較して審査が厳しくなる傾向にあるため、事前にしっかりと準備しておくことが大切
ライター:前嶋 翠(まえじま みどり)
COBOLが終わろうとする時代にプログラマのキャリアをスタートし、主にJavaエンジニアとして経験を積みました。フリーランスエンジニアとして活動していたとき、リーマンショックが起こったことをきっかけに家庭に入りました。出産を経て在宅でできる仕事として、ライターに。ITエンジニア経験のあるライターとして、IT業界のあれこれを皆さまにわかりやすくお伝えしていきます。