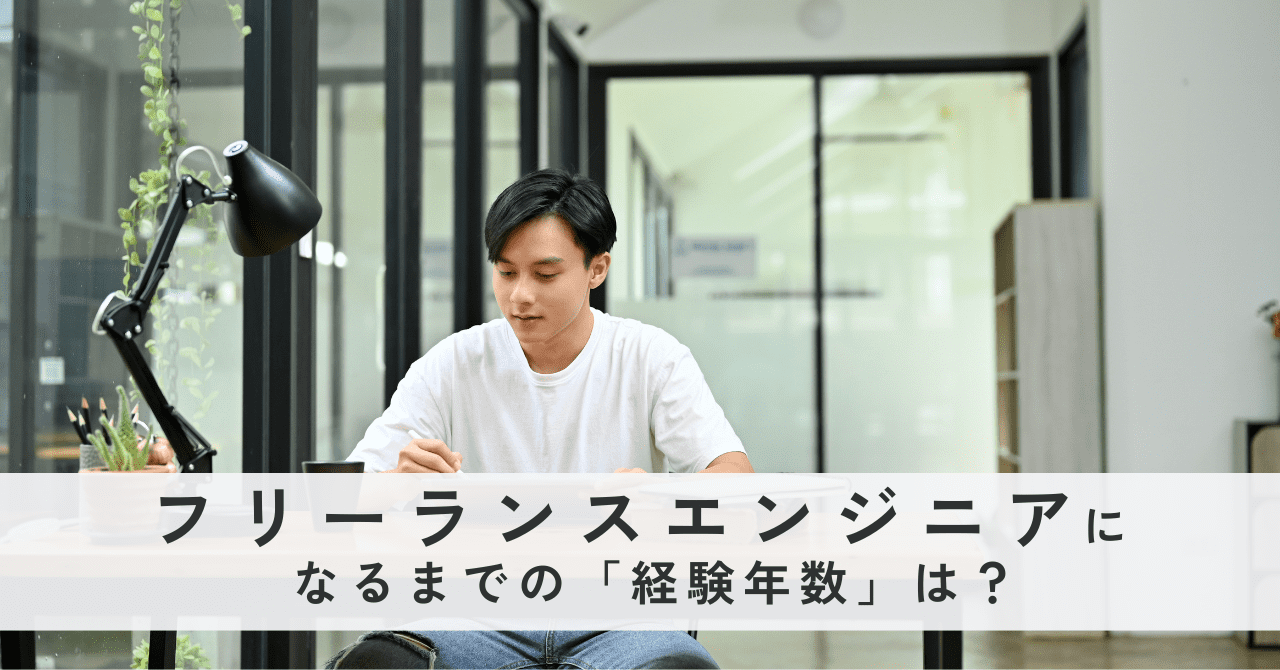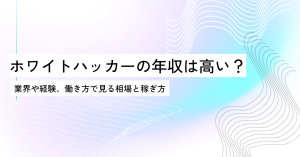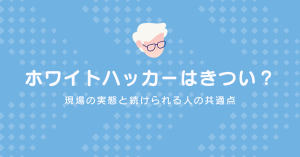終身雇用や退職金制度がない会社も増えているなかで、正社員からフリーランスのエンジニアへとキャリアチェンジを考えている方も多いのではないでしょうか?
このような方から多く聞かれる疑問が、「どのようなタイミングでフリーランスになるべきか」「実務経験は何年あるべきか?」といった質問です。
スキルや経験は人それぞれですので一概には言えませんが、結論から申し上げるとフリーランスITエンジニアのエージェント目線では、3年以上の実務経験を経た上で独立することをおすすめします。
本記事では、フリーランスになるのにベストなタイミングや実務経験の年数(1年・3年・5年)による案件の違いについて解説していきます。また、実務経験による市場価値の違いを年数別にまとめるので、実務経験やスキルをアピールしたい方は最後までご覧ください。

エージェントサービス「エンジニアファクトリー」では、ITフリーランスエンジニアの案件・求人の紹介を行っています。掲載中の案件は7,000件以上。紹介する案件の平均年商は810万円(※2023年4月 首都圏近郊のITエンジニア対象)となっており、スキルや言語によって高条件の案件と出会うことができます。
氏名やメールアドレス・使用できる言語を入力するだけで、簡単60秒ですぐにサポートを開始できます。案件にお困りのITフリーランスの方やより高条件の案件と巡り合いたいと考えている方は、ぜひご登録ください。
フリーランスエンジニアになるために必要な実務経験とは?年数別の市場価値
まずはフリーランスエンジニアになるために必要な実務経験について解説します。
経験年数ごとの市場価値の違い
フリーランスエンジニアの世界では、経験年数が文字通り「価値」に直結します。ここでは、以下の3つの区分で経験年数別の市場価値について詳しく解説します。
- 経験1年:実績が少なく、案件獲得に工夫が必要
- 経験3年:選択肢が広がり、単価交渉も可能に
- 経験5年以上:高単価案件やリーダー職も狙える
自身が当てはまる経験年数だけでなく、ほかの年数も理解しておけばキャリアプランの構築や、キャリアの見直しに役立ちます。経験年数を重ねていても、別のキャリアに転じれば1年目から再スタートとなるからです。
また、市場価値は経験年数だけでなく、どのようなスキルセットを持っているか、どのようなプロジェクトに携わってきたかも影響します。本項でまとめた経験年数ごとの市場価値を参考にしつつ、スキルアップを心がけ自身の価値を高めていきましょう。
経験1年:実績が少なく、案件獲得に工夫が必要
経験1年目のフリーランスエンジニアは、実績の少なさが影響し案件獲得に苦労する傾向にあります。したがって、1年目は実績作りに焦点を当てましょう。
まずは、クラウドソーシングサイトなどを活用し、比較的簡単な案件から実績を積み重ねていくのがおすすめです。Webサイトの修正や簡単なプログラム開発など、短期間で完了できる案件を選んで丁寧にこなし、クライアントからの信頼を得ていきます。
実績がない状態では、クライアントはあなたのスキルを判断する材料がないため、まずは「きちんと仕事をこなせる」という安心感を与える必要があるからです。また、案件獲得のためには、積極的に自己PRを行いましょう。SNSやブログで情報発信したり、勉強会やイベントに参加して人脈を広げたりするのも重要です。
このように経験1年目は、実績作りと自己PRに力を入れ、地道に信頼を積み重ねていきましょう。
経験3年:選択肢が広がり、単価交渉も可能に
経験3年目になると、エンジニアとしてのスキルが認められ、案件の選択肢が広がります。単価交渉も視野に入れておくといいでしょう。
3年の実務経験があれば、Web開発やアプリ開発、インフラ構築などの得意な分野が見えてくるはずです。自分の強みを活かせる案件を選んで、さらなるスキルアップを目指します。
得意分野を持てば高度な案件に挑戦でき、市場価値を高められます。過去の案件実績を具体的に提示すれば、クライアントに対して自身のスキルを効果的にアピール可能です。
単価交渉の際には、自分のスキルと経験に見合った金額を提示する必要があります。クライアントに納得してもらうには、過去の案件の実績や習得している技術などの提示が有効です。
経験3年目は、得意分野を活用しつつ単価交渉にも挑戦すれば、収入アップが期待できます。
経験5年以上:高単価案件やリーダー職も狙える
経験5年以上になると、フリーランス市場での評価が高まり、高単価案件やリーダー職にチャレンジ可能です。
Webサービスの開発リーダーとして、チームを率いてプロジェクトを成功に導いたり、大規模システムの設計・構築を主導したりといった役割が求められます。豊富な経験に基づいた高度な技術力はもちろん、プロジェクトを円滑に進めるためのコミュニケーション能力や問題解決能力が期待されるからです。
高単価案件を獲得するためには、実績を具体的にアピールしましょう。「〇〇プロジェクトにおいて、〇〇の技術を用いて、開発期間を〇〇%短縮し、〇〇円のコスト削減に貢献した」といった具体的な数値を提示できれば、クライアントに大きなインパクトを与えられます。
リーダーシップや交渉能力も磨いて、より責任のあるポジションに挑戦しましょう。

実務経験3年でフリーランスエンジニアになれる?
開発の案件規模やスキル要件などによって異なるため一概に言えませんが、弊社のフリーランスエンジニア案件サイトであるエンジニアファクトリーに掲載している案件の多くが、実務経験3年以上という条件になります。
そのため、実務経験を3年積んでいれば十分フリーランスエンジニアとして案件が獲得できるといえるでしょう。
開発エンジニアとしての経験年数が3年の場合
経験が3年といっても、エンジニアには要件定義、基本設計、詳細設計、プログラミング/開発、テスト、保守など、さまざまなプロセスが存在し、どのプロセスでどれだけの実務経験があるかによって変わります。
要件定義や設計経験があれば、上流工程から関わる案件に挑戦でき、より高単価な案件を獲得するチャンスが広がります。経験がない場合は、プログラミングやテストがメインの案件からスタートし、徐々に上流工程のスキルを磨いていくのがおすすめです。
どの部分において専門性があるかはもちろん、案件規模や経験した開発言語の種類によっても、選択できる案件の幅は異なります。まずは、得意な開発言語やスキルセットを活かした開発案件を中心に応募するといいでしょう。
また、フリーランスになれば、クライアントとのコミュニケーションや連絡はすべて自分自身で行わなければいけません。そのため、クライアントに対してヒアリングをする、調整をするなどマネージャーの役割を担った経験があると有利です。
インフラエンジニアの経験が3年の場合
インフラエンジニアには、サーバー、ネットワーク、セキュリティ、クラウドに関する全般的な知識が求められます。
サーバーは、Windowsか、Linuxか、Unixかによって変わってきます。もちろん、多いに越したことはありません。ただし、実務経験3年であれば、汎用的な知識よりも、いずれかひとつに特化した知識が求められる場合が多いです。
特に、LinuxはWindowsやUnixと比べると、エンジニアの数が少なく需要が高いです。案件によっては、セキュリティ対策、システムのサイバー攻撃リスクの評価、セキュアプログラミングなど、セキュリティエンジニアに近い業務を依頼されるケースもあるので、セキュリティに関する知識があるとなお良しです。
近年は、クラウドの需要が高いため、 AWS(Amazon Web Services)、Azure、GCP(Google Cloud Platform)といった経験もあると、選べる案件の幅は広がるでしょう。AWS認定資格を取得しておけば、クラウドに関する知識・スキルを客観的に証明し、企業からの信頼獲得につながります。資格取得者である点をアピールすれば、技術力を証明し、案件獲得を有利に進められます。
実務経験1年でもフリーランスエンジニアになれる?案件獲得のポイント
「エンジニアとして1年働いてみたけれど、給料が低いからフリーランスとして独立をしたい」と考えている人も少なくないでしょう。
実務経験1年でも、ポイントを抑えれば、フリーランスエンジニアとして案件獲得が可能です。詳しく見ていきます。
開発経験が1年の場合
結論から言うと、フリーランスとしてエンジニアをすることはできますが、選べる案件の種類は少なくなります
理由としては、経験値が足りなかったり、視野が狭かったりするために、ルーチンワークやそこまでスキルが求められない業務しか任されないためです。 1年目から、顧客システムや自社システムの開発プロジェクトに関わったのであれば、チャレンジしてみても良いかもしれません。
しかし、上司の開発案件でヘルプ的に開発をしていた、開発業務はしておらずテスト業務だけだったということであれば難しいかもしれません。
実績が少ないとクライアントにアピールできる材料がないため、案件獲得につながりません。実績が少ないのであれば、クラウドソーシングを活用して仕事を請け負いましょう。成果をポートフォリオにまとめれば、経験やスキルをクライアントにアピールできます。開発経験が1年であれば、まずはクライアントにアピールできる実績作りが重要です。
インフラエンジニアの経験が1年の場合
インフラエンジニアの場合、ヘルプデスクからスタートして、監視、保守・運用、設計・構築というキャリアパスをたどるのが一般的です。
そのため、インフラエンジニアで実務経験が1年だと、ヘルプデスクまたは監視のみしか経験がなく、保守・運用、設計・構築が未経験ということになります。
多くの案件では、実務経験が応募要件に含まれていることが多いです。運用の経験を1年以上積んでから、フリーランスになった方が得策でしょう。
それでも1年目からフリーランスを目指すのであれば、戦略的なアプローチが求められます。まずはクラウドソーシングやフリーランスエンジニア専門のエージェントを活用して、経験不問の案件から取り組みましょう。
監視・運用業務から始めて、インフラの基礎知識やトラブルシューティングスキルを身につけるのがおすすめです。
実務経験が少なくても案件を獲得するための戦略
実務経験が少ないエンジニアが案件を獲得するには、戦略的に活動しなければ上手くいきません。自身のスキルセットを明確にし、得意分野の絞り込みが重要です。ポートフォリオを作成して成果物を公開すれば技術力のアピールにつながります。
公開できる成果物を用意するには実績が必要です。ただ、実務経験が少ないエンジニアは、十分な実績がない場合もあるでしょう。実績が少ないのであれば、以下の3つのポイントを意識した戦略構築が重要です。
- 副業やアルバイトで実績を積む
- ポートフォリオを充実させる
- 低単価案件で信頼を獲得する
本項では上記のポイントについて詳しく解説します。ただし、これらのポイント以外にも学習意欲のアピールや、資格取得も重要です。諦めずに努力し続けて、実績を積み重ねていきましょう。必ずチャンスは広がっていくはずです。
副業やアルバイトで実績を積む
実務経験が少ないエンジニアにとって、副業やアルバイトは貴重な実績作りの機会です。
副業やアルバイトを通じて、Webサイトの作成やアプリ開発、データ分析といったプロジェクトに参加し、実践的なスキルを身につけましょう。実務経験がない場合、企業はあなたのスキルを少ない情報で判断しなければなりません。副業やアルバイトでの実績があれば、スキルレベルの客観的な証明につながります。
Webサイト作成のアルバイト経験があれば、HTML/CSS、JavaScriptなどのスキルをアピールできます。データ分析の副業経験があれば、PythonやRなどのプログラミングスキルや、統計分析の知識を示せるでしょう。
副業やアルバイトは、実務経験が少ないエンジニアにとって、スキルアップと実績作りを両立できる有効な手段です。積極的に活用し、フリーランスとしてのキャリアを築きましょう。
ポートフォリオを充実させる
ポートフォリオはフリーランスエンジニアにとって、自身のスキルや実績をアピールするための生命線です。
過去に作成したWebサイトやアプリ、プログラム、デザインなどを集めたもので、クライアントにあなたのスキルや実績を視覚的に証明できます。クライアントはポートフォリオを見て、あなたの技術力やデザインセンス、問題解決能力などを判断します。
Webサイトを作成した場合、デザインの美しさやユーザビリティ、SEO対策の有無などをチェック可能です。アプリを作成した場合、機能性、操作性、安定性などを評価できます。
ポートフォリオを作成する際には、情報を最新に保ち、使用した技術や課題の解決といった詳細な説明も必要です。具体的な説明により、クライアントにあなたの思考プロセスや技術力が伝わるのです。
ポートフォリオを適切に作成し、積極的にアピールしましょう。
低単価案件で信頼を獲得する
フリーランスとして駆け出しの頃は、低単価案件を積極的に受けて信頼と実績を積み重ねましょう。
低単価案件は、高単価案件に比べて競争率が低く、受注しやすい傾向があります。低単価案件でも丁寧にこなしクライアントの期待を超える成果を出せば、「このエンジニアは信頼できる」という評価を獲得できるからです。
納期を厳守する、丁寧なコミュニケーションを心がける、期待以上の成果物を納品するなどの行動は、クライアントからの信頼を得るために非常に有効です。
低単価案件を受ける際には、単価だけでなく、案件の内容や自分のスキルアップにつながるかどうかも考慮しましょう。クライアントからの信頼が得られれば、継続的な案件の依頼や、高単価案件の紹介につながります。
信頼と実績を築くためのステップとして低単価案件を積極的に活用し、着実にキャリアアップを目指しましょう。
実務経験5年以上ならフリーランスエンジニアとしての市場価値は?
エンジニアとして、5年程度の実務経験があれば、テストから設計・開発、保守・運用といった開発一連のサイクルを経験しているため、選べる案件の数もグッと増えるでしょう。
また、要件定義やプロジェクトリーダー、アーキテクト、PMなど上流工程を経験している方は、さらに市場価値が高くなります。
経験年数が5年を超えてくると、エンジニアとしての技量だけでなく、課題解決能力、チームマネジメント、プロジェクト推進力、ステークホルダーとの調整力など、エンジニア以外のスキルが問われます。
より市場価値を高めるための戦略を、開発系とインフラエンジニア系に分けて詳しく見ていきましょう。
開発経験が5年の場合
開発経験が5年あれば、Webアプリケーション開発やスマホアプリケーション開発といった案件から、ブロックチェーン開発といった最新の案件まで獲得できます。
一方で、特定の言語に振り切ることもできます。
開発言語の中でもPythonは、AI(機械学習・ディープラーニング)、ブロックチェーン開発などの分野で使われる言語ということもあり、急速に需要を伸ばしています。
他にも、スマートフォンアプリ開発で使われるSwiftやGO、Kotlinも、少しずつですが需要が伸びてきつつあります。比較的新しい言語であるため、プレイヤーが少なく狙い目です。
また、新しい開発言語を習得して幅を広げる選択もできます。フリーランスの求人でも、複数言語を要件とするケースが多いため、扱える言語が多いに越したことはありません。余力がある方は、新しい言語の習得にチャレンジしてみましょう。
さらに、マネジメントの実務経験がある方は、上流工程のキャリアも考えられます。要件定義やプロジェクトリーダー、アーキテクト、PMなどになれば、やはり報酬金額も高くなります。
チームでの開発経験を積極的に積み重ねてリーダーシップ経験を積んだり、プロジェクトの計画、実行、管理に関する知識を習得してマネジメントスキルを身につけたりすれば、テックリード・PM案件にも挑戦できます。
インフラエンジニアとしての経験が5年の場合
インフラエンジニアとして5年の経験を持つ場合、フリーランス市場で高い価値を持つことができます。特に、クラウドスキルとセキュリティ知識は市場価値を大きく左右する重要な要素です。
Windows、Linux、Unixのいずれかだと案件の選択肢が少なくなるため、すべての環境で経験を積んでおくことをおすすめします。もし、専門性を高めるのであれば、Linuxを中心にスキルを磨いていくと良いでしょう。
また、インフラエンジニアの案件の中には、要件として資格の有無を問うケースもあります。シスコシステムズ社が提供するベンダー資格「CCIE」、Linux技術者の認定試験「LPIC」、日本オラクル社が提供するデータベース認定試験「ORACLE MASTER」といった資格は取得しておいて損はありません。
近年は、ITインフラの仮想化が進んでいるため、クラウドに関する知識も求められています。
AWS(Amazon Web Services)、Azure、GCP(Google Cloud Platform)などの知識、Infrastructure as Codeのスキルに加え、多少のプログラミング言語を習得しておくと、なお良いでしょう。
クラウド認定資格やセキュリティ関連資格を取得すれば、クライアントに専門性をアピールできるため、高額案件の獲得につながります。
フルスタックエンジニアという選択肢も
1つの選択肢として、システムエンジニアとインフラエンジニアなど複数のスキルをもつフルスタッフエンジニアという道もあります。
開発スピードの向上や人件費削減の観点から、フルスタックエンジニアは重宝される傾向にあります。
フルスタックエンジニアとは?
エンジニアリング業務における要件定義、基本設計、詳細設計、プログラミング/開発、テスト、保守・運用といった業務プロセスと、サーバー、データベース、ネットワークなどさまざまな領域において一気通貫で行えるエンジニアのことを指します。
「マルチエンジニア」とも呼ばれます。従来は、細分化された役割分担のもと、複数人数で開発を行っていましたが、IT技術における需要の多様化・複雑化に伴って、幅広いITスキルや知識を持ったフルスタックエンジニアが求められるようになってきています。
フルスタックエンジニアには、以下のような幅広いスキルセットが求められます。
- フロントエンド技術:HTML、CSS、JavaScriptやUI/UXデザインの基礎知識など
- バックエンド技術:プログラミング言語やデータベースなど
- インフラ技術:サーバー構築・運用やネットワーク基礎知識など
- その他:バージョン管理システムやコミュニケーション能力など

フルスタックエンジニアが求められる理由
フルスタックエンジニアが市場で求められる背景には、現代のソフトウェア開発における変化と、それに対応できる人材へのニーズの高まりがあります。
特にスタートアップやDX推進の現場では、その多才さと柔軟性が不可欠となっています。
ここからはフルスタックエンジニアが求められるようになった理由について、人件費と開発速度の2つの側面から解説します。
フルスタックエンジニアに必要なスキル
フルスタックエンジニアになるには、フロントエンドやバックエンド領域におけるプログラミングや開発のスキルを基礎として、Windows、Linux、UnixといったOSやTomcat、ApacheやMySQLなどのミドルウェアにおけるスキル、さらに加えてAWS(Amazon Web Services)、Azure、GCP(Google Cloud Platform)などクラウドに関するスキルも持っておくと活躍できる幅は非常に広くなります。
フルスタックエンジニアを目指すのであれば、得意な分野から着手し、徐々にほかの領域を拡げましょう。具体的には以下のような学習方法があります。
- バックエンド: Pythonの学習
- フロントエンド: ReactでUIを構築
- クラウド: AWSでEC2, S3を触る
- データベース: PostgreSQLを使いデータモデリング
オンラインコースや書籍で基礎を固め、個人プロジェクトで実践経験を積むのが効果的です。
エンジニアの経験年数別の平均月収とは?
経験年数はエンジニアの収入を決める重要な要素です。ここでは、エンジニアの経験年数ごとの月収について解説します。
開発の経験別
開発エンジニアの平均月収は、経験年数に比例して上昇する傾向です。本項では、開発経験が1年の場合、3年の場合、5年の場合に分けて具体的に見ていきます。
また開発言語によっても平均月収は異なります。Python、Swift、C言語の3つのケースで解説するので、単価が高い言語の選び方の参考となさってください。
インフラエンジニアの経験別
案件規模や開発環境などによって異なりますが、週5回常駐と仮定したときのおおよその月収目安について解説します。
| インフラエンジニアの経験年数が1年 | 40万円前後/月 |
| インフラエンジニアの経験年数が3年 | 55〜65万円前後/月 |
| インフラエンジニアの経験年数が5年 | 80万円〜100万円前後/月 |
まず、インフラエンジニアの経験が1年の場合、月収の相場は40万円前後です。経験年数が1年だと、ヘルプデスクまたは監視の経験にとどまるため、任される業務の幅は少ないでしょう。
次に、インフラエンジニアの経験が3年の場合は、月収の相場は55〜65万円前後です。3年間であれば、保守・運用、インフラの施工管理、ネットワーク開通といった業務まで経験していることが多いでしょう。
条件面にこだわらなければ、案件の選択肢はかなり広いです。クラウドに関する経験があると、さらに報酬単価は高くなる傾向にあります。
インフラエンジニアの経験が5年の場合は、月収の相場は80万円〜100万円前後です。5年であれば、ヘルプデスクまたは監視〜インフラ構築、一通りインフラエンジニアとしての業務を経験しているため、ほとんどの案件に関わることができます。
また、チームのサブリーダーやリーダー、プロジェクトリーダーなどの経験があれば、上流工程の業務にも携われるため、さらに単価が高くなります。
さらにクラウド環境(AWS、Azure、GCP)の経験は、市場価値の向上に有効です。クラウドスキルが高単価につながる理由は、クラウド移行支援や運用自動化といった高度な案件に対応できるためです。
「AWS環境でのWebサービス構築・運用自動化」や「Azureを用いた大規模システム移行」案件などでは、高度な専門知識が求められるため高単価が期待できます。
フリーランスエンジニアになるベストなタイミングとは?
フリーランスエンジニアになるベストなタイミングはいつなのでしょうか?弊社にてご支援しているインフラエンジニアの事例を参考に、それぞれ1年、3年、5年でまとめてみました。
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | |
|---|---|---|---|
| 実務経験1年でフリーランスエンジニアになった方 | 37万円 | 38万円 | 39万円 |
| 実務経験3年でフリーランスエンジニアになった方 | 60万円 | 62万円 | 64万円 |
| 実務経験5年でフリーランスエンジニアになった方 | 80万円 | 83万円 | 85万円 |
もちろん上記はあくまで一例です。しかし、繰り返し説明しているように開発経験が浅いうちにフリーランスになると、案件でしかスキルを獲得する機会がないため、成長するには自力で学ぶ貪欲さと、新しいことにチャレンジできる覚悟が必要となります。
フリーランスは品質と成果が重視される世界なので、案件でミスやトラブルが多ければ、継続的な発注は見込めません。会社組織の研修やプロジェクトを通して、上司や先輩から基礎スキルや知識を教えてもらいたい方は、最低でも開発経験を3年積んでからフリーランスになることをおすすめします。
フリーランスエンジニアとして独立を避けるべきタイミング
失業手当を受けられるとき
確定申告の期間
今の職場に迷惑がかかってしまう時期
フリーランスエンジニアの独立に関するよくある質問
フリーランスエンジニアの平均年収はいくらですか?
フリーランスエンジニアの平均年収は、扱える言語や職種によっても異なりますが、一般的に600万円〜700万円程度と言われています。そのため月に50万円〜60万円程度の案件をこなすこととなります。
高いスキルや豊富な経験があれば年収1000万円以上も可能です。ただし経験が浅いエンジニアや、案件獲得がうまくいかない場合は、年収が500万円を下回る場合もありえます。案件単価、稼働時間、経費などを考慮し、目標年収を設定し、逆算して行動しましょう。
エンジニアファクトリーでは、ITフリーランスエンジニアの案件・求人の紹介を行っています。フリーランス案件の平均単価は66.3万円(2025年2月時点)となっており、スキルや言語によって高条件の案件と出会うことができますので、ぜひ活用してください。
まとめ

フリーランスエンジニアは、自分に適した案件やプロジェクトを自由に選択できる魅力的な働き方ですが、「自由である=稼げること」はまったく別物です。
これまでの実務経験を踏まえて戦略的に行動しなければ、市場価値のないエンジニアと評価されてしまい、案件を自由に選択できずに収入が得られない状況に陥ってしまいます。本記事で解説した実務経験別の戦略を参考にして、市場価値の向上を目指してください。
なぜフリーランスという働き方を選ぶのか、自分が考える理想の働き方を明確にしてから、案件を選びましょう。フリーランスエンジニアとして、どうキャリアを作っていけば良いかわからない、フリーランスになろうか悩んでいる方は、当社エージェントに登録してみてはいかがでしょうか。
エンジニアファクトリーでは、キャリアプランの作成などのアドバイスはもちろん、案件紹介なども行っております。
なかには、月100万円を超える開発案件、フルリモートの開発案件も多数掲載しています。なお、案件紹介や企業交渉によって発生する費用はありません。登録も無料なので、ぜひまずは下記よりご登録ください。