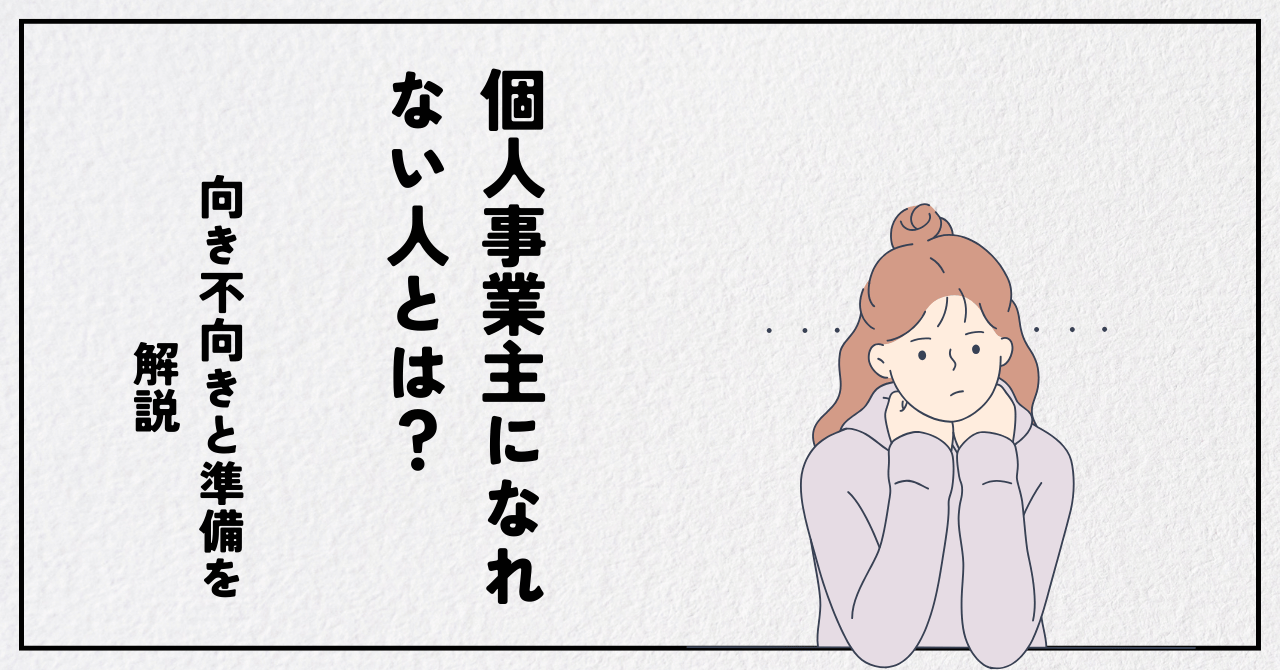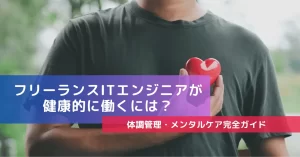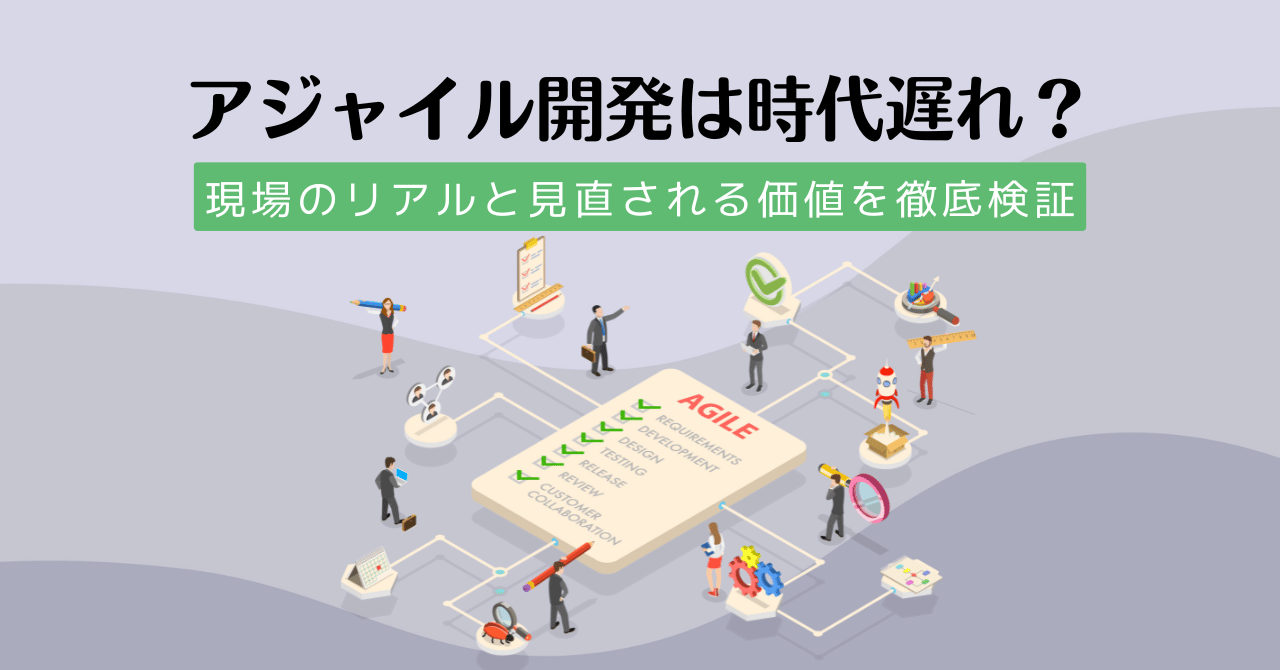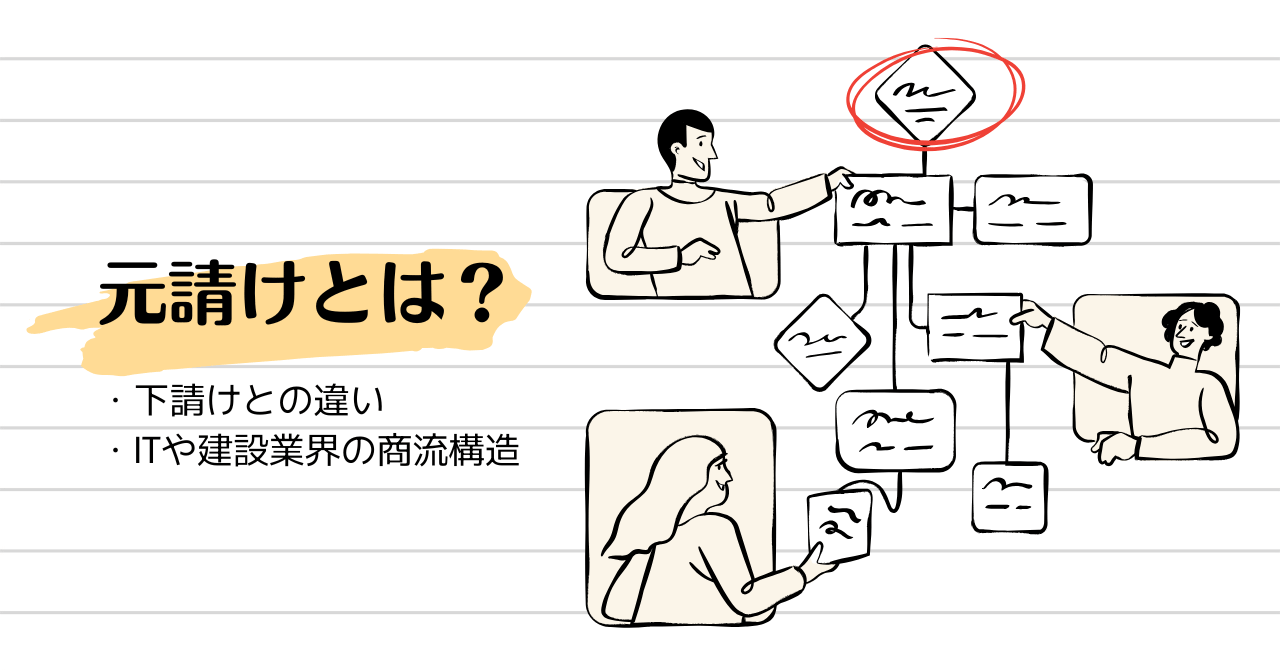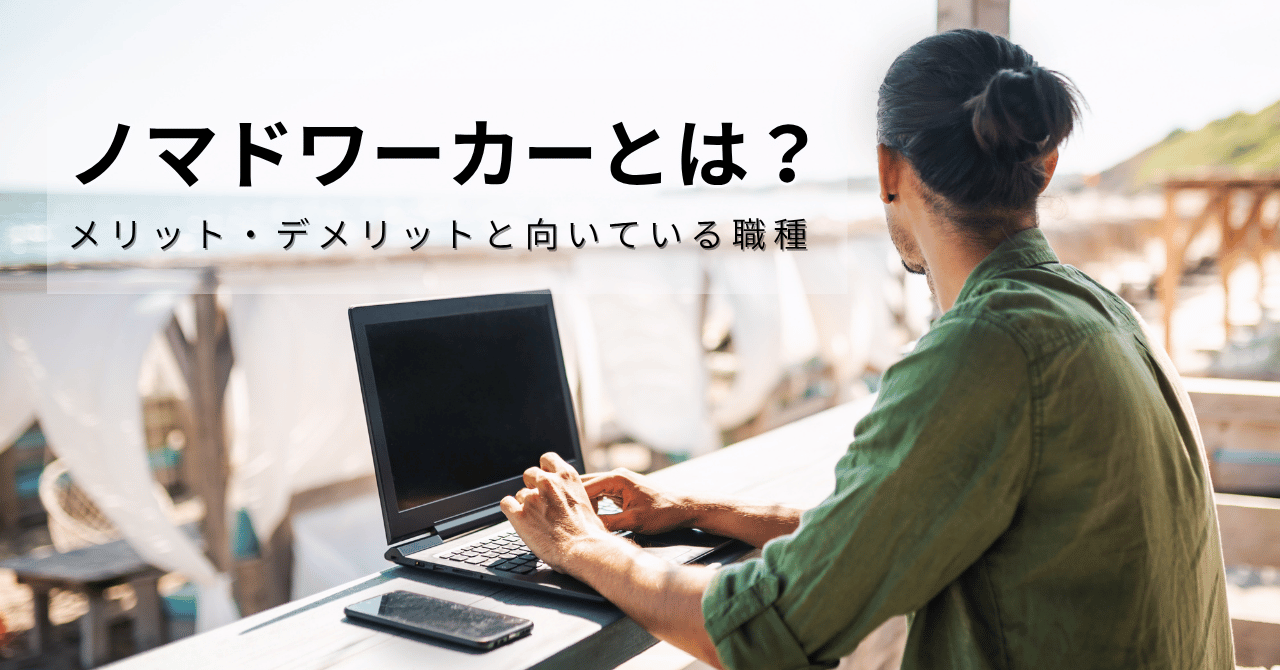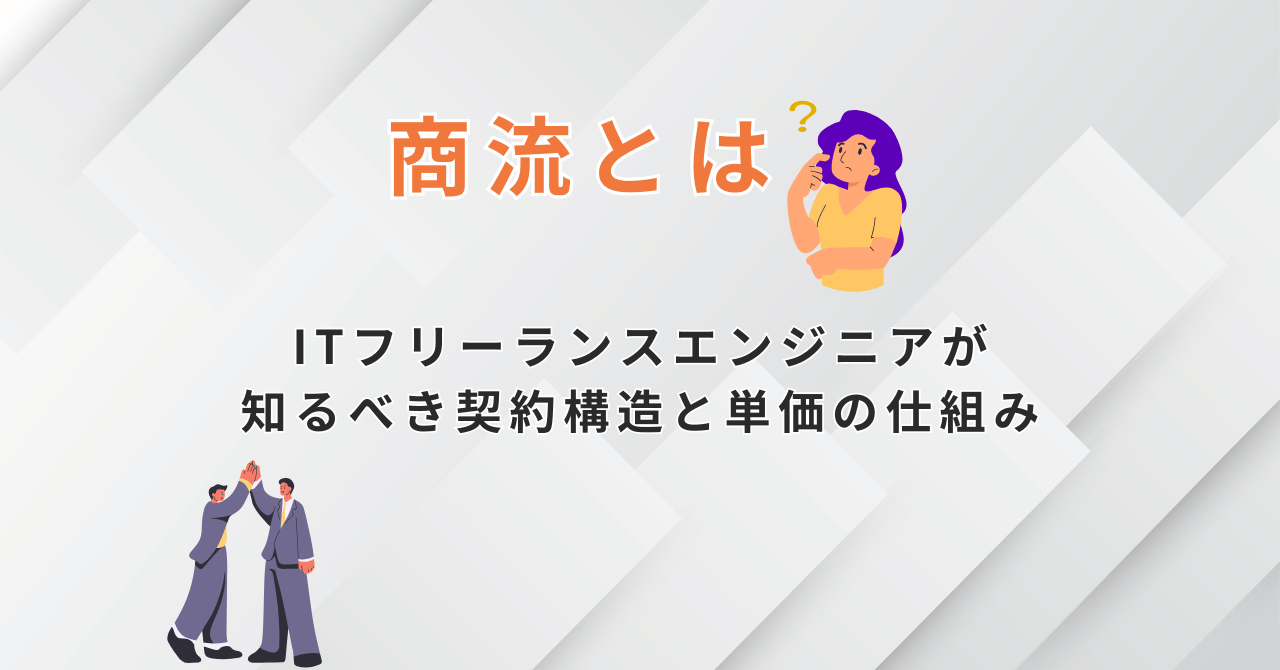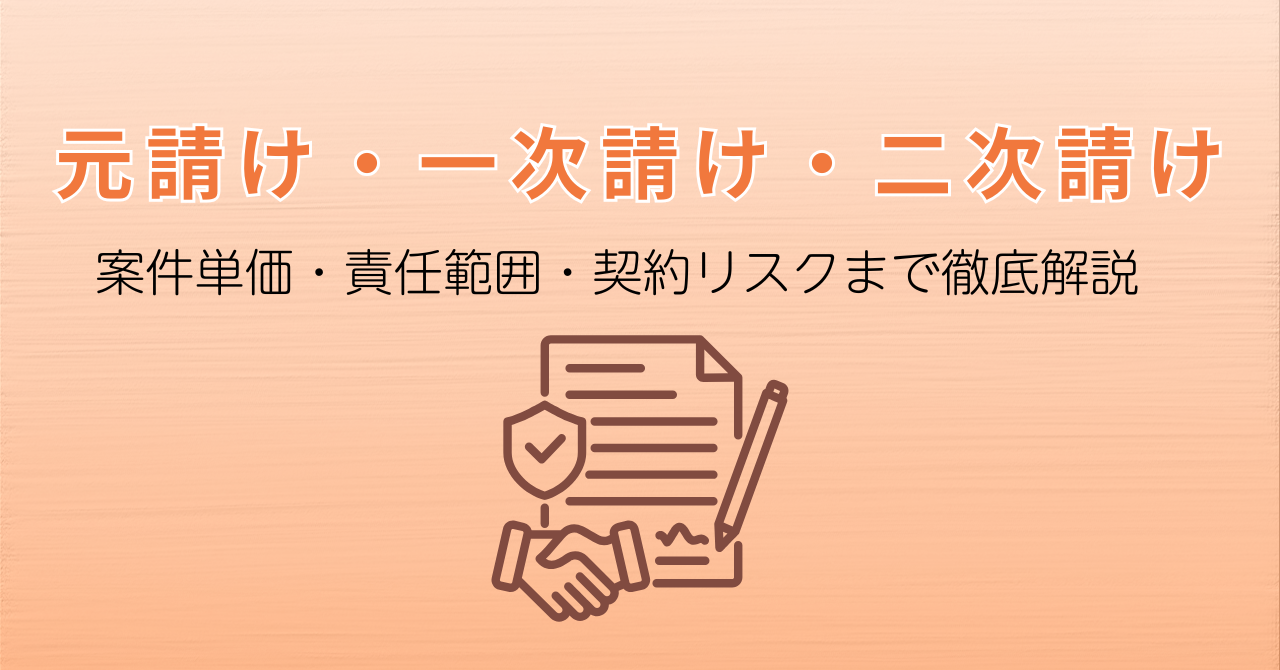個人事業主のエンジニアとして独立したくても、本当になれるのかと不安になる方は多いのではないでしょうか。本記事では、個人事業主になれない人や向いている人の特徴、必要な準備、よくある失敗事例を解説します。独立に必要な知識や心構えを理解できるため、ぜひ読んでみてください。

エンジニアファクトリーでは、フリーランスエンジニアの案件・求人をご紹介。掲載中の案件は10,000件以上。紹介する案件の平均年商は810万円(※2023年4月 首都圏近郊のITエンジニア対象)で、ご経験・志向に合った案件と出会えます。
簡単なプロフィール入力ですぐにサポートを開始。案件にお困りのITフリーランスの方やより高条件の案件と巡り合いたいと考えている方は、ぜひご登録ください。
個人事業主になれない人とは?
法的な制約や勤務先の就業規則などによって、「そもそも個人事業主になれない人」もいます。ここでは、個人事業主として開業できない主なケースを3つ紹介します。
- 公務員、副業禁止の企業に勤務している人
- 成年被後見人や破産者などの法的制約がある人
- 未成年者で親権者の同意が得られない人
公務員、副業禁止の企業に勤務している人
まず、公務員として働いている人は、法律により原則として副業が禁止されています。具体的には、以下の法令で明確に定められています。
これらの法律では、営利企業の運営や兼業が禁止されており、個人事業主としての開業も含まれるため注意が必要です。違反が発覚すると、懲戒処分(減給・停職・免職など)を受ける可能性があります。
また、民間企業で副業禁止規定がある場合も、会社に黙って個人事業主として活動することはリスクがあります。
法的な罰則こそないものの、就業規則違反として信用や人事評価に影響する可能性があるため、事前に会社の方針を確認することが大切です。
成年被後見人や破産者などの法的制約がある人
成年被後見人や破産者は、法的な制約の関係で個人事業主として開業できません。
成年被後見人とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、自分1人で適切な意思決定ができないと認定された人のことです。これらに該当する方は、事業を営むのに必要な判断能力が不足していると見なされています。
クライアントとの契約書には、報酬の支払い期限や納期、契約期間などの重要な情報が書かれています。成年被後見人が内容を理解しないまま契約すると、どちらかが不利益を被る可能性があるため開業ができません。
また、破産者も破産手続きが完了するまでは開業が制限されます。手続きが終了すれば開業できますが、開業のための融資を借りるのは信用上の問題から難しいとされています。
未成年者で親権者の同意が得られない人
18歳未満の未成年者で、親権者の同意が得られない場合は開業できません。民法第5条で、未成年が契約を結ぶ際は法定代理人の同意が必要だと決められているためです。
そのため、未成年者が開業する際は親権者の同意を得た上で事業を開始しなければなりません。万が一未成年者が親権者の同意を得ずに契約した場合、その契約を取り消すことが可能です。また、同意に加えて親権者が法定代理人だと証明する書類を用意する必要があります。

個人事業主に向いているエンジニアの特徴
「個人事業主に向いている人」にはいくつか共通点があります。ここでは、個人事業主として安定して活躍しているエンジニアに見られる4つの特徴をご紹介します。
- 自己管理能力が高い人
- 課題解決力と柔軟な思考がある人
- 新しい技術への好奇心と学習意欲が強い人
- コミュニケーション能力が高く、クライアントとの関係構築が得意な人
自己管理能力が高い人
自己管理能力が高い人は、個人事業主に向いています。
個人事業主は、会社員のように部署同士が連携して仕事を進めていくわけではありません。契約の締結から業務の遂行、経理、納期調整まで1人で進める必要があります。
自己管理能力が高い人なら「A案件は〇日までに納品する」「B案件は来週に回す」などとタスクの優先順位を自分で決めながら仕事を進められます。納期遅れも発生しにくく、クライアントからの信頼も得られるでしょう。
また、個人事業主は勤務時間の決まりがないため、自分で納期を意識したスケジュール管理が求められます。1日のスケジュールや時間配分を事前に決めた上で仕事を進められる人ほど、効率的にタスクをこなせるでしょう。
課題解決力と柔軟な思考がある人
課題解決力が高く、常に柔軟な思考で仕事を進められる人も向いています。
エンジニアは、不具合やエラーの修正、仕様変更などの予期せぬトラブルに迅速に対応する必要があります。
例えば、システムの復旧をする際は、まず不具合が起きている原因を探ります。個人事業主は、原因の特定から復旧作業、再発防止策の考案まで全て1人で対応しなければなりません。このとき、問題の原因を分析して解決策を冷静に考えられる人は、安定して質の高い成果物を提供できます。結果としてクライアントからの信用度も高まり、必要とされるエンジニアとなるでしょう。
また決まったやり方に固執せず、市場の変化に応じて新しいアイデアを取り入れられる人は、信頼できるエンジニアとして高い評価を得やすくなります。
新しい技術への好奇心と学習意欲が強い人
新しい技術に関心を持って仕事に取り組める人も向いています。
IT業界は常に変化しており、新しい言語やフレームワーク、技術が次々と生まれています。案件によっては、これまでの知識や技術では対応できない場合があるでしょう。
常に技術や知識を吸収しようとする人は、情報の移り変わりが早いIT業界にも柔軟に対応することが可能です。幅広いニーズや要望に対応できれば、クライアントからの信頼度も向上します。信頼性が上がることで、経験値を増やせるのはもちろん、報酬アップなどの収入面でのメリットも期待できるでしょう。
また、学習意欲がある人は学んだ知識や技術を実務でしっかり実践します。案件をこなすごとにスキルが向上し、長期にわたって活躍できるエンジニアとして評価されます。
コミュニケーション能力が高く、クライアントとの関係構築が得意な人
コミュニケーション能力も、エンジニアに必要なスキルの一つです。個人事業主のエンジニアとして長期的に活躍するには、継続案件を受注する必要があります。そのためには、技術力だけでなく、クライアントとの信頼関係の構築も重要なポイントとなります。
事前にクライアントの要望を丁寧にヒアリングし、何のために作るのか、どのような成果物をイメージしているか確認しましょう。また「〇日までに納品予定です」「現在ここまで進んでいます」と進捗報告をこまめに行うのも、信頼関係を築く上で大切なポイントです。
報連相をしっかり行い、クライアントと密にコミュニケーションを取っていれば、信頼性が向上して継続的に案件を任されるようになるでしょう。
-17.jpg)
個人事業主に向いていないエンジニアの特徴
個人で働くという選択肢には魅力がある一方で、向いていないタイプも存在します。以下のような傾向がある方は、独立後に苦労する場面が多くなるかもしれません。
- 安定志向が強く変化を好まない人
- 自分で意思決定するのが苦手な人
- 自己管理が苦手でスケジュール管理ができない人
- 孤立を感じやすく、1人での作業にストレスを感じる人
安定志向が強く変化を好まない人
安定志向が強く変化を好まない人は、個人事業主の働き方が大きなストレスになってしまう可能性があります。
会社員は、毎月決まった給料が振り込まれます。一方、個人事業主は案件が獲得できなければ、収入がゼロになるリスクもあります。継続的に案件を受注できても、その生活が今後も続くとは限りません。クライアント都合で契約が打ち切りになった場合、急に数十万円単位で収入が下がるリスクもあります。
そのため、安定した給与収入を求める人は、会社員として働くほうが適しているでしょう。また、個人事業主は、市場のニーズやクライアントによって仕事の進め方を変える必要があります。常に決まったやり方で業務を行いたい方は、いずれストレスを感じてしまう可能性があります。
自分で意思決定するのが苦手な人
自分で意思決定するのが苦手な人も、個人事業主に向いていない可能性があります。
仕事でトラブルがあった際、会社員なら上司に相談すれば解決策をすぐに教えてもらえます。しかし、個人事業主は基本1人で仕事を進めるため、何かトラブルが発生した際は自分でどう対処すべきか判断しなければなりません。
トラブルの対処に限った話ではなく、仕事量やタスク管理、価格交渉なども自己責任で行う必要があります。判断が遅ければ、案件獲得のチャンスを逃してしまったり、クライアントと円滑なコミュニケーションができなったりする可能性があります。
そのため、自分で物事を判断するのに時間がかかる方は、会社員で上司や同僚にアドバイスをもらいながら仕事を進めるほうが良いでしょう。
エンジニアファクトリーなら、案件参画後もエージェントが継続的にサポート。
職場環境やプロジェクトの進め方、対人関係等のお悩みを一人で抱え込むことがありません。
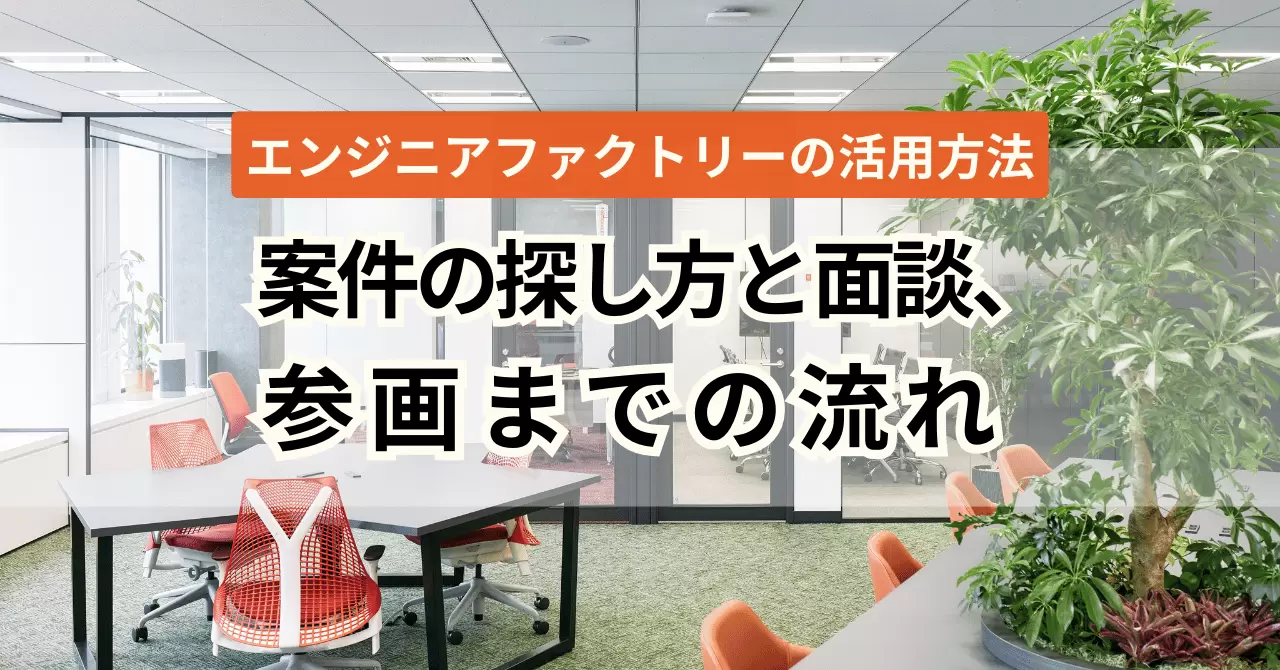
自己管理が苦手でスケジュール管理ができない人
自己管理が苦手でスケジュール管理ができない人は、フリーエンジニアとして長く活躍できない可能性があります。
個人事業主は、納期に合わせてスケジュールを自分で組む必要があります。誰かが進捗を確認してくれるわけではないため、どの案件をいつまでに行うのか全て自分で判断してタスクを組まなければなりません。スケジュールが適切に組めていないと、納期遅れが発生してクライアントに迷惑をかける可能性があります。納期遅れは全体の流れに遅れが生じるだけでなく、信頼性低下の原因にもなりかねません。
また、1つの案件で納期が前倒しになった場合、必要に応じて他案件の納期を調整しなければならないときもあります。自己管理が苦手な人は、日々のスケジュール管理が負担になってしまう可能性があります。
孤立を感じやすく、1人での作業にストレスを感じる人
1人での作業に孤立やストレスを感じる方は、個人事業主の働き方が合わないと感じる場合があります。
フリーエンジニアの方のなかには「悩みがあっても周囲に言い出しづらい」「自分で解決しなければ」と思いすぎてしまう人も多いようです。納期が重なったり、難易度の高い要望が続いたりする場合は、メンタルが不安定になってしまう可能性があります。
また、チームメンバーの入れ替えやリモート作業等、環境によっては孤独を感じるタイミングもあるでしょう。そうした場合には、職場のリーダーや同僚のほか、エージェントに相談するという方法もあります。そうした手段を通じて孤独感の解消に向き合っていけるかどうかが重要となります。
エンジニアが独立するために準備すべきこと
エンジニアとして独立する前に準備すべきことは、スキルアップや収入源の確保、人脈づくりなどが挙げられます。以下で詳しく見ていきましょう。
スキルアップと自己ブランディング
長期的に活躍するエンジニアになるためにも、スキルアップと自己ブランディングに力を入れましょう。常にスキルを磨き続け、自分の強みを売り込めばクライアントからの信頼度も向上します。
スキルアップの代表的な手段は、有料教材やスクールで知識や技術を学ぶことです。最新技術を学ぶために勉強会や書籍で勉強したり、資格勉強に励んだりするのも良いでしょう。また、持っているスキルや経験分野はポートフォリオに反映し、常に最新の状態にしておきましょう。ポートフォリオには、実績だけでなく、自分にしか提供できない価値や得意な分野も盛り込むと他のエンジニアと差別化できます。
スキルアップと自己ブランディングを継続的に行い、長期的なキャリア形成を目指しましょう。
安定した収入源を確保する
エンジニアとして独立する際に重要となるのが、安定した収入源の確保です。
個人事業主は、案件の数や単価によって収入が変動します。特定のクライアントが収入の大部分を占めている場合、そのクライアントの案件が終了した際に一気に収入が減ってしまう可能性があります。長期的かつ安定的に収入を得るためにも、複数のクライアントと契約し、収入源を分散させましょう。
また、長期プロジェクトに参画するのもおすすめです。長期案件は半年から1年以上取引が続く場合もあり、単発案件よりも安定的な収入を得ることができます。
仕事を進める中でクライアントと信頼関係が構築できれば、単価アップにつながったり、新たな分野の案件を依頼してくれたりする可能性があります。
人脈の構築とネットワーキング
安定的に仕事を受注するためにも、積極的に人脈を広げましょう。
業界イベントや勉強会は、同じ分野で働くエンジニアや企業担当者と直接交流できる良い機会です。会話を通じて信頼関係が構築できれば「この人に依頼したい」と思ってもらえる可能性があります。人脈が広がれば、何か悩みがあったときに相談できる仲間も増えるでしょう。孤独になりがちなフリーランスにとって、悩みを共有できる人の存在は心の支えにもなります。
また、LinkedIn(リンクトイン)やXなどのSNSを活用するのもおすすめです。SNSでは、自分の考えや強みを気軽に発信できます。交流の場としてはもちろん、自分の専門性をアピールするための材料としても活用可能です。
資金管理と独立後のリスク対策
資金管理と独立後のリスク対策もしっかり行いましょう。個人事業主は、案件ごとの報酬で収入が決まります。万が一収入が途絶えたときに備えるためにも、3~6か月分の生活費を準備しておくと良いでしょう。
また、ケガや病気などで仕事ができなくなったときに備えて、保険に加入しておくことをおすすめします。個人事業主は、会社員のように有休や傷病手当を活用できません。保険に入っていれば、一時的に仕事ができなくなったときに収入の一部を補償してもらえる可能性があります。
例えばエンジニアファクトリーでは、フリーランスエンジニアが安心して働くための福利厚生サービス「AIM CARE」をご用意しています。所得保障保険やFP相談サービスを活用すれば、お金の心配を減らすことができます。
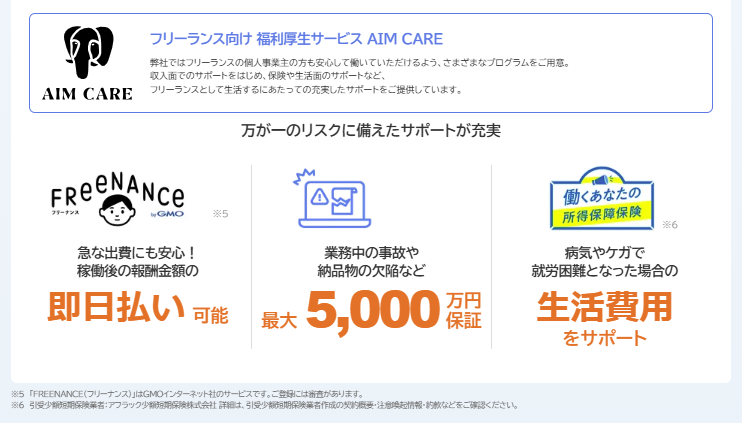
法律・税務知識の基礎を押さえる(開業届・確定申告)
法律や税務関係の基礎知識は押さえておきましょう。個人事業主になるには、開業届を最寄りの税務署に提出する必要があります。開業届は、事業を始めた日から1カ月以内に提出しましょう。提出方法は、税務署で直接提出か、e-TAXでのオンライン提出の2パターンです。
また、以下に該当する方は確定申告で年間の所得を申告する必要があります。
- 会社員で副業の所得が年間20万円を超える人
- 個人事業主で年間の所得が48万円を超える人
なお、所得は売上から経費を差し引いた額を指しています。所得を正しく申告するためにも、業務に使った物品購入費や通信費などの経費は記録しておきましょう。売上や経費の帳簿作成は、会計ソフトを活用すればスムーズに完了します。ぜひ試してみてください。
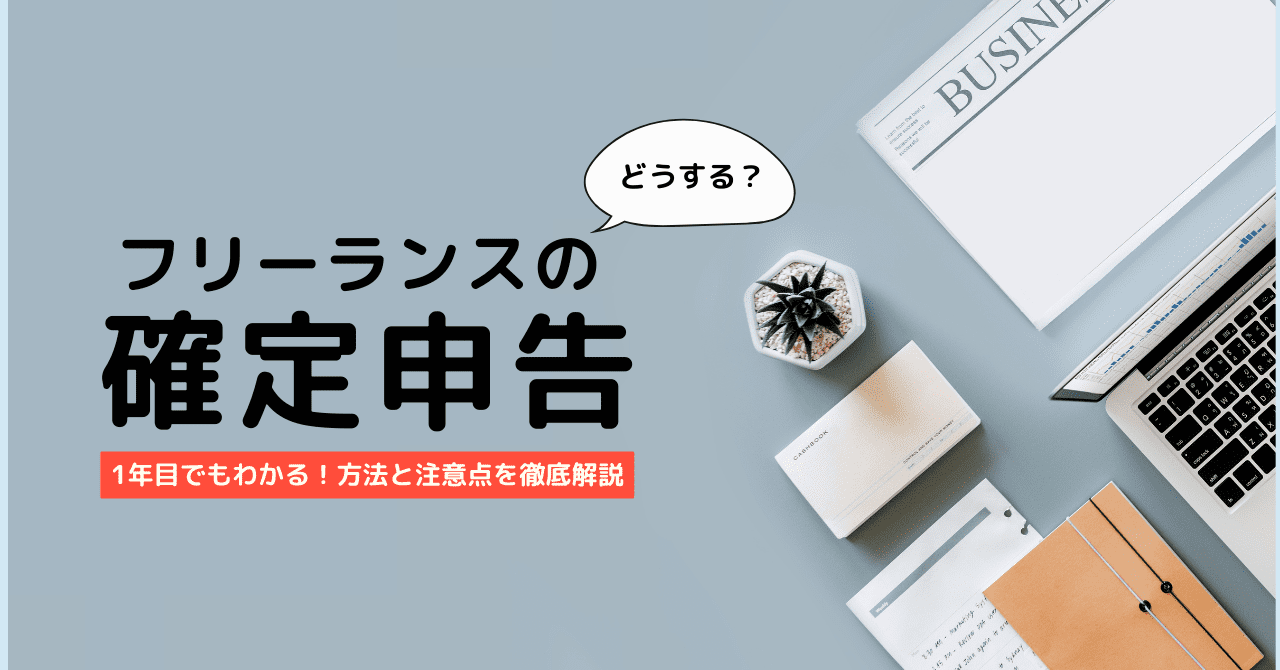
働き方とライフプランの設計
自由な働き方を目指して独立するなら、仕事と生活のバランスをどう整えるかがカギになります。
個人事業主は時間に縛られず働ける反面、気づけば常に仕事を抱えている状態になりがちです。納期に追われて体調を崩すケースも珍しくありません。無理のないペースを保つには、案件を詰め込みすぎないこと、あらかじめ休日をスケジュールに組み込むことが大切です。
また「この先、どの分野で、どんなエンジニアとして活躍したいのか」といった将来像も早めに描いておきましょう。キャリアの方向性が定まれば、いま取り組むべき案件や学ぶべき技術が見えてきます。さらに、老後を見据えた備えも必要です。個人事業主は会社員に比べて公的年金が少なくなるため、小規模企業共済やiDeCoなどを活用し、自らの手で将来を支える準備を始めましょう。
目の前の案件をこなすだけでなく、「どう働き、どう生きたいか」まで視野に入れること。それが、個人として無理なく続けられる働き方をつくる第一歩です。
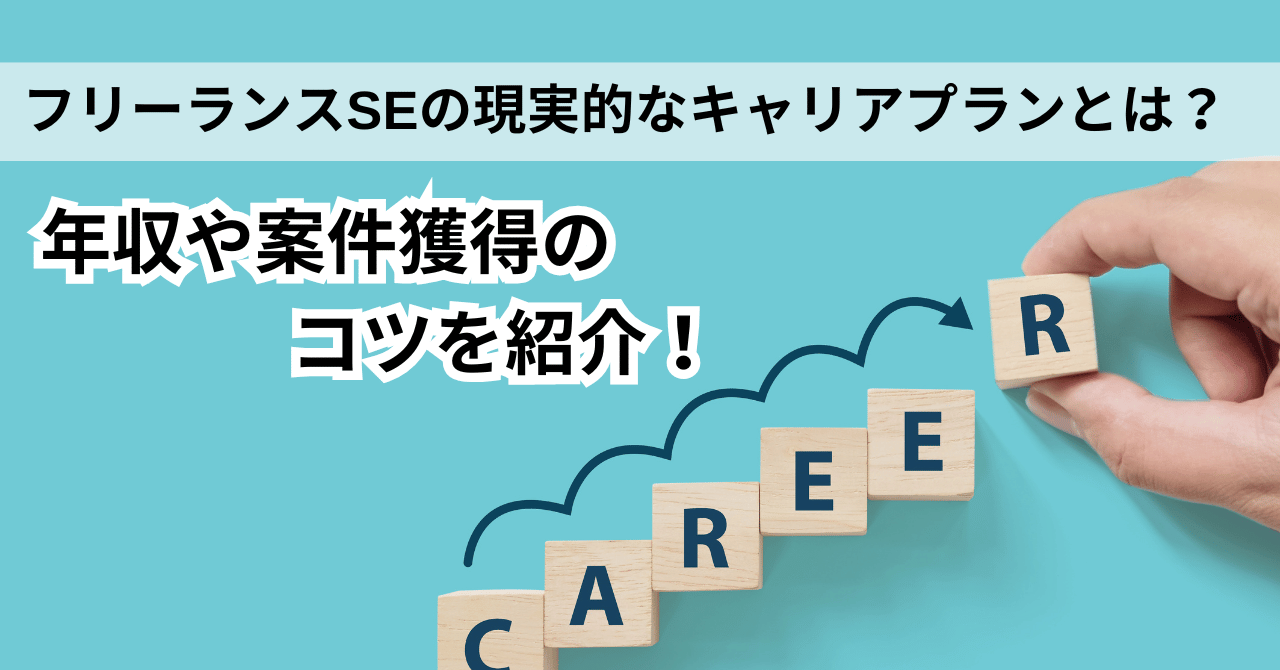
独立後に失敗するエンジニアの共通点とその理由
独立後に失敗しやすいエンジニアには、収入面やコミュニケーション面で共通する特徴があります。どのような理由で失敗につながるのか見ていきましょう。
安定した案件獲得の仕組みを作れなかった
独立後のよくある失敗が、なかなか案件を獲得できずに収入が伸びないケースです。
個人事業主は自らスキルや実績を売り込んで案件を獲得しなければなりません。やっとの思いで案件を獲得しても「1回限りで継続的な案件ではなかった」「低単価案件で収入が伸びない」と悩んでしまう場合もあります。こうした理由からフリーエンジニアとしての働き方に限界を感じ、独立を諦めてしまう人も少なくありません。
安定して案件を獲得するには、事前にどれくらいの価格帯の案件を受けるのか、どこから仕事を受注するのか明確にしておくことが重要です。ポートフォリオの作成やエージェントサービスの活用、交流会への参加など営業活動の幅を広げるのも方法の一つです。
収入の波に対応する資金管理が甘かった
不安定な収入に対する資金管理が甘かったのも、よくある失敗例の一つです。
個人事業主は、毎月決まった給料が振り込まれるわけではありません。受注した案件が少なければ収入は下がり、全ての案件が途絶えれば報酬はゼロとなります。また、クライアントによっては、納品後の報酬支払いまでに2~3カ月かかることもあるでしょう。回収できない期間は少ないお金でやりくりしなければならない場合もあります。
こうした収入の波を想定せずに独立した場合、生活費や税金、固定費の支払いに対応できず、貯蓄を切り崩す生活が長く続いてしまう可能性があります。最終的に廃業しなければならない場合もあるため、収入の変動リスクに対する資金管理はしっかり行いましょう。
スキルアップを怠り市場価値が低下した
スキルアップを怠って、市場価値が下がってしまうのもありがちな失敗例です。
IT業界は、常に情報やトレンドが変化しています。これまで重宝されていたスキルが、いつの間にか市場のニーズから外れて戦力外になるケースも珍しくありません。めまぐるしい変化の中でフリーエンジニアが生き残るには、常にスキルを磨き続ける必要があります。
例えば、JavaやPythonなどの主要な言語だけでなく、最新のフレームワークなども習得すると良いでしょう。ある程度経験値を積んだら、より高度な技術が求められる案件に挑戦してみるのもおすすめです。
必要とされるエンジニアになるためにも、常にスキルを習得し続け、自身の市場価値を高めていきましょう。

クライアントとの関係構築がうまくいかない
クライアントとの関係構築がうまくいかないのも、よくある失敗例の一つです。
個人事業主のエンジニアが安定的に仕事を獲得するには、クライアントとの良好な信頼関係が欠かせません。しかし、進捗報告や相談、確認を怠ったことで関係性が悪化するケースもあります。例えば、作業途中で不具合が発生しているにもかかわらず、クライアントに報告せずそのまま進めてしまい、後から重大なトラブルに発展するパターンが代表例です。
他にも、メールやチャットのレスポンスが遅く、円滑に業務を進められないのも関係性悪化の原因となります。質の良い成果物を納期までに納品するのはもちろん、日々の進捗報告やトラブル時の相談も欠かさず行いましょう。
個人事業主についてよくある質問
「興味はあるけど、実際どうなの?」という声にお応えして、個人事業主として働く上で多くの方が気になるポイントをQ&A形式でまとめました。
会社員を続けながら個人事業主として活動できる?
会社員を続けながら、個人事業主として副業することは可能です。ただし、企業によっては副業を禁止または制限している場合があります。就業規則に違反した場合、人事上の注意や指導の対象になる可能性もあるため、事前に社内規定を確認しておくことが大切です。
また、副業で得た所得が年間20万円を超える場合、会社員であっても確定申告が必要です。会社からの給与は年末調整で処理されますが、事業所得や雑所得は自分で申告する必要があります。
なお、所得とは売上から経費を差し引いた金額を指します。たとえば、副業の年間売上が100万円、経費が30万円だった場合、課税対象となる所得は70万円です。申告漏れがあると延滞税や加算税が発生することもあるため、注意しましょう。
個人事業主が法人化を検討したほうがいい年収はいくら?
法人化を検討する目安は、売上ベースではなく「課税所得(利益)」が年間600万円〜700万円以上になった頃です。
個人事業主の場合、所得が増えるほど税率も上がり、最大で45%近くに達することもあります。一方、法人化すれば、法人税や所得分散を活用して、実質の税負担を大きく抑えることが可能です。
たとえば、売上が900万円でも経費が多ければ利益は少なく、法人化のメリットは小さいかもしれません。逆に、売上が800万円でも経費が少なく、利益が多ければ法人化によって手取りが増える可能性があります。
また、売上が1,000万円を超えると、個人事業主は消費税の納税義務が発生します。法人設立によって、一定期間は消費税が免除される制度もあるため、あわせて検討する価値があります。
税負担を最適化したいと感じたら、「売上」ではなく「利益(課税所得)」を基準に法人化を考えるのが現実的です。
フリーランスと個人事業主、どちらが有利?
「フリーランス」と「個人事業主」は似たような意味で使われますが、厳密には少し違いがあります。
フリーランスは、会社に属さずに個人で仕事を請け負う働き方全般を指します。一方、個人事業主は、税務署に開業届を出して事業を営んでいる人のことを指します。ただ、実際にはフリーランスとして継続的に働くなら、多くの人が開業届を出しており、個人事業主として活動しているケースが一般的です。
個人事業主になることで、青色申告特別控除(最大65万円)や経費計上の幅が広がるなど、税制面でのメリットがあります。収入が一定以上あるなら、開業届を出して個人事業主として活動したほうが、節税や信用面で有利になるでしょう。
独立後の失敗を防ぐポイントは?
独立して後悔しないためには、「なぜ独立したいのか」「どんな状態をゴールとするのか」を自分の言葉で明確にしておくことが大切です。動機や目標が曖昧なまま走り出すと、モチベーションを保てず、途中で挫折してしまうリスクが高まります。
たとえば、「半年後に月20万円の安定収入を得る」「3ヶ月で初案件を2件受注する」など、数値を交えた具体的な目標を設定しましょう。目指す地点が見えていれば、進む道に迷いにくくなります。
また、収入面の不安がある場合は、副業から始めるのも現実的な選択肢です。会社員としての収入を確保しつつ、スキルや営業の経験を積んでおけば、いざ独立したときの不安は格段に減らせます。
思うように収入が伸びないときも、焦らず立ち止まることが大切です。必要なのは、やり方の見直しであって、自分を責めることではありません。学習方法を変える、営業のアプローチを見直す——小さな改善の積み重ねが、理想の働き方への最短ルートになります。

フリーランスとしての働き方を現実的に考え始めたなら、まずは今の経験で参画できる案件を知ることから始めませんか?エンジニアファクトリーでは、実務経験のあるエンジニアが独立に向けて準備を進める際の案件探しやキャリア相談をサポートしています。
公開中の案件は8,000件以上。エンド直の高単価案件も多数取り扱っており、営業活動なしで内容や単価を比較できます。専任のエージェントが希望やスキルを丁寧にヒアリングし、ミスマッチの少ない案件をご提案。案件選びに迷う段階でも、情報収集の場として活用いただけます。経験を活かして、次のキャリアを考えたい方は、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
個人事業主として働くことは、エンジニアにとって現実的な選択肢の一つです。原則、誰でも開業は可能ですが、公務員や破産者、副業を禁止している企業に勤めている場合など、一部制限がある点には注意が必要です。
また、個人で働くには自己管理力や柔軟な対応力など、「向いているタイプ」があることも事実です。自分の志向やライフプランを踏まえた上で、将来のキャリアをどう描くかを考えておきましょう。
エンジニアファクトリーでは、実務経験をもとに独立を目指すエンジニアをサポートしており、案件継続率は95.6%、年商が最大300万円アップした事例もあります。
独立を検討している方も、まずはご希望の働き方を整理するところから、お気軽にご相談ください。