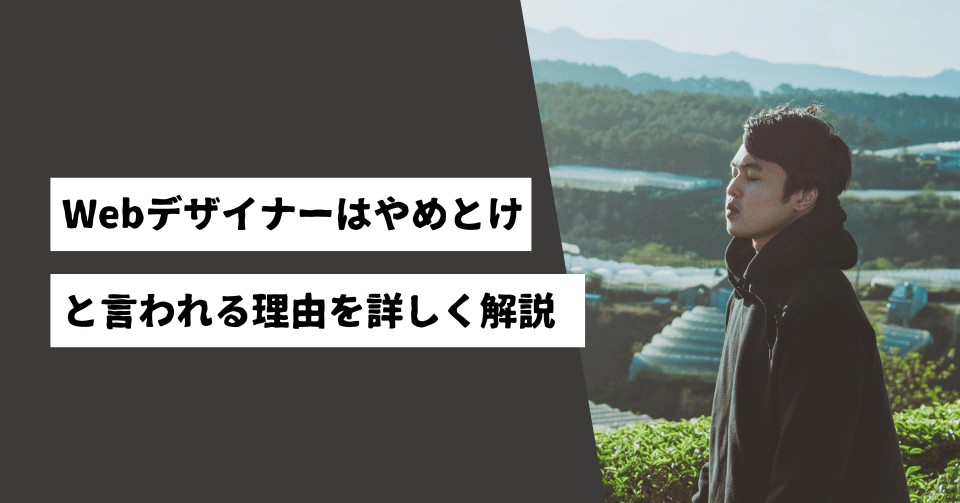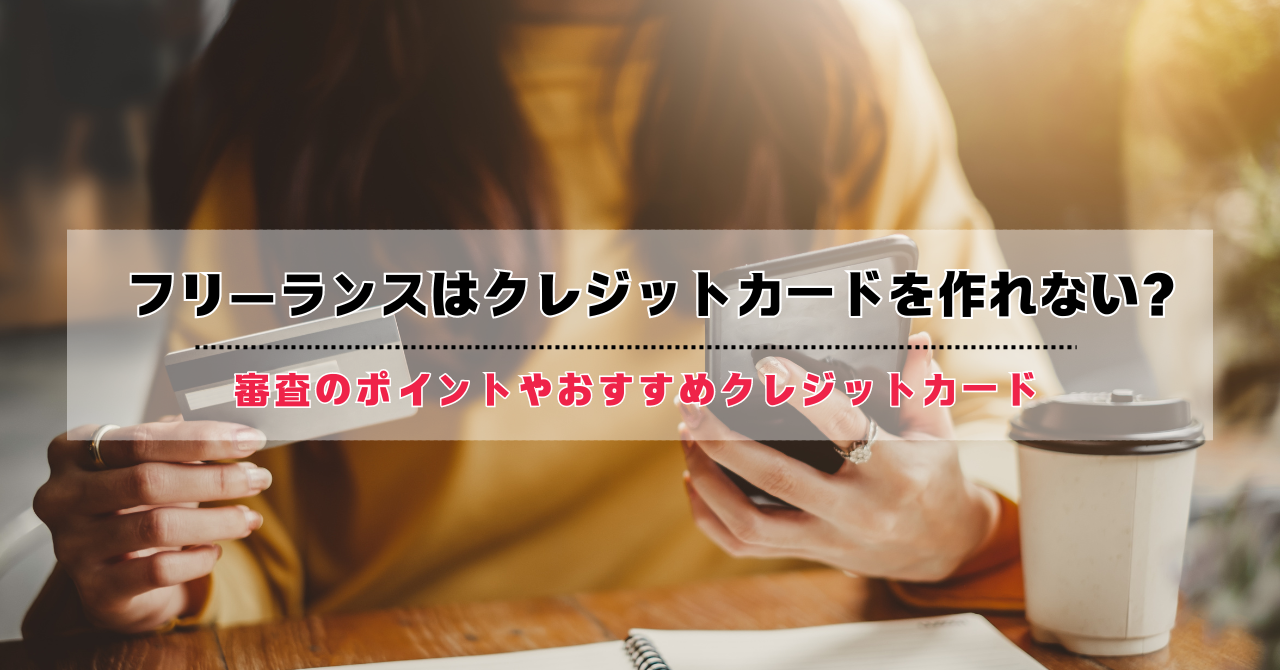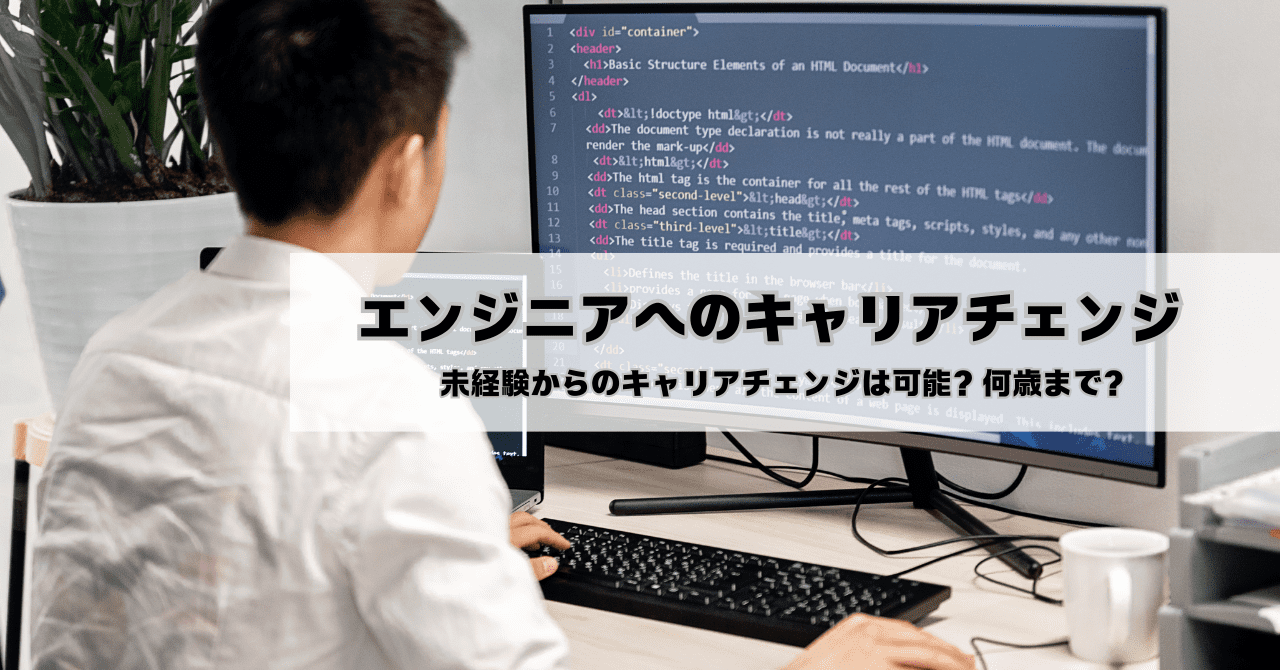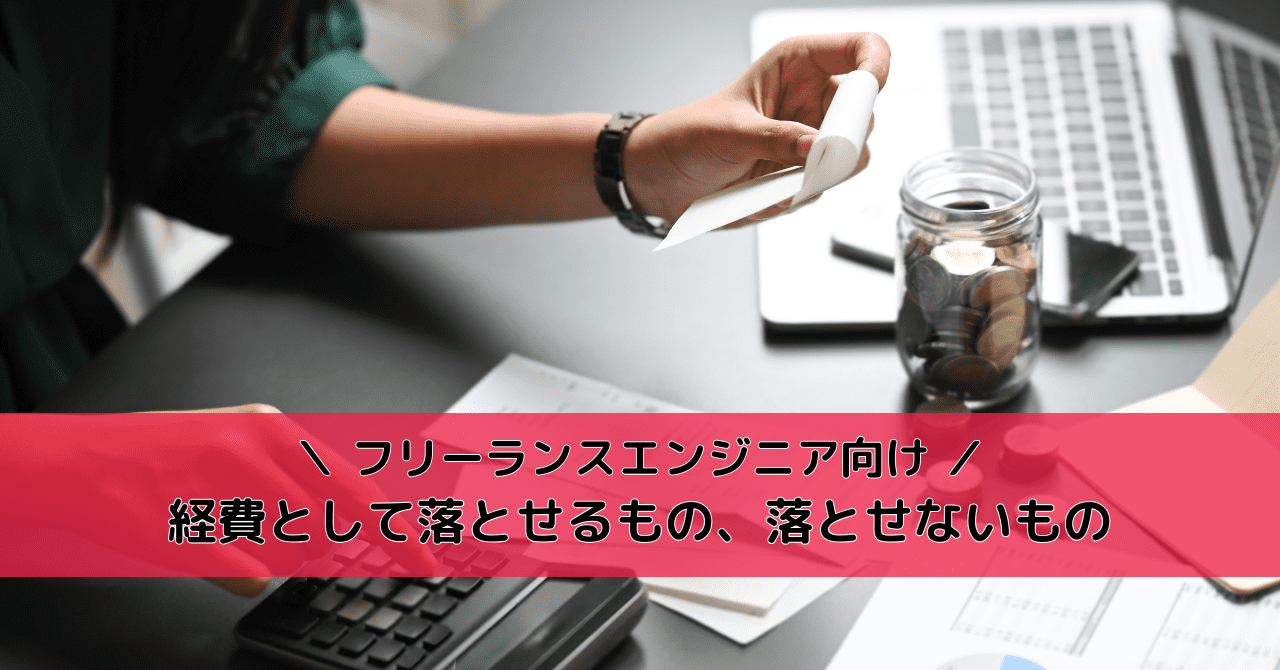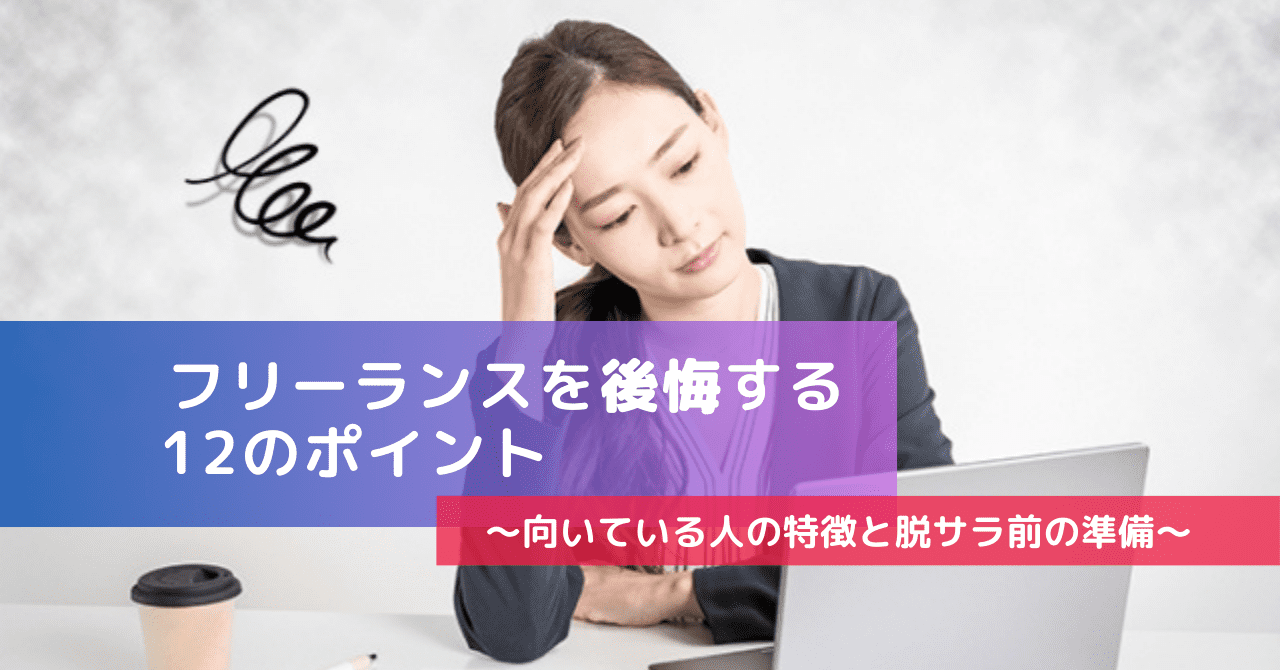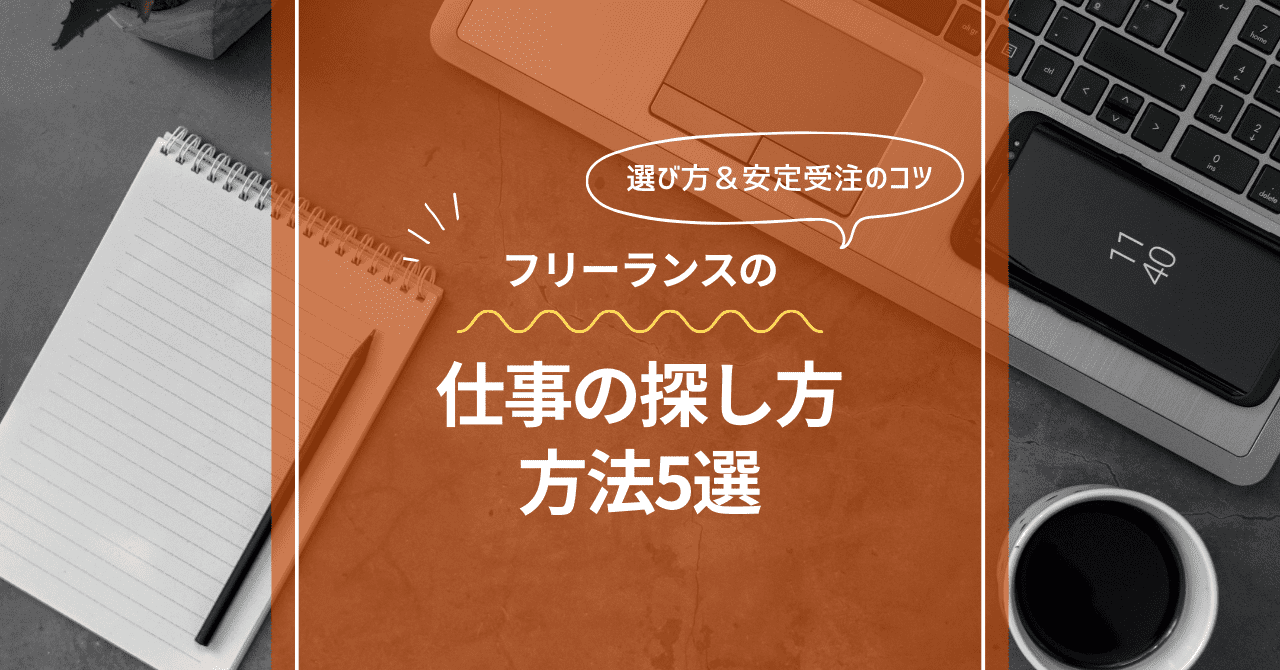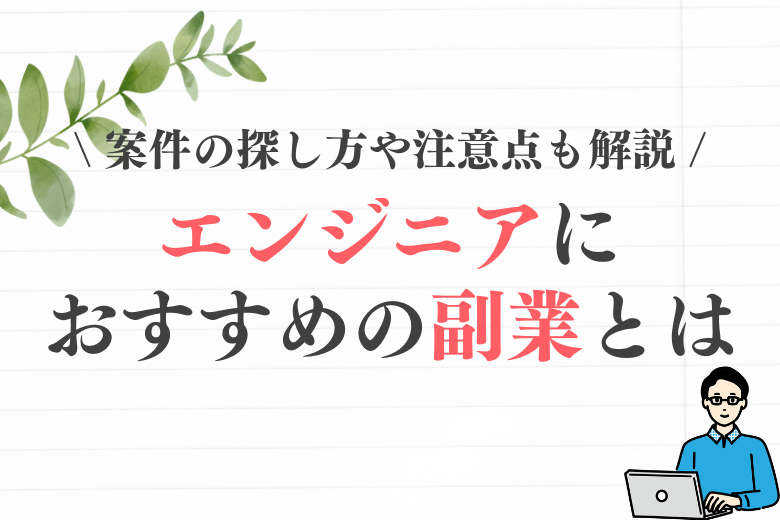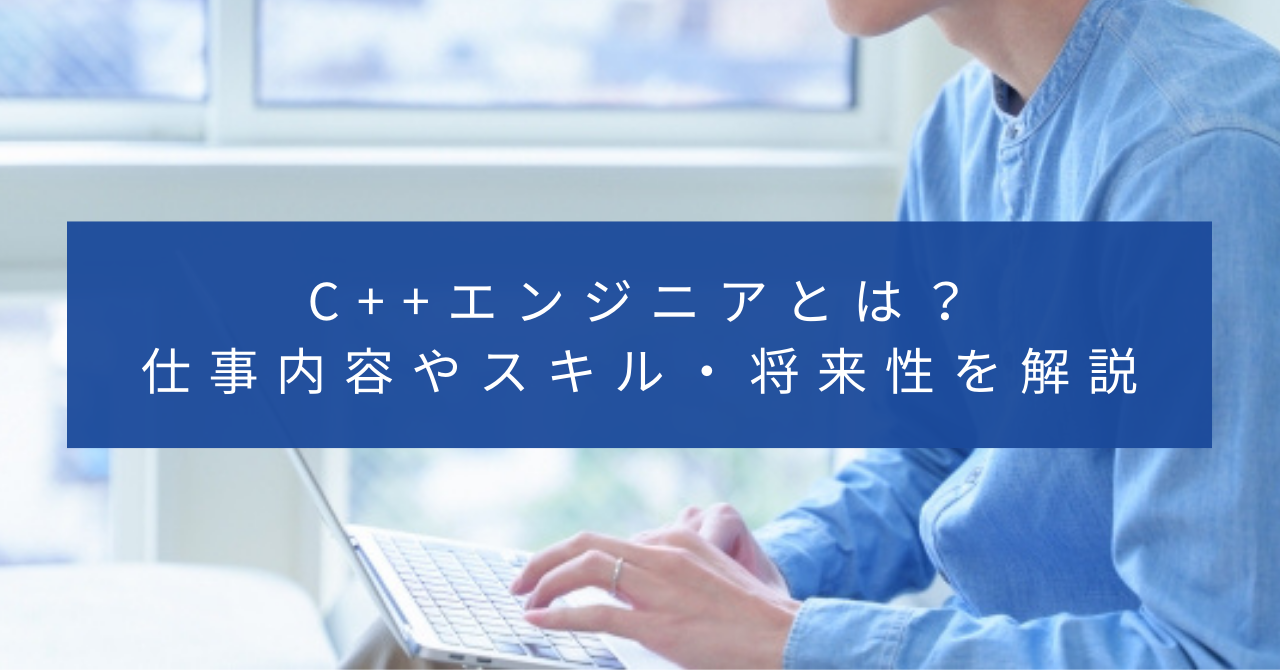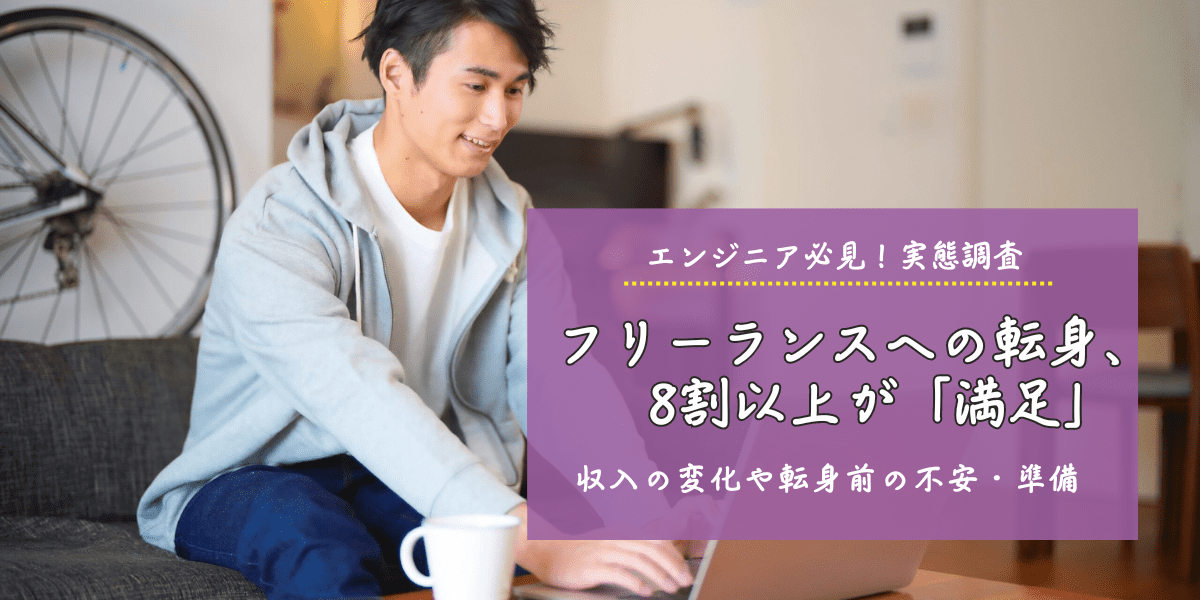フリーランスが支払う税金はいくら?種類や控除、それぞれの節税対策をご紹介!

フリーランスとして働く場合、健康保険の加入や経費の精算、確定申告を自分で行わなくてはいけません。フリーランスとして働くとき、どのような税金がかかり、どのような控除を受けられるのでしょうか。
本記事ではフリーランスが支払う税金の種類や控除を開設し、節税対策を紹介します。

エージェントサービス「エンジニアファクトリー」では、ITフリーランスエンジニアの案件・求人の紹介を行っています。紹介する案件の平均年商は810万円(※2023年4月 首都圏近郊のITエンジニア対象)となっており、スキルや言語によって高条件の案件と出会うことができます。
氏名やメールアドレス・使用できる言語を入力するだけで、簡単60秒ですぐにサポートを開始できます。案件にお困りのITフリーランスの方やより高条件の案件と巡り合いたいと考えている方は、ぜひご登録ください。
フリーランスが支払う税金の種類
フリーランスが支払う税金は、主に以下の8種類です。ここではフリーランスが支払う、主な8つの税金について、詳しく解説します。
- 所得税
- 復興特別所得税
- 住民税
- 国民健康保険料
- 個人事業税
- 消費税
- 固定資産税
- 国民年金保険料
①所得税
所得税は、自営業者やフリーランスのような個人が収益に基づいて国に納める税金の一つです。従業員が給与から自動的に引かれる税と同じく、フリーライターやフリーのグラフィックデザイナーなどが受け取る報酬に先立って引かれる税も、所得税の一部として計上されます。
税額を計算するには、まず収入からの必要な支出と様々な控除を引いた「課税所得」を算出します。以下の式で課税所得を特定しましょう。
課税所得=収入-必要支出(経費)-各種の控除次にこの課税所得に基づいた税率を適用して税金を計算します。その後、適切な控除を適用して最終的な所得税額を求めます。課税所得を元に計算できる控除額は、以下です。
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
上記の表の控除額は、所得の多寡にかかわらず全ての人に適用されます。日本の所得税体系は、所得が増えるにつれて税率も高くなる「累進税制」を基盤としています。
しかし所得が増えたとしても、突然税額が大幅に増加することはありません。税率は段階的に適用されるのです。
たとえば所得が700万円の場合、最初の195万円には5%の税率、次の330万円までは10%、695万円までの部分は20%、そして最後の50,000円部分には23%の税率がそれぞれ当てはまるわけです。この方式を「超過累進税率方式」といい、具体的な税額を知るためには、各区分ごとの計算と、全体の合計を照らし合わせて確認することが必要です。
②復興特別所得税
復興特別所得税は、東日本大震災の復興支援のために設立された特別な税金で、2013年から2037年まで、毎年の確定申告において、通常の所得税と共に申告・納付するものです。具体的な復興特別所得税の額は、該当する年の標準所得税の2.1%とされています。標準所得税とは、総所得税から各種の控除をした後の金額を指します。
各個人に対する標準所得税の額は、以下より算出されます。

2023年を起点とするとあと14年ほど、復興特別所得税が課されることになります。一人ひとりの支援が震災からの復興の大きな支えとなることを、改めて認識したいところです。
③住民税
住民税は、フリーランスや自営業を営む個人が地方自治体に納める税金を指します。住民税は、収入に基づく「所得割」と、居住地域による一律の「均等割」の2つで構成されています。
前年度の所得に基づいて計算される「所得割」は、全体で10%(県税が4%、市町村税が6%)です。収入の多寡に関わらずすべての納税者が一律の金額となっている「均等割」は、合計4,000円(県税1,000円+市町村税3,000円)となっています。この2つの税額を合計したものが、要求される住民税の総額です。
2024年までは、東日本大震災の復興支援のため、特別税として年間1,000円が追加で徴収されます。納税の期限は年に4回、6月末・8月末・10月末・翌年1月末です(期日が休日の場合は翌平日が締切)。
所得税が非課税でも、住民税が課税される場合があることを認識しておく必要があります。所得税にも住民税にも「基礎控除」という免税額があり、所得税は38万円、住民税は33万円となっているためです。たとえば収入が35万円の場合、所得税では免税となりますが、住民税は課税対象となります。
④国民健康保険料
国民健康保険とは、フリーランスや自営業の方、年金を受給している方など、企業に所属していない方々が加入する公的医療保険制度のことを指します。日本の国民皆保険制度は、全市民が何らかの公的医療保険に参加することを義務付けています。
会社に所属する方々は会社の医療保険に加わり、保険料は給料から直接引かれます。しかしフリーランスの場合、住所地の自治体が管轄する国民健康保険に加入することとなるのです。
各自治体によって料金の名称は「国民健康保険料」や「国民健康保険税」となることがありますが、実質的には同じ意味です。
国民健康保険の保険料は、前年度の収入に基づき、決定されます。たとえば今年フリーランスとして活動を開始したものの、前年は企業に勤務していた場合、その年の収入に基づいて料金が計算されます。したがってフリーランス開始後の収入が減少しても、前年の収入が高かった場合、保険料も相応に高くなることがあるため、注意が必要です。
国民健康保険料は、一括での支払いや分割しての支払いが可能です。また、納めた料金は確定申告時に社会保険料としての控除が適用される点も留意しておきましょう。
⑤個人事業税
個人事業税は地方税の一種で、都道府県に納めます。個人事業税の税額は、前年度の所得に基づき算出されます。
フリーランスの中で、地方税法を始めとする法的規定に基づく特定の事業を営む者は、個人事業税を支払う義務が生じます。2022年8月時点で、これら特定の事業は約70の業種にわたります。ただし、一年間の事業収入が290万円を下回る場合、通常、個人事業税の支払いは免除されます。
所得税や住民税の申告をすでに行っている方は、再度、個人事業税の申告を別途行う必要はなく、確定申告の「事業税の該当事項」のセクションに情報を記載すれば、都道府県からは自動的に納税の通知が届けられます。この通知に従い、大体8月と11月、年2回で税金を支払います。
個人事業税の税率は、業界や居住する自治体により差があります。具体的な税率について不明点があれば、自らの事業所がある都道府県に問い合わせてみてください。
東京都の場合の法定業種(個人事業税を支払う義務がある業)と税率は、以下です。

⑥消費税
フリーランスとしての活動が特定の条件を満たしている場合、消費税の支払いが必要です。
以下の「基準期間」や「特定期間」という期間中の課税対象売上が1,000万円を超えると、消費税の納税が求められます。フリーランスにとっての消費税の申告や支払いの締め切りは、該当する課税期間の次の年の3月31日となります。
<個人事業主の期間定義>
- 基準期間:2年前の1月1日~12月31日
- 特定期間:前年の1月1日~6月30日
消費税を支払うか否かは2年前の売上額に基づいて決まるため、通常、ビジネスを開始してから2年は消費税の支払いが不要です。ただし「特定期間」である半年間の売上や給与の合計が1,000万円を超えた場合、事業開始直後から納税対象となるケースがあるため、注意が必要です。
2023年10月から「インボイス制度」が導入される予定です。インボイス制度の下でフリーランスは、取引先から要請された際、税率や税額などを明記した「インボイス」を提供することが義務づけられます。また、消費税の控除を実施するためには、取引先からのインボイスを適切に保管することが要求されます。
インボイスの発行は消費税の課税事業者のみが行うことが可能です。インボイス制度を適切に遵守するため、売上の総額に関係なく税務当局への「消費税課税事業者の届出」を行い、その後「適格請求書発行の登録」をする手続きが必要です。
また消費税は、他の税額と比べて高くなりがちで、利益が出ていない時期でも納税義務が発生します。そのため、資金計画には慎重な管理が必要です。消費税が発生する年度に向けて、納税予備預金などを活用して、日々適切に資金を確保しておくことが求められます。
⑦固定資産税
土地や建物にかかる固定資産税は、所有している不動産に基づく税金です。フリーランスの方が自宅を仕事の場として利用している際、この税金を家賃に見立てて、業務とプライベートの使用比率に応じて経費として処理することができます。
具体的には、ビジネス利用と個人利用の比率を考慮して、ビジネス部分の固定資産税を経費として計上することが許されているのです。固定資産税の申告は不要で、自治体から納税通知が来るので、それに基づき期限内に支払いを行います。
固定資産税は通常、3年ごとに評価額が再検討されることが特徴です。この再評価は、その時期の市場価格を基に課税を適切に行うための手続きで、主に土地と家屋が評価対象となります。
⑧国民年金保険料
国民年金保険料は税金とは異なりますが、フリーランスも支払う義務があります。原則として、20歳以上60歳までの日本在住の者は国民年金への加入が必須です。従業員の場合、給与から厚生年金保険料を自動的に差し引かれることが多いですが、フリーランスは振替や納付書を用いて自分で保険料を支払う必要があります。国民年金の料金は年度ごとに変動し、2022年度では月々16,590円、2023年度では16,520円となっています。
フリーランスは、会社員のように給与から自動的に一部を差し引かれるわけではありません。また会社員が厚生年金の保険料の半額を会社が負担してくれるのに対し、保険料全額を自分で支払う必要があります。ただし国民健康保険料は、確定申告の際に全額を控除可能なため、税金削減のメリットもあります。
フリーランスに効果的な節税対策3選
ここからはフリーランスに効果的な以下の3つの節税対策を、詳しく紹介します。フリーランスになろうとしている方、フリーランスになるにあたり、税額を把握しておきたい方は是非参考にしてください。
- 経費として計上できる税金を漏らさず計上する
- 青色申告で手続きを行う
- 各種控除を利用する
経費として計上できる税金を漏らさず計上する
事業の経費は、確定申告の際に正確に申告することが大切です。なぜならフリーランスが受けとる収入は「売上」であり、その売上から「経費」を引いた金額が課税対象の「収入」となるからです。正確な経費計上をすることで、税額を節約できるのです。
多くの税金は経費としての計上が難しいですが、業務関連の税金ならば経費扱いが認められる場合があります。たとえば個人事業主が支払う税や消費税(税込方式の場合)は経費計上が許されます。自宅をビジネスのために使用している場合、その使用部分に関する固定資産税も経費として計上できます。
生活の中で業務とプライベートのコストが混在する場合、合理的な基準で分けることを「家事按分」といいます。家賃や光熱費、通信費、業務で使用している車の経費など、適切に家事按分を行い、確定申告に反映させることが重要です。さらに、ビジネス開始前に発生したコストも、起業に関する費用として経費として計上できます。
青色申告で手続きを行う
フリーランスが確定申告を行う際、「青色申告」と「白色申告」の二つの手法から選ぶことができます。
青色申告を選択する事業者は、特定の基準をクリアすることで、最大65万円の「青色申告特別控除」を受けることが可能です。この特別控除を利用することで、課税対象となる所得が減少し、結果として所得税が削減されるため、節税メリットが得られます。
65万円の特別控除を享受するためには、一連の手続きと、複式簿記を採用しての帳簿記入、さらに確定申告時には貸借対照表や損益計算書の提出、e-Taxや質の良い電子帳簿保存方法の利用などが求められます。指定された基準を満たさない場合、特別控除は最大55万円や最大10万円に制限されるため、注意が必要です。
各種控除を利用する
確定申告の際、所得から差し引くことができる「所得控除」があります。該当する条件を満たしている場合、それぞれの控除額を所得から引くことで、課税対象の所得を算出することができます。
大きくわけて物的控除と人的控除にわけられます。具体的には以下です。
| 物的控除 | 雑損控除 | 災害や盗難などによって生活上の資産が損害を受けた場合に受けられる事業用の資産の場合は、事業の損失として計上できますが、雑損控除にはできない |
| 医療費控除 | 納税者本人とその人と生計を一にする配偶者やその他の親族の、一定額以上の医療費を支払った場合に受けられる 支払った医療費(最高で200万円)-保険会社から受給した保険金など-10万円※=医療費控除額(※合計所得金額200万円未満の場合は合計所得金額の5%) 【特例】 セルフメディケーション税制 対象医薬品の購入費-1万2,000円=所得控除額(1万2,000円超部分について、上限8万8,000円の医療費控除) | |
| 寄附金控除 | ふるさと納税など国や地方公共団体などに寄附を行った場合に受けられる | |
| 社会保険料控除 | 健康保険料(税)や国民年金保険料などの公的な保険料を支払ったとき、または生計を同じくする配偶者や子供、親族の公的な保険料を支払ったときに受けられる | |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済で支払った掛金の全額が所得から差し引かれる 対象:小規模企業共済、企業型確定拠出年金(企業型DC)、個人型確定拠出年金(iDeCo)、障害者扶養共済制度などの掛金 | |
| 生命保険料控除 | 民間の保険会社に生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料などの保険料を支払った場合に受けられる 最高額12万円まで | |
| 地震保険料控除 | 特定の損害保険のうち、地震による損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる 最高額5万円まで |
| 人的控除 | ひとり親控除 | 婚姻歴や性別にかかわらず、同一生計の子(合計所得金額など48万円以下)を扶養していて、納税者本人の合計所得金額が500万円以下の単身者は、ひとり親控除として35万円の所得控除を受けられる |
| 寡婦控除 | 原則として、その年の12月31日の現況で「ひとり親控除」に該当せず、次のいずれかに当てはまる場合に27万円の所得控除が受けられる 1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得額が500万円以下の人 2. 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人 | |
| 勤労学生控除 | 働きながら通学する勤労学生で、その給与収入が130万円以下である場合に受けられる | |
| 障害者控除 | 納税者本人や配偶者、扶養親族が障害者または特別障害者である場合に受けられる 控除額は、障害者一人あたり27万円、特別障害者が40万円 | |
| 配偶者控除 | 控除対象となる配偶者の給与収入が103万円以下の場合、13万~48万円(納税者の所得額および配偶者の年齢で決まる) 納税者の合計所得額が1,000万円を超えると控除を受けられない 青色事業専従者給与・事業専従者控除との併用は不可 | |
| 配偶者特別控除 | 配偶者がいて、配偶者控除の適用外(配偶者の所得が48万円超133万円以下であるなど)の場合に受けられる 控除対象となる配偶者の給与収入が103万円以上の場合、1万~38万円(納税者の所得額で決まる) 納税者の合計所得額が1,000万円を超えると控除を受けられない 青色事業専従者給与・事業専従者控除との併用は不可 | |
| 扶養控除 | 配偶者がいて、配偶者控除の適用外(配偶者の所得が48万円超133万円以下であるなど)の場合に受けられる 控除対象となる配偶者の給与収入が103万円以上の場合、1万~38万円(納税者の所得額で決まる) 納税者の合計所得額が1,000万円を超えると控除を受けられない 青色事業専従者給与・事業専従者控除との併用は不可 | |
| 基礎控除 | 配偶者がいて、配偶者控除の適用外(配偶者の所得が48万円超133万円以下であるなど)の場合に受けられる 控除対象となる配偶者の給与収入が103万円以上の場合、1万~38万円(納税者の所得額で決まる) 納税者の合計所得額が1,000万円を超えると控除を受けられない 青色事業専従者給与・事業専従者控除との併用は不可 |
フリーランスITエンジニアの案件ならエンジニアファクトリー

エンジニアファクトリーは、フリーランス案件も多数紹介しています。掲載している案件は、Webアプリケーション開発やネイティブアプリケーション開発、バックエンド開発といったITエンジニアの領域で、非常に多岐に渡ります。
エンジニアファクトリーにはIT業界に精通したコンサルタントが在籍しているため、エンジニアの立場を理解し、希望条件や懸念事項を考慮に入れたご提案が可能です。
案件を受けるか決めていない段階でもご相談を受け付けています。まずは無料会員登録のうえ、何でもお気軽にご相談ください。
まとめ

本記事で紹介したように、フリーランスとして働くことを選ぶと、働く場所や時間を自分のタイミングで決められるメリットがあります。一方で、税金の申告や納税を自ら行わなくてはいけない、健康保険料が上がってしまう、といったデメリットもあることがわかりました。
エンジニアとしてのキャリアを考えたとき、フリーランスの道を選ぶ場合は、安定した収入や納税の手間といった会社員のメリット以上に、収入面や働き方といったメリットがあるかどうかをじゅうぶんに検討する必要がある、といえます。
合わせて読みたい記事
フリーランスエンジニアが経費として落とせるもの、落とせないもの
ライター:前嶋 翠(まえじま みどり)
・プロフィール
COBOLが終わろうとする時代にプログラマのキャリアをスタートし、主にJavaエンジニアとして経験を積みました。フリーランスエンジニアとして活動していたとき、リーマンショックが起こったことをきっかけに家庭に入りました。出産を経て在宅でできる仕事として、ライターに。ITエンジニア経験のあるライターとして、IT業界のあれこれを皆さまにわかりやすくお伝えしていきます。